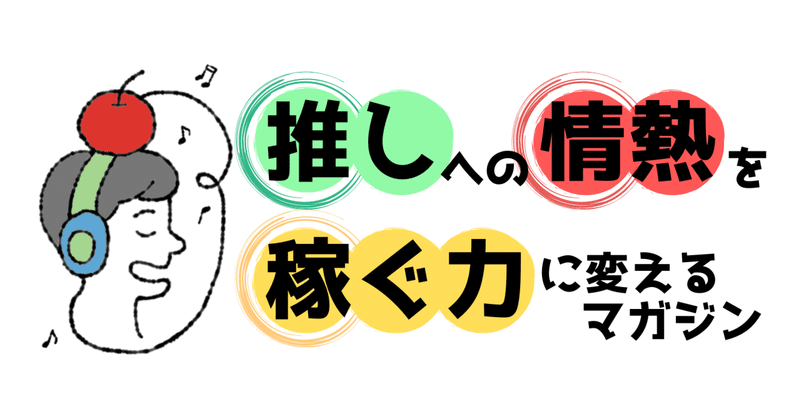
収入を上げたい人が知っておくべき、評価の決まり方と心がけ
僕は普段、推し活についての記事を書いていますが、推し活において、仕事は切っても切り離せないものです。
「もっとグッズを買いたい」
「もっとライブに行きたい」
「推しから認知されたい」
「推しがもっと人気になって欲しい」
推し活におけるファンの欲求は様々ありますが、これらを満たすためにはお金が必要不可欠です。
イベント参加やグッズ購入にはもちろんお金が必要ですし、推し活のための時間確保という点でも、お金があれば取れる選択肢が増える。推しにとっても、人気になるためには売上が伸びる必要がある。何を取っても、突き詰めて考えていくと必ずお金が関わってきます。
お金をより稼ぐためには、他人からより高く評価される必要があります。社会貢献の対価としてお金を貰っているのですから、当然のことです。
ではどうすれば他人から高く評価されるのでしょうか。
本記事では、僕が15年以上推し活を続けている中で本気で収入を上げようと試行錯誤した経験と、大企業でエンジニアをしながら採用・新人教育にも携わってきた経験を元に、収入を上げたい人が人が知っておくべき評価の決まり方と心がけについてお伝えします。
あくまで僕の見解であり、僕もまだまだ試行錯誤を続けている最中ではありますが、一気に年収を100万円上げられた実績もありますので、そこそこ信憑性はあるのではないかと思います。
誰が見ても「そりゃそうだな」と思ってもらえるような内容なるよう、客観性・論理性にも気を配って書きますので、是非最後までお付き合いください。
評価の正体

高評価を得るための方法について触れる前に、まず前提として、「評価って何なの?」ということについて明確にしておきましょう。
意見が分かれるところかとは思いますが、僕は『評価=期待値』だと考えています。
『評価=実績』だと捉えている方も多いのではないでしょうか。僕も概ね同意ではありますが、少し不正確な部分があるのではないかとも思っています。
例えばAmazonで商品を買う時、レビューを見て評価が高いものを選びますよね。レビューの評価が高いということは既に買った人の満足度が高いということですから、ここで言う評価は実績であると言えます。
しかし、いざ商品が自分の手元に届いて使ってみたとき、必ずしも満足できるとは限りません。自分には合わないかもしれないし、不良品が届くかもしれない。あくまで多くの方が満足できた実績があるから、自分も満足できる可能性が高いというだけ。つまり、評価とは期待値であり、過去の実績はあくまで期待値を決める要素の一つと捉えるのが正確ではないでしょうか。
商品を例にしましたが、人についても同じです。その人が良い成果を出してくれることを期待できるから、会社がその人を雇用したり、依頼主がその人に仕事を依頼したりするのです。
このことをふまえると、高評価を得るためには如何に自分の期待値を高く見せるか、という点を考えていく必要があります。
評価の決まり方

自分の期待値をアピールする際、必ず抑えておかないといけないのが相手の評価軸と観点。つまり、『何を求めているか』と『何処を見て評価しているか』です。
評価軸については相手状況によって様々です。ヒアリングやリサーチで情報を集めるしかありません。しかし、観点に関しては突き詰めれば一つしかありません。それは、行動原理です。
行動原理の定義は次の通りです。
行動の根源的な動機となる本能・欲求・願望・信条・価値観など。
・仕事における評価とは、成果の期待値のことである。
・成果は行動で決まり、行動は行動原理で決まる。
これらをふまえると、評価しようとすると自然と行動原理に着目するようになるのです。
僕が前職で採用活動や新人教育に関わっていた時も、裏側では
「Aさんは質疑応答で深く疑問点を掘り下げてたから、慎重に手堅く仕事を進めてくれそうな印象だった」
「Bさんはいつも元気よく挨拶してくれるから、お客さんとも良好な関係を築いてくれそう」
といったような、評価対象の未来の成果を予測するような会話がとても頻繁に行われていました。
どれも直観的な印象の話だけのように思われますが、決してそうではありません。言葉遣いから鞄の置き方まで、細部をとことん観察し、掘り下げて行動原理を予測しようとしているのが伺えました。
就活で学歴フィルターというものがあったり、アルバイトの募集条件に頭髪の色の制限があったりますが、これらは全て採用する側が行動原理を効率的に見極めようとした結果できあがったものだと推測できます。
「高学歴だからといって仕事ができるわけではない!」「髪色で人を選ぶなんて価値観が古い!」といった意見が散見されますが、採用する側も学歴や髪色で人を評価できるなんて思っていません。
どれだけ時間を掛けても人が他人を正確に評価するのは不可能であること。一人一人の評価に掛けられる時間は限られていること。これらを心得ているからこそ、質と効率のバランスを重視した結果、多少取りこぼしが出ることも承知の上で、選択している手段なのです。
高評価獲得のための心がけ

以上のことをふまえると、高く評価されるためにすべきことは、見せ方をデザインすることだと僕は考えています。相手のニーズに合った人材であることを行動や言動から読み取らせる。あるいは自分のアピールポイントを行動や言動で示して選んでくれる相手を探す。こういったことが必要になります。
具体的に何をすべきかは自分のアピールポイントや相手のニーズによってケースバイケースです。例えば、ある程度の勤勉さを担保するために企業側が学歴フィルターを設けているのであれば、学歴が要求ラインを満たせていなくても難しい資格取得の実績など、別のアピールできる事例をもって直談判すれば、チャンスが生まれるかもしれません。
個別の事例はその場に応じて考えていく必要がありますが、それ以前に、誰であっても、如何なる場合においても、必ずアピールしておくべきことがあります。
それは、誠実さです。
言葉にすると凄く凡庸に思われるかもしれません。しかし、僕は今までの社会人経験から、無数に存在する評価軸の中で、『誠実さ』が最も威力が高く、最もコスパがよく、最も恐ろしい要素だと実感しています。
そう感じている理由を一言で言うと、評価の土俵に上がれるかどうかを決める要素だからです。順を追って説明します。
まず原点に立ち返って考えていきましょう。なぜ働けばお金を稼げるのでしょうか。もちろん、社会に価値を生んでいるからです。突き詰めれば例外ではないかと思えるものもありますが、基本的には誰かの役に立てているから、対価としてお金をもらえているのです。
では、どうすれば誰かの役に立てるのでしょうか。ざっくり整理すると以下の2つです。
①相手の役に立てる能力を持っていること
②相手の役に立とうとする意思があること
能力については後から身に着けることができます。現時点で能力が不足していたとしても、将来的に能力を習得する見込みがあると相手に思わせられれば、期待値を補うことができます。
しかし、意思については違います。その人の行動原理で決まるからです。行動原理とは本能・欲求・願望・信条・価値観のことであり、これらは人格を形成している根本的な要素です。そう簡単に変えることはできません。
では以上のことを踏まえて考えてみてください。例えば電車で2人分の幅を取って座っている人がいたとします。その人の行動原理は、周囲の人から見てどう推測されるでしょうか。「他人を押しのけてでも自分の利益を優先する人」だと推測するのが自然ではないでしょうか。
もちろん実際にどうかはわかりません。普段は優しく思いやりのある人なのかもしれませんし、他人が近付いてきたら席を空けようと思っていたかもしれません。しかし、周囲の人からすれば、「近付けば席を空けようと思っている人ならそもそも幅を取って座るはずがない」「席を空けるようお願いしても、最悪の場合怒鳴られたり暴力を振るわれるかもしれない」といったことを考え、結果として「近付かないでおこう」という判断になります。
つまり、一見して誠実さが見えない行為をしていると、実際にどういう人かを深掘りされないまま、一瞬で低評価が確定してしまうのです。
これと類似のことが、採用や人事考課の現場でも起こっています。ひどい寝ぐせが付いたままで面接に来た。出社する時に歩き煙草をしているのを見かけた。こういった些細なことがきっかけで気付かないうちに能力や実績を見てもらうことすらできない状態に陥っている、いわば評価の土俵に上がれていない人が少なくないのです。
僕が誠実さを「最も威力が高く、最もコスパがよく、最も恐ろしい要素」と表現したのは、
・どんな仕事でも最重要視される(=威力が高い)
・その気になれば誰でも簡単に実行できる(=コスパが良い)
・マイナスに振れた時の損失の大きさが計り知れない(=恐ろしい)
といった理由からです。
ここで是非押さえておいて欲しいのが、これは評価する側にとって合理的な判断であるということです。「マナー悪いやつはムカつく!」とか「こんなやつは社会的なに評価されるべきでない!」とか、そういった感情論や倫理観の話をしているのではありません。
他人の役に立つことでお金をもらっているという社会人の性質上、誠実さは社会人として期待値を示すために最低限必要な要素であり、誠実な行動をすることは、自分の利益を高めるための合理的な手段です。
人間は完璧な生き物ではありませんし、誰しもどこか自分勝手な一面はあるものです。他人の役に立てといっても、自己犠牲の精神で働くのは負荷を伴うので長続きしないし、表面だけ取りつくろおうとしても、何処かで必ずボロが出てしまう。
他者貢献が最終的には自分のためになる。このことが腹落ちしてはじめて、本気で他者貢献の先にある収入アップを目指せるのではないかと思います。
まとめ
評価=期待値である
評価する側は、相手の行動や言動から読み取れる行動原理を見ている
高い評価を得るためには、見せ方をデザインする(相手のニーズに合った行動原理を示して評価させる)必要がある
如何なる場合においても必ずアピールすべきなのは『誠実さ』である
どの行動・言動を見られてもいいよう、『誠実さ』の重要性を理解し、日常生活から無意識に誠実な行動をとれるようになるべきである
さいごに
僕は3年半ほど前、新しく作る会社の立ち上げメンバーとしてオファーをもらえたことで、年収を100万円上げることができました。
オファーをもらえたきっかけになったのは、とある飲み会でした。僕が急な仕事で飲み会に遅れて到着した時、僕がリーダーを勤めていたチームのメンバーの表情が晴れたのを社長が偶然見ていて、そこから僕に興味を持ってくれていたそうです。
僕は当時から誠実に仕事に向き合うことを意識していましたし、メンバーへの接し方にもかなり気を付けていました。しかし、知らない間にそんなチャンスを掴んでいたとは、後から話を聞くまで思いもしませんでした。
このことを踏まえると、逆にふとした行動や言動から、気付かないうちに大きなチャンスを失ったこともあるかもしれません。
いつどんなチャンスが降ってくるかはわからない。いつ誰から評価の対象にされているかわからない。
僕にとって今の会社への転職は、そういったことを強烈に実感するような出来事でした。
本記事が、読んでくださった皆さんにとって、何か新しいの気付きのきっかけになれば幸いです。いいねやコメントなどいただけますと、大変励みになりますので、お待ちしております。
また、僕は『推し活を起点とした経済的・精神的に豊かな生活の実現』を目指した情報発信を行っています。その一環として、noteの記事投稿、電子書籍の出版・制作代行、企業様のHP作成などにも取り組んでいます。
まだ公表していないけど準備を進めていることもありますので、興味を持っていただけた方は是非noteやTwitterをフォローしてお待ちいただけると幸いです。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!
サポートいただいたお金は、参考文献の購入など、本活動に関する費用に充てさせていただきます。収益獲得がメインではありませんが、全て自費でコンテンツ作成しておりますのでサポートいただけると大変ありがたいです。
