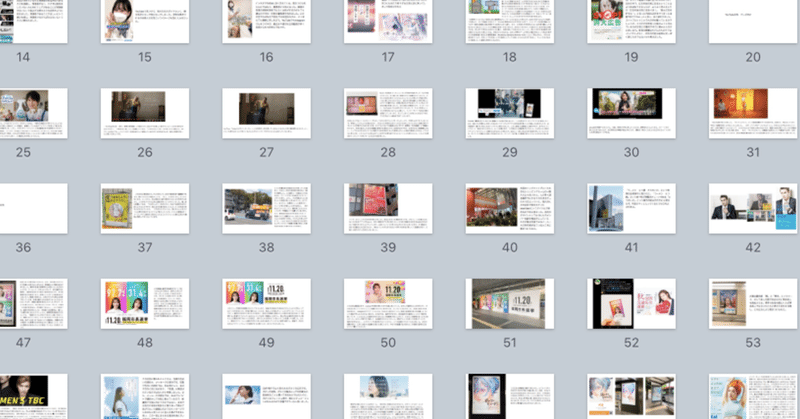
「ジェンダー表現とメディア」を学ぶプログラムを作りたい(広告観察ワークショップ編)
2020年から男女共同参画センターのイベント、写真フェスティバルのセミナー、オンラインイベント、高校や大学での授業、研修会など、さまざまなな機会を通して、広告観察幅広い年齢層の方を対象に行なってきました。
このワークショップの目的は、広告の表現を観察・分析することを通して消費社会とジェンダーの関係を考え、観察を通して自分のものの見方を言語化して他者に伝え、それぞれに異なるものの見方が存在することを確かめ合うことです。
過去にTIP(TOKYO INSTITUTE of PHOTOGRAPHY)で行ったワークショップの案内の中で趣旨を説明しています。
ワークショップの形式としては、広告とジェンダー表現に関する講義を行った上で、 ジェンダーの観点から気になった(見ていてモヤモヤする、違和感を抱く)広告を撮影して、コメントを添えて(コメントの長さはとくに指定しません)提出してもらい、添えられたコメントと写真に対して、こちらが比較参照できるような画像を探して、スライドにまとめ、コメント(投稿者の名前は伏せて、匿名の状態にします)とともに紹介してワークショップの参加者全員で共有します。
私が提出してもらった画像とコメントをもとにスライドを構成する際に主に以下の点に注意しています。
広告の表現の特徴を解説した上で、同類の広告を画像検索し、提出された画像と表現の仕方の違いや、表現のバリエーションを提示する。
複数の参加者が同じ広告を挙げている場合は、それぞれのコメントの記を確認して、着眼点、意見の違いを確認する。
素材として使われているイラストや写真などの視覚表現のあり方に注目し、その中に含まれている要素・価値観を言語化する。
このようなプロセスを経ることで、参加者それぞれが発見したものを通して、表現について掘り下げて考え、「モヤモヤする」ことを、具体的な方向性を持った意見、例えば「この表現のこの点が差別的・ステレオタイプ・時代錯誤・改善すべき」と指摘できるような意識を持つことができるようになるはずです。
過去に高等学校(大阪)と大学(福岡)で行ったワークショップで提出された広告の事例と、そこから展開して作ったスライドと、私の解説コメントを紹介します。
ベビーカーマークの広報ポスター

ベビーカーマークは、2015年にJIS化されたマークで、公共交通機関に周知用のポスターが掲出されています。国土交通省のウェブサイトでは、2018年以降の掲出物、パンフレットのデータを閲覧できます。
提出されたのは2021年度版のポスターで、コメントに「ベビーカーを押しているのが女性な所」とあり、ジェンダー役割として女性・母親の役割を固定しているところに違和感を抱いた、という見方が示されています。
ピンクを基調とした画面であること
右側のタレントの女性(アイキャッチ役)にフォーカスが合っていて、ベビーカーを押している女性の後ろ姿はぼやかされて背景化されていて、育児をする女性を主体として描いていない。
ということも、追加して指摘できるところです。

類する広報物との比較 1
イラストによる描写で、左と右はピンクを基調とした色合いで、女性が押している様子を描き、中央は人を描かずに、ベビーカーを中心に配置して、左右をピンクとブルーに分けている。

類する広報物との比較 2
男性がベビーカーを押す様子を描いたイラストが使われていて、色合いがピンクではなく、グリーンや青などを用いて、ピンク色を使わない表現になっている。2022年度は、男性・女性をイラストで描き、ポスターも女性の写真を使わないものになっています。
徐々に公共広報のジェンダー表現が変化している好例と言えるでしょう。
大阪産業創造館の広報誌Bplatz Press

大阪の地下鉄やシェアオフィス、教育機関などで配布設置されている大阪産業創造館が発行するcの表紙を、地下鉄で見つけて手に取り、「自分らしく生きてみると言っているのに女の人がいなくて男の人の絵しか載ってない」というコメントをつけてくれました。
ピンクを基調とした画面で、ショッキングピンクの唐草模様のスーツに黄緑色のネクタイ、アフロヘアでヒゲを蓄えた男性にセリフが「カラクサモヨウノスーツキタカッタンダヨネ〜♪」と片言風の日本語風で表記されている。
典型的なサラリーマン、労働者像としての日本人男性像からかなりズレた様相の人物を描くことで「自分らしく生きる」ということを誇張・戯画化している表現になっている。(果たしてそれは「自分らしさ」なのか?という問いも出てくるでしょう)
ということも、追加して指摘できるところです。


Bplatz pressのバックナンバーを紹介するページで、近年の刊行号と10年前の刊行号の表紙を比べてみると、近年の方が女性が登場するものが増えていることがわかります(10年前はほぼスーツ姿、作業着姿の男性のみです)地域産業振興のための広報物で、公共性が高いものですから、徐々にジェンダーに対する意識が変わっていることは見て取れるのですが、コメントで指摘されているようにまだ、仕事の場面では男性が主体として描かれている傾向は否めません。高校生が指摘する違和感を受け止めて、女性の就労や仕事ぶりをより多く伝え、印象づける広報誌になってほしいと思います。
理髪店チェーンこうのいけ(福岡)
一つの看板を二人が別の面を撮影してくれました。福岡県を中心に展開する理美容院こうのいけの看板です。


白人男性と、少年の写真にそれぞれ「ラーメン もつ鍋 こうのいけ」、「パパ!僕もこうのいけにつれてって!」というキャッチコピーが添えられており、白人の素材写真と言葉の組み合わせが否が応でも目を惹いた、というのが共通の見解です。

美容やファッション業界を中心に、広告写真の中で白人が理想化された消費者像として提示され続ける傾向は、広告産業に内在する人種意識の問題として指摘されています。この広告で使われている男性の写真は、ネクタイが理髪店の赤白青のサインポールに合わせていますが、元の素材写真では薄いグレーの無地で、加工されていることがわかります。この写真は東京・目黒にある男性脱毛サロン、サムライスパのウェブサイトのトップ画像にも使われており、いわゆるビジネスシーンの「デキる男」像のテンプレート表現的な写真と言えます。この男性、福岡でも東京でもよく働いています(写真が)

福岡市長選挙
2022年11月20日に行われた福岡市長選挙では、福岡出身で、SNSを通したインフルエンサーとして活躍する菅本裕子(ゆうこす )が投票を呼びかけるキャンペーンに起用され、注目を集めました。大学で行ったワークショップでも反応を示した人が多く、それぞれのコメントに見方が反映されています。注目を集めたという点では、キャンペーンとして成功していると言えますが、「女性の表象と役割」については色々な意見がありました。







ここで示したワークショップでの事例から明らかなように、それぞれの参加者は短いコメントとして違和感を表明する人もいれば、背景や環境も含めて分析しながら意見を述べる人もいます。関心の持ち方やコミットの仕方は人それぞれに異なりますが、人が示した見解に対して、まずはそれを受け止めること、類似する表現や時期的に前後して作られたものを比較してみることによって、それぞれの表現の見え方や課題も浮かび上がってきます。このようなプロセスを通してお互いの見方を理解し、コミュニケーションをはかるジェンダー表現とメディアリテラシーのワークショップを展開していけたらと思っています。
企画・実施にご興味のある方、団体など、お声がけいただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
