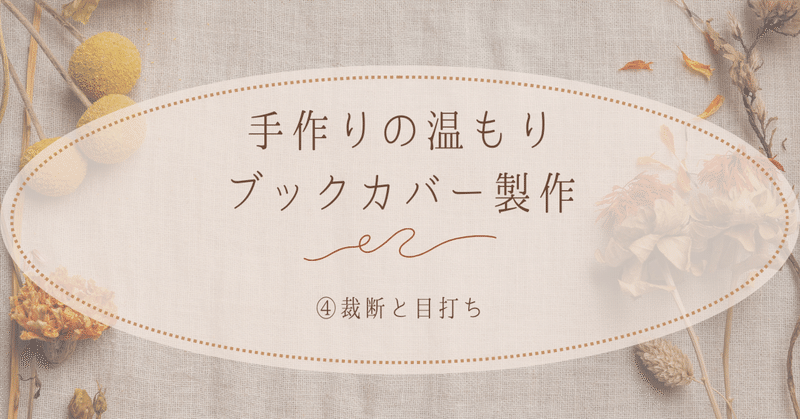
手作りの温もり ブックカバー製作④裁断と目打ち
こんにちは!
「手作りの温もり ブックカバー製作」シリーズ、第四回です。
このシリーズでは、本革ブックカバーを製作する過程を紹介しています。
前回は革の染色と色止めを行いました。
↑前回の記事はこちら
また、間に特別編という名の失敗談の記事も執筆しました。
そちらもぜひご覧ください。
↑特別編はこちら
今回の工程では、前回染色した革を裁断して、いよいよ工作らしい作業に入っていきます。裁断と目打ちの作業を行います。
それではどうぞ、お付き合いくださいませ。
裁断
裁断なんて大層な単語をチョイスしましたが、型紙の通りに革を切り出すだけの作業です。
まず革の上に型紙を乗せて、目打ちという先の尖った道具で外形を写していきます。この作業をけがきと呼びます。

ここではそれほど強く力を入れる必要はありません。
革の表面を見て跡がついているのが確認できる程度でOKです。

1点注意することがあるとすれば、けがきの途中で型紙がズレてしまわないようにすることです。
しっかりと意識して指で押さえるか、あるいは型紙の上に文鎮のような重りを乗せて押さえるのも良いでしょう。
けがきが終わったら、けがき線に沿ってカッターナイフで切り出していきます。本格的にレザークラフトをする方なら革包丁という専用の道具がありますが、私は持っていないので一般的なカッターナイフで裁断しました。
バネホック装着
今回のブックカバーは、閉じひもと本体に「バネホック」と呼ばれるボタンを付けて閉じられるようにします。
服や小物など日常の様々なところで利用されている、押してパチンッと留めるあの金具です。

こちらの金具を、このタイミングで取り付けしておきます。
というのも、この後の工程を進めると少し取り付けが難しくなるためです。
バネホックにはオスパーツとメスパーツがあり、それぞれ2つの金具で構成されています。

革に小さな穴を空け、細長い首部分を穴に通して、革の反対面に出た首部分を専用の打ち台と打ち棒、木槌を使って塑性変形させることで革に金具を固定します。

打ち台の表面には大きさの異なる窪みがあるので、メスパーツを取り付ける際はサイズの合う窪みに金具をセットして打ちます。
打ち台の裏面は平坦になっているので、オスパーツを取り付ける際は裏面を使用します。
金具の首部分を通す穴は、ハトメ抜きという道具と木槌を使って空けます。

ハトメ抜きにも色々な穴の径がありますが、私の場合は金具の首部分がギリギリ通る小さめの穴を空けています。
注意点は、画像にもあるように革の下にゴム板を敷いて打つことです。
ハトメ抜きは刃物なので、なかなかの貫通力があります。
作業板や机を傷付けないためにも、ゴム板は必須です。
目打ち
バネホックを取り付けたら、目打ちをしていきます。
目打ちとは、革に縫い穴を空ける作業です。
革は布と違って分厚く強度があるため、手縫いの場合は針で直接穴を空けながら縫うことができません。事前に糸を通す縫い穴を空けておく必要があるのです。
今回は薄めの革なので、2枚を貼り合わせて一度に穴を空けてしまうのが良さそうです。
まず、縫い合わせるパーツを両面テープで仮止めしておきます。

「両面テープ?そんな接着力で大丈夫か?」
「大丈夫だ。問題ない」
あくまでも仮止めなので、これで大丈夫なのです。
フラグではありませんよ?
仮止めができたら、何となくやすりを使って端を整えます。
その後、ねじ捻という道具を使って、端から3mmのガイドラインを引きます。

ガイドラインを引く理由は二つあります。
目打ちを正確にまっすぐ打つため
ガイドラインの溝に縫い紐を食い込ませ、紐が損耗するのを防ぐため
です。
ガイドラインが引けたら、その上に沿って目打ちをしていきます。

1mm厚の革2枚を貫通するためには、けっこう強めに打たないといけません。
周辺の迷惑にならないように、木槌を使った作業は昼間やりましょう。
この作業では、4本菱目打ちという道具を使っています。
一度に4つの穴を空けることができます。
ですが等間隔に綺麗に穴を空けるためには、こちらの写真のように刃の1本を前の穴に合わせるようにして打ちます。

ところで、しれっと「菱目打ち」と言いましたね。
そうです。日本で一般的に使われる目打ちは、刃が斜めの菱型をしています。
対して刃が真っ直ぐな目打ちもあり、そちらは「平目打ち」や「ヨーロッパ目打ち」と呼ばれるようです。

なぜ菱形なのか、不思議ですよね。
これは私の推察でしかないのですが、菱目打ちで穴を空けて縫うと、縫い線が斜めに掛かるようになるので、見栄えが良くなるからではないでしょうか。
あるいは破壊力学的に、目打ちの端の応力集中を斜めに逃がして破損を防ぐため…という理屈っぽい解釈もできますが、ここでは止めておきましょう!
今回も最後までご覧頂き、ありがとうございました!
次回は目打ちをした穴に糸を通して縫い合わせる「平縫い」の作業について執筆しようと思います。
アドバイスやスキ、コメント等頂けると、大変励みになります。
それではまた、次回もよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
