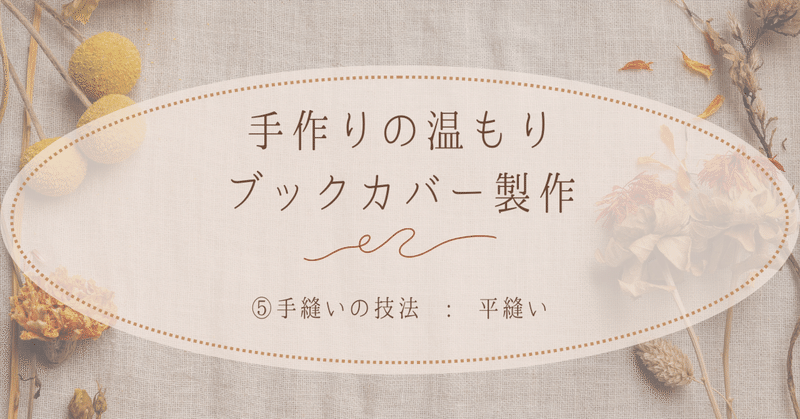
手作りの温もり ブックカバー製作⑤手縫いの技法 : 平縫い
こんにちは!
「手作りの温もり ブックカバー製作」シリーズ、第五回です。
このシリーズでは、本革ブックカバーを製作する過程を紹介しています。
前回の記事では、革の裁断と目打ちについて解説しました。
↑前回の記事はこちら
今回は革細工の花形ともいえる、平縫いの工程を解説していきます。
それではどうぞ、お付き合いくださいませ。
平縫い
前回は両面テープを使って、簡単に革を貼り合わせました。
ですが、あの程度の接着では簡単に剥がれてしまいます。
ボンドを使って接着する方法もありますが、それでもやはり接着力が足りず、すぐに剥がれてしまいます。
なので革材料を貼り合わせた後には、糸を使って縫い合わせる必要があるのです。
前回「目打ち」の作業で空けた穴に糸を通し、縫い合わせていきます。

まず、どれくらいの長さの糸を準備するべきでしょうか?
革の厚みにもよるのですが、一般的には
「(縫い合わせる距離)×4」
くらいの長さがあれば十分です。
今回はロウ付糸という、毛羽立ちを抑えるためにロウを引いてある糸を使用します。ロウというのは、ロウソクで御馴染みのあののロウ(蝋)です。
糸が用意できたら、両端をそれぞれレザークラフト用の針に通します。

これで縫い始める準備ができました。
あとはひと針ひと針縫っていく、地味な作業に入ります。
私の場合、縫い合わせる革を万力ではさみ、表側と裏側を混同しないようにして作業をします。

簡単に手縫いの手順を説明します。
表(左)側にある針から次の縫い穴に通す
通した糸が上になるように糸を引き締める
表側から通した糸と同じ穴に裏(右)側にあった針を通す
表側に出てきた針を次の縫い穴に通す
2~4の工程をひたすら繰り返して、ひと針ずつ丁寧に縫っていきます。
綺麗な縫い線を作るコツは
必ず表側にある針から次の縫い穴に進むこと
引き締める際に上に来る側の糸を間違えないこと
縫い穴の菱形の方向を意識すること
です。
な、何を言っているのかわからねーと思うが、私にも何を言っているのかわからなかった……。
ま、まあこのあたりの手順は慣れるしかないのかもしれません。
詳しくはコメントでお気軽にお問い合わせ頂けたら幸いです。(丸投げ)

可動部など、頻繁に引っ張られる箇所は一度返し縫いをして、強度を高くしておきます。今回の作品では閉じ紐部分、縫い始め、縫い終わりを返し縫いします。

縫い終わりは画像のようにひと針縫い戻して、ライターの火で糸とロウを溶かして焼き留めします。ライターの火力は最小にするのがポイントです。
???「おいおいイーノック、そんなところで留めて大丈夫か?」
ごめんなさい、たぶんベテランさんに見られたら怒られそうです。
ここはもうひと針返し縫いをして、段差がない場所で留めるべきでしたが、時すでに遅し。反省。
という茶番は置いておいて、手順通りに進めると綺麗な縫い線ができます。

このようにして、本体パーツと、両端パーツ、閉じ紐パーツを縫い合わせたらほぼ完成です。

縫い線があるだけで、全体の印象ががらりと変わりますよね。
手縫いならではの革製品の良さだと思います。
あとは次回、仕上げのコバ磨きという作業をして完成にしたいと思います。
今回も最後までご覧頂き、ありがとうございました。
アドバイスやスキ、コメント等頂けると、大変励みになります。
それではまた、次回もよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
