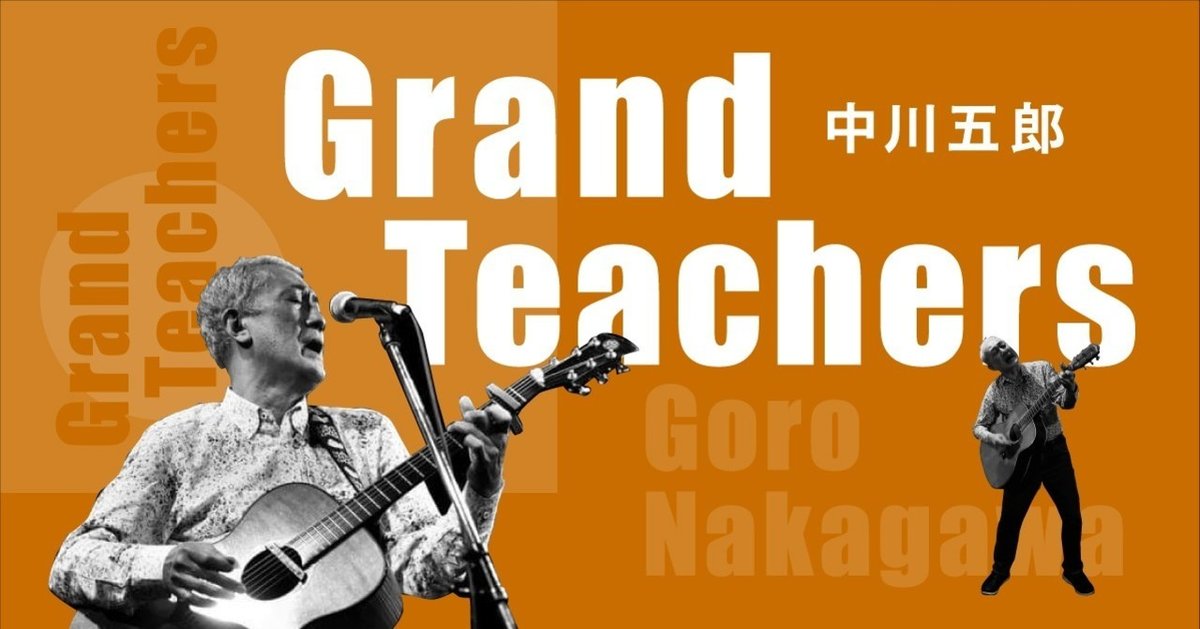
【アーカイヴス#3】境界線のない音楽 *2009年6月
こんにちは、midizine編集部です。これまでミディに関する情報をマガジンとして自社サイトにアップしてきましたが、今後は媒体名を「midizine」と改め、noteより発信していきます。中川五郎氏による連載「Grand Teachers」も引き続き、更新されていきます。
リニューアルに合わせて、中川氏に許可を頂き、これまでの記事を【アーカイブス】として初回から順にnoteに転載していきます。中川氏が10年間かけて発信してきた素晴らしきTeachersたちの音楽を一緒に振り返りませんか。
......................................................................................
6月12日、井の頭線の新代田駅前に新しくできたライブ・ハウス、FEVERにアクロン/ファミリー(AKRON/FAMILY)のライブを見に行った。
ぼくがFEVERに行くのはその日が初めてで、実はこの場所は以前スーパー・マーケットだったが、数年前に閉店となり、その後ずっと空き物件のままだった。それが恐らく今年の春頃から改装工事が始まり、気がつくと何とスーパー・マーケットがライブ・ハウスに変身していたのだ。
その場所がまだスーパーだった頃、新代田は住んでいる場所の近くだったこともあって、ぼくはたまに利用していた。昼間に行って食料品や飲み物を買ったり、下北沢のラ・カーニャで飲んで、深夜酔っ払って歩いて帰る時(確か深夜2時までの営業だったかな)、ふらっと立ち寄ってサンドイッチや助六寿司を買っていたスーパー・マーケットがライブ・ハウスになってしまうとは、何とも奇妙な感じがする。
外観はそのままだが、もちろん中に入るとちゃんとライブ・ハウス用に内装工事がなされていて、ホールとロビーにきちんと分かれていたりして、とても広くて立派なライブ・ハウスになっている。でも「あっ、このあたりは鮮魚が売っていたなあ」、「そうそう、ここは総菜売り場だった」なんて、FEVERの中に入っても、あっちへ行ったりこっちに来たりするたび、スーパー・マーケットの面影を追い求めているぼくなのであった。面影ラッキー・ホール。
アクロン/ファミリーは、2002年にニューヨークはブルックリンで結成されたバンドで、地元ウィリアムズバーグのコーヒー・ハウスを拠点にライブ活動を展開すると共に、ブルックリンのアパートの部屋で録音した音源を、元スワンズのマイケル・ジラが主宰するヤング・ゴッド・レコーズに送り続けていた。
アクロン/ファミリーの音楽を気に入ったジラは、彼らとレコーディング契約を交わし、2005年の春には記念すべきアクロン/ファミリーのデビュー・アルバム『AKRON/FAMILY』がヤング・ゴッド・レコーズからリリースされた。彼らがマイケル・ジラに送り続けた、アルバム数枚分にも及ぶ音源の中から13曲が厳選されていて(YACCA/Inpartmaint inc.が制作した日本流通盤は、ボーナス・トラックが3曲収められて全16曲になっている)、もちろん改めてレコーディングし直すのではなく、最初の音源がそのまま使われている。
ウィキペディアによると、アクロン/ファミリーは、「フォーク・インフルーエンスド・エクスペリメンタル・ロック・バンド」と定義されているが、確かにデビュー・アルバム『AKRON/FAMILY』に耳を傾けると、フォークがその世界の中心にあるように思える。
彼らはアコースティック・ギターをフィンガー・ピッキングで爪弾きながら、高い声で繊細なヴォーカルや美しいスリー・パートのハーモニーを聞かせたりするが、いわゆる伝統的な、あるいはルーツ・ミュージック的なフォークとは似て非なるものだ。そこにエレクトロニクス加工が施されたり、サイケデリックな世界に移行してみたり、実験的なフリー・インプロビゼーションを試みてみたりと、まさに彼らだけのオリジナルな音楽を作り上げている。
そんなわけで彼らの音楽はフリー・フォークと呼ばれたりもしているが、確かに「フォーク・インフルーエンスド・エクスペリメンタル・ロック・バンド」というのは、とりあえずは正鵠を得ていると言うか、彼らの音楽のことを乱暴ではあるが、手っ取り早く説明している言葉なのかもしれない。しかしいずれにしてもジャンル分けやレッテル貼りにこだわりすぎるのは、よくないことだ。
アクロン/ファミリーがスタートした時は、ダナ・ジャンセン、セス・オリンスキー、ライアン・ヴァンダーフーフ、マイルス・シートンの四人組で、ダナがドラムスでマイルスがベース、セスとライアンがギターと、一応基本的な担当楽器は決まっているが、メンバーそれぞれが20種類以上の楽器を演奏できるマルチ・ミュージシャンで、曲によってさまざまな楽器に持ち替えている。
ちなみにデビュー・アルバムでメンバーが演奏している楽器として、ドラムスやベース、ギター以外に、バンジョー、メロディカ、アコーディオン、オルガン、ピアノ、グロッケンシュピール、コンピューター、各種パーカッション楽器、そして各種がらくたなどがクレジットされている。そして四人全員がヴォーカリストだ。
2003年春のデビュー・アルバム以降、アクロン/ファミリーは、2005年秋にマイケル・ジラのエンジェルズ・オブ・ライト(Angels of Light)と曲を半分ずつ収録したスプリット・アルバムの『AKRON/FAMILY and Angels of Light』、2006年秋には彼らが敬愛するジャズ・ドラマーのハミッド・ドレイクをゲストに迎えたミニ・アルバム『Meek Warrior』、2007年秋には『Love Is Simple』、そして今年の5月には最新アルバムの『SET’EM WILD, SET’EM FREE』と、コンスタントに作品を出し続け、作品ごとにその世界はどんどん変化し、進化している。
一口で言うなら、アルバムを重ねるごとにデビュー・アルバムに濃厚だったフォーク的なもの(フォークそのものではない)が表面的には影を潜めるようになり、より実験的でサイケデリックな部分、ファンクやジャズやラテンの部分が前面に出て来るようになった(やっぱりジャンルやスタイルで音楽を説明してしまうなあ。難しい。つらい…)。
また2007年秋、『Love Is Simple』のレコーディングに参加したのを最後に、オリジナル・メンバーのライアン・ヴァンダーフーフがバンドを離れ、仏教徒としての修行をするために中西部へと旅立ち、アクロン/ファミリーは三人組になっている。
最新アルバム『SET’EM FREE, SET’EM WILD』を聴いて、三人組となった今のアクロン/ファミリーがどんな音楽を奏でるのかよくわかっていたが、それにしてもFEVERで見た彼らは、ぼくの予想を遥かに超えて、ファンクでエクスペリメンタルでサイケデリックなロックを聞かせてくれ(ああ、またカテゴライズだ)、ホールを埋め尽くした若者たちは、その場でジャンプしたり、控えめにモッシュしたりして、彼らの音楽に酔いしれていた。
太い二の腕を丸出しにしたベーシストのマイルス・シートンは客席に飛び込んで咆哮したり、天井のパイプにぶら下がったりと、まさにパンク以上にパンクだったが(これもまたカテゴライズしているのか?)、およそ90分間のライブで、アクロン/ファミリーは轟音ファンク、サイケデリック・エキスペリメンタル(何じゃそれは?)一辺倒で攻め続けたのではなく、アコースティック・ギターを弾きながらフォーク調の内省的な歌を聞かせたり、ほとんどアカペラで美しいコーラス・ハーモニーを聞かせたりしてくれた。
最新アルバムのラストに入っている、「去年はきつい一年だった/ずっと長い間/今年はぼくらの年になるだろう」という歌詞を延々と繰り返すだけの「Last Year」は、聴衆みんなとのシング・アウトになったし、確かアンコールの曲は「ぼくらはウディ・ガスリーのアメリカに暮らしたい」という歌詞を、これまた延々と繰り返すものだったように思う。
FEVERでのアクロン/ファミリーのライブは、彼らの前にほかのバンドが二組出て、予定ではアクロン/ファミリーの出番は8時30分過ぎだったが、実際に始まったのは10時頃だった。満員の若者たちに交じって、じっと立って待ち続け、いざライブが始まってもステージは低くてよく見えないと、あとひと月で60歳になる身としてはなかなかつらかった。
しかも近くで見ようと、こちらは早い時間から前の方に立って待っているのに、いざアクロン/ファミリーのステージが始まると、後ろの方からそんなぼくらをかき分けてステージ前へと突進する若者がいたりする。そしてそんな若者にかぎって、大きなリュックを背負っていて、それをまわりのみんなにゴンゴンぶつけながら突進したりするのだ。
ライブだから、そうした無作法な輩に目くじらを立てるつもりは毛頭ないが(そんなことをしていたら小言じいさんになってしまう)、いい音楽を楽しみたいなら、自分のことだけ考えずに、みんなと一緒に楽しもうという気にもうちょっとなってくれたらいいのに(こんなことを言うのも年寄りの証拠?)。
FEVERでのアクロン/ファミリーのライブは、音楽ライターや放送局の人、レコード会社の人など業界関係者を別にすれば、観客のほとんどが二十代、三十代の若者たちで、恐らくぼくがFEVERでフィーバーしていた最年長者だったに違いない。それにしてもこんな面白い音楽を若者たちだけに独占させてしまうのは、ちょっともったいなくはないか。
ジャンルにこだわることと共に、自分の年齢で聴く音楽を決めてしまったりしていると、面白くていい音楽に出会う絶好の機会を逃してしまうことになる。そんな凝り固まった音楽の聴き方をしている人が絶対に出会うことのできないバンドのひとつ、それがアクロン/ファミリーで、そうした頭の固い、固定観念でがちがちになっている聞き手をしなやかに拒絶しているところに、アクロン/ファミリーのすごさがあるのだとぼくは思う。
中川五郎
1949年、大阪生まれ。60年代半ばからアメリカのフォーク・ソングの影響を受けて、曲を作ったり歌ったりし始め、68年に「受験生のブルース」や「主婦のブルース」を発表。
70年代に入ってからは音楽に関する文章や歌詞の対訳などが活動も始める。90年代に入ってからは小説の執筆やチャールズ・ブコウスキーの小説などさまざまな翻訳も行っている。
最新アルバムは2017年の『どうぞ裸になって下さい』(コスモス・レコード)。著書にエッセイ集『七十年目の風に吹かれ』(平凡社)、小説『渋谷公園通り』、『ロメオ塾』、訳書にブコウスキーの小説『詩人と女たち』、『くそったれ!少年時代』、ハニフ・クレイシの小説『ぼくは静かに揺れ動く』、『ボブ・ディラン全詩集』などがある。
1990年代の半ば頃から、活動の中心を歌うことに戻し、新しい曲を作りつつ、日本各地でライブを行なっている。
中川五郎HP
https://goronakagawa.com/index.html
midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。
