
見誤るな 直視せよ 中国の真実 矢吹晋著作選集完結記念 特別インタビュー
今日の中国に関する素朴な疑問に、矢吹さんが答えます。
聞き手は山下茂さんです。
なおこのインタビューは『チャイナウオッチ 矢吹晋著作選集 第五巻 電脳社会主義』別冊付録として制作されました。

2023年6月完結
四六判並製函入 本体各2700円
ISBN 978-4-89642-675-5
中国は経済成長を続けられるか
――これからの中国、大丈夫か? まず、そのことをお聞きしたいと思います。アメリカを中心とする経済封じ込め、とくに半導体関係の禁輸措置の影響をどうみるか。国内的にも成長が減速し、労働力不足・高齢化という厳しい状況を迎えています。果たして中国は持ちこたえることができるのか、という疑問です。
矢吹 現状、少々厳しいということは否定できません。しかし歴史を振り返ってみれば、ニクソン訪中の1972年当時、中国は本当に弱かった。国内は毛沢東の文革派と周恩来を中心とする脱文革派が対立し、それを周恩来がまとめて日本との国交正常化を果たしますが、当時は「貧乏を我慢」しながらソ連と対決し、一方でアメリカとは朝鮮戦争以来の対立が続いていました。あの時代は、相当な危機でした。
それに比べたら、いま中国は超大国で仲間もたくさんいる。危機のレベルがまったく違います。ただし、アメリカによる封じ込めを受ける前に比べれば、「厳しい」でしょう。「世界の工場として、部品を仕入れ、組み立て、全世界に売る」ことで、EUとアメリカから湯水のようにお金が入ってきていましたから。しかし、トランプ、バイデンの締め付けによって発生している今回の危機がどの程度かというと、「中程度」。ニクソンや田中角栄を迎えた1971、72年当時の何も持っていなかった中国と比べたら、重大な危機とはいえません。
――半導体等の「封じ込め」によって、中国の「経済成長エンジン」がかからなくなる危険性は?
矢吹 アメリカはそれを企図していますが、事実上、不可能でしょう。半導体については、一桁前半ナノの最先端半導体の生産が難しいという話であって、一桁後半のナノの半導体は自力で生産できています。台湾のTSMCや韓国のサムスンに比べたら負けますが、中国経済にとっては、最先端分野で負けても構わない。当分、成長は止まりません、巨大な国内市場があるのですから。最先端の半導体不足が問題になるのは、スマートフォンと防衛だけ。その点でも、アメリカを追い抜くのが遅くなるだけのことで、中国にとっては小さな問題です。
たとえば、スマホについて。ファーウェイという会社に対してアメリカが半導体の供給をやめたとき、ファーウェイはすぐにスマホから手を引きました。ほぼすべての製品に輸入半導体を使っていたのですから、もはやファーウェイは全部アウト……と日本の評論家たちは言っています。しかし、これは、まちがい。そもそもファーウェイにはスマホの独自開発力はないのです。得意なのは、もっと大規模な通信分野。5Gの通信基地などは別に最先端の半導体がなくてもできる。日本がいま熊本で作ろうとしているのは旧式の三級品ですが、通常の通信であれば十分に間に合います。それと同等のものを中国は国産できる。アメリカが盛んに喧伝している「制裁」というのは、中国の最先端技術開発の遅れを象徴的に叩いているだけの話です。
中国は、もともと持久戦に強い国です。朝鮮戦争以後、経済的に封じ込められても、香港からこっそり機械を購入したり……、様々な手段を用いて生き延びてきた経験がある。逆境に対して、猛烈に打たれ強い。
いま習近平政権に対して、反スパイ法等々で市民の自由を奪っていると周辺国は盛んに非難しています。なぜそのようなことをやるのか。なぜ中国国内から大きな反発が出ないのか。そこを考えるべきです。中国は自分たちが生き抜くためにやっている。そのことを、百年以上に及ぶ辛い経験から、国民が熟知しているのです。

――急速に進む高齢化、それに伴う生産労働人口の減少については?
矢吹 いわゆる「先老未富」の問題ですよね。国民一人当たりのGDPがまだ先進国並みの水準になっていないのに、国全体が老いてしまう。
いま中国が必死に進めている産業の高付加価値化が、実現できるか。そのことに関係してくると思います。これまでのような「世界の組み立て工場」から脱却して、技術開発力を高めて、近未来社会の核となるテクノロジー分野で主導権を握ることができるかどうか。これが間に合えば、労働集約型産業構造つまり安価で大量の労働力に頼る社会を卒業できる。高齢化社会が到来しても、乗り越えることができるでしょう。
少子化問題について、一人っ子政策をやめた後も出生率が上がらないことが指摘されています。特に都会に住む夫婦が二人目の子供を作ることに消極的です。ますます激しさを増す競争社会の中では、わが子を少しでもいい学校に入れておく必要があって、塾などの教育費に多額のお金を注ぎ込むようになった。もう一人産みなさいと言われても、そんな余裕はない。そこで習近平は、都市部の塾をことごとく廃業させました。
こうした政策を打ち出すことの最大の効果は、国民の意識の中に、政府が本気で警告を発しているのだと認知させることです。かつては子供の数を減らすことが国策でしたが、今度は出生率を上げることが重大な国策だという認識が、国民的に広がっていく。そして、政府の指導に従うことが自分たちの国が生き延びる道だと納得していく。そういう流れになるでしょうね。
覇権国家になろうという野望はあるのか
――中国は、覇権国家になるのでしょうか?
矢吹 中国がたとえ世界一の経済大国になったとしても、アメリカ・EUのような強い経済圏が既に存在するのですから、圧倒的な世界一にはなれません。アメリカによる一極支配構造から多極化した世界に変わるだけです。私は2020年7月に『コロナ後の世界は中国一強か』(花伝社)を刊行しました。〈中国一強〉とは、多極化した世界における〈相対的な世界一〉のことであって、世界を力で押さえつけることはできません。
――アメリカとの対立状態は、今後も続くと?
矢吹 アメリカは歴史の浅い国で、建国以来、敗戦の経験がありません。敗れ方を知らない。一例をあげます。トランプが大統領選挙で敗れると、彼の支持者たちは敗北を認めず、国会議事堂になだれ込む暴挙に出ました。負け方を知らない国民性の典型例でしょう。
アメリカという国が敗れ方を知るには、時間がかかります。中国経済が圧倒的に強くなり、誰の目から見てもアメリカの巻き返しは不可能……と納得できるまでの長い過渡期を経てはじめて、再びアメリカと中国が互いを補完しあう協調の時代が訪れるのではないか。私はこの関係を「チャイメリカ」と呼んでいます。
――アジア・アフリカ・中東・中南米と中国との関係は、今後さらに発展すると思われますか?
矢吹 ますます多極化の進む世界の中で、最も経済力のある、影響力を持つ国として、各国間の理解と和解のために動くことを期待しています。
なぜか? 中国は、欧米帝国主義の侵略に悩まされ続けてきました。1840年のアヘン戦争から数えても、二〇世紀半ばの第二次世界大戦終了まで、百年以上も。そして現在も「帝国主義の落とし子=台湾」との統一を果たせないままです。中国は、たとえ世界一強い国になっても、これまでの植民地・従属国だった時代の体験を忘れることはないでしょうね。
その一方で、アメリカやイギリス、そして日本が、かつての自分たちの帝国主義的侵略を棚に上げて、「民主主義」や「人権」を押し付けながら圧力をかけ続けている。中国側に立って考えてみれば、まさしく笑止です。
欧米諸国は、中国にお説教するまえに反省が必要です。自国内の有色民族に医療保険を適用できているか。コロナ患者を治療したのか。自国内の移民難民や有色人労働者にどのような待遇を与えてきたか。コロナ禍は、そのほころびを白日のもとにさらしました。「揺りかごから墓場まで」と謳う福祉国家は、いまやそれを支える経済力を失って、貧すれば鈍する事態に陥っています。
――これまで、欧米諸国には「自由」「民主主義」などの共通の価値観があるとされてきました。中国はその価値観を共有しないまま進み続けると?
矢吹 「自由」「民主主義」という大義のもとで、かつて植民地化が進められたという事実も直視すべきです。それらの大義自体に問題があるとは言いません。しかし、その大義のもとで何があったか。何が行なわれてきたのか。そこが問題です。敗戦後の日本は、それらの大義を良しとして受け入れてきましたが、旧植民地の国々は大義なんて眉唾ものだ……とわかっている。G7側が「民主主義」や「人権」などと騒いでみたところで、G7こそ世界中を植民地化して人々を奴隷的に使いまくったではないか……と考えています。
これからの世界で共通の価値となりうるのは、「反植民地主義」や「反帝国主義」でしょうね。かつて支配される側にいた国々が覚醒して立ち上がると、G7など経済力ではたちうちできません。ここ一〇年に関していえば、G7の経済成長の合計より中国一国の成長分のほうが大きい。そのことを理解する必要があります。
大航海時代以来500年の長きにわたって、西洋が世界を支配するという時代が続いてきました。それが、いま、ひっくり返ろうとしている。先進国が世界を指導する時代が終わって、新興国が主導権を握る時代がはじまろうとしています。その中心に、中国がいる。そのことを理解しないと、大局を見誤る。
ウクライナ情勢、台湾有事問題はどうなる?
――世界の軍事的な緊張や紛争を、「親分」として鎮める。そんなことを中国は目指していると?
矢吹 少なくとも、やろうとしているでしょうね。ウクライナ戦争でも、そのことを周辺国が中国に期待していることは明らかです。アメリカは戦争を煽っているだけで、もはや仲裁能力はありません。一方、習近平はウクライナ大統領ゼレンスキーと電話会談(2023年4月26日、新華社報道)して動き出しています。かといって、軍事力で脅かそうとしているわけではない。
日本人の中国に対する根本的な思い違いは、覇権国アメリカと同じことを中国がやると決めつけていることです。日本がアメリカに従属しているのは事実ですが、中国は日本を従属させようとは考えていません。日本人はアメリカという枠組みの中からしかものを考えていない。日本人自身の問題です。
――多極化すると、世界は不安定になるのでは?
矢吹 必ずしもそうとは限らないと思います。アメリカは第二次大戦後に、経済的にはブレトンウッズ体制によって、また強大な軍事力によって、唯一の覇権国となりました。アメリカ一強の時代です。しかし、至る所にほころびが出ています。ベトナム、アフガニスタン、アラブ中東……様々なことをやった挙句に、ドルの力が相当に弱くなってきました。安定した国際通貨だったドルが不安定要因になっている。これがいまや世界の常識です。日本はドル・ベースでしかものを考えないから、鈍感になってしまっているだけです。
たとえば、直近の例をあげると、中国がイランとサウジアラビアの和解を取り持ったこと。この経緯を踏まえて、石油の人民元決済をフランスが認めました。中東の石油は、一部、人民元で取り引きされるようになっています。ほかにも、アメリカの圧力でドルが使えないので、やむをえず人民元で取り引きをしている国や地域が多くあります。たとえばロシアにものを売る場合、ロシアにはドルがないので、人民元で決済する。ロシアとの関係が強いインドとも、主として人民元を使っています。ブラジルも同様です。しかし、人民元は従来の国際通貨ドルの代わりにはなりません。それには、膨大なコストがかかるからです。中国が人民元を使いたいと言っているのではなくて、ドルが頼りにならないから、なるべく当事国の通貨で取り引きしたい。そういうことです。
――今後、中国がより強大になって、習近平がロシア・プーチンによるウクライナ侵攻のような行動に出ることは? ありえないことでしょうか。
矢吹 その可能性は少ないとみていいでしょう。習近平は、プーチンのウクライナ侵攻を批判しています。
ただし、ウクライナの場合、話はちょっと複雑です。
ウクライナが、ロシア連邦から離脱して主権国家を主張していることについて、これを他の主権国家がそうした場合と同様に考えていいのか? その問題です。
クリミアという港湾都市とそこに続くドンバス工業地帯は、かつてソ連がドイツ(NATO)と対峙する前線でした。だからこそ、航空母艦基地を作り、核兵器の基地を作り、工業都市に整備されました。ウクライナを警戒するためではなくて、ドイツ(NATO)と戦う最前線だからこそ力を入れていたのです。
また、ソ連首相のフルシチョフはウクライナ人だったので、あくまでもソ連邦の一部としてクリミア周辺の主権を認めました。いわゆる主権国家の主権とはちょっと意味合いが違います。括弧付きの「主権」と考えたほうがいい。そこを混同して、プーチンは主権国家ウクライナを侵略しているという非難だけが、世界中に飛び交っています。しかし、ウクライナの「主権」には留保が必要だということは、当事者であるEUの人たちはわかっています。日本人は、わかっていない。主権国家に対する侵略だと決めつけて、ゼレンスキーを国会に呼んで、プーチンと喧嘩している。いかに日本が国際情勢音痴か。日本の安全保障を考えたら、プーチンと喧嘩できるはずがありません。国境の問題でも、石油の問題でも。ロシアが核兵器を大量に保有する国連常任理事国だということを忘れている。本当に、危険です。
――台湾問題について。アメリカが日本を正面に立たせて肩代わりさせようとしている……という見方も?

矢吹 そもそも日本に、そんな能力はありません。政治的にもできないでしょう。「台湾有事」というのは、アメリカのまったくの妄想と考えるべきだと思います。
つまり、世界の半導体市場の六割を握っている台湾TSMCを中国に取られたらたいへんだという被害妄想です。しかし、先ほども触れましたように、最先端の半導体が作れなくなるというだけで、TSMCを取らなくても中国には大きな半導体工場が少なくとも数個あります。中国はTSMCを取る気など、まったくありません。アメリカがいちばん恐れているのは、中国にTSMCを抑えられると、アメリカの防衛システムは崩壊し、最先端の飛行機やミサイルが飛ばなくなることです。
アメリカはなぜ、そんな妄想を抱くのか? もはや、かつてのように、アメリカ国内で最先端の半導体を生産できないからです。専門労働者の質も劣化している。新たにアリゾナに最新の生産拠点を作る計画もありますが、はたして間に合うかどうか。
つまり、中国には武力で台湾を奪い取る必要などありません。台湾有事など、ありえない。ただしアメリカが妄想的な危機感から中国叩きに躍起になっているので、何らかの偶発的きっかけで衝突するリスクもある。現にペロシの台湾訪問など様々な形で挑発していますから。危機を未然に防ごうとお互いに言明しているとしても、アクシデントが起こる可能性はあるでしょうね。
中国は資本主義国家になるのか
――胡錦濤政権時代までは、中国はいずれ資本主義国になると西側諸国は思っていました。しかし、ならなかった。習近平中国を、いったいどう捉えればいい?
矢吹 国家が統制する資本主義です。国家資本主義あるいは官僚資本主義と言ってもいいですね。資本主義は、中国で、現実に機能している。しかしマーケットは習近平政権がコントロールする。そういうことです。
たとえば、アリババ問題。サイトを作って物販しているだけの間は、誰も文句を言いません。が、アリババがアリペイという形で消費者金融を始めると、政府が動きます。アリペイは一か月間無利子でしたから、銀行はアウトです。銀行のクレジットカードなど誰も使わなくなって、あっという間に銀行秩序は壊れる。それで、ドーン! 習近平政権はアリペイ金融を抑えました。政府として当たり前のことをしただけです。しかし日本のジャーナリズムは事情をきちん伝えません。金融の専門家もアメリカ目線で悪口を言ってばかりいます。
――中国は、欧米式の資本主義を信じていない?
矢吹 資本主義はいま暴走しています。狂い始めている。2008年のリーマン・ショックがその象徴です。
1991年の12月にソ連が崩壊して、資本主義陣営は勝利宣言をしました。アメリカが唯一の超大国になって、それからはやりたい放題です。そこで、何が起こったか。それまで資本主義の暴走を食い止めるために設けられてきた諸規制の撤廃です。中でもいちばん重要なのが「グラス・スティーガル法」の廃止でした。
世界恐慌というバブル崩壊直後に制定された法律で、商業銀行と投資銀行を厳格に区別して、銀行が預金を勝手に企業投資に回すことを禁じる。世界恐慌という資本の暴走を経験して、その教訓を法制化したものです。当時、新しいソ連という社会主義国が、五か年計画で経済を順調に発展させていました。これに対抗するため、資本主義を健全に保つ必要があった。
ところが20世紀の末にソ連が消えてなくなると、もう規制は不要とばかり、クリントン政権時代の1999年に廃止されます。同じような規制が次々と取り払われて、金融の自由化が徹底されます。こうして、実体経済を離れてマネーがマネーを生んでいく、資本が自己増殖する時代がやってきたのです。たとえば金融派生商品というものもできて、低所得者でも家が買えるようになる。こんなマジックは、遠からず馬脚を現します。それがリーマン・ショックでした。
しかし、世界恐慌のときと違って、アメリカは反省しません。富の格差は広がる一方で、国内はいまや分裂状態になりつつあります。2023年のシリコンバレー銀行の破綻やクレディ・スイスの売却は、資本主義の危機が一向に克服されていないことを改めて証明しました。アメリカの資本主義は、もはや自分をコントロールできません。このことを直視すれば、ああはなりたくないと中国が考えるのも当然ではないでしょうか。
――農村と都市の格差は、続くのでしょうか?
矢吹 まだまだ時間がかかるでしょうね。その格差をなくそうと最初に動いたのは、毛沢東です。しかし、たいへんでした。時間もかかります。少しずつでも底上げしていくしかないのだと思います。
ただし、農村戸籍と都市戸籍という格差問題は、すでに、事実上、ほとんどないと言っていいと思います。
北京、上海、天津などの大都市はこれ以上人口を増やしたくないから、親が市民であれば住民票を認めますが、外から入ってくる人は認めません。農村出身者だからダメだという理由ではなくて、都市があまりにも大きくなりすぎたという問題です。
都市と農村ではまだ明らかに差がありますが、では農村の人が本当に大都市に住みたいと思っているかというと、必ずしもそうではないようです。地方で農業をやっている人々と、大都会で情報化社会にさらされながら生きている人々では、生活そのものが大きく異なります。むしろ中都市を増やして、そこで農村出身者を受け入れる。そういう方向で動いているようです。
習近平政権は何を目指しているのか
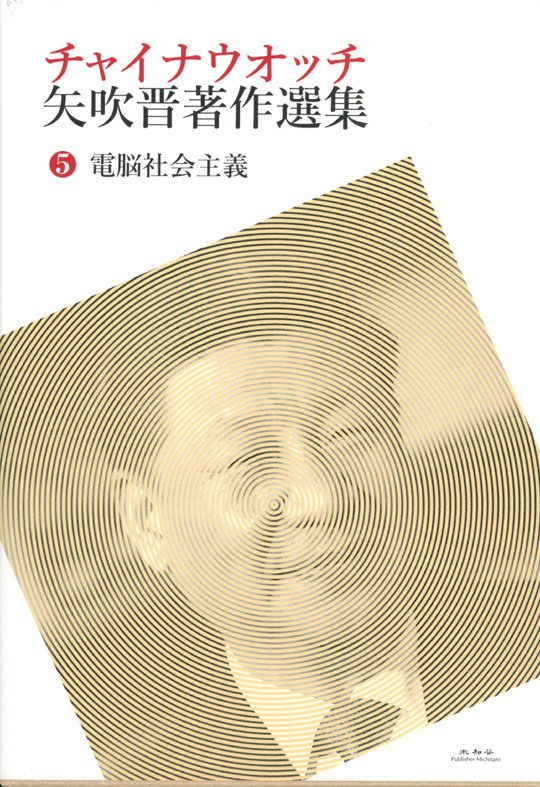
――第三期習近平政権は、どうなっていくと?
矢吹 それは、これからの中国をウオッチングしていかないと明言できません。
おそらく、習近平の頭にあるのは、鄧小平です。鄧小平時代に中国は経済的に豊かになり、外国と自由に付き合えるようになった。いま、「さらに前へ、その次へ」という欲求が国民的に高じてきています。鄧小平は、「韜光養晦」に徹しました。爪を隠して、低姿勢で付き合え、と。その間に、体力がつきます。そうすると、やはりナショナリズムが浮上してきます。習近平時代を迎えて、そろそろアメリカや日本に「はいはい」と従わなくてもいいんじゃないか、少しは文句を言おう、と。しかし、まだまだ弱いということを彼らはよく知っています。半導体にしても弱いし、軍事力についても弱い。
ただし、アジアにおける軍事力に限って言えば、中国は既に自信を持っています。もし台湾有事が現実化したら、中国は台湾に武力行使するのではなくて、沖縄の米軍基地に中距離ミサイルを撃ち込むでしょう。台湾に米軍基地はありません。そうなったら「THE END」です。アメリカが応援に駆けつけるといったって、何日も何十日もかかるのですから。戦場になるのは台湾ではなく沖縄の方です。そんなことが許されるのか。
10年ほど前に、アメリカの軍事シンクタンク(ランドコーポレーション)が台湾海峡で戦争が起こったら中国に勝てないと報告しています。中国は軍事的にはそこまで強くなっていますが、台湾に対して軍事力を発動したら、中国の負けです。だって、同胞ですからね。戦争によって奪還するなんて、ありえないでしょう。同胞という大前提が崩れます。反米感情や反日感情はあるけれども、だからといってこれを実行してしまったら、習近平は失脚します。わかっているからやらないのです。
――2027年に習近平の第三期が終わります。台湾問題を解決して、歴史的な業績として残したい……という思いが、習近平にはあるのでしょうか?
矢吹 それはないと思います。香港返還の場合は租借期限が迫っていました。本当は鄧小平だって取り戻すか否か、だいぶ悩んだはずです。ここで決断をしないと無期限の租借になるから、返そう、取り戻そう……。それが鄧小平とサッチャー英首相との会談でした。
香港の自由が奪われた……と盛んに報道されましたが、2019年のデモではアメリカの星条旗を掲げて「香港の独立」を叫ぶ集団まで出ました。こうなると、中国としては鎮圧せざるを得ない。北海道や九州、四国が他国の国旗を掲げて独立を叫ぶようなものですから。
そもそも香港は、日本の占領地でした。1945年の敗戦のとき、すかさずイギリスが占領したんです。もちろん中華民国政府も取り戻そうとしましたが、間一髪、間に合わなかった。そのことをほとんどの日本人が忘れています。「分裂」こそ、中国にとって最も避けなければならない事態なんです。そのことを知るべきです。
台湾に武力行使してしまったら、2400万人の同胞が不満分子になるでしょう。そのうち大多数は外国に亡命するかもしれない。そうなったら、中国は全世界に敵を作ることになる。とんでもない愚策です。
――習近平はウクライナ情勢をどう捉えていますか?
矢吹 中国とウクライナは、良好な関係です。ソ連が潰れたとき、中国は真っ先にウクライナと交渉して協定を結びます。ウクライナは核をロシアに返還すること、中国はウクライナに対して核は絶対使わないことを約束して、軍事を含む経済協力関係をスタートさせました。まず、中国はウクライナ製の航空母艦を買います。ミグ戦闘機の強力なエンジンもウクライナが作っています。中国が軍事強国になるためにウクライナが果たした役割は、とても大きい。
中国は、ロシアとウクライナ双方と話し合える関係にあります。膠着状態の打開可能なポジションにいる。先般、習近平がプーチンと会い、さらに習近平がゼレンスキーと電話で会談したのは、調停工作の第一歩です。これから中国を中心とした調停工作が本格的に始まります。ウクライナ情勢以外にも、中国が調停しないと収まらない局面が、今後は増えていくでしょうね。
中国共産党には見えない文化がある?

――中国の政治中枢には、外からはなかなかうかがい知れない部分があるように思えます。
矢吹 そこは、やっぱり難しい。難しいというより、そこが、あの共産党という組織の凄さでもあります。
鄧小平が復活したときも、私たちはビックリしました。かつては副総理としてナンバー2の実権を握っていたのに、文革で散々に叩かれたわけですから。あのとき、失脚した鄧小平を保護するように動いたのは、周恩来です。毛沢東に「これからはやっぱり鄧小平を使ったほうがいい」と進言しています。
朱鎔基も、同様です。朱鎔基は精華大学の学生会主席の秀才で、国家計画委員会(日本でいう財務省のような組織)のエリート党員でしたが、一九五四年の高崗事件(権力闘争)の巻き添えを食って干されます。しかしラッキーなことに、地方には飛ばされず、北京で英語教師を続けます。それから30年ほど経った1980年に、50代の朱鎔基がいきなり上海市書記に抜擢されて、すぐ総理になる。こんな人事、日本では絶対にありえません。鄧小平が抜擢したわけですが、朱鎔基を支える人脈も党内にあったということでしょう。
――共産党政権の奥深くで、密かに働く、意志あるいは知といったものがあるのでしょうね。
矢吹 ありますね。中国という国の伝統……といってもいいでしょうね。たとえば李白や白居易などの例をみても、一度政争に巻き込まれて、敗れて飛ばされて、しかし、また誰かに呼び戻されて返り咲く。使える人材なら誰かがしっかりと覚えていて、忘れられることはない。こんな例はいくらでもあります。集団的、集合的な知恵とでも呼ぶほかない。その「誰か」は、中国の官僚世界特有の人脈ということでしょうが、それが文化的伝統となって連綿と伝えられている。いまの中国共産党の中にも、確かに同じような文化があるのだと思います。
ただし、軍人の場合は、こうはいきません。まず、復活できない。宋代以来(元帝国は例外として)、中国では軍人は文人よりずっと軽く見られていました。こういう言葉があります。「好鉄不打釘 好人不当兵」。「よい鉄は釘には使わず、よい人間は兵士にしない」という意味です。中国では、政治組織上も文人の方が軍人より上です。だから中国では、政権運営に軍人が携わることは、まずない。中国共産党政権でも、まったく同様です。軍は、組織上も共産党の下に付属しています。
これから中国とどう付き合うべきか
――日本は、今後、中国とどう付き合っていけばいい?
矢吹 安倍晋三政権および安倍なき安倍路線を歩む岸田文雄政権は、1945年以来最強の親米路線を追求しています。しかし、成功する可能性は、きわめて少ないと言わざるをえません。中国は国連常任理事国の一つとして、国際政治的にも大国となり、軍事的にも東アジア世界では米軍を上回っています。核兵器を保有するこのような大国=中国を封じ込めるという発想は、妄想というしかありません。アメリカにも、アメリカ+日本にも、そんなことは不可能です。
歴史を冷静に俯瞰してみれば、中華経済圏に加わる以外に、もはや選択の余地はありません。ただし、これは中国に従属する道ではなく、あくまでも良き協調関係を築く道です。太平洋戦争後にアメリカは日本を従属させましたが、中国は日本の従属を求めません。中国は歴史的にも日本を従属させたことは一度もないのです。
――実現可能で、もっとも賢明な、中国という国への対し方は、どうあるべきだと?
矢吹 田中角栄と周恩来との共同声明の精神に立ち返り、日中不再戦の精神を再確認して、日本が〈アジアの孤児〉にならない選択を行うこと。これが大切です。
繰り返しますが、そもそもG7は旧帝国主義国連合で、アジアの大部分の国々の旧敵です。日本がG7と価値観の共有を語るのは、アジア諸国に敵対することを意味する。少なくとも、アジア諸国の人々は、そのように受け止めます。そのことを忘れないでいただきたい。
日本の安全保障にとって最も肝要なのは、朝鮮半島および中国大陸との関係、台湾海峡両岸との関係、そして大国ロシアとの関係です。このことを忘れて、G7の立場から安全保障を語るのは空論です。この空論に日本の政治が支配されている現状は、とてつもなく危うい。
いま、韓国、台湾などかつて日本が植民地にした国々が、一人当たりGDPで日本を上回っています。この逆転の意味を真剣に考えるべきです。欧米諸国とその旧植民地だった国々の間では、まだ逆転していません。
日本は、史上もっとも遅れて登場した最後の帝国主義国だったのです。しかも、朝鮮、台湾、中国などのもともと高い文化を持った国々を植民地化してしまった。
明治維新以降、いわゆる「脱亜入欧論」が一世を風靡しました。アジアを捨てて、欧米に仲間入りせよ。いわゆる進歩的インテリたちがこの脱亜入欧路線を突っ走り、先を争ってヨーロッパの真似をする。それが、国民的な支持を集める。似たり寄ったりのアジアの国同士で無理やり植民地化を進めて、日本だけが立派に近代化できた……なんて威張っていたんです。いまこそ、この明治維新以降の歴史を直視して、猛省すべきでしょう。アジア近代史において、日本という国が無理を重ねてきてしまったことのしっぺ返しを、いま、受けている。
――尖閣問題以来、10年以上こじれにこじれてきた両国の対立感情を解きほぐすことはできるのでしょうか?
矢吹 ここまで来たら、無理でしょうね。残念ながら。
ともあれ、われわれ老齢のシニア世代は、日中関係の歴史を直視しながら、根気強く協調発展の道を築いていくしかないように思います。
もっと若い世代、いわゆるZ世代には、期待したい。中国人も日本人も、若い世代はもう文革のことなんか知りませんし、アニメや漫画、ポップスなどのサブカル分野では、日本好き・中国好きが根強く育っています。情報も人流も物流もますます盛んになっていく時代ですから、バイアスがかかっていない若い世代には期待が持てます。どんどん交流してください!
なぜ、中国が、大事なのか

――矢吹さんは、若くして中国ウオッチングの道を志されます。なぜ、中国が大事だと思われたのですか?
矢吹 たとえば『源氏物語』です。国文学の分野でどれだけ問題にされているのかよく知りませんが、この長大な物語のいたるところに白居易をはじめとする漢籍の知識と教養が埋め込まれています。驚くべきボリュームで。
日本という国はずーっと「和魂漢才」でやってきたんです。中国という優れた大国の隣にあって、徹底的に中国の文化、政治を学びながら、上手につきあってきた。遣隋使や遣唐使を派遣したり、足利義満は「私を王に任命してください」なんて頼んだりして、とにかくうまく付き合ってきた。しかし、明治になって和魂漢才から和魂洋才に掌を返すように切り替える。まだ、和魂洋才と言い始めて、たかだか100年です。2000年近くも和魂漢才を貫いてきたのに……。いまこそ、和魂漢才の精神に回帰すべきでしょうね。
私が大学に入った1958年当時、日中関係は冷え切っていました。平和条約は結ばれないまま、法的には戦争状態が続いていたんです。私の周辺の左翼学生たちは世界革命を主張していましたが、私は日中復交という民族的課題を先行させるべきだと考えていました。
当時、中国では毛沢東の提唱する「人民公社」が作られていて、もちろん、その中国的な社会主義像にも関心を抱きました。あまりにも急進的、野心的な試みで、まもなく挫折しましたが、この理念は失敗しても繰り返し試行するに値するものだと私は確信しました。条件の整わない、理念的な社会主義は失敗しますが、現実的な条件さえ整えば、成功できるはずです。
――50年以上にわたって、中国政治のウオッチングを続けてきた、その原動力は? その醍醐味は何だと?
矢吹 劇的なんですよ。とにかく、ドラマチック。たとえば、善人だったはずの林彪が突然悪人に変身する。かと思えば、悪人・鄧小平が突如復活する。この政治劇は、一度観察し始めたら、面白くてやめられません。
鄧小平路線がようやく軌道に乗り、江沢民と胡錦濤時代に経済成長が顕著な成績を上げたと思ったら、腐敗と汚職が蔓延してしまう。
2022年12月に、習近平がこんなことを言ったようです。「江沢民・胡錦濤時代に太ったネズミ(汚職で肥え太った官僚)が溢れて、赤い猫(紅毛=毛沢東主義者)が消えた」。資本主義の病に誰もが蝕まれてしまったから、ここで一石を投じる、と。風説の形をとっていますが、おそらく習近平自身のメッセージでしょうね。習近平は、鄧小平以来すっかり定着したかにみえた集団指導体制をガラッと一強体制に変えてしまいました。
まったく、シェイクスピアも顔負けです。日本の戦後史と比べても、登場人物たちのスケールも破格で、筋書きも読めない。劇的としか言いようがありません。
もちろん、今後も予断を許しません。習近平政権の周辺にも、欧米に牙をむくのは早過ぎる、欧米との協調路線に戻るべきだという意見も根強くある。彼らが何かの拍子で勢いを得たら、習近平政権だっていつ転ぶかわからない。そういうことです。
――「チャイナウオッチ」をする際に、矢吹さんは、とくに何を見逃すまいと心がけているのでしょうか?
矢吹 経済学の景気循環論に、①短期循環、②中期循環、③長期サイクルという三つの大きな枠組があります。この考え方は、中国をウオッチングする際に役に立ちます。①の短期循環は、五か年計画期内の変化です。②の中期循環は、総書記の任期。二期10年単位。江沢民、胡錦濤時代……など。③の長期サイクルは、毛沢東時代、鄧小平時代、習近平時代……などの数十年単位の長期スパンです。いま注目しなければいけないのは、鄧小平時代から習近平時代への大きなうねりです。
日中関係にこの長期スパンを当てはめてみると、明治以来続いてきた脱亜論というアジア蔑視の時代が、いま中国や韓国の躍進によって乗り越えられようとしている。そう考えるべきでしょう。若い世代は別としても、多くの日本人は西洋崇拝・アジア蔑視の感情に汚染され、その結果、アジアの覚醒、中国の躍進の可能性を直視できないままでいます。
――最後にもう一度、お聞きします。これから中国と稔りある付き合いをするには、何が大切なのか?
矢吹 中国はわけがわからない、異質の国だ。われわれ日本とはまったく違う……。そういう見方をずっとしてきたわけですよね、とくに戦後の日本人は。遠くから、他人事のように眺めて、批判する。
しかし、いま、中国という国が直面しているのは、人類社会全体の問題だと考えるべきです。
いま世界は、資本主義の限界、市場経済の行き詰まりという大問題に直面しています。市場は有限で、巨額の投資マネーが暴走し、格差は拡大する一方です。環境問題も緊迫している。この難局をどう乗り越えるか。二十一世紀の世界的な大テーマです。中国は、この大問題に、巨大な国家として向き合っている。共産党政権による社会主義国家ではありますが、鄧小平以降、グローバルな市場経済にどっぷりつかることで成長してきたので、現代資本主義の諸問題は中国にとっても切実です。
もちろん、私たち日本人にとっても、切実です。
隣国の異質な側面ばかりに目を向けて敵視するのではなくて、自分たちの問題として、いま世界が直面する大難題に取り組む代表者として、ウオッチングしていただきたい。それができたら、ミスリードも少なくなる。
私は「電脳社会主義」という言葉を使っています。習近平政権がビッグデータとAIを駆使して経済・社会の動きをつかんでいく手法は、マネーの暴走や富の偏在を食い止める一つの有効な手段になるのではないか。楽観的だといわれるかもしれませんが、グローバルに世界を見回してみる限り、ほかにこれぞという有効な手立てが見当たりません。理想や希望を捨てることなく人類社会の将来を見据えようとするなら、現代中国の取り組みとその行く末は、ますます重要になってくるでしょう。冷静にウオッチングを続けていきたいと思います。
――ありがとうございました。
(2023年5月8日 聞き手=山下 茂)

著者の略歴
やぶきすすむ
1938年福島県郡山市生まれ。県立安積高校在席時に朝河貫一を知る。1958年東京大学教養学部に入学し、第二外国語として中国語を学ぶ。1962年東京大学経済学部卒業。東洋経済新報社記者となり、石橋湛山の謦咳に接する。1967年アジア経済研究所研究員、1971~1973年シンガポール南洋大学客員研究員、香港大学客員研究員。1976年横浜市立大学助教授・教授を経て、2004年横浜市立大学名誉教授。現在、21世紀中国総研ディレクター、公益財団法人東洋文庫研究員、朝河貫一博士顕彰協会会長。
著書は単著だけでも40書を超え、共著・編著を合わせると70書をゆうに超える。ここでは本シリーズ「チャイナウオッチ」からははずれる朝河貫一の英文著作を編訳した『ポーツマスから消された男――朝河貫一の日露戦争論』(東信堂、2002年)、『入来文書』(柏書房、2005年)、『大化改新』(同上、2006年)、『朝河貫一比較封建制論集』(同上、2007年)、『中世日本の土地と社会』(同上、2015年)、『明治小史』(『横浜市立大学論叢』、2019年)の6書、朝河を主題とする『朝河貫一とその時代』(花伝社、2007年)、『日本の発見――朝河貫一と歴史学』(同上、2008年)、『天皇制と日本史――朝河貫一から学ぶ』(集広舎、2021年)の3書を挙げておきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
