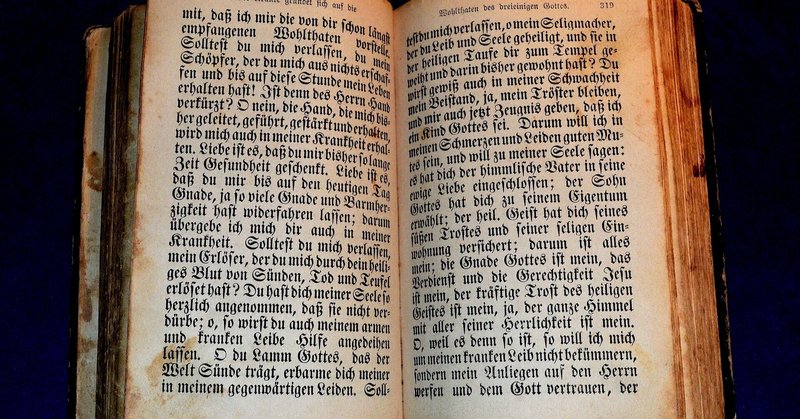
落研の落語の覚え方
学生時代の部活動で僕が必死で取り組んだ、落語。オーストラリアに来てからも日本語放送のラジオだったりシェアハウスだったりで披露させていただいた。今後これで生計を立てていくつもりは特にないが、落語も僕と人をつなげてくれたものの一つ。生涯こいつが体から完全に消失してしまうということはなさそうだ。これからもよろしく。最近新しい街に越してきたのだが、実は来月にも公演予定が入っていたりする。果たしてどうなることやら、楽しみである。
落語を披露するためには、短いもので10分ほど、長いもので30分ほどある噺(話)の台詞を全て覚えて、サラで言えるような状態にしなくてはならない。カンペを読みながらなんてのはもってのほかだ。中には『リーディング落語』とやらを披露する三遊亭円丈師匠などの例外もいらっしゃったりするけどね(笑)あれはあれで面白い。それは置いといて、
どっかの資料によると、プロの落語家の方々が落語の噺を覚える際には、実際に師匠が目の前で区切り区切りで演じてくださるのを真似ながら覚える、いわゆる「口伝え」といった方法が主流らしい。何度か稽古を重ねて、教えていただいた師匠から許可が出て初めてお客さんの前で噺を演じることができる、のだそうだ。
一方落語研究会、通称落研はというと、多くの人が台本を用いてネタを覚える傾向があると思われる。プロの落語家の方で台本を見て覚えるといった話は僕は聞いたことがないが、落研連中はまず、噺を覚えるのに台本を作る。これはプロの方がやっている噺の音源、つまりテープやCD、動画などを見たり聴いたりしてノートに書いたり、ワードだったりに打ち込んだりして作成する。
そして時折、各種落語の噺の速記などがウェブサイトに載っていたりもする。特に上方落語に限定されるが、この「世紀末亭」と呼ばれるサイトは、関西の落研界隈では有名なサイトだ。
中には「楽だから」という理由で自分で台本を作成せず、これらの速記をそのまま台本として使用する落研の輩がいるが、正直これはオススメしない。それはなぜか。
落語は、そもそもお客さんに笑ってもらう芸能である。その笑わせるために最も必要な落語の基盤となる部分は、口調、間、トーンといった音としての要素である。つまりオリジナルの音源を聴き込むことが大切であって、台本はあくまで覚えるためのヘルプでしかない。既に間や口調が出来上がっている人は、速記だけで完成度の高い落語を披露することも可能なのだが(マイナーな噺の中には音源が存在せず、速記のみ残っているものもある)、落語始めたての人が音を聞かずに台本のみで覚えてしまっては、出来上がったものはかなり陳腐になってしまう可能性が高い。ただ、たまたま上記に挙げた速記と自分が聴いていた音源が同じものであれば、それは非常にラッキーだ。そのまま台本として起用できるだろう。
また、音源を参考にする際にもプロのものではなく、先輩がやっていたものの録画などから噺を覚える人もいるらしいが、これもあまりよろしくない。学生の音源で噺を覚えてしまうと、プロの間とは違う、笑いが取りづらい間で噺を再現してしまうリスクが高まる上に、言葉遣いや所作など他の部分も間違ってしまい、演じるクオリティが総合的に下がる場合がある。しかしながら「お、この演出いいなぁ」みたいな発見も先輩方含む学生の動画を見ている時に感じることもあったりするのも事実。噺を覚える正規の音源として用いるのは望ましくないものの、参考資料として使うのは良いかもしれない。
とまあクドクドと誰が得するんだといった情報を並べただけの記事となってしまったが、たまにはこういうのもいんじゃない。将来どんな知識が役に立つかは分からんけんのう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
