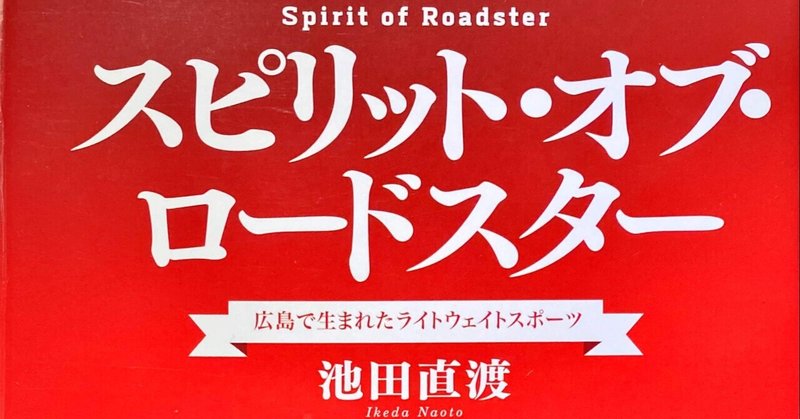
『スピリット・オブ・ロードスター』ノート
池田直渡著
プレジデント社
前回のカメラに続いて、また趣味のことを書くことにする。車に興味がない方は〝スキ〟だけ押して、読み飛ばしてください(われながら勝手なヤツ)。
いままで学生時代を含め、何台車を買って乗ったか、記憶を辿ってみたら9台乗り継いできた。初めての車は大学の先輩から買った18万円のスバル1300GSSという水平対向エンジン・ツインキャブ(いまや死語だ)のよく回るエンジンで、4000回転まで上げてクラッチをつなぐと、ローで60㎞/hまで出た。エンジンの構造上、高回転に上げても振動がほとんどなく、素晴らしいエンジンで、さすが前身が航空機メーカーだけあった。ただ、いまみたいにブレーキアシストなどはなく、ブレーキの効きがよくなかったので、ヒヤッとしたことが何度かあった。
乗った車9台のうち、スバルが1台と三菱が1台、フォードが1台、そして昨年買ったマツダ以外の5台は日産車。なぜか日産車のフィーリングが好きで、そうなってしまった。サニーGX5、セフィーロツーリング、グロリアグランツーリスモ、スカイラインクーペ350GT、X-トレイル・ブラックXトリーマーX(いま気付いたが何故こんなにXが付くんだ? これは今も現役)。
そして本題のマツダ・ロードスターND(幌式・2シーター)――私のプロフィルの写真に半分くらい写っている――昨年10月に意を決して購入したオープンのライトウエイトスポーツカーだ。これはスカイラインクーペ350GTを下取りに出して買った。スカイラインは17年間も乗っていたので、さすがに目に見えないガタが来ていて、燃費も悪くなり、車検も修理代を入れたら軽自動車が買えるくらいの金額だったので、思い切って買い換えた。スカイラインクーペはスタイルも好きで、ノーマルエンジンだったが、ヘビーウエイトの車体をよく引っ張り、伊豆のくねくね山道を楽しく走った。
ロードスターは、スカイラインなどのような車種の固有名詞ではなく、本来はオープンモデルの一つの分類だ。ほかにはオープンモデルの呼び名にはスパイダー、ガブリオレ、コンバーチブルなど、国によって、またクローズ状態を基本とするかしないかによって、同じオープンカーでも呼び名が違うようだ。
さて、マツダ・ロードスターは普通の車と較べたら、不便この上ない車だ。トランクはまあまあの容量はあるが、車内は狭く、グローブボックスもない。助手席に人を乗せると、バッグを置く場所もない(後席がありませんから)。ドリンクホルダーもペットボトルが取りにくい場所にある。助手席の膝元に一個は移動できるが、助手席に座ったら邪魔になる。
乗るにあたって不便はあるが、自分が乗る最後の車はオープンカーと決めていたので、迷わず買ってしまった。
乗ってわかったことだが、冬もシートヒーターと暖房を入れると、オープンでも快適だ。なんとなくイメージは〝夏〟みたいな(映画の観過ぎ?)のがあったので、これは大きな発見だった。12月の気温5℃くらいの晴れた日に秩父方面を走っていた時、信号待ちで隣に並んだ車が窓を開けて、「寒くないんですかぁ?」と聞かれた。
オープンで走っていたので、誰でもそう思うだろうが、「いいえ、とっても快適なんですぅ」と答えたら驚いていた。それとすれ違うロードスターのドライバーが例外なく手を振ってくれるので、「何?」と思ったら、どうもそのような仲間意識の発露のような仕草がロードスター乗りの間で暗黙の了解のようだ(それとも冬にオープンで走っているよというサインか?)。その後も、ロードスターとすれ違ったが、もちろん私もぎこちなく手を振り返した。
それと逆に、夏の日差しが強い時は頭のてっぺんが焼けるほどなので、帽子が必須。それにお構いなく四方から光が入ってくるので、サングラスも必要だ。エアコンを使ってもいいが、私が初めて乗った頃の車はクーラーやエアコンなんてオプションでもないし、ひたすら三角窓を開けて風を取り入れて走っていた。だから、いまもエアコンは夏の雨の日以外は使わない。
車体も長さが4メートルを切るし(ドアを開けるとすぐ後ろに後輪がある)、車体も軽いので、1500ccのノーマルエンジンでもワインディングロードを非常に楽しく走れる。それに燃費がとてもよい。
と、書いてきて、取り上げたこの本の中身のことを思い出して、この車の開発者の狙った意図通りに出来ている車だと改めて感心した次第だ。
車づくりのコンセプト――スタイル、エンジン、軽量化、運転して楽しい車を作り上げてきた設計上の苦労話(作り手はそれも楽しんでいる)は興味が尽きない。
実はそろそろ買い換えようかなと思っていた時に大きな書店の趣味のコーナーでこの本を見つけて買って読んだことが、購入の最後の一押しになったことは間違いない。
書名通り車づくりの職人の魂が籠もった本である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
