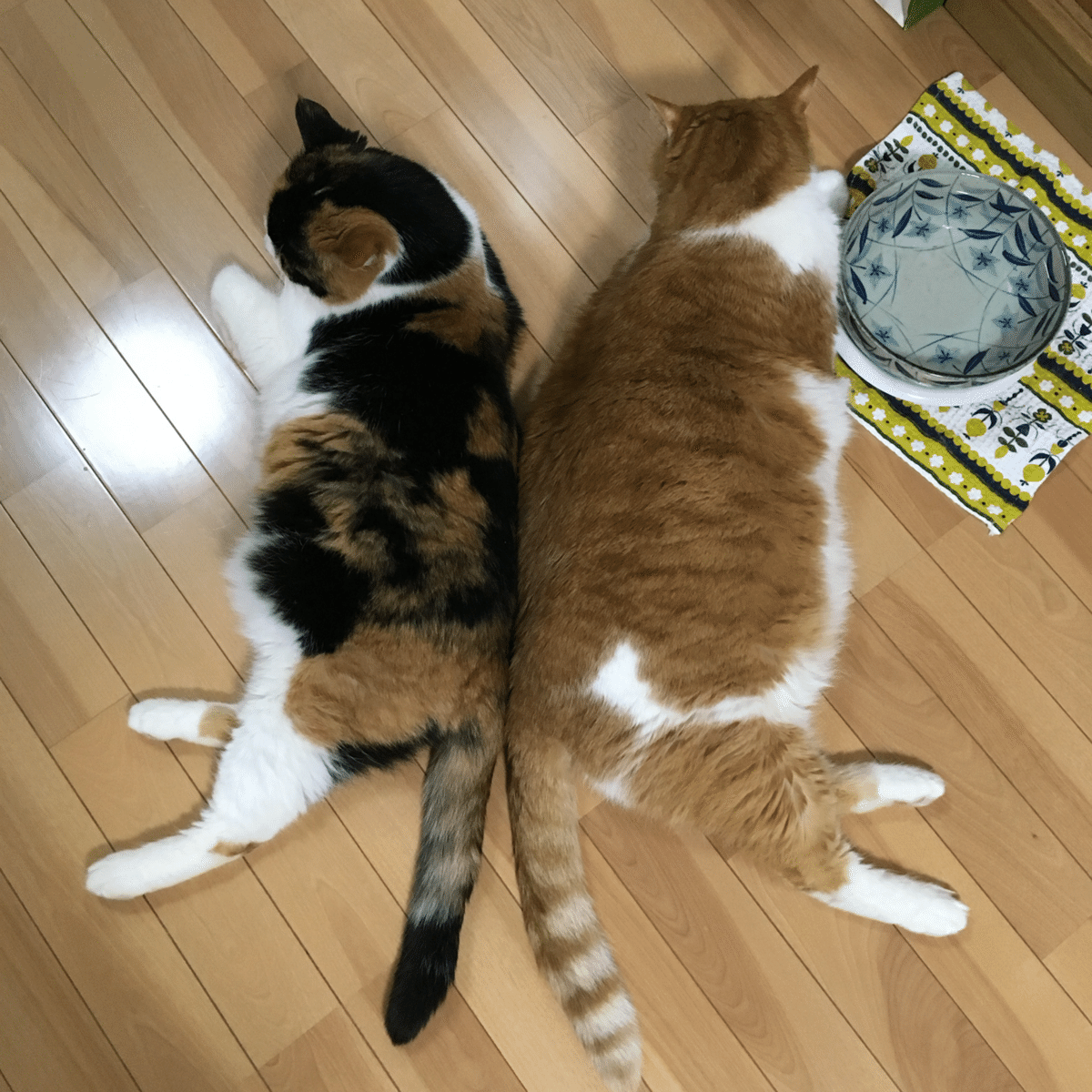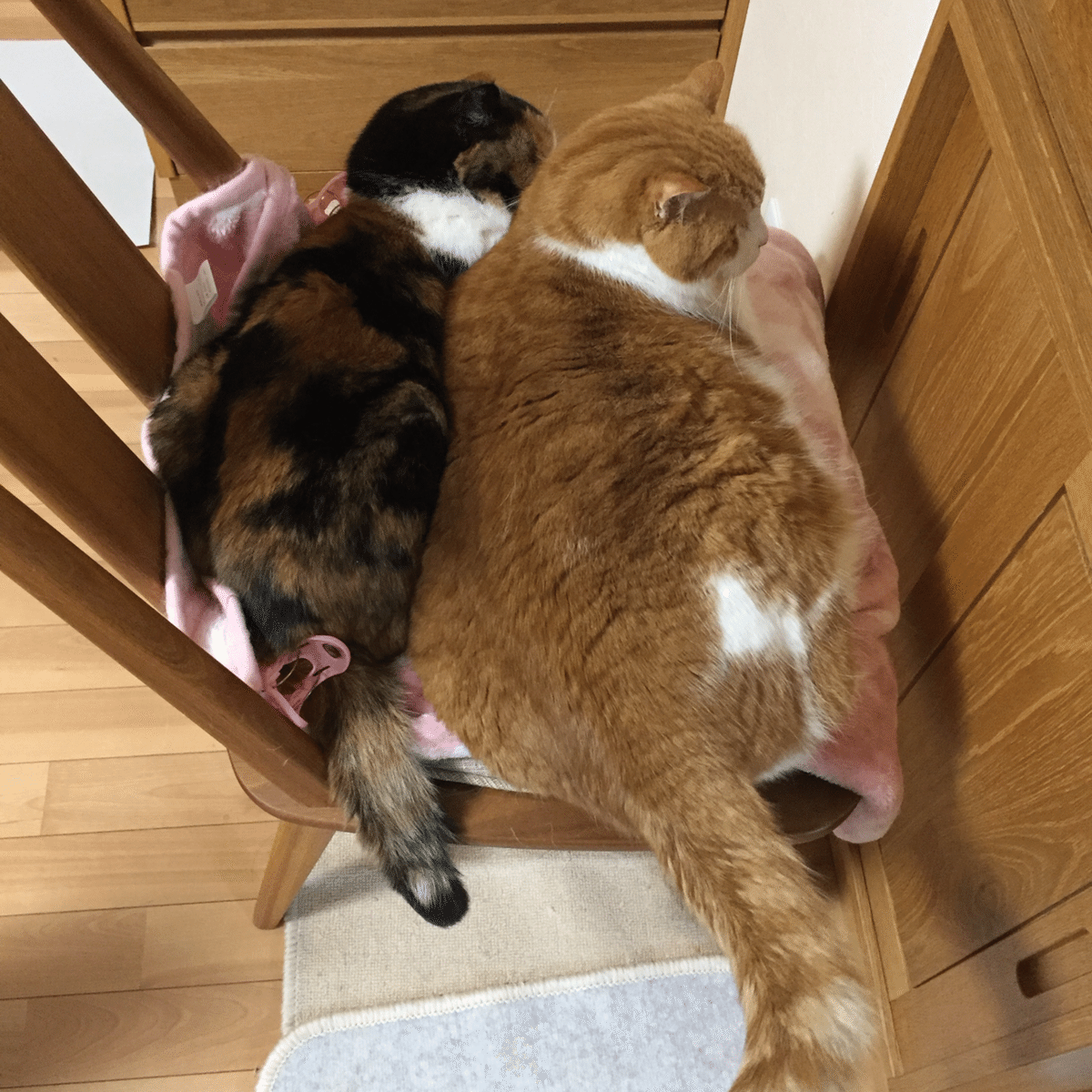さみしき秋の夜
なにかに言いながらも、関西にも秋は着実にやって来ているようである。
夜遅くに駅から帰る途中、いつもと違う道を歩く。秋の乾いた空気は酔った私を闇に誘っているようである。そんな季節がやって来たのである。
私の手の届かない離れた塀の上から、駐車場の隅っこから、私にそそぐ視線を感じる。彼ら彼女らもこんな季節を嬉しく思うのであろう。
こんな出会いが私は嬉しい。
猫たちの夜遊びの季節もやって来たのである。
そして気がつけば2年前、愛猫ブウニャンを自転車の籠に乗せて病院に通った道にいた。公園の入口の邪魔な車止めに腰を掛け、ベンチの陰に佇む白猫をただ見やる。猫は友を待っているのか、猫は何を考えているのだろうか。考えても分かることのないことをしばらく考えあきらめ立ち上がる。私に気付く白猫は薄目で私を眺めている。
ああ、猫よ、白猫よ、できれば手を出し撫でてやりたい。出来れば抱いて会話をしたい。
でもそれをしてはいけない。彼ら彼女らには彼ら彼女らの世界がある。覚悟が無ければ中途半端なことはできないのである。
夜のこんな時間が待ち遠しい季節になった。
今まで犬と猫との生活が長かった。共に生活をすれば責任はあり自分の生活に制限が生まれたりする。きっかけはさまざまであろうがその時点でともに生活していれば人間中心の社会では弱者の犬たち、猫たちの生活を成り立たせてやる義務が人間に生まれる。
そんな世界で生きることを彼ら彼女らはそれをどう思っているんだろう。私が子どもの頃の昭和30年、40年代にはまだ野良犬がいた。山や野原を駆け巡っているわけじゃなくて、町をうろつくのにどうして野良犬なんだろうと不思議に思ったことがある。どうやって生き抜いたんだろうかと今になって気になる。でもあんがい幸せを感じて生きていたんじゃないかと思ったりする。
あまり好きな言葉じゃないが愛玩動物なんて言葉がある。可愛いから犬や猫を手元に置いたことは過去に一度も無かった。経緯はさまざまで、たまたま共に生活をするようになった犬や猫であった。一緒にいれば情は移り、当たり前に可愛いという感情は湧いてくる。でも努めて共にいる空間作りだけをした。先に逝く小さな彼ら彼女たちの姿を見るのが辛いからである。気が付けば、そこにいる。そんな付き合いをする仲で、ある日おさらばの日がやって来れば良いと思っていた。でも一度もそんな別れは無かった。
だから、もう一緒に生活できないと思っている。最後まで共に生きることができないのは無責任だし、私が悲しみに暮れたように私が先に逝ってしまえば、彼ら彼女らだって同じように悲しみに暮れるに違いない。だからもう一緒に生活できないと思っている。
遅い帰りに猫たちの生態を観察し、帰りがなお遅くなる日がこれから増える。不審者に間違われないようにこれからの夜を楽しもうと思うが、やはりそんな秋の夜はさみしいものである。