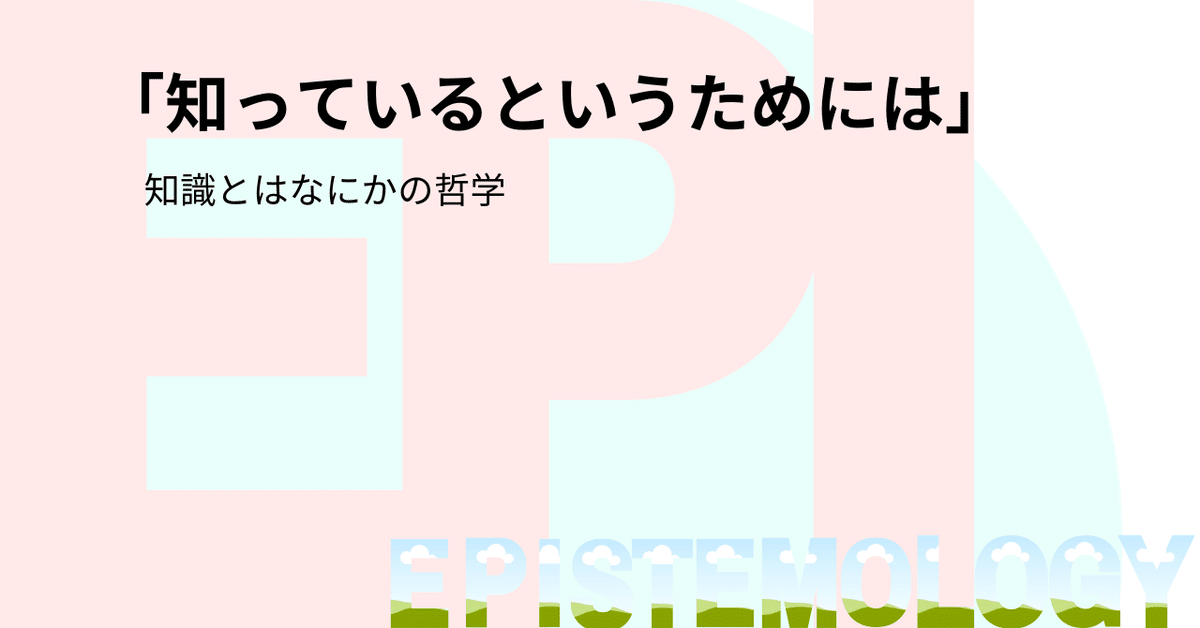
「知っている」というためには
私たちは色々なことを知っている。あるいは色んなことを知らないままだ。だけどそもそもこの「知っている」とはどういうことなんだろう?
言い換えれば何かを「知っている」ためにはどのような条件が必要なんだろう?
このような「知識とはなにか?」を問う哲学分野を認識論という。以下では知識の条件について見ていこう。
知識の標準分析(JTB)
知識とはなにか?という問いに対して標準的に与えられた条件のことをJTB(Justified true belief(正当化された真なる信念))という。
aがpを知っている ↔
(1)pが真である(p)
(2)aがpを信じている(Bap)
(3)aがpと信じるのが正当化される(JBap)
これはプラトン『テアイテトス』にて示された。『テアイテトス』はまさに知識とはなにか?についての哲学書である。そしてその中で、『真実なる思いなしに言論を加えたものが知識』(岩波,201)という文があり、JTBもそこから来ている*¹。
JTBは知識の必要十分条件か?
JTB、すなわち正当化された真なる信念が知識の定義というのはプラトンからの伝統的なものということを見てきた。
では本当にこれが必要かつ十分な条件となっているのだろうか?
命題: {J,T,B}⇆知識
(1){J,T,B}→知識
(2)知識→{J,T,B}
(1)JTBは知識の十分条件
まず、JTBを満たす状況の例を出す。その状況で知識でないような状況があるかを調べる。(JTBを満たしているのに「知らない」といえる状況があれば反例になる)
・「ルーブル美術館に『モナリザ』がある」と私は思っている。(Bap,aは私)
・なぜそう思っているかというと、高校の美術の先生に聞いた/公式サイトで展示品を調べた/実際にルーブル美術館で見た/etc…からだ。(JBap)
・実際にルーブル美術館には本物の『モナリザ』がある。(p)
上の例はJTBを満たしている。このとき「「私はルーブル美術館に『モナリザ』があると知らない」というのは極めて不自然だ。つまり、「私はルーブル美術館に『モナリザ』があるのを知っている」。したがって、少なくともこの例において知識はJTBの十分条件である。
(2)知識はJTBの必要条件
まず、確実に「知っている」と言える知識の例を出す。それがJTBを満たすかどうかを調べる。(「知っている」といえるにも関わらずJTBを満たしていない事例があれば反例になる)
「私はソクラテスが毒杯を仰いで死んだのを知っている」(知識の例)
i)実際にソクラテスは毒杯を仰ぎ死んだ。(p)
ii)「ソクラテスは毒杯を仰いで死んだ」と私は思っている。(Bap,aは私)
iii)私はソクラテスが毒杯を仰ぎ死んだことを伝えるプラトンの著作『パイドン』を読んだため、ii)と思うようになった。(JBap)
少なくとも「私はソクラテスが毒杯を煽って死んだことを知っている」という場合、JTBを満たしている。したがって、この知識の例に関しては、知識はJTBの必要条件であるといえる。
そしてこの(1),(2)に対する反例が見つからない限りJTBは知識にとって必要十分条件である。
ゲティア問題
20世紀に入ってからもプラトンにより提示された知識のJTB説は目立った反例も見つからず、必要十分条件であると思われてきた。しかし、1963年、その反例は突如、$${\textit{ Is justified true belief knowledge? }}$$という3ページ程度の短い論文により示された。
その内容はJTBを満たすにも関わらず実際には「知らない」事例があり得るというもので、これは知識のJTB説(の十分条件)に対して投げかけられた問いだった。この論文から始まる一連の知識の条件に関する議論を論文著者E.ゲティアからとってゲティア問題という。
ゲティア問題の構造は次のものだ;
pは真でない.(¬p)
しかし、aはpと思っている(Bap),またその信念は正当化されうる.(JBap)
qはpから正しく推論される命題.(p→q)
したがってqも正当化された信念である.(JBaq)
そして偶然qは真である.(q)
事例を一つだそう:
スミスとジョーンズは会社の面接に来た。どちらかが採用されるのだが、スミスはジョーンズが気に入られているのを見て「ジョーンズが採用される」と思った.(JBsp)また,ジョーンズが面接前に100¢のコインを上着に仕舞っているのを見ていた。ここから「採用されて、上着に100¢の入った人がいる」という正しい推論をした.(q)またこれは正当化された信念から出た推論なので,qも正当化された信念である(JBsq)
ところで,実は採用されたのはスミスの方だった.(¬p)さらにスミスも忘れていたのだが偶然にも自分の上着にもちょうど100¢が入っていた。したがって、スミスの「採用されるのは上着に100¢の入った人だ」という正当化された信念は真である.(q)*²
しかし、スミスは自分が採用されるのを知らない!

上の事例は確かにJTBを満たしているにも関わらずそれを「知らない」ことの事例である。ゲティア問題において重要なのは私たちは偶然真であるような事実を知っているとはふつう言わないという示唆だ。
終わりに
ゲティア問題をどのように解決していくかについてはそれこそ本が一冊出せるくらいに議論されている領域なのでここでは深入りしない。*³そのため知識についてどのような条件があるか考えるのは難しいかもしれないがどんな事例がゲティア問題として考えられるか、また別の角度からJTBに反論できないかを考えてみるのも面白いかもしれない。
脚注
*1;ちなみに『テアイテトス』においてソクラテスは知識について様々な条件を挙げさせては反例を出し否定する。そして『真なる思いなしに言論の加わってできるものでもない』(210a)と続ける。つまり『テアイテトス』の中でも知識の必要十分な条件は示されていないのだ。
*2;途中わざと先に説明したゲティア問題の構造に合わせて論理式を省略した。
(1)"ジョーンズが採用される"(Pj, P_は「_は採用される」,jはジョーンズ)
(2)"ジョーンズの上着には100¢が入っている"(Rj, R_は「_の上着に100¢入っている」)
(1),(2)よりPj∧Rj(ジョーンズは採用され、かつ上着に100¢入っている)
したがって、∃x(Px∧Rx)(採用され、かつ上着に100¢入っている人がいる)‥‥これを命題qとおく
(1),(2)はともに正当化された信念なのでJBa(Pj∧Rj),したがってJBa(∃x(Px∧Rx)),すなわちJBaq(qは正当化された信念)
ところでRs(sはスミス)かつPsであった((Ps∧Rs)は真)
そして(Ps∧Rs)から∃x(Px∧Rx)は導出可能である。(qは真)
*3;ゲティア問題は主に知識のJTB説におけるJ,すなわち"正当化"に関して疑問を呈したものだ。したがってその解決のためには信念が"正当化される"というものがどのような条件のもとで行われるべきかが問われることになる。
例えば偽なる命題pから正当化された信念を導いてはいけないとするもの。正当化は事実との間に因果関係がなければならないとするもの(因果理論)。知識というのは通常の事態であればpと信じるのがふつうな状況でも、なにか異常事態が起きてpが偽だと分かれば修正を求められるものだとするもの(条件法理論)などがある。参考図書としては上枝美典,『現代認識論入門』(2020)や戸田山和久,『知識の哲学』(2002)などが網羅的なようだ(まだ読んでいない)
参考文献
プラトン,訳 田中美知太郎,『テアイテトス』,岩波文庫,(1966)
E.Gettier, "Is justified true belief knowledge?", (1963)
細川 雄一郎,「ゲティア反例の多領域様相論理による分析を通じて」,科学基礎論研究47号1巻,p. 15-34,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kisoron/47/1/47_15/_pdf/-char/ja
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
