
植民地支配の記憶をどう承認・継承するか~大嶋えり子「旧植民地を記憶する:フランス政府による〈アルジェリアの記憶〉の承認をめぐる政治 」(吉田書店)
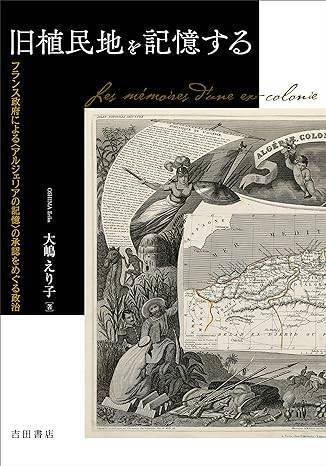
著者は現在慶應義塾大学経済学部准教授で、専門はフランス政治~特に移民、ポスト・コロニアル問題など。これは著者の早稲田大学大学院での博士論文を加筆修正の上で出版されたもの。この研究者のことはSNS上でたまたま知ったが、この研究成果は私の日頃の関心領域にまさに「ドンピシャ」だったので、非常に興味深く読んだ。そして大変いい勉強になった。
アルジェリアは1830年から1962年独立までの約130年間フランスによる植民地支配を受けたが、その歴史をどう受け止め評価し国家間相互でその認識を共有するかについては、まだまだ「共通認識」が確定できてはいない。1990年代の冷戦終結以降~世界的に「過去の支配の歴史の見直し要求」が高まる中で、フランスの各政権・大統領や自治体がどういう姿勢・対応を取って来たのか、フランス社会はアルジェリア独立戦争を経て大量に帰国して来た「帰還者」らをどのように迎えその後の経緯はどうだったのか~この研究ではそうした流れを詳細に論じている。
私には第二次大戦中ヴィシー政権下でのナチスドイツのホロコーストへの加担という(分かりやすい)罪過に比べて、アルジェリア支配の加害性については関係する「アクター」がより複雑で、その評価も各層で対立構造を生み出すという特性が印象的だった。ピエ・ノワールと呼ばれるフランスを初めとした欧州系アルジェリア植民者たち、現地のイスラム・アラブ系住民~独立戦争ではアルジェリア民族解放戦線(FLN)、フランス側として戦ったアルジェリア人「ハルキ」~基本的に1990年代まではアルジェリア植民地支配の加害性を認める世論はほぼ形成されず、ピエ・ノワールら帰還者の名誉・功績を称える風潮が長く続いてきた。「アルジェリア戦争法」や「帰還者法」も、独立戦争を(フランス側で)戦った兵士やその後のフランス本土への帰還者に感謝の意を表明し、補償を与えるものであった。そして「ハルキ」たちの承認・包摂のあいまいさ。
フランスは共和国としての国家原則で、「共同体」としてではなくあくまで「個人」として共和国と繋がり「出自に関わらず皆平等」という理念に沿った者がフランス人~と定義するが、移民「統合」を目指す中でえてして置き去りにされるマイノリティの民族的アイデンティティ。90年代以降、フランス政府や自治体が<アルジェリアの記憶>を承認したのは、あくまでそれと地続きの関係にある移民統合と国民的結合のためであった。
一方、南仏・スペインとの国境付近(フランス領カタルーニャ)の中心都市ペルピニャン市での引揚者団体などへの配慮を色濃く反映した(つまりはアルジェリア植民地支配を肯定的に捉えた)「資料センター」開設と、そうした状況を生み出したフランス南部に多いピエ・ノワール(帰還者)の存在や、フランスが国家としては容認しないとしている特定の集団による「共同体主義」が、ここでは反故にされている側面。フランスの多くの地方自治体での首長選出が議会によって行われるため、良くも悪くも議会と首長が密接な関係を築きやすく「長期政権」を容易にしていること~ペルピニャン市でも父子2代にわたる「支援者への利益供与型政治」が長く続いてきたことが大きな要因。
そうした反面、フランス国家としてのアルジェリア植民地支配時の過酷な収奪・虐待・拷問などの加害責任については、それを国家として認めるまでにかなりの時間を要している。2003年のジャック・シラク大統領のアルジェリア議会での演説でも、かつての歴史の暗部に言及しつつもその責任所在は曖昧なまま。2007年のニコラ・サルコジは「過去の過ちと犯罪」に言及したが2012年のオランド大統領に至って初めて具体的な不正義の事例に言及している。そしてマクロン現大統領になってようやく「人道に対する罪」として植民地支配を捉えるようになるが、「法的責任」には決して踏み込まない。これは21世紀になってのオランダ・ベルギー・ドイツなど他の欧州諸国と同じである。
本著で著者は「責任と和解」について、まずは旧宗主国が加害の責任を認めること&謝罪を通じて<記憶の承認>と旧植民地国との和解を目指しながらも、「その後の旧宗主国の継続した努力が必要」と強調する。日本と朝鮮半島の従軍慰安婦・強制徴用など歴史認識問題を巡る混乱と対立を引き合いに出しながら、「せっかくの<記憶の承認>と謝罪がその後の政権・社会での逆向き対応・発言によって無効化される」状況が何度も繰り返されてきたことを反面教師のように捉えている。至極もっともなことである。そしてこれはフランス&アルジェリアだけでなく、世界中の「旧植民地支配国と被支配国」に共通する課題でもある。
<付記>著者あとがきによると、彼女は幼少期にベルギー・フランスで過ごした経験があり、そうした外国生活や所謂「帰国子女」としての日本での扱いなどの経験から外国人差別・移民などの問題に意識が向かうようになったという。そうした経緯に大いに共感するし、「エイリアン」として今もこの国に生きる者として、今後の研究にも期待したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
