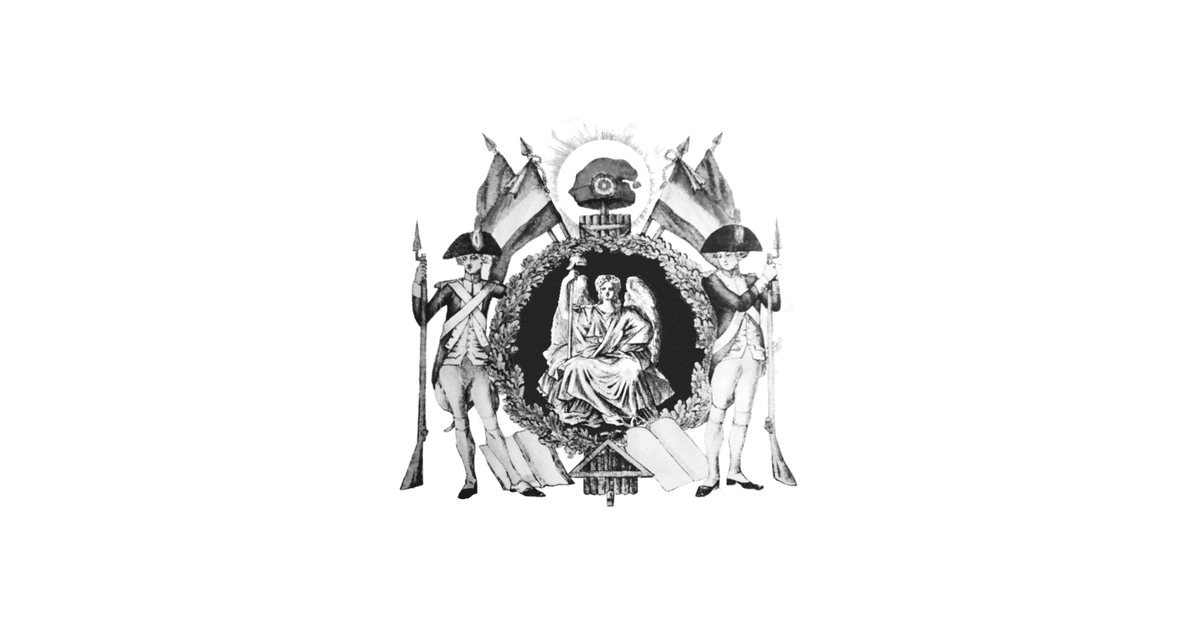
カエサル、ヘラクレス、そして理想郷:フランス革命における古典的熱狂
共和暦二年実月十四日(西暦1794年8月31日)、ロベスピエールの首が落とされて一月余りが過ぎた時、勝利の混沌が各々の企みを抱えるテルミドール派の間で混乱を生み出していた。ジャコバン派の怪物は首を切られたものの、フランスはまるで崖っぷちでふらつく酔っ払いのように不安定であった。公安委員会の暴政は終わりを告げたが、新たな暴政がどこかの隅から突如として現れないと誰も保証できなかった。パリの空気は血の臭いが少し減ったかもしれないが、餓えを感じていたのはギロチンだけではなく、「全面限価令」(Loi du Maximum général)の効果にますます失望していた底辺民衆の数万もの腹であった。
ある人物にとっては、これらの争いはあまり関心を引かないようであった。ブロワの司教で、国民公会の代表であり、ベストセラー作家であるアンリ・グレゴワールはこの日、「バンダリズムによる破壊行為とその抑制手段に関する報告書」(Rapport sur les destructions opérées par le Vandalisme, et sur les moyens de le réprimer)を公会に提出した。この文書では、革命が勃発してからフランス各地の文化財が故意に破壊されたこと、特に1793年末から1794年初にかけての非キリスト教化運動中に教会財産が受けた被害を非難していた。この文書が後世に注目された主な理由は、グレゴワールが作り出した「ヴァンダリズム」(vandalisme)という言葉がタイトルにあり、速やかに広く使われるようになり、「故意の破壊行為」(特に公共財産や文化財に対する)の代名詞として定着したからである。この言葉のインスピレーションは明らかに、古代ローマを襲撃し略奪したヴァンダル族から来ており、そのイメージは多くのヨーロッパの言語で「野蛮な行為」あるいは「無礼な行動」を表す「フン族」に相似している。これらは古を取り上げて今に議論する手法であり、時代の混沌を象徴する古典的典故を用いて現在の弊害を批判しているのである。
フランス革命の最中の複雑なる情勢のなか、アンリ・グレゴワールはその報告書において、単に古典的な意図を示すにとどまらず、深い洞察を込めた比喩として「ヴァンダリズム」の概念を提示した。共和国の代表であり、かつて1793年1月にルイ16世の死刑に賛成票を投じた彼は、ヴァンダリズムへの糾弾を通じて、革命の旗印が少数の非行者によって汚される事態を防ごうと試みていた。彼の批判は決して革命そのものではなく、革命の理念に背く破壊行為に対するものであった。
1794年夏の終わり、フランス軍は各戦線で未だに不透明な運命に直面していた。総動員令は差し迫った危機を回避するための措置であったが、それだけでは短期間で逆転勝利を収めるには不十分であった。不確実性に満ちたこの時期に、グレゴワールは楽観的な幻想を抱き、いずれ共和国の勇士たちが凱旋の歌を歌いながら、古の帝都に輝かしい革命の栄光をもたらす日を夢見ていた。彼は熱情を込めて記述している。「今日のローマには英雄がおらず、しかし、ローマの彫像や記念碑は依然として文明世界の注目を集めている……もし我が勝利の軍勢がイタリアに入り、ヴァティカンのアポロやファルネーゼのヘラクレスを持ち帰ることができれば、それはいかに栄光に満ちた征服であろうか!」
グレゴワールの帝国主義的幻想は、当時のフランス人が革命戦争を「新世界の自由人と旧世界の奴隷」との戦いと見なしていた傾向と密接に関連していた。彼は引き続き書き記している。「ギリシャがローマを飾り立てたように、古人の傑作は今日、奴隷の国々を飾り立てている;フランスはそれらの最後の避難所となるべきである……野蛮人と奴隷は知識と学問を憎み、芸術品と文物を破壊するが、自由人はそれらを愛し、守り、そして大切にする。」
グレゴワールは幸運であった。彼の空想は僅か2年後に現実のものとなった。1796年春、ナポレオンが率いるイタリア戦線の軍は奇策により勝利を収め、わずか2週間でこれまでのフランス軍が2年間突破できなかった僵局を破り、ピエモンテおよびロンバルディアを次々と攻略し、マントヴァにてオーストリア軍と激闘を繰り広げたのである。更に2年を経て、永遠の都も次第に勝利を重ねるフランス共和国によってその領土に加えられた。グレゴワールのイタリアの文化財に「新しい家を探す」という奇想は突然、非常に現実味を帯びてきた。フランス軍がイタリアに足を踏み入れて以来、アペニン半島の珍宝は次々とアルプスの彼方へと消えていった。初めは無秩序な自発的な略奪が多かったが、やがては軍隊と執政政府による統制が行われ、より効率的かつ目的意識的なものへと変貌した。フランスに持ち込まれた古典文物の多くは、開館間もないルーヴル美術館の展示品目録に加えられた。
1798年7月28日、パリはさらに大規模な凱旋パレードを組織し、奪われた文化財を街頭で展示した。しかし、露骨な文化財の掠奪は革命における新古典主義の神話を構築するプロセスの一環に過ぎなかった。革命下のフランスでは、随所に古典世界の影響が見て取れた。歴史学者クロード・モッセはこれを「古典世界への革命的熱狂」と表現し、文献学者フェルディナン・ブリュノーは革命時代の流行を描写する際に、「最も一般的な誇示の形式の一つはトガを纏い、古代ローマ人の様式を模倣してポーズをとることだった」と記述している。「革命の画家」と称されるジャック=ルイ・ダヴィッドは、革命が始まる前から古典芸術に魅了されていた。彼の1784年の作品「ホラティウス兄弟の誓い」は、題材から象徴に至るまで古典的な意味合いに満ちており、彼は「私はローマ人を描くためにはローマにいなければならない」と、妻を伴いわざわざローマへ赴いてこの作品を描いたのである。
「ホラティウス兄弟の誓い」に続き、革命前のダヴィッドは、「ソクラテスの死」(1787年)と「ブルータス邸に息子たちの遺骸を運ぶ警士たち」(1789年)という二つの古典的主題を扱った作品を相次いで完成させた。革命は彼の職業生涯に疑いなく新たなる高みをもたらした。彼はある意味で革命の宣伝家であり、記録者であり、新古典主義の筆を用いて革命の波乱に満ちた歴史を描き出し、後世に「マラーの死」、「ナポレオンのアルプス越え」、「ナポレオンの戴冠式」といった不朽の名作を遺贈した。また、彼は革命の演出家であり、舞台装置師でもあり、革命の主役たる者たちに彼らの嗜好に合致した背景を提供した。
特にロベスピエールとの協働は顕著であり、その支持のもとで1793年8月10日の「共和国一体不可分性の祭典」と1794年6月8日の「最高存在の祭典」の二つの未曾有の盛大な祝祭を企画した。古典芸術への熱烈な情熱と革命への熱意がダヴィッドにおいて見事に融合されていた。彼の革命初期の作品において頻繁に用いられた象徴の一つは、神話における英雄ヘラクレスである。たとえば、「共和国一体不可分性の祭典」においては、ヘラクレスが九頭のヒドラを討伐する伝説を借り、フランス民衆を英雄に見立て、国内の反動勢力を九頭のヒドラに喩え、ヘラクレスがオリーブの棍棒で蛇を打つ姿の彫像を製作し、祝典の行列に彩りを加えた。
マラーが暗殺された後、ダヴィッドはマラーの遺骨をパンテオンに移す行進を主催した。共和国軍が反乱のトゥーロンを奪還した後には、ダヴィッドは再び壮大な祭日のパレードを計画し、これら一連の行列は、ダヴィッドとその同僚たちが古代ローマの凱旋式に対する新時代の解釈を随所に反映していた。
理想的な新世界を建設しようとする革命が、なぜ遠い過去にこれほど夢中になるのか?この問いに答える前に、別の疑問を考えるべきである。共和理念を神格化する革命家たちが、二千年前の紙の山から霊感を求め、同時代の大洋の彼方へ視線を向けないのはなぜか?ラファイエット、バルナーヴ、ミラボー、ダントン、マラー、ダヴィッド、ロベスピエール、サン=ジュスト、バベフの心中を探ることはできないが、一つの推測としては、対岸のアメリカ合衆国はまだ幼弱であり、歴史深い文明国フランスに対して模範や指導を提供するには不十分であり、古典世界の主人公たち(アテナイ、スパルタ、ローマ)が二千年を経て数々のロマンチックな伝説で彩られた神秘的な魅力には欠けていた。もっと重要なのは、古代の伝説や故事が、当事者の参加感を失い、革命家による自由な改変や歪曲を受け入れやすい状態にあったことである。
1792-1794年の党派争いが激しかった時期の革命の言説は、この現象を大きく反映していた。「死の大天使」と呼ばれたサン=ジュストは、彼の死後に編集され出版された「共和制度に関する断片」(Fragments sur les institutions républicaines)で、国民公会内の代表を善と悪、「アッティカ流」と「スパルタ流」に分けている。「アッティカ流」の話者は、華麗で罠に満ちた弁舌で聴衆を惑わし、欺くのに長けているが、「スパルタ流」の話者は率直で胸の内を述べ、サン=ジュストの目には美德の化身である。もちろん、サン=ジュスト自身が革命期に最も優れた演説家の一人であり、彼が不道德と見なす手法で高らかに美德を讃えるのは、皮肉なことである。彼が紙の上で弁舌を否定しても、彼自身の政治生活は巧みな弁舌と切り離せないものがあった。ルイ16世の裁判中、サン=ジュストは煽動的な演説を何度も行い、国民公会を古代ローマの元老院に例え、議員たちにカエサル暗殺の元老院議員のようになるよう呼びかけ、裏切り者ルイ・カペにこれ以上時間を浪費するなと主張した。
国民公会の議事堂内での雄弁が、街頭や小道にあふれる新聞、週刊誌、そして宣伝パンフレットによって街中に響き渡っていた。古典世界の記号や象徴は、報道記者、出版者、煽動家にとっても同様に有用な道具であり、中でも最も広く知られているのは、バベフと彼の『人民トリビューン』(Le Tribun du Peuple)である。バベフはローマで土地と財政改革を試みたグラックス兄弟を模範とし、1796年5月にいわゆる「平等主義者の陰謀」を組織したが、実行に移す前に密告によって鎮圧された。バベフは一年後に総裁政府によって処刑され、彼自身と心の中で理想とする模範の悲劇的な運命を結びつけた。
革命時代に、パリでは45の新しい劇場が開場し、上演された劇の大部分が、ダヴィッドの絵画作品と同様に、古代の故事を借りて革命を讃える内容であった。1793年8月2日には、国民公会は条例を発布し、「ブルータス」「ウィリアム・テル」「ガイウス・グラックス」の三つの革命を描いた劇をパリの劇場で週に三回上演することを要求した。この時期に作成された他の古典的主題の劇本には、アルノーの「マリウスのミントゥルナエ」、ルグーヴェの「エピリスとネロ」、シェニエの「ティモレオン」、メシエの「アテネのタイモン」、ルメルシエの「アガメムノン」などがある。しかし、全ての創作者が古を借りて現を讃えるわけではない。詩「若き女囚の歌」の作者、アンドレ・シェニエ(先に述べたシェニエの兄)は、ジャコバン派の独裁政治からの迫害に直面し、「古人に新知を語らせる」(Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques)と選択し、1794年の「風刺詩」で美しい過去の景色と暗黒と抑圧に満ちた現在とを対比させた。シェニエは1794年7月25日にギロチンに送られ、彼を処刑に送ったロベスピエールの死とわずか三日しか隔たっていなかった。
ナポレオンが権力を掌握した後、革命と共に生じたこれらの近代神話を歴史のゴミ箱に捨てることなく、彼の統治に有利な部分を選択的に維持し、バベフの平等理論やジュストが古典世界に抱く血塗られた二元的暴力論理を覆い隠した。これはナポレオンが革命に対して持つ全体的な態度と一致している:意識形態の熱狂が新世界への期待を虐殺に変えることを許さず、また、旧世界に対しても非現実的な郷愁を抱くことは決してない。モッセの言葉を借りれば、「古典的な典故は依然存在するが、帝国の統制を受け入れなければならない」のである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
