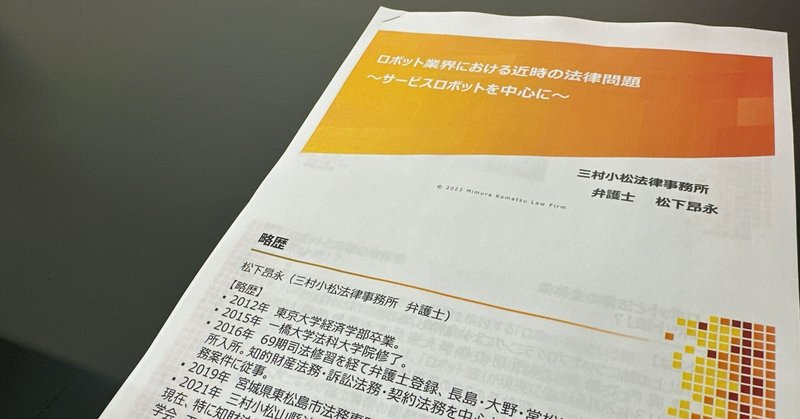
【セミナーレビュー】ロボット産業に関わる人のための法律入門@三村小松法律事務所
皆さん、こんにちは、JapanStep(ジャパンステップ)編集部です。
いつも、MetaStep(メタステップ)やJapanStep公式noteをご覧頂きありがとうございます。
メディアプロジェクト「JapanStep(ジャパンステップ)」を掲げているクロスアーキテクツでは、各業界とも親和性のある「ロボット」分野に注目しており、今秋にはサービスロボットのメディア「RoboStep(ロボステップ)」を立ち上げる予定です。
また、以前記事でご紹介したとおり、サービスロボットの業界団体ロボットビジネス支援機構(RobiZy(ロビジー))さんに、Web3・メタバースのメディアMetaStep(メタステップ)の後援としても参加頂き、様々な共創を開始しています。
後援をご縁に、RobiZyの広報担当として、サービスロボットの普及を支援させて頂くとともに、新たなプロジェクトも進めている最中です。ぜひご期待ください!
さて、今回の記事の本題。JapanStep(ジャパンステップ)編集部は昨日6/25(火)、RobiZy内のセミナー「ロボット産業に関わる人のための法律入門」に参加すべく、丸の内の明治生命館「三村小松法律事務所」様へお邪魔してきました!今後の産業であるサービスロボットに関わる法律知識を学べるものとなっています。

エレベーターひとつとっても、歴史の趣を感じます。


一転してスタイリッシュな事務所となっておりました。
宇宙ロボット分野
まず初めに、三村弁護士事務所の藤村 亜弥さんのお話から。
藤村さんは、宇宙ビジネスを法的側面から研究・支援する団体、日本スペースロー研究会(Japan Space Law Association)の会員でもあります。
【宇宙ロボットは3つある】
・軌道上ロボット:宇宙ステーションや人工衛星に搭載。宇宙ステーションのロボットアームなど
・月惑星探査ロボット:月の表面で働く 月面探査車(ローバー)など
・有人宇宙活動支援~代行ロボット:船内船外の宇宙飛行士のサポート機器
【日本の特許出願は少ない】
日本の特許出願は世界的と比べ少なく、知的財産分野において世界に後れを取っているのが現状。圧倒的に伸びている中国と比べ日本の特許出願率は1/8程度。内閣府も、日本の知財分野への支援を進めています。
【世界と戦う宇宙ビジネスにおいて、特許は重要】
宇宙ビジネスはこれまで、国や一部の企業しか行っていなかったこともあり、そもそも特許を侵害される可能性も低い状況でした。
しかしここ数年、宇宙ビジネスに進出する民間事業者が増え、製品も増えてからこの状況が見直されるように。
地上での製品と同様に、模倣品や特許の侵害におけるトラブルなどの可能性がゼロでは無くなってきたのです。これまで未開拓であった宇宙ビジネスにおいても特許侵害事例が発生することを危惧し、特許権取得などの動きが進むと見込まれています。
サービスロボット分野における法律の重要性
お次は、同じく三村小松法律事務所の松下昂永さんによる「ロボット業界における法律問題」の講義。

【重要性が高まる「ロボット関係の法律」】
今後、サービスロボットの市場規模が広がるにつれ「ロボット関連のトラブル」も増えると想定されています。
しかし現状、特定のロボット法は存在せず「ロボットに関連する法律」が存在しているというだけ。
ロボット産業においては、どんな法律問題が発生するか議論しておくのは有益という事で、今回のセミナーを含め様々な事案が共有されています。
【どんなところでロボットが問題に?①知的財産権】
・自社で開発したロボットが、既に特許を取られていた
・後発の企業に特許侵害だと訴えられた
こういった事例を未然に防ぐために、知的財産法(特許権、意匠権、著作権、商標権、不競法)を抑えておくと、下記のようなメリットがあります。
1.防御(他社から訴えられた時に守れる)
2.攻撃(侵害している企業を訴えられる)
3.抑止(予め他社の進出を防止)
4.提携(共同研究時、特許保有側が契約条件を有利にしやすい)
5.PR(特許取得済み、という宣伝効果)
※特許を取るデメリットは、アイデアを一般公開しないといけないこと。
なので、他社がそのアイデアから着想を得て革新的な商品を生み出される可能性も孕んでいます。
サービスロボットの「Pepperくん」ソフトバンクロボティクスによって商標権を登録されており、他社に模倣される可能性が低くなっています。これからロボット開発をする企業にとっては見逃せないポイントですね。
【どんなところでロボットが問題に?②製造物責任法】
「製造物責任法=PL法」とは、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律。
今回は「犬型サービスロボットの一部分で怪我を負った」事例を想定。
どこに「欠陥」があるのかが争点です。製造時・設計時・指示警告の不足・もしくは製造業者の不備なのかーー。さらに、実際に起きた医療用ロボットの死亡事故を紹介。サービスロボット関係者にとっては非常に緊張感が高まる場面でした。
松下さんは最後に「ロボット分野はまだまだ発展途上であり、これからも新規の規制が多数生じる可能性があります。そのため、新たな規制動向に目を光らせておく必要があるでしょう。そこが競合他社との差にもなります。
疑問があれば専門家に相談するのもいいですし、特許庁や経産省から契約ガイドラインが出ているので適宜参考にしてほしいですね」。と伝えセミナーを締めくくりました。

自社の事例を想定した質問も多く飛び交っていました。
【終わりに】
「人と共に働き、生活をサポートする」サービスロボット。
今後大きな産業になるからこそ、押さえておかなければいけない法律関係。参加者の皆さんの真剣な表情が印象的でした。
本日もお読み頂き、ありがとうございました。
スキやフォローを頂けると、やる気が1%アップしますので、是非よろしくお願いします!
MetaStep(メタステップ)へのパートナー企業への参画ご相談や、取材のレコメンド、その他お問い合わせは、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ!
運営会社クロスアーキテクツへの制作のご相談は、公式HPのフォームよりお願いします!

