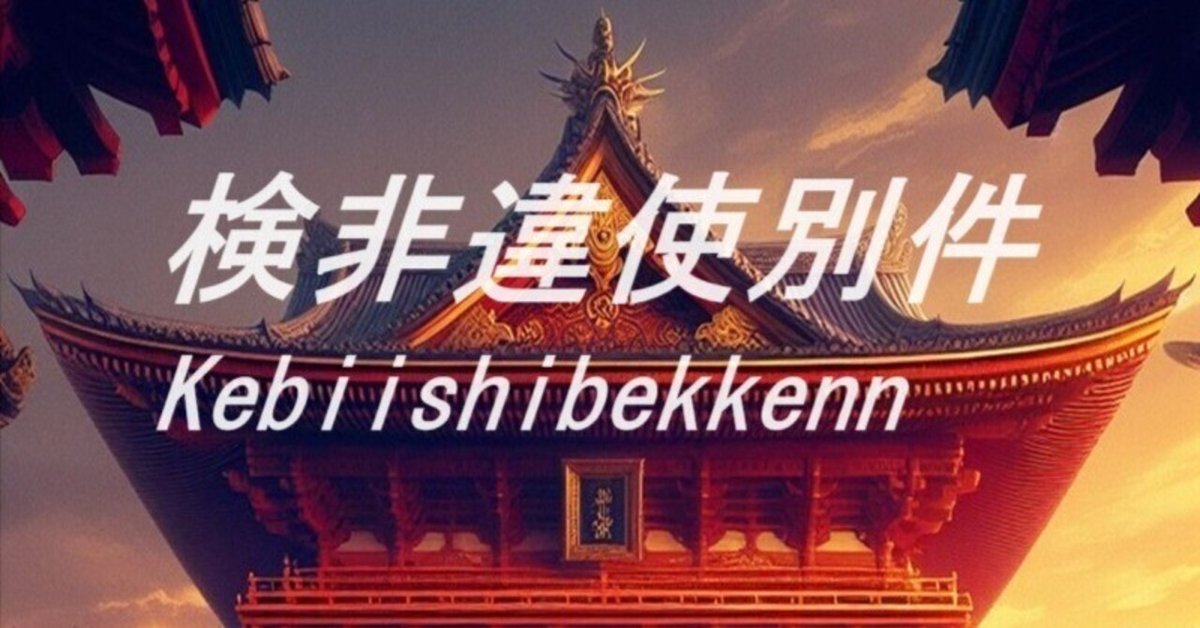
検非違使別件 七 ⑬
「稲若。なぜ、お前がここにいる」
退紅色の狩衣についた汚れを払い落としながら、仁木緒は稲若に問いかけた。稲若は悪びれない。
「ゆずかを探しに、ここへ来ていたんだよ」
「そ、そうか……」
すぐ泥蓮尼にも厳しい視線を向けた。
「あなたにも、聞きたいことがあります。稲若とは顔見知りですか」
能原門継との関りを真っ先に確かめるつもりだったが、とっさに口を突いて出たのはそんな質問だった。錦行連の言葉から、お互い見知っていることもたったいま知ったばかりだ。落ち着いているつもりが、かなり狼狽しているらしい。仁木緒は額の汗を指先でぬぐった。
「あ、申し遅れました。わたしは検非違使庁の看督長で佐伯仁木緒。危ないところを助けていただいた。礼を申し上げます」
「わしは多紀満と申します。しかし、ここでは詳しい話もできますまい」
横から口を入れたのは、手首に数珠を巻いた老人だった。
(この老爺にも見覚えがある)
ついさっきまで泥の固まりを投げつけていた人々の顔を、仁木緒はぐるりと見回した。
泥蓮尼と稲若を入れて八人。その中で、白髪を烏帽子でおおっている多紀満老人は質素な柿渋色の小袖をまとっていた。その隣には肉付きのいい色白の女がいる。豊かな頬とたれた目じりには愛嬌があった。
「色白たれ目の女……手首に数珠を巻いた老人……おぬしたちは」
稲若のそばには十歳くらいの少女がいる。薄いそばかすが散ったその顔立ちにも覚えがあった。
「……そうだ、儀式の前日……おぬしらは左獄のそばで泥蓮尼に礼を述べていたはず」
「佐伯さま、この子がゆずかだよ」
稲若がそばかすのある少女のたもとをつかみ、前に押し出した。あわてた多紀満老人が「これこれ」とたしなめたものの、ゆずかを仁木緒の視線から隠そうとはしなかった。
「ゆずか……着鈦の政直前、囚人たちが待機しているそばで……笛を吹いていたことに間違いないか」
問われたゆずかはちらっと泥蓮尼に視線を走らせただけで、うなずきも、否定もしない。表情を強張らせている。泥蓮尼が素早く墨染のたもとでゆずかの肩をおおって、抱きしめるしぐさをした。
「いきなりの問いかけで驚いているのですわ。一体何があったのやら……。どうぞ順を追ってご説明いただけませんでしょうか?」
もっともな言い分ではあるものの、仁木緒の胸に疑念ばかりがわだかまる。
泥蓮尼と笛吹童子に扮していたゆずかが、同時に目の前にいる。
このつながりは何を意味しているのか。
「路上で立ち話もありますまい」
再び多紀満老人が言い、厳かに頭を下げた。
「陋屋でお恥ずかしいかぎりですが、どうぞわしの家においでくださいませ」
「そうですね。多紀満どのから井戸水をいただいて、みんなも手足を洗わせていただきましょう」
泥蓮尼が子どもたちを振り返って笑みをこぼす。
実際、稲若もゆずかも、泥濘の固まりを投げたせいで手はひじまで黒くなっていたし、足首もすっかり泥まみれだ。泥の飛沫で汚れた顔の滑稽さに気づいたらしく、お互いを指さして子どもらが再び笑い声をはじけさせた。
「わしの名は多紀満と申しまして」
数珠の老人が歩きながら改めて、仁木緒に言葉をかけた。
「山小路のはずれの小泉庄で百姓をしております」
「泥蓮尼どのとはどういう付き合いです」
「さよう、もう十年になりましょうか。近くの尼寺……このあたりでは『光蓮寺』と呼んでおります……今は亡き翔蓮尼さまというお方が一人きりで切り盛りしている、とても小さな寺がございましてな。その翔蓮尼さまのもとに、まだ幼かった泥蓮尼さまが身を寄せたのでございますよ」
「待て。以前、どこの寺に住まっている尼僧なのかと聞いたとき、知らぬと申したではないか」
「あのときは、所用がありまして……説明する手間を惜しんだのでございます。無礼な態度をお許し下され」
深々と頭を下げられ、仁木緒は詰問する間合いを失った。
「……それで、光蓮寺の住持となった泥蓮尼どのを慕っているというわけか」
「はあ……実は、三年前にわしは息子夫婦を亡くしまして……。孫のゆずかを抱えて難儀していたときに、泥蓮尼さまが野良仕事や飯炊きを手伝ってくださり、息子らの魂に経を読んでいただいたのでございます。寂しがるゆずかに、笛の稽古をつけてくださいました」
「あの若さで仏の教えを守り、楽曲にも秀でているとはすごいことだ」
「はい。泥蓮尼さまは、病のときにはご祈祷や薬をくださる、ありがたいお方でございます」
「ゆずかの音曲の才には目を見張るばかりですわ」
そっと合掌して泥蓮尼がうなずいた。
「神仏からあたえられた素晴らしい才です。ゆずかの笛の音で、天上の魂も救われましょう」
「して、検非違使のお方が、何用でこちらに?」
多紀満老人がいぶかしげに問いかける。仁木緒は咳払いした。
「泥蓮尼どのを見かけてここまで追ったのだが、実はある男を探していた。先月まで、右京三条の藤原登任さまの邸に勤めていた牛飼いで名を千歳丸という。ご存じあるまいか」
「それはあたしの夫でございますよ」
驚いたことに、たれ目の太った女が尻をゆらして追いついてきた。
「あたしはとよめと申します。はい、夫は千歳丸。右京三条のお邸を放り出されたとき、なんでも伴家継とかいう家司さまから、殴る蹴るの乱暴を受けましてね。特に頭につけられた切り傷がむごいことでございましたよ」
まるで自分が暴行されたかのように、しきりに平手で中空を叩き、足をあげてその様子を表現した。すぐに葦の茂みの向こうを指さした。
「幸い、泥蓮尼さまのお薬が効いて回復いたしまして、今は、すぐそこのあたしの家で休んでおります」
「泥蓮尼さまはこのあたりの者たちにとって、生き仏さまのようなお方でございます」
多紀満が合掌する。泥蓮尼本人は小さくほほ笑んで首を振る。
「わたくしごときに、もったいない言葉です。亡き師の翔蓮尼さまに少しでも近づけるよう精進しているだけのことでございます。すべてはみなさまの信心のたまものですよ」
多紀満老人の家はそのあたりでは、割と大きな百姓家だった。
ところどころ破れた網代垣の隙間から、ニワトリが行き来している。しおり戸を抜けるとすぐ右に柿の木と鶏舎があった。
井戸と呼ぶには貧弱な石積の雨水をためておく水たまりがあって、みなはひしゃくでその水をくんで手足を清めた。
とよめが汚れた手足を洗い終わったのを見計らい、仁木緒は「ここへ千歳丸を呼んでくれ」と言いつけて家へ帰した。
手を差し出しているゆずかにひしゃくで水を注ぎながら、稲若が言い聞かせている。
「だからさあ、お前が笛吹童子だったのはもう分かってんだぞ。おいら、佐伯さまには義理があるんだ。正直に全部話しちまいなよ、あの人、悪いようにはしないから」
「……それより稲若、石見丸は獄舎で大丈夫かしら。心配ね」
唐突に石見丸の名が出され、悲劇を思い出した稲若が声をつまらせた。
「……獄舎で、殺されちまった……」
「えッ。どうして? 誰に?」
「能原門継って極悪人が、石見丸を刺したんだよ。よくわかんねーけど、そいつ、荒彦のニセモノなんだって……」
荒彦の名に、ゆずかがどういう反応を示すのか。仁木緒はそっと少女をうかがった。
ゆずかは立ちすくみ、目をしばたたいた。稲若、かわいそうに……と肩に手をおいてなぐさめている。幼い横顔からは、稲若への同情しかなさそうだった。
(ゆずかは自分が、荒彦脱獄に手を貸した事実を理解しているのか、いないのか……。舞姫のさゆりと荒彦について、どこまで知っているのだろう)
仁木緒は肩をそびやかし、多紀満が「陋屋」と謙遜した家に入った。
広い土間は藁を叩くための道具や農具が隅に置いてあり、ほうきで掃き清めてあった。朝にはこの土間をそうじし、夕べには藁束を打つであろう少女と老人のつましい生活がうかがえる。
(役目とはいえ、あんな年端もいかぬ娘に詰問せねばならんとは……)
気が重い。
(だが、まずは千歳丸だ。一か月前に、登任さまの邸で何があったのだろう)
板の間に上がると、すぐ多紀満老人がやってきて白湯をすすめた。のどが渇いていた仁木緒はありがたくそれを頂戴する。
泥蓮尼は現れなかった。子どもたちの手足を井戸で洗ってやっているらしい。「水遊びしなさんな、もっと手を前に差し出して」などと小言と一緒に子どもたちの歓声が響いている。
泥蓮尼のはつらつとした声色に、仁木緒は思わず笑みをこぼしそうになった。
白湯のカワラケを置いて、多紀満老人に頭を下げた。
「検非違使庁の用向きでうかがいました。ここをお借りして、千歳丸、ゆずか、泥蓮尼どのから話しを聞きたいのですが、よろしいですか」
「はあ、これも御仏のお導きでしょう。わしは構いませぬよ」
多紀満は数珠をまさぐっている。
「ゆずかにとって、答えにくい、恐ろしいことを聞かねばなりません。証人、あるいは介添え役として、そばについてやってください」
「もちろんでございます。ところで、稲若……あの子を放免にでもお使いですか?」
「いずれ、正式にわたしの従者として面倒を見るつもりです」
「川猟師の石見丸が拾って来たみなしごです。親から川に捨てられた自分が、同じように溺れていた稲若を救ったのも何かの縁だろう、と石見丸は申しておりました。川魚を捕らえる網が流され、稲若を育てるためにやむなくあの男は賭博に手を出したのです……。諸行無常なことでございます」
「お前さまぁ! さあ、こっちだよぉ」
外から素っ頓狂なほど甲高いとよめの大声が流れて来た。
板の間から庭に首を伸ばすと、鼻に小豆大のほくろがある、頭に包帯を巻いた男の小袖にとよめがまとわりついている。
初めて見かけたときは怪我のために烏帽子をかぶれないのか、と思っていたが、牛飼い童であれば髷は結い上げない。千歳丸は総髪を後ろで一つにくくっていた。
「泥蓮尼さまに言われてケンカに加勢したんだよ。イヤな目つきの武士たちに、子どもらと一緒になって泥んこをぶつけてやったんだよ。で、検非違使のお方を助けたのさ。あたしの活躍をあんたに見せたかったよ」
「わかったわかった。とよめ、みっともないマネはよせ」
千歳丸が抱きついてくるとよめを振りほどこうとじたばたしている。
仁木緒はぼうぜんとした。着鈦の政前日に泥蓮尼と共に見かけた男女がここに全員そろうとは。
「とにかく落ち着いてください。頭の傷に障りますよ」
駆けつけた泥蓮尼にたしなめられ、とよめはあわててむっちりとした頬を千歳丸の首筋から離した。
広縁から仁木緒は千歳丸を呼んだ。
「こっちへ上がってくれ、千歳丸。登任さまの邸で、荒彦が捕縛された先月の事件について洗いざらいしゃべってもらいたい」
肩をゆすり、千歳丸は庭先から上がろうとはしなかった。きまり悪そうに包帯に包まれた頭に手をやっている。
「へえ……しかし、家司の伴家継さまから、『勤めを退いても主家の体面を汚すな』と、口止めされておりまして」
用心深い足取りで広縁に近づき、両掌を床板にのせて身を乗り出す。口止めされていると断りをいれてはいるものの、本心では暴露してしまいたそうに唇をなめている。文屋兼臣の忠告を思い出し、仁木緒は少し押してみた。
「見上げた忠義の心だ。しかし、その家司に怪我を負わされたのだろう。しかも今日まで黙っていたのだから、もう忠節は充分果たしたはず。今は正直に話すべきときだぞ」
「……いえ、しかし……いつ、伴家継さまがここへ現れるかと、気が気じゃなくて……」
「伴家継が監視しているというのか?」
「はあ……」
みじろぎし、左右を見回した。どこかに伴家継が隠れていて、いきなり飛び出してくるのではないかと千歳丸は怯えているようだった。
「もし脅されているなら、ますます正直に話すべきだ。話してくれればおれがおぬしを守ると約束する。なによりも、正直者を神仏が見捨てるはずがない」
「神仏が」
千歳丸が目を潤ませる。その目じりからぽろりと一筋涙が流れた。たもとでそれをぬぐうと、やっと広縁にあがった。そのまま仁木緒と一緒に板の間に入った。
敷かれたむしろに腰を落とすと、開口一番に「実はつらくってね」とつぶやいた。
「登任さまの邸……わっしは物心ついたときから勤めていたんですよ」
藤原登任は多くの貴族と同様、出雲や大和の国守(受領)をつとめる一方で、内裏に詰める役人も兼務していた。そのため都の自邸に住まいながら、国守の役得を得る場合も多い。
少年のころから千歳丸は、右京三条の邸で牛車の手入れや牛の世話をしてきたのだという。
「陸奥守の勤めを果たすため藤原登任さまが陸奥へ赴任しているあいだ、主不在のお邸を守って参りました。……もう十年ほどたってしまいましたね、陸奥国鬼切部での戦……ですか。あの敗北で都へお戻りになってから、主人はひどくふさぎ込み、荒れておりまして……。失脚の憂き目と敗戦の屈辱がおつらかったのか、憂さを晴らすように伎楽にうつつを抜かして、若君さまたちを困らせていらっしゃいました。……はい、若君さまは四人いらっしゃいます。ご長男の長宗さま、長明さま。その下のお二人は僧籍に入っていらっしゃいまして、|任尊さまと実覚さまです。上のお二人は武官として他国へ赴任なさったのですが……任尊さまと実覚さまは、右京三条のお邸にしばしば訪れては父君に『遊興をつつしまれますように』とたしなめてらっしゃいました」
「そのお二人は、どこの寺僧だ」
「叡山と聞いています」
叡山の僧と一口にいってもさまざまだ。
叡山延暦寺の頂点に立つ天台座主ともなれば、学識高く、儀式、修法に通じている。叡山には朝廷の奉幣使と応接する高僧もいれば、経典を研究する学僧もおり、寺社が営む荘園を盗賊から守るための僧兵もいる。
僧となれば官職を得て廟堂へ出仕する貴族ではなく『御仏の弟子』である。だが、出身の家筋とまったく縁が切れるというのではない。任尊と実覚二人の僧にとって、叡山にまで届く父親の放埓な酒宴や伎楽への執着は、堪えがたい思いがしたのだろう。
「調べでは、その邸に伎楽殿という舞台があり、そこが焼け落ちたと聞いたぞ」
荒彦の放火について、仁木緒は用心深く言葉を選んだ。
「ともし火が倒れた程度ならすぐに消し止めることができたはず。それが焼け落ちるほど火勢があったとは珍しい。その日は強風だったかな」
ひと月前は春の嵐が吹き荒れた記憶はある。だが、その風が舞台を焼け落ちさせたかどうか、確かではない。
「たいした風はなかったですよ」
思案顔で千歳丸がつぶやいた。
「世話している牛の体を洗ってやった日でしたんで、よく覚えています。濡れた牛の体が冷えちまうといけないんで、あんまり強風の日にゃあ牛を洗いやしませんから」
「そうか、では出火したのはいつごろか、覚えているか?」
「ええ、亥の刻(午後十一時)前だったと思います。……実は、そこへ真っ先に駆け付けたのは、このわっしなんでございますよ……」
千歳丸は自分の鼻先を指さした。
「もちろん、手桶一杯の水を持ってね。ところが、家司さまや護衛の武士、お客さまがたが、水桶をつかんだわっしら使用人たちを近づけさせねえんで……。それでもわっし一人は武士たちをやり過ごし、伎楽殿に近づいた。夢中で水をぶちまけたんだが、大きな炎の中で三人の人影が苦し気に、踊り狂っておりまして……」
地獄絵図そのものであったその記憶に、千歳丸は身震いした。そばで聞いていた多紀満老人が数珠をまさぐって念仏を唱えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
