
メルヘンハウス online club Vol,2
早くも Vol,2を皆さんにお届けします!
メルヘンハウス 二代目 三輪丈太郎の「文章」と、メルヘンハウス 三輪哲の「肉声」をお楽しみください!
なお、2回目となる「三輪哲のBetter Books for Young people!」のタイトルは、「ピカソの境地へ」です。何十年も交流のある手作り絵本の集まりの話から、孫から影響を受け、挙げ句の果てには「ピカソに追いつけ追い越せ!」と壮大な話となっています。
メルヘンハウス 二代目 三輪丈太郎の「文章」
本離れは戻ってくる
僕は1975年生まれ。メルヘンハウスがオープンしてから2年後から「子どもの本の専門店の息子」というキャリアが始まった。
それから、10年ぐらいの年月は、絵本や幼年童話や読みものをよく手にしたし、父と一緒に本を楽しんだ記憶もある。しかし、小学3年生ぐらいから、野球に夢中になり、「子どもの本の専門店の息子」というキャリアが少しずつ薄れていった。
世間で言われる「本離れ」は、僕にも例外ではなく訪れたのである。
別に本が嫌いになったわけではない。当たり前に生活の中にあった本の時間を、夢中になることに充てた結果であった。と言っても「子どもの本の専門店の息子」という稀なポジションは、僕の中で少々嫌気がさしていたのも事実である。
僕は世間から「子どもの本の専門店の息子」だから、「本が好きであろう」、「よく読むのであろう」、「読書感想文も優秀であろう」と、いつも勝手に目に見えないプレッシャーを感じていた。もしかしたら、そのプレッシャーから解放されたかったかもしれない。
プロ野球選手になりたい!
僕は小学生から中学生にかけて、本気で「プロ野球選手になりたい!」と思い、部活動だけではなく、近所に住むチームメイトの友達と、早朝にランニングやキャッチボール、近所にあった大学のグランドに忍び込んで、勝手に壁に的を書いて「壁当て」なる練習をしていた。
ポジションはピッチャーだったが、僕がなりたかったポジションではない。先生が勝手に決めた。理由は僕が左利きだったから。ただそれだけでピッチャーになった。
野球を知らない人はわからないと思うが、左利きができるポジションは限られている。一塁か外野かピッチャーである。元々運動神経が良いとは言えない僕は、足も遅かったし、機敏な行動が苦手だった。そうなると外野は俊足を求められ、一塁は機敏な行動を求められるため、残ったところでピッチャーしかなかったのだ。
サウスポーのピッチャーというと聞こえは良いが、僕の場合は消去法にて得たポジションである。
中学になっても最初からピッチャーであった。大概は小学生の時に決めた、あるいは僕のように決められたポジションがそのままスライドしていく。中学になると練習も急にハードとなり、「先輩」と「後輩」という関係も出てくる。小学生の時はあだ名で読んでいた1歳年上のチームメイトも、中学生になると急に「〜先輩」と呼ばなければならなかった。歳を関係せずに、たった1歳年上の友達が遠い存在になっていった。
THE BLUE HEARTSに衝撃を受ける
そんな人間関係が嫌だったこともあるが、中学1年生の時に野球以上に夢中になれるもの出会ってしまった。それが「音楽」である。そして、その音楽こそが、THE BLUE HEARTSである。スピード感のある歪んだサウンドに乗っかった「叫び」に近いようなストレートな歌詞に、僕は一気にやられてしまったのだ。
それまでも音楽は好きで、今では懐かしいラジカセ(ラジオカセットレコーダー)にて、ラジオや歌番組をカセットに録音して聴いていたりもしていた。まだCDが出始めた頃で、町には「貸しレコード屋」が何軒かあった。
80年代の中頃から後半にかけて、世の中では「バンドブーム」が起こり、今まで聴いていた歌謡曲を歌うアイドル歌手やバンドとは異なる、カッコいいロックバンドがたくさん登場した。
そんな中でも僕にとっては、THE BLUE HEARTSは特別な存在であった。当時はインターネットなどまだ登場していない時代である。情報はレコード(CD)ジャケットや歌詞カード、音楽雑誌から得るしかなかった。
まず見た目から入る僕は(父譲り)、THE BLUE HEARTSのボーカル甲本ヒロトが破れたジーンズを履いているのを見て、すぐに自分のジーンズの膝を破った。母は、「あの人たちはお金がないからジーパンが破れても、買えないだけ!」と僕を叱った。
本の世界に戻ってくるのは、思いがけない「キッカケ」
ギターのマーシーはクールでとてもカッコ良かった!何かのインタビュー記事で『マンハッタン少年日記』(晶文社)と、中原中也の詩の世界に影響を受けていると書いてあったので、速攻で父に本を入手するように頼んだ。本離れしておいて、勝手な時だけは父を利用したのだが、父は喜んでいたような記憶がある。
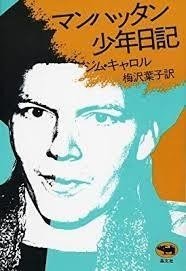
中学生の僕には、『マンハッタン少年日記』も、中原中也の詩の世界観も全く理解できなかったが、自己満足な共有に浸っていた。共感、共鳴からなる共有ではなく、遠い存在であるマーシーが読んでいる本を自分も持っているという、モノとしての共有である。
その後の人生において、『マンハッタン少年日記』も中原中也の詩の世界観も、理解することが出来るようになり、今でも愛読書の中に入っている。もちろん、THE BLUE HEARTSの音楽も、今も身体に染み込んでいる。
突然途切れた本の時間が少しずつではあるが、THE BLUE HEARTSの影響にて自分の中に戻ってきたのは確かである。もしかしたら、「本離れ」とは「親離れ」と近いのかもしれない。
一度離れても必ず戻ってくる。
メルヘンハウスでの接客時、講演会などで、子どもの本離れについて質問をされることが多々ある。「あれだけ本が好きだったのに、、、」と、皆さんはとても残念そうに語る。しかし、僕は「必ず戻ってくるから大丈夫!」と答える。それはこんな実体験に基づくことだから、自信を持って言える。
僕の場合は、THE BLUE HEARTSがキッカケではあったが、子どもたちは何かのキッカケで、また本を手にするようになる。それは早かれ遅かれ必ずやってくる。
しかし、「本離れ」という言葉は、本を手にしてきた子どもたちに起こる現象であり、本を手にしてこなかった、一緒に楽しんだ大人たちがいなかった子どもたちには、無縁な言葉だ。僕はくどいようだが、「子どもの本の専門店の息子」であり、本に囲まれた生活が当たり前にあったから「本離れ」を経験した。
つまりは今、小さな子どもたちと接している方々は、存分に本の世界を一緒に楽しんで欲しい。そんなベーシックがしっかりとあれば、近い将来、たとえ子どもたちが「本離れ」をしても、心配無用であることを忘れずに!
また、本は読まなければならないものではなく、読みたいものである。「本離れ」をした子どもに、無理矢理にでも本を読むように仕向けるような行為は絶対にして欲しくない。それは逆効果である。
今だから「子どもの本の専門店の息子」とは、なんて恵まれた環境だったんだろうと思える。ちなみに「本離れ」をせずに、ずっと本を読み続けてきた人の心情は僕にはわからない。それは僕が経験していないことだから。そんな人の話を聞くのも興味深いと、最近は思う。
プレイバックする本の時間
最近は、この「メルヘンハウス online club」の父の「肉声」コンテンツの収録(盗聴)のため、実家にいくことが多くなった。先日、実家に行った際に書庫(ものすごく狭小で、おそらく皆さんのイメージとはかけ離れているため、書庫の写真などの公開は控えさせていただく)にある本を色々と物色していた。
よく読んだ記憶がある本もあれば、「こんな本読んだかな?」と、ページをパラパラとめくるうちに、「読んだ!この本読んだわ!」と思い出が一気に蘇るものまで、色々と物色をした。
その中で僕の忘れていた過去を思い出させる1冊の絵本を再会をした。その絵本の裏表紙には、下手な文字(今でも字は汚い)で「みわじょうたろう」とわざわざ書いてあった。
ここから先は
¥ 500
サポートして頂いた金額は、実店舗の運営資金として大切に使わせて頂きます。「メルヘンハウスユーザーから、メルヘンハウスメンバーへ」。皆さんと一緒にメルヘンハウスメルヘンハウス を創造していけたら、とても嬉しく思います。
