
【議論/詭弁】① 議論の技を学ぶための『議論入門』その1
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
マガジン『能ある鳩はMBA② ビジネススキルで豆鉄砲』での、ビジネススキルにまつわる情報の紹介です。
前回の記事はこちらです。↓↓↓
今回からは、MBAの授業で目立ち、社会で生き抜くためには欠かせない「議論」そして「詭弁」の技術について、香西秀信先生の著書を頼りに見ていきます。
忙しいビジネスパーソン向けとして、最後にこの記事の「まとめ」を用意していますので、先にそちらを読んでいただいても結構です。
なお、全て無料で読めますが、
「良い記事だったなあ」
と思っていただけるようでしたら、記事代をいただけると励みになります!
議論の技を学ぶ
今回取り上げる内容は『議論入門』からの引用です。
同書の序文には、なかなか手厳しい言葉が述べられています。
ディベートの実践記録などを見ると、
生徒の議論の粗雑さ、単調さが目につき、
子供のチャンバラを見せられているような印象が残るが、
これは議論における論証の方法(論法)を教えられてないことによる。
議論は多彩で複雑なものであるから、
それに熟達しようと思えば、より多くのことを学ぶ必要がある。
また、出来合いの論法を学ぶだけでなく、
状況に応じて自ら新しい論法を作り出す能力も身につけなくてはならない。
が、それはある程度のレヴェルに達した後で悩めばいいことであり、
本書で扱った程度の論法を習得していない人には無縁の話である。
まずは基本から始めていただきたい。

とはいえ、これは真実をついた話でもあります。
鳩がビジネススクールに通っているとき、MBAの授業では、
「発言者の、どの意見も尊重する」
というスタンスでした。
「自分でも何かわらんが、このフレームワークをくらえッ!」ですとか、
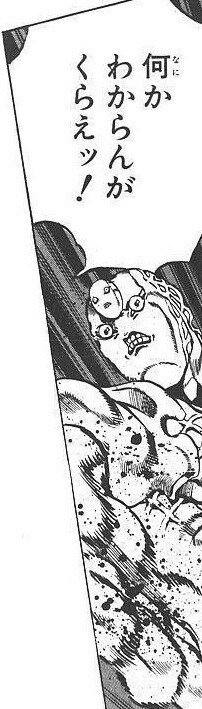
「俺の発言……理論のどこかに当たってくれ!」ですとか、

そんな勢いで、
「基本を学習するよりも、とにかくペラペラ話すこと」
が重視される授業もありました。
何かを考え、発信するには、基本を学んでおくことが大事。
それは議論においても同様だ、というわけですね。

それでは、『議論入門』であげられている議論の技術を見ていきましょう。
議論の技術① 定義:記述的定義と規約的定義
『議論入門』では、
「定義にはいくつかの種類がある」
と指摘されています。
○記述的定義
その言葉が普通はどのように使われているかを示す定義
(例)
・辞書の中で見られる定義
○規約的定義
特殊な文脈で使われる定義
(例)
・ある言葉を「私は○○という意味で使いますよ」という個人的な定義
・ある学問において、ある言葉を特別な意味で使う定義
一般的な辞典などに登録されている言葉の定義は、
「記述的定義」
と言えるでしょう。
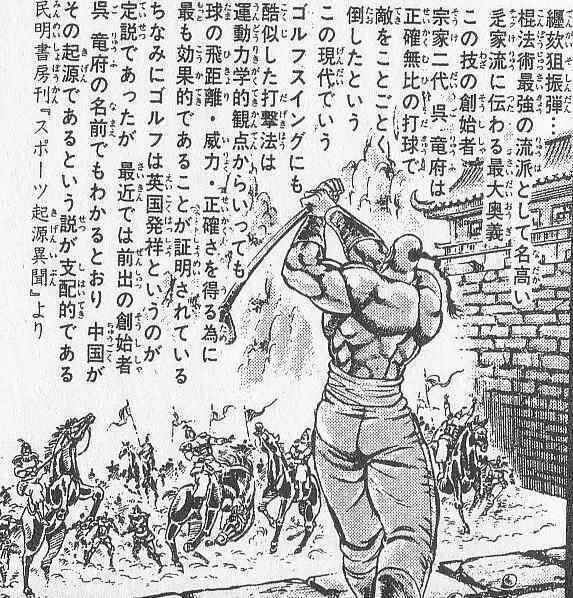
一方、個人やある学問が、
「ここではこういう意味で使っています」
と特殊な意味を持ちだすのが、「規約的定義」というわけです。

説得的定義
さて、定義の種類にはこれら2つに加えて、
「説得的定義」
というものがあります。
「説得的定義」は「規約的定義」の亜流です。
「規約的定義」とは、特殊な取り決めでした。
これを、あたかもこの世の真理であるかのように用いると、
「説得的定義」
と呼ばれるようになります。

説得的定義の例を挙げてみましょう。
「この〇〇の本質は××だ」
という発言は、「自分は頭がいい」と思っている会社の上司や教師、評論家に多数見られます。
「〇〇の本質は××だ」と言われると、
「あたかも客観的なこの世の真理」
のように聞こえます。
しかし実際には、本人が勝手に「本質」とやらを決めただけのこと。
ただの、説得的定義なのです。
例えば、「自分はこの言葉をこのように使っている」は本来規約である。
それが、「この言葉の真の意味はこうだ」となり、
「この言葉はこの意味で使用すべきだ」となってきたら、
この種の「定義」を一体どのように扱うべきなのであろうか。
この問題は、「説得的定義」と呼ばれる定義の一種と関わってくる。

説得的定義は善か悪か
「私はこういう意味で使っています」という定義を、
あたかもこの世の真理のように用いる……
そんな「説得的定義」。
しかし香西さんは、
議論の相手や聞き手が納得する or 反論できないなら、
説得的定義はそのまま、みんなの合意する定義としてオーケイ
周りが納得しないならば、説得が失敗するだけのこと
というシンプルな見方をしています。
重要なのは、
「自分はいま、説得的定義でモノをしゃべっているか」
「相手はいま、説得的定義でこちらを丸め込もうとしているのか」
「いずれにしても、説得力は十分か」
に注意を払うことかもしれません。

「定義からの議論」の注意点① 情緒的・評価的定義
さて、「定義からの議論」には注意点がいくつかあります。
同書では、
「『よい/悪い』といった情緒的・評価的定義は、トートロジーに陥りがち」
と指摘されていました。

たとえば、
「勇気とはよいものか、どうか」
という議論をしているとしましょう。
ここで、
「勇気を持つとは、よい行いをするのを恐れないことだ」
と、恣意的な説得的定義を仕掛けてくるひとがいるとしましょう。
この人は、
・勇気を持つとは、よい行いをするのを恐れないことだ
→だから勇気とはよいものだ
と説得してくるかもしれません。
なんか、それっぽいですね。良さげです。

しかし、
「勇気を持つとは、よい行いを恐れないことだ
⇒だから、勇気とはよいものだ」
は、よく見ると、同じ言葉を繰り返し言っているだけのことです。
つまり、同語反復……トートロジーですね。
加えて、情緒的・評価的定義は、前提を疑うことを忘れさせます。
そして私たちは、なんとなく説得された気分になってしまうのです。

「定義からの議論」の注意点 ②語源が根拠
2つ目の例は、「語源おじさんに気を付けろ!」という話です。
語源詐術による誤った定義については、
どんな論理学書にも書いてあることで、
ここでわざわざ取りあげる必要もないほどのものであるが、
現実にはこの種の定義に騙されてしまう人が非常に多い。
ある言葉の「真の」「本来の」「正しい」意味の根拠として語源を持ち出すのは、考えてみればおかしな話で、われわれが現在使っている言葉が、語源によってその使い方を拘束させなければならぬ理由はどこにもない。
しかし、この種の定義はいかにも学問的な衣装をまとって現れてくるので、それに接する者はつい気後れがして、無批判に受け入れてしまうのである。
さて、ここではよく現れる語源おじさんの例を見てみましょう。
「学ぶの語源はまねぶ。型を真似ることが学びの本質だ」みたいなそれらしいこと言う「語源=本質」おじさん、いますよね。
— 白山 鳩/note連載中 (@mbapigeon810) May 17, 2021
あれ、「語源であるという事実」をそのまま「真理である」こととすり替えていて、セコいなといつも思うんです。
「”logic(論理)”の語源は”logos(言葉)”です。なので”論理=言葉”なのです」
— 白山 鳩/note連載中 (@mbapigeon810) May 3, 2021
という話を昔聞いたのですが、さっぱり理解できませんでした。
「”哀れ”の語源は”あはれ(趣深くて素敵)”です。なので、”哀れ=趣深くて素敵”なのです」
と説明されたら、「なんか勘違いしてないか?」と思いませんか?
特に「論理とは言葉だ」おじさんは、かつて鳩が受講したロジカルシンキングの研修で出現しました。
「言葉の定義を大切にすることが、ロジカルシンキングでは特に大切だ」
とおじさんが語っていただけに、
「言葉の定義を大切にしてんのか、
人をだましてんのか、
何が何だか わからない……」
という感情のまま研修を終えたことをよく覚えています。

議論の技術② 類似:正義原則、相互性の議論
「定義」に続き、2つ目に紹介するのは「類似」からの議論です。
ここでは「正義原則」という、得も言われぬ響きの言葉が紹介されています。

みなさんもこの記事を読んでぜひ明日から、
「ああ、その議論は”正義原則”に適っているね」
と華麗に語るスーパービジネスパーソンを目指してください。

さて、正義原則とは、
「同じ本質的範疇に属するものは同じ待遇を受けるべきである」
という考えです。
Aという事例に対してSという扱いをしたならば、
Aと「同じ本質的範疇に属する」(本質的諸点において類似している)事例BについてもSという扱いをすることが正義に適っている(公正である)とみなされる。
もし敢えて他の扱いをしようとするならば、それを正当化する理由の説明が要求されるのである。
簡単にいうと、「ダブル・スタンダードを許すな」という考えです。
「『あれは秘書がやったことで……』は通用しない!」
と、与党議員を批判していた野党政治家がいるとしましょう。
そんな政治家がある日、今度は自分がスキャンダルに見舞われた際、
「あれが秘書がやったことで……」
と会見したとしても、これまで自分が批判していたときと同じように批判されることでしょう。

このバリエーションとして、同書では、
「相互性の議論」
にも触れています。
要するに、
「おまえがそうするなら、こっちもそうさせてもらうわ」
という議論です。
「類似からの議論」への反論
「類似からの議論」では当然AとBが類似していないといけませんが、
AとBがたいして似ていない場合、
「それとこれとは話が別だろ!」
と言われかねません。
香西さんは、
「英語が上手になりたければ、学校の授業以外でも勉強が必要だ」
という福原麟太郎氏の議論を引用しながら、次のように解説しています。
福原氏は言う。
「野球選手だって水泳選手だって、
体育の時間だけであれだけ練達したのではない。
国際社会で外国語の選手になりたければ、
野球や水泳の選手なみに猛訓練を受けるべきである」。
これに対して次のように反論したとすればどうだろうか。
「英語の時間には英語だけを勉強しますが、
体育の時間には野球や水泳だけを練習するのではありません。
したがって体育の時間だけで野球や水泳がさほど上達しないのは当然です。
もし、英語の時間なみに野球の時間水泳の時間というのがあれば中高六年間で相当上達するはずです。
英語は学校の授業時間だけでは上達しないなどというのは言い逃れです」。
福原氏の、
「学校での英語」≒「学校での野球・水泳」
という類似からの議論に対して、
「それとこれとは話が別だろ!」
という指摘をして反論しているわけですね。
そもそも、ある事柄を別の事柄と比較している時点で、
大なり小なり「つっこみどころ」を用意しようと思えば、いくらでもいちゃもんをつけられます。

類似からの議論は強力である一方、
「差異を指摘されると弱い」
と覚えておけば議論のときにうまく突っ込めることでしょう。
まとめ
さて、ここまでの内容をまとめましょう。
【「定義」には、次の3つがある】
①記述的定義(辞書の中で見られる定義)
②規約的定義(「私は○○という意味で使います」という個人的な定義)
③説得的定義(②の規約的定義をこの世の真理のようにして相手を説得)
【「定義からの議論」の注意点】
①情緒的・評価的定義
「よい」「悪い」といった情緒的・評価的定義は、トートロジーに陥りがち
②語源を根拠にした説得的定義
ある言葉の語源を利用して、「なのでこの言葉の本質は~」と語る説得的定義は、典型的な詐術だが、無批判に受け入れてしまいがち
【正義原則】類似からの議論
「おまえが言うな」「ダブル・スタンダードを許すな」の原理。
ある主張をした人が、主張と異なる行いするならば、それを正当化する理由が必要。
【類似からの議論は、差異を指摘されると弱い】
類似からの議論は、「それとこれとは、話が別だ!」と指摘されると、途端に弱身を見せる
以上、議論の技を学ぶための『議論入門』から、
「定義」「類似」からの議論を見てきました。
次回の記事では、引き続き『議論入門』から、「譬え」「比較」からの議論を見ていきます。
お楽しみに。
to be continued...
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
