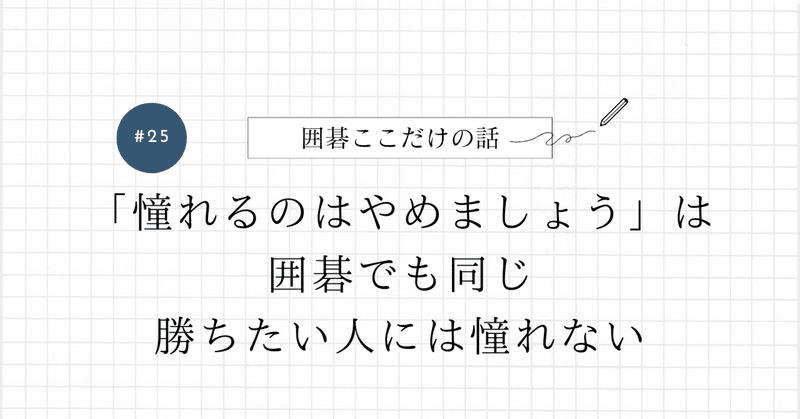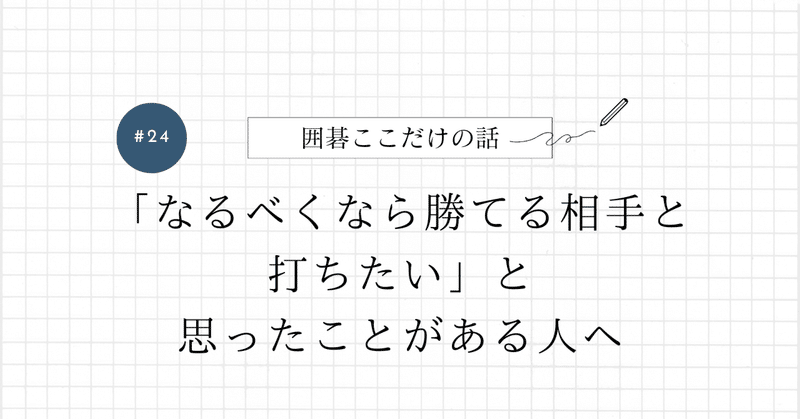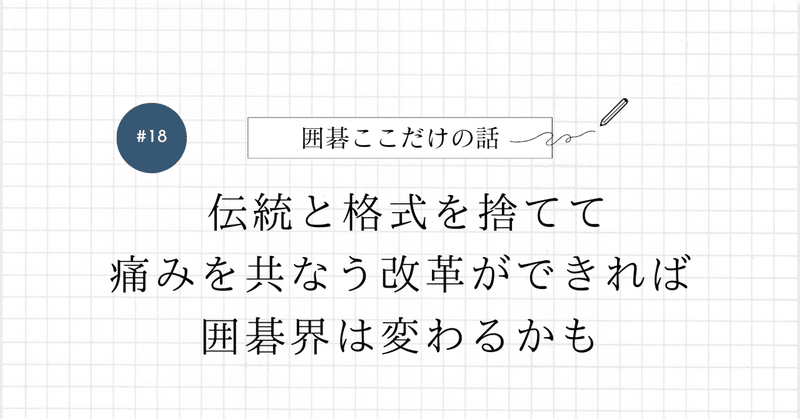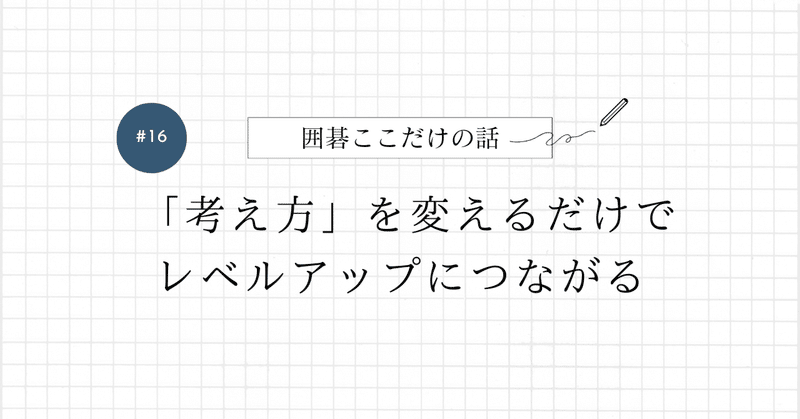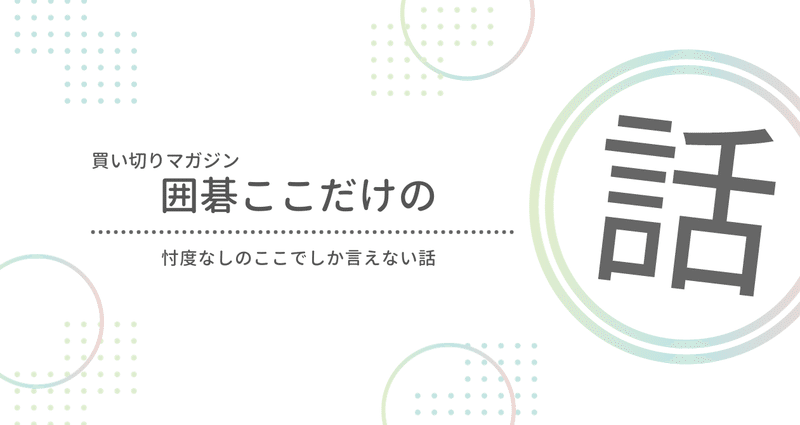
- 運営しているクリエイター
#自分
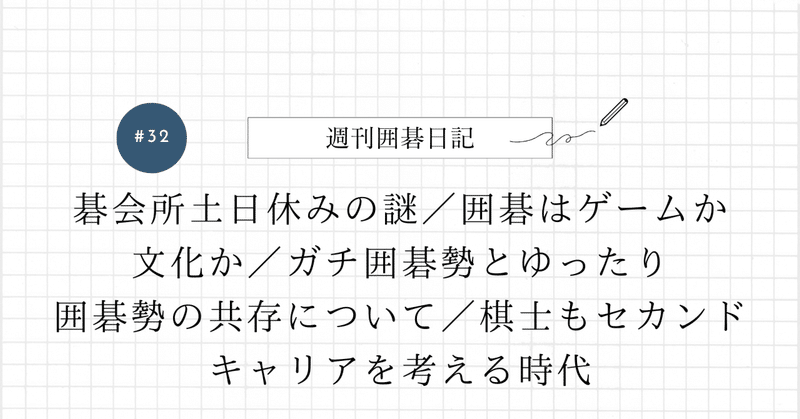
#32 週刊囲碁日記/碁会所土日休みの謎/囲碁はゲームか文化か/ガチ囲碁勢とゆったり囲碁勢の共存について/棋士もセカンドキャリアを考える時代
こんにちは。瀧真有子です。GWも終わり、日常が戻りましたね。 囲碁の世界はGWなどほぼ関係ないようです。プロの対局が大型連休と無関係なのはもちろんのこと、イベントなども、囲碁のビジネスの場合、人の余暇の時間をいただいて、自分たちの仕事に変えていかなくてはいけないわけですから、休日は業界人にとって稼ぎ時なのかなかな、と思っていました。 という中で、Xでは、下記のような記事に反響がありました。 麻雀を楽しんでいた方が、囲碁を始めたことで、苦労していることをまとめた内容ですが
有料
500