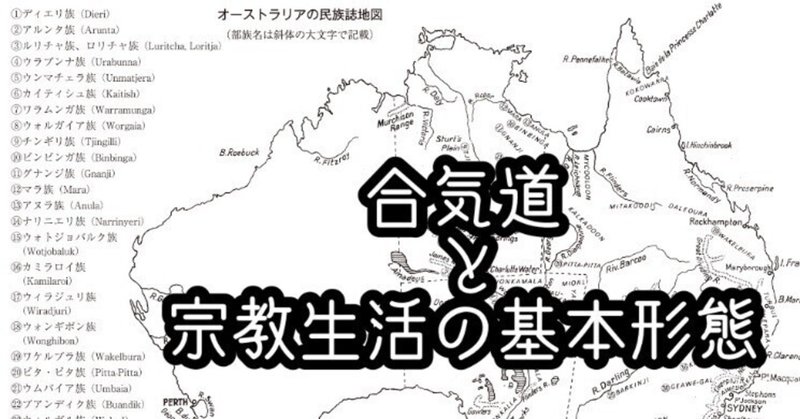
集団と個人のどちらが宗教を産み出すのか?【宗教生活の基本形態と合気道⑤】
宗教の発生は必然なのか偶然なのか、個人からなのか集団からなのか?
原始の宗教を探求することでそういうことも明らかになる。
輪廻転生について
輪廻転生は祖先崇拝のひとつの形で、先祖の霊は再び人になったり、あるいは他の動物になって家族の元へやってきたりするというもの。
こうした輪廻という発想はまず家族が安定して生活できるレベルまで文明が築かれないと難しいらしい。
トーテミスムは逆に集団を重視していて、神話と地続きの集団生活を生み出しており、それは自然との一体化を目指すものともまた違う。
個人と集団どっちが先?
トーテミスムから考えると集団こそが先にある。
神話の根源は「拡散するエネルギー」であり、プラスの現象もマイナスの現象もあらゆるものを神が司っており広がっていく。

分類するためにはまずそれだけの群が必要だ。
トーテミスムの拡散は人類の拡散とも変わらない。
1人の人間から産まれて増えて拡散していったのと同じように宗教も人が増えるとともに人々に拡散した。
なぜなら人が増えてはじめて分類が必要になるからだ。
集団が神聖さを感じた時に神が産まれ、集団が大きくなるにつれてさらに様々な形に神が拡散されていく。
そうしたプロセスの原点がトーテミスム。

つまりは集団から生まれ、分類と分散から生まれた信仰の形だ。
禁忌の存在
人と言うのは忘れる生き物で、神の存在も忘れられがちだ。
トーテミスムでは時にすべての部族が集まって、あらゆるタブーを破るという集会を行う。しかも2週間。

そうすることで強烈な印象を残しつつ、日常ではトーテムが身近にあることで神のことを片時も忘れないようにできているのかも知れない。
身近なほど忘れにくいけれど、身近なほどありがたみも感じにくくなる。それを祭りという非日常をつくることで思い出させる。この循環が信仰の維持に役立つ。
そういう意味では合理的な集団の管理システムでもあるのかも知れない。
合気道と二重性
この日常を非日常と二重性は合気道にも通じる。
武道というのは一般的には日常では使えそうもないけど、むしろ日常でこそ、合気道の要素を分解して考えてみるというのが修業のひとつになる。

合気道というのは分析の一手法でもあるし、物事の共通点を探す練習だ。
信仰というのもそういうもので、反転して色んな場面で使っていくことが大事なのだろう。
関連記事
マルセル・モースの『贈与論』と考える合気道と贈与
レヴィ=ストロースの『野生の思考』から考える合気道と人類の構造
エミール・デュルケームの『宗教生活の基本形態』から考える合気道と宗教
マツリの合気道はワシが育てたって言いたくない?
