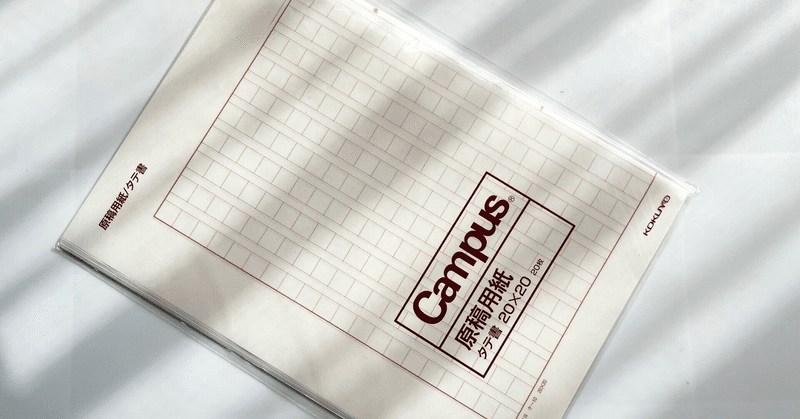
『パッシブ・ノベル』(創作大賞ver)第一話
九月下旬の休日、安達は想いを寄せる六歳下の薬剤師・智鶴さんと、その恋のライバル・白井との三人で中古本を売るフリーマーケットを開催する。安達は、甘い恋心とひりつく競争心のせめぎあいを、理性的な計算で乗り切りながら自らの優位性を構築していく。そんな中、白井が小説を書いていることを知り、感想とアドバイスを求められ、その計算の都合上読むことになるのだが、読み終えた直後からトラブルが発生してしまう。白井の小説に込められた「力」に翻弄される安達と智鶴。「あれは無色の虹。パッシブ・ノベルなんだ」。白井の真意とはいったい何なのだろうか。
むせるような長い残暑が、やっとのことで去った九月下旬の休日、図書館前のプロムナードで中古の本を売るフリーマーケットのテントに、スタッフとして僕は居た。
少々黴臭いのは本たちのせいでもあるし、古びたテントのためでもある。その中からすっと立ちあがって新鮮な空気の世界へと抜けでた。しばらく客が途切れていたし、智鶴さんとの会話もすとんと落ち着いてしまっていた時間帯だったからだ。
午後の黄色くまるい日射しを全身に浴びた。つかの間、舞い上がった気持ちをいくらか落ちつかせたかったのだけれど、速く強い脈拍は我が道を行ったまま、加速こそしなかったにせよ、同じスピードで走り続けていた。
遠くの低い山々を見渡す。それらに四方を囲まれた静かな町のほぼ中心に位置するのがこの図書館だった。
視界には、ぽつら、ぽつら、と薄く小さな雲が五つ、六つ浮かんでいた。今にも別世界へと旅立ち、消え去っていくかのような、儚げな雲たちだった。でも、そちらをまず気にしたものだけれど、今日の主役は断然、雲たちよりも大空のほうだった。
雲たちが自らの揺るぎない舞台としている大空の、今日の青の密度。こちらの肺の奥にまで沁みわたってくるような感傷的な色味、厚みがあるのにあっさりとしてもいるその青がいつにも増して僕の目を惹きつけてやまない。そこには永遠に答えを知らされることのない底なしの謎のような魅力が溶け込んでいた。様々な解釈を許す大空だと言えた。
眺めれば眺めるほど、言葉が意味を成さなくなっていく。正面から向き合ってこそ気付くことだが、大空を構成する多義性って、きっと人知を超えているのだ。
その大空の姿が放っている、伝わるに違いない人だけに向けた訴えというものが実は存在する、と僕は感じ取る。なぜわかるのか? 僕はそれを受け取ったからなのだろう、つい泣き出しそうになったからだ。切ないからじゃない。悲しいからでもない。たぶん今の恋心と反応を起こしたからだった。
恋心。そう、最っ高の店番を、まさに僕は今していた。なぜ最っ高かといえば、恋心がずっとはぜ続けるベスト・オブ・ザ・ワールドの店番、つまり至福の店番だからだ。そう、智鶴さんなのだ。
だけどもしも、その恋心の背後で手綱をひく理性の手元が狂い、万が一にでも御しそこねてしまったら、と考えると、もの恐ろしく感じた。それに、だ。恋心が想定よりもずっとはぜてしまって、そのサポートに多くの力が必要になることだって十分に起こり得るのだし、そこでの対応がうまくできるかどうかに自信があるとはちょっと言えなかった。対応できなければ、氾濫した恋心の濁流が理性の防波堤を乗り越え、これまでたくさんの時間をかけてわずかずつ造り上げてきた「好印象の像」を突き倒していってしまうだろう。かすり傷では済まない被害を受ける。間違いなく。
意識のどこかで自身を客観的に見つめ、冷たく監視する集中力を切らさないでいられることが、今のこの状況の大きなポイントだった。理性による統制下でならば、心を全面的に向けていていい、テントの下、共に本を売る智鶴さんへと。
それはそうと、どうして智鶴さんに恋をしているのと、空の素晴らしさとが反応するのだろう。お互いに通じるキュンと胸をつく気持ちは一体なぜなのか。
考えていると大学生の頃にバイト先で川村先輩が言ったことを思い出した。スーパーマーケットの休憩室で教え諭すように、でももそもそと聞きとりづらい、いつものそんな口ぶりで彼は話してくれた。
「なあ安達。恋をするとなにもかもがそれまでと違って見えるようになるっていう話、聞いたことあるか? ある? じゃあどうしてかわかるか。わからない? そうか。じゃあ俺が特別に教えてやるから聞いてみるか? よし。恋人同志になっての大目標って、はっきり言うけどセックスだよなぁ。将来の初セックスを達成する時点を固定して、そこから振り返るように考えてみるとわかることがあるんだ。セックスって、なにかのプレイとか強姦とかじゃなきゃふつうはお互い裸になってするものだろ。それはいきなりだと恥ずかしいものだよな。なんだ、照れた顔なんかして。ここからが大事だから、そんなに照れずによく聞いてくれよ。それでだ。だから肉体的な裸に先駆けて、まず心を裸にしてみせあって予行練習するのが恋愛の進行ってものの、実は内実なんだよ。それに相手がどんな人なのかがわかってくる段階じゃないとセックスするのは危なくもあるからな、だから大丈夫だろうかって予行練習するんだ。で、恋をしていないときの心はふつう、裸じゃない。まあ、いつだって裸に近いヤツもいるけど、それはちょっと例外とする。ふつうは誰に対してでも心を裸にしてると、不意に傷つけられたり、悪意のあるヤツに見つけられたなら標的にされて痛めつけられたり、まあ生活が持たないと思うんだ。でも恋人同士でだったらな、お互い好き同士なんだし心を裸にしてても攻撃なんかしあわなくて優しく撫で合うものなんだよな。恋をしてると世界が違ってみえる、生きいきとして見えるのはなぜか。心を裸にする時間ができたためだよ。もっと解説するとだな……」
つまりは、恋によって心が裸になっているぶん感度が上がるんだ、ということだった。敏感で傷つきやすい半面、たとえば裸でいることで外れた五感の防御フィルターは、いつもだったなら素晴らしい大空からの訴えの多くを余分なものだと判別して跳ね返してしまうところだけれどそれがなくなり、跳ね返されずに素直に伝わってくる。
だからこそ、心が裸である僕の今日の一日はほんとうに生きている実感に満ちていた。智鶴さんのおかげで、世界が何倍にも豊かになっているんだ。空と恋とのその源にある共通項については正直よくわからない。でも、空と恋の共鳴は、僕の内部にちゃんとハートが備わっていることを教えてくれる。相手に対してかけがえのない想いがして、嬉しくなって、知るんだ。観念でしかないはずのハートが、マテリアル然として実際、僕の内部にきちんと存在するようだ、と。ふだん、計算ばかりを頭でしがちな僕であっても。
車道に面した花壇には黄色いマリーゴールドが列を成していて、近くのバス停には紺色のリュックを背負ったじいさんがあたりに視線を漂わせながらバスを待っていた。さっき、僕たちから月の写真集を買っていったじいさんだった。
まもなく到着するバスから、白井が降りてくることになっている。携帯で時刻を確かめる。一時五八分着だから、あと七分だ。白井の到着を思うと、裸の心の居心地が悪くなった。
ちゃんと服を着ていなければいけない。さらには鎖帷子でも着込むとか。そんな気構えじゃなければ、白井との対峙に耐えられなくなりそうだ。丸裸で会っていい相手ではない。あいつがどんなふうに考えているのか、はっきりとはわからないにしても、智鶴さんを間にすると僕とあいつはおそらく敵同士なのだから。
表面上は友好的に接しあっているが、少なくとも僕にとってはその水面下では凍えそうなくらい気持ちが強張っている。
バイトの先輩だった川村先輩は、こういう場合の対処法についてはなにも教えてくれないどころか、彼との間ではかすりすらしなかった。川村先輩も僕も、当時まだまだ牧歌的な世界にいたのだ。想い想われるだけじゃ割り切れない三角関係の息の詰まる水中戦なんて、現実の話ではなく、小説やテレビドラマなんかで扱われる劇的な想像物の範疇のものしかないと、自分たちから切り離していた。今振り返ればわかりすぎるほどだけど、僕はもちろん、もそもそした口調で語るイデオローグである川村先輩だって、ずいぶん人間の厚みがぺらっぺらだったのだ。
白井のバスの到着時間まであと三分を切った。武者震いこそしなかったけれど、全身にどことなく余分な力が入り始めている。
現実はおもむろに刃先を見せて迫ることがある。そんなときはどうする? こちらも刃先を見せて受けて立つか、それとも睨み合いながら間合いを外すか、その場からあとずさって逃げの手にでるか。あるいは、丸腰だったなら、はったりをかまして心理戦に持ち込むか、一目散にその場から走り去るか、さっさと白旗をあげて現状の保証を乞うか。
三角関係に陥るということは、そういった局面を迎えることに近いと思う。この局面にいると体力的にも精神的にもとても消耗することを知ってしまった。白井だって僕と同じか僕以上に消耗しているんじゃないだろうか。いやいや、そうじゃないとまずい。白井の消耗がそれほどではなかったならば、ここぞという時に勝負をしかけても簡単に跳ね返されてしまいそうだし、反対に向こうから勝負をしかけられたときには、その太刀筋の素早さにうまく対応できなくてあっという間に打ち負かされてしまいかねない。
率直に言うと、白井が今どういう心理状態でいるのかまったく読めていない。表面上、あいつの表情やふるまいにはなんの苦しみもダメージも迷いも浮かんではいないからだ。智鶴さんと僕と白井は、三人集まるとまるで三人だけの仲良しの友人同士というような様相になる。だから、自分たちを遠くから眺めるようにして考えてみると、僕は単なるひとり相撲をとっているだけなんじゃないかと思えてきさえする。智鶴さんを好きなのは僕だけで、実は白井は恋愛感情で智鶴さんを見ていないのではないかと。
智鶴さんは智鶴さんで、気のせいかもしれないけれど、白井に対するときの目許の表情がわずかながら僕へのものより屈託のないように感じられるのがひっかかった。
白井に恋愛感情がないとすれば、僕が智鶴さんを好きだということをはっきり白井に告げて、邪魔をしてくれるなよなり、応援してくれよなり言えば、局面はがらりと変わるのではないか。というより、僕の頭にへばりつく今の苦しみの局面は、ただの幻想にすぎないものとして片付き、解放へと向かうのではないか。
バス停のじいさんがリュックの背負い紐を両方ともがっしりと掴んでたたずまいを直しながら右方を向いた。白地の横に赤のラインが入ったバスがやって来る。そのバスから白井が降りてくるのかと思うと、マスクのなかで吐く息が思わず太くなった。
僕はフリーマーケットの少し黴臭いテントに戻り、智鶴さんに「今日の空はほんとうに気持ちいいよ?」と声をかけた。それまでの楽しかった気分が名残惜しかった。そのとき智鶴さんが、ひこうき雲、と言ってわずかばかり細めた目の表情が生きいきとしていて素敵で、今このときからしばらく時が止まればいいのにと思わず願ってしまった。
振り向いて再び空を仰ぐと真っ白いひこうき雲が直線状に引かれはじめていた。
「ほんとだ。」
向き直ると、風が遊んで、台の上で平積みの古い映画誌のページがぱらぱらとめくれていった。
「何冊、売れましたか?」
無骨さのある短く刈りこんだ髪形の白井は、黒のカラージーンズを履き、灰色のショルダーバッグを下げた朽ち葉色の格子柄のネルシャツ姿で、テント前に立ち止まるとめがねの曇りを気にしてマスクを一度顎下までずりさげながらまず僕に尋ねた。
ついに口火が切られてしまった形、案じていた局面が進行していく形だ。実際ほんとうにただの幻想だったらいいのに、というさきほどの思いがぐちゃぐちゃと葛藤を起こしはじめる。めまいのように回転する心中に気を取られつつ、売上表に書き込まれた書名の数を数え始める。視線が文字の上を何度も上滑りしてしまう。
「お仕事お疲れさまでした。来て頂けて助かります。すみません、ご無理させてしまって。」
隣に座っていた智鶴さんが身を乗り出すので、売上表から目を持っていかれた。目許も声音もとてもやわらかい。売上表をつかむ指に力が入り、端がぐしゃりと歪んだ。
「前からシフト希望をだしてましたし、なんでもないですよ。それに楽しみでした。」
気持ち口角をあげてみせる白井の働くホームセンターはこの町では一番大きな店だ。白井は二年前の春先に秋田県から移住してきた。以来、パート勤務をしている。一度旅行に来て北海道の雰囲気がとても気に入り、そのときから移住を考え始めたのだそうだ。こんな田舎町でも、彼の故郷よりずっと人自体がさっぱりしているのだという。智鶴さんと白井と僕の三人で食事をしたとき、この町は世間が狭くて窮屈じゃないかと聞いても、白井は微笑むだけだったのを覚えている。今みたいな口角の持ち上げ方だった。
「二七冊。当初予想していたよりいいペースで売れてる。絵本を一三冊買っていったお母さんがいたのがデカい。」
事務仕事の口調になったのは、二人の間を漂いだした空気がおもしろくなかったからだ。熱を帯びる前に、冷ましてやりたい。
「僕が出した文庫本は軒並み並んだままですね。」
白井は背表紙を並べた文庫本の列が四列、みっしりと収まっているダンボールを眺めつつマスクをつけ直している。
「今日は大型本や単行本が、なんだか売れる日みたいで。私の文庫本もまだ手がついていないです。」
間を置かずに話を引き取る智鶴さん。
悔しいけれど、どうやら温まっていく雰囲気には抗えないことが瞬時に察せられた。それじゃ僕も話の流れに乗ってやろうと気持ちを翻して言った。
「僕の新書もまったくなんだよ。興味を惹くものばかりだと思ったんだけどな。わかんないものだね。」
フットワークの良さでの勝負を試みる。
「私のも、読んでよかったぁって思ってもらえそうなものばかりなんですけど。まるで。」
智鶴さんが、久々に僕の目を見てくれた。ふう、なんだ、ちょっと焦ったけれど、簡単に追いつけたんじゃないかな。
「僕の海外古典だって贔屓目じゃなくても良いもの揃いなんですが、やっぱり好みの問題なんでしょうか。」
白井は同意を求めるような目つきで、僕と智鶴さんを交互に見た。
「でもまあ、僕らの出した本ってのは、はっきり言わせてもらえば全部そうとう地味だし、お客さんの目にまったく留まらなそうではあるんだよね。客層が違うっていうか。」
腕組みをして軽く鼻を鳴らした。万座爆笑を予期したのだが、智鶴さんと白井は悲しげな顔をして俯いてしまった。
すみません、と声がした。白井の後ろから三〇代くらいの女性が二人、顔をのぞかせている。どうぞどうぞ、見ていってくださいと応えた。いらっしゃいませ、どうぞご覧になっていってくださいと智鶴さんにもさっと笑顔が戻った。白井も、ごゆっくり、と客の二人に声をかけ、テントの内側へとするりと移ってきた。
さきほどのひこうき雲は長く南へたなびききり、智鶴さんが声をあげたときに比べて、もはや上空のつよい風にほどけて薄くなり、まったく動じることのない大空を背景に、太く歪み、曲がりくねってほとんど消えかけていた。
白井が図書館のトイレに行っている間、隣で智鶴さんがため息をついた。売り上げがもうちょっと欲しいのかな、と聞くと、それはそうなんですけど、ともう一度浅く短いため息を吐いた。
「安達さんには教えてもいいって白井さんは言ってるんですけど。」
安達さんとは僕のことだ。
「うん。なんだろ。」
「白井さん、実は小説を書く人なの。毎年新人賞に応募しているんですよ。でもこの町じゃ珍しいでしょう、同人誌をやるったってまるで仲間がいないくらいに書き手はいない。かといってネットで仲間を作って同人誌をやるのは性に合わないって言ってるし。投稿サイトも好きじゃないみたい。それでもとにかく書きたくて、書きあげたものをいろんな人に読んでほしくて。それで、読んでもらうのに一番いいのはプロになることだって、もう自分が歩く道はこうだって決めたんだって。」
「そう教えてもらうと、そんな雰囲気はあるわ、白井さん。もとからそういう人だったように思えてきた。」
「彼は海外小説が好きだし、読んでいる割合もそういったものにずいぶん傾いている。だから、自分の文体がどうしても翻訳文みたいになるのをどうにかするべきなんじゃないかって考えていて。わたしは反対に日本の小説ばかり読むほうだからアドバイスを頼まれるんだけど、でもわたしが読むもののほとんどは女性作家のものだから、あんまり助けになれなくて。男性作家の文体の傾向だとか文章の性質だとか、違いがあるでしょう?」
「僕はノンフィクションばかり読むタイプだから、もっと助けにならないだろうな。」
「ううん。小説を書くには小説ばかり読んでいてもだめだって白井さん、言ってました。だから安達さんに相談して、これは読んだほうがいいっていうノンフィクションをいくつか教えてもらいたいって。それに、白井さんが書いているもののなかで現実味を増した方がいいような部分を指摘して欲しいって。」
「それは、僕に白井さんの書いた小説を読んで感想や助言をもらいたいってことなのかい?」
「たぶん、あとで頼まれると思う。言いだしにくそうだったら、わたしが仲介するかたちでと考えていました。どうですか? なんだか白井さんより先に根回ししているようになってしまいましたけど、わたしとしても安達さんに力になってほしいんです。」
「そっか。考えておくよ。しかしなんだか重大な任務のような気がして気後れするんだけど。智鶴さんはもう読んだんだね?」
「はい。三作品読みましたよ。一番最後に読んだのが、白井さんのとっておきで。これから時間をかけて直していきたい作品だそうです。この作品を安達さん、頼まれると思います。」
「ちょっと前知識いれておきたいな。内容を軽く教えてくれないかい。」
「それは無理なんです。」
きっぱり言い切った智鶴さんの眼光が一瞬、奇妙なほど鋭利になった。それから目の表情の色がなんら前兆すら見せずにすとんと消失した。不意打ちをくらったように僕は気圧され、心ならずも視線を逸らさずにはいられなかった。自然と呼吸も弾みだす。
「え、なんで?」
「先入観なしに、白井さんの作品世界に触れてほしいからです。」
智鶴さんの視線が気まずそうにどこか所在なげに宙をうつろう。
「それだけ? なにかがさ、あるんじゃない?」
反対に僕が場の空気を損ねだしてでもいるようになってきて急激に居心地が悪くなった。ソーシャルディスタンスを保っている智鶴さんと僕との間が、急に一枚の透明な膜の出現にぐいと深く隔てられた気がした。コロナ禍のほとんどの店で使われているアクリルの透明な板やビニールシート、これらによって仕切られているときよりもなにげなく隔てられた気はしたのだけれど、しかしながらそこにはなんらかの意思がしっかり存在し、ぽーんと突き放された距離感みたいな心理的生々しさがあった。それは仲間外れを静かに決行されたときの空気のように。
無言の智鶴さんに、繰り返し「ほんとにそれだけなの?」と聞いてみたが、人が変わったように口をつぐんでしまった。智鶴さんの頑なさは、露骨な反応ととれる。白井の小説に、何かひっかけがあるのかもしれない。あるいは、僕に読んでほしいというその頼みごとの意図になにがしかの裏がある。そして、智鶴さんと白井の間に、なにかの結託があってもおかしくはなさそうだ。不気味さよりも嫉妬を覚えた。
すこしでもヒントをひっぱりだしたくて、智鶴さんへの巧い声のかけ方を考えてみたが、そうとは思いつかずやきもきしているうちに客が来て智鶴さんが応対し始めた。
ツバ付きのニット帽をかぶった若いお母さんと赤い薄手のキャラクタートレーナーを着た幼稚園児くらいの歳の女の子の親子連れだった。絵本ってどんなのがありますか、と智鶴さんに聞いている。どうやら今日はほんとうに絵本のでる日だ。
本を売るテントの右横に重い存在感を漂わせる図書館のファサードは、全面がガラス張りでところどころ淡い白色の光がつるんとした曲線状に反射しくるくる動いている。その奥から白井が出入口のドアへ近づいてくるのが見えた。
あのひこうき雲はもう散っただろうな、どこまで散ったかな、とテントの影から抜け出て大空を見上げると、すでに跡形もなく消え去っていて、どこにあのひこうき雲が引かれていたのか、そのだいたいの位置ですら見当をつけられなかった。
親子連れの客は、絵本を二冊購入して帰っていった。主に応対した智鶴さんはいつもの笑顔に戻っていたし、親子連れとは和気あいあいのやり取りをして、テント内に戻ってからの僕は複雑な気分だった。けれど、なんにせよほっとしたのだった。
白井がトイレから戻ると、入れ替わりで智鶴さんが図書館内のトイレへと立った。白井と二人きりになる。プロムナードをかすめるように黒い犬と散歩する中年の女性の姿を眺めた。
「安達さん、ご存知ですか?」
屈託のない声かけだった。
「なにをかな。」
犬を連れた婦人の姿をまだ目で追っていた。朱色と灰色のウインドブレーカーにピタッとした黒のパンツ。大きなサングラスをしている。
「このフリーマーケットの売り上げの行きどころですよ。」
「そういえば聞いてなかったな。智鶴さんの収入というわけではなさそうだけど。」
黒い犬は芝生の中に何度も入りたがるのだが、婦人は意に介さずリードを強く引きながら直進する。そのまま建物の陰へ歩き去っていった。
「図書館に寄贈する新刊の資金にするそうです。あと読書会の足しにしてもらうと。ここに集まった本はほとんど読書会のメンバーたちからのものだそうです。」
テントの屋根が視界の妨げになっていたので背を縮め、上目遣いで右前方すぐの図書館を見た。建て替えになってもうすぐ一年が経つ図書館だ。
「そういえば智鶴さんに読書会に来ませんかって誘われてた。白井さんは読書会に参加してるの?」
「いえ。僕はあんまりそういう、多人数の集まりって苦手で、避けてしまいがちなんですよ。」
「白井さんはどこで智鶴さんと知り合ったんだったっけ?」
「図書館でですよ。同じ棚の前にずっと二〇分くらい隣同士で立っていて。まあ僕にしてみればいつもの海外小説棚なんですが、智鶴さんにとっては珍しく探しものでその棚に来ていて。智鶴さんは作家名も小説の名前も忘れてしまって、おまけにスマホを車内に置いてきてしまっていて、どうにか思いだそうしていたみたいですけど無理で、僕に声をかけてきたんです。ずいぶん昔に映画化されていて、とても有名な女優が主演で、アカデミー賞を獲ったんじゃなかったかなあ、その原作なんですが、と。『ピグマリオン』だったんですけどね。」
「ごめん、知らない。」
そうですか、といって白井はマスク越しに鼻の頭を掻きながら少しだけ微笑み、そのあとしばらく沈黙が続いた。小説家になりたいんだって? と聞きたかったけれど、智鶴さんのあの態度が硬直化した場面が頭をよぎったことで、なんだか言いだす気がしぼんでいった。くわえて、それがずっと頭にこびりついて離れず、会話を再接続するためのきっかけになるような他の話題をなかなか思いつけなかった。
「あのさ、秋田より暮らしやすい?」
ようやく声がでた。別に話を続けなくてもいいかなという気になってはいたのだけど、白井が秋田出身だったことをはっと思い出すと考えるより先に話しかけていた。
「はい。伸びのびと生活できています。パートだから収入は少ないですが、贅沢しなければ、まあなんとかなっていますし。」
「白井さんさ、全然なまらないよね。」
「小さい頃からなまりが嫌いだったんですよ。標準語でばかり喋るようにしてて。だから嫌なこどもだったんですよ。自分はみんなと違わないといけないって思ってる雰囲気、隠せませんでしたから。」
「居心地が悪かったってそういうことだったの?」
「ええ。それも大きいです。」白井は視線を一段下に落とし、「僕とは理由が違うようだけど、智鶴さんも居心地が悪かったって。学生の頃まで。」そう言いきってから眼鏡を指で持ちあげ、そして顔をあげた。
白井の穏やかな目の表情に、軽い真剣さというか浅い深刻さというか、さきほどまでとは打って変わってほのかな影が差しこんでいた。
「薬学部って六年でしょ。それだと居心地の悪い期間が長めだったのかな。でもどうしてだろう。智鶴さんからはそんな感じしないけどなあ。」僕は商品台を蹴らないよう静かに脚を組んだ。
智鶴さんは薬剤師だ。それより、白井は智鶴さんとそんな個人的な話までしていたのか。憎たらしい。はっきりと遅れを取っているその嫉妬心で胸がむかむかしてきた。
「智鶴さん、誰かが陰で人をバカにしたり悪口を言ったりするのって、ほんとうに受けつけないんですって。そういうのはたとえ心の中で思ったとしても、言葉にして他人に言うべきじゃないっていう主義だそうですよ。」
「女子の世界ではとくに居心地が悪そうだね。これは女子への偏見というわけじゃないと思うけど。」
「そうですねえ。大学を卒業後すぐ就職して新しい場に属することになったけど、学生時代よりも個人主義を優先できるようになったからかなり楽になったそうです。」
「人間関係か。智鶴さんも白井さんも。」
「安達さんも人の悪口は言わないじゃないですか。だから智鶴さんは、安達さんにもこのお手伝いをお願いしたそうですよ。」
好印象を持ってほしい相手の周りでぺらぺらと誰かの悪口をいったりなどするもんか。間近の人間の目に映る自分の印象にはけっこう気を配るほうなのだから。簡単にいうなら、計算。そして、計算していることを悟られないようにするのも、さらに計算の業だった。僕の理性の防波堤は堅固なのだ。白井程度にはけっして破られないだろうと思う。
「人の悪口を言うほどヒマじゃないから。」
きっぱり言ったが、嘘の成分が八割はあった。
「思うがままに悪口を言う人は、自分の悪い部分を自制していないから偽善者にあたるっていうようなことを智鶴さんは言っていて。智鶴さんの考え方ってそうなんですよ。」
僕は悪口は言わなかったが、偽善者であることには間違いない。このさい割り切ってしまうけど、自分をよく魅せるため、善く思わせるようなふるまいをするからだ。
人聞きがいいとか悪いとかいう言い方がある。いわゆる外聞のことだ。僕は、外聞のいいような結果になることから逆算して何かを言ったりやったりする。でも、そんなの、誰かに白状しないかぎりわからないじゃないか。
「白井さんもそう思う?」
「智鶴さんの意見を聞くまではそうじゃなかったですよ。やっぱり、心に悪い言葉や考えが浮かんだ時点でもう悪人であって、それを隠すような行為は偽善だって思ってました。でも智鶴さんの考え方は、人が悪いことを考えてしまうのは当り前なんだっていう前提に立っていて。それは人間への諦めってことだし、なおかつ赦しでもある。これって成熟してますよね。」
「だね。僕より六歳下なんだぜ。そんなこと、これまで思いつかなかったよ。」
悪いことを考えてもそれが赦されるとしたら。叶わない祈りのようなものだったとしても、僕はほんとうの裸の心になれるのかもしれない。ずっと最後まで掴んで離さない電卓を捨て去った上での裸。
僕は考える。ほんとうの裸になるには、これまでの立ち位置を大きく変えなくてはならない。そうすると、なんの疑いも無く肩を寄せ合っていたこれまでの人生が、するっと裏返しになって悪友との関係へと翻る。それでも自分の意思で変えた立ち位置からは動かないと腹を決めたならば、その悪友は鬼の形相で襲いかかってくるに違いない。
悪友からの乱暴にはどうやら耐えなければ次にはいけない。逃げるだけでは及ばなくて、がっちり受けとめなきゃいけないのだと思う。そうやって受けた痛みからしか、赦しは得られないだろうからだ。償うわけではないのだけれど、痛みを感じないで赦しを得るなんていうのは都合がよすぎるし、たぶん赦しの効力だって得られないだろう。そういう気がした。
「どうしました? 具合が悪いんですか?」白井が僕の顔を覗きこんでいる。
僕にそんなことができるだろうか。こめかみが痛くなり始めていた。つれて頭が少しばかりふらついた。
「今週、忙しくてさ。ちょっと疲れてるんだ。」
こめかみを指でもみながら、嘘をついた。
智鶴さんが戻った頃からテントを訪れる客が増えだし、四時の閉店まで休みがないほどだった。絵本がよく売れ、ひと昔前の小説の単行本がちらほら売れた。初学者向け科学雑誌のバックナンバーなども売れたし、巻数が揃っていないにもかかわらず古い漫画本を何冊もまとめて買っていった中年男性客もいた。二時間余りで一五〇冊以上の古本が売れたのだった。
売れ残った古本をみんなで数箱の大きくて厚手の段ボール箱にしまい終わると、白井が智鶴さんの車にそれらを運びだしたので、僕は重りとしてテントにぶら下げた水で満たしたポリタンクの、結んだ紐の結び目をほどき、それからテントをたたみにかかる。
テントの脚を崩すときに左手の人差し指の腹の肉を金具にはさめてしまった。強烈な痛みに悲鳴が出たわりにはわずかな出血だった。智鶴さんがすぐさま駆けつけ、バッグから消毒液のはいった容器をとりだしてチューッと指にかけてくれた。指はじんじんじんと強く疼いていて、沁みたかどうかもわからない。智鶴さんは小さなガーゼをつかみポンポンポンと傷口の消毒液をぬぐうと白いチューブから軟膏を薄く塗りこんでくれて、さらに絆創膏を貼ってくれた。無駄のない流れるような手際だった。
「ありがとう、智鶴さん。ドジってしまったな。」
「ううん。テントのほうを安達さんひとりに任せてしまってたから。こちらこそごめんなさい。」
「いやいや。というか、やっぱり医療関係。薬剤師だね。手当てが速いよ。」
智鶴さんはそう言われて照れもせず、そのままの柔らかい眼差しで首を振ってポニーテールを揺らした。それがとても素敵だったのだ。この瞬間を記憶に刻みつけなければ、と即座に念じたほどに。
ワンテンポ遅れて駆けつけてきた白井が、大丈夫ですか、と心配してくれる。白井に向けたものとしてはお釣りが欲しくなるくらいの笑顔で肯いてしまった。耳がじんわりと熱くなる。
すべての後片付けが終わった頃、闇に溶けていきそうな夕焼けが僕らを照らしていた。智鶴さんはポニーテールをほどいた髪を指で梳いている。それを横目で眺めていた。気付かれないように、ずっと。
第二話↓
第三話↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
