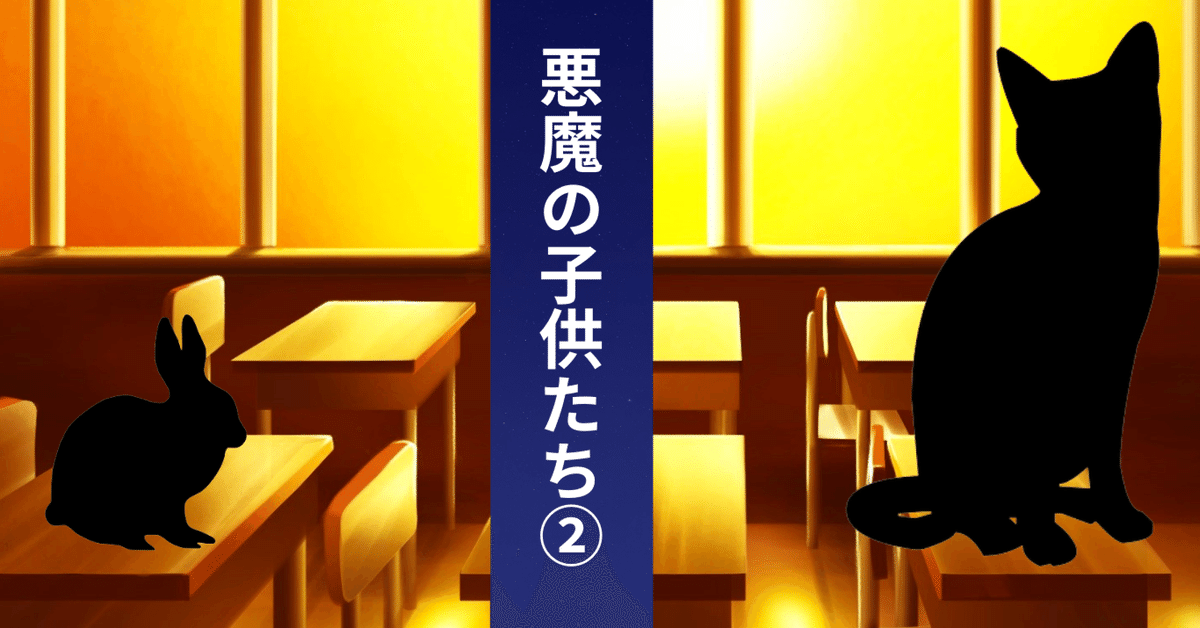
悪魔の子供たち②
2 自由運動
入る学校を間違えたか――。
たまにそう思うことがある。
俺のような日常的に校則を犯し恒常的に勉学に励まないような劣等生は、進学校においてはどうしても異分子となってしまう。簡単に目立ってしまう。すぐに際立ってしまう。
別に俺はいじめられているわけでもないし、学校がつまらないわけでもない。先生の軽い小言さえ我慢すればそれなりに自由に動き回れる。本当はそれもダメなのだが、俺は比較的好き勝手に行動できているということだ。ことあるごとに小言なるものを告げられるのはおそらくそのせいでもあるのだろう。
いや、あいつもそうかな……。
俺の通う私立茜灯高等学校は本来なら頭の良い人々が通う狭き門の進学校なのだ。そんな学校に、模試の時点で合格率が10%を切っていたはずのこの俺が合格してしまったのだ。
受かろうなどとは思っていなかった面接では諦め半分の境地の中、無礼と指摘されても文句の言えないくらいの自然体で、フレンドリーさで、横柄さで面接官どもに応対してやったのだが、あれが意外と高得点だったのかもしれない。
そんなわけで、入学初日から俺はオチコボレまっしぐら。勉学などさっさと投げ出し、現在に至るまで成績不振。しかもそれを悲観するでもなく、まあこんなもんだろと納得した挙句改善はしないという、諦観と悟りの中間のような感情でオチコボレを継続しているという救いようのない有り様なのだ。逆立ちしても競争相手になり得ない俺には却って友人もたくさんいるし、オチコボレなれば妬みや恨みを買うなどという悲劇も無い。実に平和に、ノーストレスで学校生活を謳歌しているのだ。本当は成績不振こそをストレスに感じなければならないのだろうが、俺は多くを望まない。やるべきことをやらずに後で後悔する代わりに、その空いた時間は目一杯楽しむという短絡的で自堕落な素晴らしき平和人間となるべく、現行の怠惰を今後も維持し続ける所存だ。
人は何も考えないくらいが丁度良い――という境地に、俺の年齢で辿り着いている者は果たしてどのくらいいるだろうか。どうにか俺はその極地を目指しているのだけど、常識やら環境やらがそれを容易には許さないようだ。特にこういった進学校は人様のケツを蹴りつけることを生業にしている部分もあるので油断がならない。
もっと不真面目な学校だったらよかったのに。
そう常々思う。
しかしまあ、バカであることを己が自覚し、周囲の人々もこいつはバカであると認識している環境下でお望み通りの道化を演じてさえいれば、意外なほど無害でいられるという利点はかなりでかいような気がする。その利点こそ俺が茜灯高校で構築した最重要のインフラなのだ。現にこうして、神に見放されるくらいお気楽に学校生活を謳歌できているのだから。
そんなこんなのなんだかんだで俺は最初の一年を遣り過ごした。校内唯一の、そして随一のオチコボレとして場違いな環境の中をダラダラと生きながらえてきたのだ。茜灯高校などというガチガチの進学校で学生の本分を見事に無視し、自由気ままな学校生活を一年も送ることができたということ。これ全てインフラのお陰である。周りから諦めの視線で見られることと引き換えに手に入れた俺なりの自由がそこにあるのだ。とにかく俺は校内で自由に動き回りたかったのだ。
そしてスタートした二年次。
急転直下である。俺がというより、学校全体が。
今その優秀な進学校様は荒れに荒れている。
普段は優秀で問題の無い学校だからこそ、いざ問題が発生すると大事になり対応も後手後手になってしまうのだろう。だろうというより、現状そうなのだから確定事項だ。
問題が一つ発生しただけでもおもちゃ箱をひっくり返したような大騒ぎになる学校が、立て続けに問題を起こしてしまったのだ。
どうやら生徒間による傷害沙汰のいじめと、茜灯高校に娘を通わせているPTA会長様がその娘に対して行き過ぎた教育、すなわち虐待していることが発覚してしまったようなのだ。全国ニュースにはなっていないが、なっていてもおかしくはない案件なのだろう。
いじめ、虐待。あっという間のツーアウト。
ツーアウトにも関わらず、ほとんど学校に遊びに行っているような感覚の俺にとってはそのことによる混乱など何も無い。今日もまた陽気だが肌寒い春先の晴天の下「さみい。ねみい」などという嘘の無い真っ直ぐな感想意見を独り言ちながら、見慣れた通学路を遅刻すれすれのペースを保ちつつ人に見られては困るような欠伸を交えて歩いていくのみであった。
本日もまたいつものように保健室の衛生的なベッドでも利用しようかな、などと考えていると、いつもの十字路でいつも出会う、いつも一緒に行動を共にしているいつもの問題児と今日も今日とて出会ってしまった。コイツは一年の頃から学年一頭が良いくせに、俺に並ぶお騒がせ生徒としてそのポジションを確立してしまっている。
俺たちの何が学校をお騒がせしているのかというと、二人とも、二人しかいない新聞部の部長と副部長だということ。そう、新聞部。校内のゴシップを嗅ぎまわるハイエナが俺たちの正体なのである。
「あら、おはようナツ。今日もまた怠惰が顔面に貼り付いているわよ」
ウチの部長が天使のように優しげで爽やかな微笑みと共に、隠す気のない毒を浴びせてくる。毒も笑顔も青空に映えている。
「今日だけじゃない。明日もだ。ハルも明日、それを知ることになるさ」
「抗えない運命ってやつですね」
とまあ思考を介さずに出てくる諧謔(かいぎゃく)的な言葉遊びで互いに応酬しながら一緒に登校する遅刻ギリギリ組の二人。これもいつもの平和な俺の日常だ。
桜井葉流(はる)と白沢南都(なつ)。
新聞部の二人組として学内では両者ともに有名人だった。この奇妙な名前の符号から、春と夏が揃っていて暑苦しいと先生に言われたことがある。北海道の春は涼しげだろうに。あと、サマスプだとか言われたこともある。サマーとスプリングのことだ。それならスプサマだろうに。
「今週、どんな記事にするか考えてきましたか?」
ハルが早速宿題の提出を要求してきた。まずます怠惰な顔になる俺。そして宿題をやってない俺。
「もちろん考えてきた。三時間も考えた。本当に俺は頑張った。ただそれを口にするかどうかは別だ。ああ、いや、よく考えたら四時間だったかな」
言い訳にもならない言い訳の中で、ハルの大人びた美しい横顔が人を見下す微笑に染まっていく。
「別にやってないならやってないで構いません。私とてナツがやってくるなどと思っていないわけですし」
しれっと宿題の件をゴミ箱に捨てたハル。お前から突っついてきたことだろうに。
「ああそう。それを十秒前に言ってくれれば救われた人がいたのにね。とっさの言い訳などという無駄な努力をせずに済んだ人がさ」
「その人は何をどうしても救われませんよ」
「死ぬ程ひどいこと言うよね」
「抗えない運命ってやつですね」
「抗って自重してくれよ」
このなけなしの非難さえも無視して歩き続けるハル。コイツはとにかく俺をからかうのがこの世で一番うまい人間なのだ。
「それに私は、宿題をちゃんとやってくるナツなんて見たくないわ」
ふとこちらに目線を寄越したハルが、そのからかうような目でよく分からないことを言ってくる。コイツはいつも無表情なのだが、たまに子供じみた悪戯っぽい笑みを見せてくることがある。この世の男子全員が味方してしまうであろうその悪魔の微笑みを。
「つまり、ナツは何もやらないことで見事私の期待に応えてくれているのです」
この一年の高校生活の中で何かを期待されたことなど一度としてなかった俺に対し、ハルはむしろ俺のそういう部分をこそ期待しているのだという。
「ああ、お前が俺を馬鹿にしてそんなこと言っているってことくらい、俺はちゃんと分かってるからね」
「まあ、分かってらっしゃる。では馬鹿ではないのかもしれませんね。頑張ってください」
何をどう頑張れと。
ハルは俺を下男のようなものだと思っている節がある。ハルから見た俺は全然しっかりしてないし、行動的でもない。無考えの指示待ち人間に過ぎない存在だ。前にハルがナマケモノとは動物のことではなく俺のことなのだと真面目な顔で言っていた。確かに俺は二十四時間中二十時間はダラけている。今もなお眠たそうな顔を継続している。先程十字路でハルに指摘された通りの生態だ。
「あなたが普段通りの怠惰なあなたであることに、私は本当に期待しているんですけどね」
そう言って謎の主張を曲げなかったハル。しかも「まあ理解してくれなくていいや」という苦笑を見せながら。これはずるい。信じてしまいそうになる。
ハルは紛れもなく美女だ。もう、間違いなくそうだ。これは学校中の共通認識なのだ。いつも隣にいる冴えない男など引き立て役にすらならない。そいつだってそれなりに整っているが(それなりに!)、コイツの完成されたビジュアルには遠く及ばない。人類よりも顔が小さくて、人類よりも肌がきれいで、人類よりも髪がサラサラしている。つまりハルは人外の生き物ということになる。何より目が好い。鋭さと無邪気さと奥深さを全て兼ね備えたその目はハル以外にない。もしそんな目が落ちていたらハルに届ける。しかも違和感なくそんな目の存在が許される場所はハルの完成された顔面以外にないのだろう。全てのパーツの形と位置が人に愛される条件を満たすものとなっているということ。普段本気を出すことなどまずない余裕をぶっこいた神が、珍しく全神経を集中して創り上げない限り存在し得ない究極の顔面偏差値がそこにはあるのだ。背は170センチちょっとの俺がなんとか勝つくらいだが、それでいて抜群のスタイルを保持しており、制服越しにもそれが認識できるほどのプロポーションなのだから、もはや誰にも文句のつけようがない。とにかくまあ、一緒に歩いていると比する自分が哀れに思えてくる存在ということだ。
才色兼備の完璧人間に思えるこの女は、しかしながら俺と同じレベルの問題児として扱われているのだ。先生方からも、生徒たちからも。
まず新聞部に所属しているという時点でまともではない。ハルは運動が苦手なわけではないし(握力が60kgもある)、何をやらせても器用にこなす。それなのに俺などと一緒に面白半分の悪ふざけ記事を追いかけることに没頭している。そしてたまに二人で先生方から大目玉を食らってしまう。おかげで二人ともいまや学校中の有名人だ。特にハルは目立つ。その容姿だけでも十分目立つというのに、コイツは入学式の時からすでにその名が知られてしまっているのだ。生徒にとっても父兄にとっても先生方にとっても退屈でしかない入学式をかつてないほど盛り上げたのはこの女だった。あれこそハルの奇行癖を分かりやすく説明している。
主席合格したことでハルは新入生代表の挨拶を任されることになってしまったのだ。大学などではよく見られるお決まりの行事であり、選ばれた者にとっては非常に名誉なことのはずだ。だがこのハルという女、後から聞いた話では学校側からの再三の要請を「慣例など知ったことではない」と無下に断っていたらしい。式典を台無しにされかねない学校側は肝を冷やされ、なんとかしようと思い、台本を拵(こしら)えてきたのでこれを読み上げてくれと入学式当日に彼女に頼みこんだそうなのだ。そして俺も記憶にあるあの入学式のスピーチだ。あの時ハルは台本など持っていなかった。ハルが新入生代表の挨拶を強要された腹いせに壇上で取った行動とは、新入生代表の挨拶の前にステージに立っていた校長のスピーチの全否定だった。校長のハゲが進行したのはあの時からだろう。
「先程校長を名乗る男が努力は必ず報われるなどと、ギリギリ理解できる範囲の日本語でほざいておりましたが、報われずにゴミと化した精神疲労と時間の総量にいつまでも目を向けずに、五千時間かけて進んだたったの一歩を神格化して崇めさせる現実離れした綺麗事には、わたくし、一切賛同できません。彼が過ごしてきたような暇な時代はとうに過ぎ去ってしまったのです。我々は一時間で百歩進める方法を探す方が先決です。あの人たちは無駄になった膨大な時間に目を向けず、それを歴史的な教訓にして私たちに伝えることすらしていないのです。ハゲたくなければ、みなさん、思い切って思いっ切り無視しましょう」
台本は体育館につながる渡り廊下の隅っこのゴミ箱に無造作に打ち捨てられていた。
無視しましょうと無邪気に笑いかけた絶世の美女の登場シーンに、その日から男子も女子も夢中になった。
桜井葉流は要するに自分の好きなことがしたくて、それ以外はしたくないという、普通にわがままな女子なのだ。スピーチの時のようにしたくないことをさせられるときっちりお礼するところも奇矯なのだが、何より「自分の好きなこと」の範囲が異様なのだ。新聞部でやっていることといえば、たとえば新任の先生の紹介記事だったり、部活の大会経過報告だったりするのだが、それを真面目な記事などには絶対にしないのがハルだった。何をするにも諧謔的にしてしまうのだ。新任の先生をインタビューした時の受け答えを自作の心理テストにかけてみて、「この人は少女である自分を捨てきれていない」などとゴリラみたいな男性教諭に対して書いた記事を掲載し貼り出した時は、烈火のごとく怒られた。何故か俺も怒られた。
面白可笑しく、からかい半分。
それがハルの生きる理由なのだ。面白可笑しくの基準がハル以外には理解できない点がハルを異端児にしている最も大きな要因となっているのだろう。とりあえずハルが好きなように人をからかい、ハルだけが面白ければそれでいい……という最っ低の女なのである。
物怖じしない。動じない。精神が鉄筋コンクリートで出来ている。成績も常にトップの独立不遜。それなのに成績がずっとビリの俺なんかと共に進学校に似つかわしくない振舞いをすることが多々ある。今日もまた当然のように二人して遅刻するかもしれない。
しかしここ最近は二人とも新聞部として真面目に活動しようとしていたのだ。真面目と言ってもそれはそうせざるを得ない事件が続発したことでの内なる強制でしかなかった。だが結局は事件に関するそれらの報道を学校側に力尽くで止められてしまったというハルにとっては不満の残る結果となってしまった。
学校とはいつの時代も臭いものに蓋をしたがる組織なのだろう。その蓋に潰された我が新聞部の記事。怒る新聞部部長。
ここで宿題の話に戻った。
「てかさ、どんな記事にしようかって考えたところでさ、どうせ本当に記事にするべき事案は取り扱えないわけじゃん。現茜灯高校職員室政権による不当な軍事介入によってさ」
俺は宿題をやってこなかったことの言い訳としてちょっとした真実に抵触した。
「政治介入とも言うわね」
ハルが不満気な俺を見て楽しそうに応じた。
「お説教とも言うし大人の振舞いとも言うわね。まあ一番悪いのは生徒のナーバスな部分に触れるああいった事件を、面白半分に記事にしようとするマスコミなんだけどね」
「お前な」
「若干二名いるって話よ」
「お前が中心のな」
ハルはいちいち反抗する俺の方を見て、大きな目をパチパチとしばたたかせた。どうして家臣であるこの男は主君に逆らうのだろうという、俺にとっては毎度おなじみの反応である。
「今朝、私の母がスマホをうっかり水没させてしまった父に向かってウジウジ悩んでないで仕事へ行けと檄を飛ばしておりました。ウジウジですって」
大きな目をこちらに向けながらハルが何事かを語り出した。そして疑問符の付いた顔でこう言ってきたのだ。
「どうして母はあの時あなたの名前を二回続けて呼んだのでしょう」
「は?」
彼女はフッと悪戯っぽく微笑んだ。
「ふふふ。いずれあなたも空を自由に飛べるようになるでしょう。あなた方は羽化しますからね。ただ全然憧れないですね。下等ですし」
無邪気な少女のようにクスクスと笑うハル。
俺は閉口して立ち止まってしまった。
相手を馬鹿にする。貶める。その為だけに生きている女。それが何より楽しい女。
化け物め。
俺は追いついてわざとらしくだがこう言ってやった。
「あー、さっさと羽化したいなあ」
「あら、決心しましたか虫けら。では空を飛べたらどうしますか?」
こちらも見ずにハルが訊ねてくる。
俺は、どうしようか。迷った。
「うーん。どうもこうもないなあ。空を飛ぶこと自体が目的なんだし」
「そう。結局そうなっちゃうのよ。人間に必要の無い能力であることを人間が一番よく知っているの」
夢のある話ほど、人間に置き換えると味気ないものになってしまう。ハルはむしろ嬉しそうにそう言った。
「ああ、でも俺一つ思い浮かんだよ。空を飛ぶことの目的」
俺は頭の後ろで手を組ながらリラックスした感じでダラダラ歩いていた。
「まあ何でしょう」
ハルは機械のように一定のリズムで歩行しているのだが、これがハルにとってのリラックスなのだろう。
「優越感にひたること」
「虫けらですね。さっさと羽化してください」
なんて毒づくハルだったのだが、それと同時に屈託のない表情でクスクスと笑っているのだった。俺も半分は笑わせようとしてやってることなので、むしろ笑ってくれないと困ってしまう。もちろん、ハルもそれを知った上で笑っている。
それにしてもハルが笑っている時の顔は小学生のように幼くなる。無邪気になる。微笑の時は大人びるのに、笑顔の時は若返る。こんな奇人であるのに、たったそれだけで人間としての奥行きが広がるような気がするのだ。
遅刻気味のまま歩くペースを変えず、俺たちは道幅の狭い住宅街から大通りへと出た。
「ナツ、あれ」
二車線道路を挟んだ向こう側の歩道、ハルの視線の先には一人の女子生徒がいた。うちの制服を着ている。
知っている女子だった。
地球の裏側と対話しているかのようにその女子は俯いていた。項垂れていた。
茜灯高校では珍しく、髪の毛を遊んでいるタイプ。セミロング気味の毛先を撥ねさせている。スカートも短くしている。目が大きく、表情が分かりやすそうな丸顔。それだけ見るとお気楽タイプのはずが、今はその面影は微塵もない。見るからに沈んでいる。
「ナツのノーテンキさを半分わけてあげたいわ」
ハルの口から減らず口が飛び出してきた。
「人の宝物を勝手に半分も持ち出そうとしてんじゃねーよ」
「人助けじゃない。何よりあなたが救われる」
他愛のなくない口喧嘩が勃発。
ただし向こう側の歩道の時間の流れはこちら側とは別なのだろう。俺たちがふざけ合っているうちにも彼女は姿勢も歩調も変えずスタスタと通り過ぎて行ってしまった。
最近になって頻繁にあの子をこの通りで見かけるようになった。おそらく通学路を変えたのだろう。きっと通学時間も。
あれ以来。
二週間前に我が校で発生した「いじめ事件」。彼女、高屋美樹はその被害者だった。
珍しいのは不登校になったのがいじめた側の女子であって、いじめられた側の高屋美樹は事件後一度も学校を休んでいないということ。
いじめが顕在化したことで保護者説明会も開かれるほどの大騒ぎとなった。しかもそれを前後に今度はいじめっ子の方が不登校になってしまい、今またそれが軽い問題となってしまっているのだ。
「学校の先生だけにはなりたくないね。やだやだ」
俺は癖に従って頭の後ろで手を組み、ついつい本音を漏らしてしまった。
「嫌な面だけに目を向けていると、この世からなりたいものなんて無くなっちゃうわ」
ハルは俺の何でもないツイートを拾って、何でもないような顔でそんなことを言ってきた。
「そりゃそうだ」
素直に感心する俺。
「でも良い面なんて実際になってみないと大抵分かんないものだから。人生なんてみんな博打よ」
またまたハルは何でもない顔を継続しながら含蓄のあることを述べてきた。思わず頭の後ろで組んでいた手が解けて左右にぶら下がる。
コイツはたまにこういうことを言うものだから、やっぱり頭の良い部類の人間なのだなあと痛感する。
「高屋さんにとっては良かったのかもしれないわね」
続けてハルが言った。
「何が?」
「立て続けに事件が起こったことがよ。女子高生などという短絡的生命体の生態が良い例じゃない。彼女たちのブームや流行と一緒で、新しいものが登場すればそれ以前のものは驚くほど簡単に忘れられてしまう」
「ああ……」
「いじめ事件よりも、今は「虐待事件」の方に注目が集まってる。それまで盛り上がってたはずのいじめ事件の関係者はホッと胸をなでおろしてるんじゃないかしら」
それでも茜灯高校の印象は二次関数的に悪くなるのだろう。事件が単発だったら全然見方が違っていたのだろうが、続発となるとそれが日常みたいに思われてしまうのだ。
いじめ事件の二週間後、今度は虐待事件なるものが我が校を襲ったのだ。
俺には該当しないことなのだが、茜灯高校ほどの進学校ともなると学業成績を何よりも重要視する家庭が珍しくないらしい。親が子の成績を気にするあまり、ついつい厳しさのリミッターを解除してしまうこともままあることなのだろう。以下ハルの受け売りなのだが、子に対する親の身勝手な期待は、親次第では期待ではなく強制になってしまうとのこと。ではもしその強制に子が応えることができなかったら?
そして事件は起こった。成績第一主義の家庭で育ったある女子生徒が、先日茜灯高校で行われた定期考査という名の謎の儀式(どうやらハルはその奇祭において「一番」を取れたらしい)の結果が振るわなかったらしく、娘に過度な期待を寄せていた母親がその結果を見て牙を剥いたらしいのだ。今回は目撃者がいたことでそれが明るみに出てしまった。しかもその母親、なんと茜灯高校のPTA会長を務めていたものだから事件は捨て置けるものではなくなったというわけだ。当然これについても保護者説明会が催されることとなった。つい先日のことだ。
新聞部でもこのネタを取り上げようとしたのだが、職員室から待ったがかかった。ハルが面白半分で反抗してみたところ、頭ごなしに発禁を命じられてしまったのだ。
それにしても、事件だけでなく保護者説明会までも連続。学校側としては開校以来の大惨事なのだろう。
「なんかこう、裏で全てを操っている悪い黒幕みたいなのがいるんだよ、きっと」
「少年マンガ的発想で夢を語るそこの少年、その夢が叶うといいわね」
からかうようにハルは言った。
「おやおや部長。黒幕の存在を否定するんですか?」
「いいえ。新聞部としてはありがたい存在じゃない」
意味あり気に微笑む魔女。そうなれば本当に愉快な記事が出来上がるというわけである。
「いるわけねーだろ、んな危険思想の持ち主」
「でっち上げればいいのよ」
これ以上続けたら本気でフェイクニュースを実行しかねないと思い、俺は欠伸をして聞いてない振りを装うという秘奥義を繰り出す羽目になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
