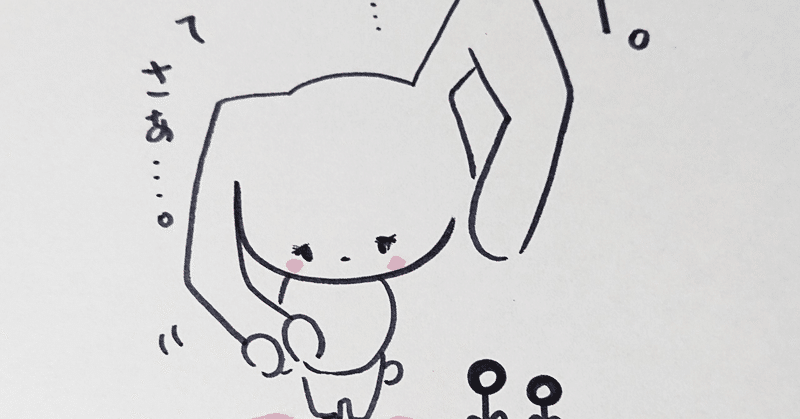
本歌取り技法と万葉集
和歌の作歌技法に「本歌取り」と云う技法が、あります。これをフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に参照すると、つぎのような解説があります。
本歌取(ほんかどり)とは、歌学における和歌の作成技法の一つで、有名な古歌(本歌)の一句もしくは二句を自作に取り入れて作歌を行う方法。主に本歌を背景として用いることで奥行きを与えて表現効果の重層化を図る際に用いた。
例えば、
古今和歌集 巻2-94番歌 紀貫之
三輪山を しかも隠すか 春霞 人に知られぬ 花や咲くらむ
万葉集 巻1-18番歌 額田王
三輪山を しかも隠すか 雲だにも 心あらなも かくさふべしや
この、二作品を比較すれば明らかなように、貫之は額田王の第一句・第二句をそのまま採用して、第三句以後を自作としている。
こうした本歌取については様々な受け取り方があった。六条藤家の藤原清輔はこれを「盗古歌」(こかをとる)ものとして批判的に評価した。これに対して御子左家の藤原俊成はこれを表現技法として評価している。
俊成の子・藤原定家は、「近代秀歌」・「詠歌大概」において、本歌取の原則を以下のようにまとめている。
1.本歌と句の置き所を変えないで用いる場合には二句未満とする。
2.本歌と句の置き所を変えて用いる場合には二句+三・四字までとする
3.著名歌人の秀句と評される歌を除いて、枕詞・序詞を含む初二句を、本歌をそのまま用いるのは許容される。
4.本歌とは主題を合致させない。
5.本歌として採用するのは、三代集・「伊勢物語」・「三十六人家集」から採るものとし、(定家から見て)近代詩は採用しない。
ここで、この解説から「本歌取」の技法で最重要なことは、「本歌を背景として用いることで奥行きを与えて表現効果の重層化を図る際に用いた」技法であることから、本歌は皆が知る歌でなければなりません。つまり、本歌取の技法が成立するには、古歌(本歌)が十分に和歌を詠う人々に認識されている必要があります。従いまして、特定少数の人だけがその古歌を知るのではなく、広く人々が知るためにも古歌が載る歌集などが存在して流布している必要があります。和歌の専門家の間では、この本歌取の技法が成立するための要請上、万葉集の歌が詠われた時代では古歌が載る歌集の流布問題から、まだ、本歌取の技法は成立しないと考えられているようです。そのためか、先の参考例として取り上げた紀貫之が詠う「三輪山を しかも隠すか 春霞 人に知られぬ 花や咲くらむ」の歌を本歌取の技法が使われた、早い時期のものと考えるようです。
本歌取の技法について言葉としては、平安時代中期から後期には「詠み益し」と云う名称で知られ、「引用した古歌を越えるものなら良い」と云う立場で「古歌引用」した歌が詠われていたようです。この作歌技法は平安時代後期ごろには「盗古歌」とも呼ばれます。およそ、「本歌取」と云う技法名称とは別に、紀貫之たちが活躍した「古今和歌集」の時代前後には「詠み益し」と云う形で本歌取の技法は始まっていたと推定されています。紀貫之の歌の例の他に古今和歌集には次のような歌も見つけることが出来ます。
古今和歌集 852番歌 題しらず 読人知らず
和歌 須磨の海人の塩やく煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり
万葉集 巻7 集歌1246 読人知らず
原文 之加乃白水郎之 燒塩煙 風乎疾 立者不上 山尓軽引
訓読 志賀の海人し塩焼く煙風を疾(と)く立ちは上らず山に棚引く
ここで山口女王が大伴家持に贈った歌を紹介しようと思います。この歌は山口女王自身が詠ったものです。
山口女王賜大伴宿祢家持謌五首より一首を選抜したもの
集歌616
原文 劔大刀 名惜雲 吾者無 君尓不相而 年之經去礼者
訓読 剣太刀(つるぎたち)名(な)し惜しけくも吾はなし君に逢はずて年し経ぬれば
この歌の解釈を身近な万葉集解説書から探してみますと、次のような解釈を見つけることが出来ました。
解釈1;新日本古典文学大系 岩波書店
(剣太刀)名などは私には惜しくはありません。あなたに逢わず年が経ったので。
解釈2;日本古典文学全集 小学館
(剣太刀)立つ名の惜しいことも、もうわたしにはありません あなたに逢わずに 年が経たので
解説;剣太刀 名の枕詞。刃の古語ナと名をかけた語という
解釈3;新潮日本古典集成
浮名が立つのを惜しがる気持ちは、もう私にはありません。あなたに逢わずにこんなに年月が経ったものですもの。
解説;剣太刀 「名」にかかる枕詞。刃(カタナ)のナは刃の意。このナと「名」とをかけたもの。
解釈4;万葉集 伊藤博 集英社文庫
浮名が立つのを惜しがる気持ちは、もう私にはありません。あなたに逢わずにこんなに年月が経ったものですもの。
解説;剣太刀 名の枕詞。「刃」の「な」は刃の意。この「な」と「名」とをかけたものかという。
解釈5;万葉集 全訳注原文付 中西進 講談社文庫
りっぱな剣太刀の名など私は惜しくありません。あなたにお逢いせず年月もたっていきましたので。
解説;刃物をナという(カタナ・カンナ・ナタ)によってつづく。
これらの解釈は共通して、解釈1の新日本古典文学大系では明確には説明されていませんが、初句の「劔大刀」を枕詞として歌を解釈しています。ただ、枕詞とした時、その理由付けに「発声」には関係しない「剣太刀 名の枕詞。刃の古語ナと名をかけた語という」と云うような苦しい解説を行う必要があります。それに万葉集歌の中で「剣太刀」や「釼刀」と表記され、「つるぎたち」と読む言葉が特定の言葉「名」を修辞するかと云うとそうではありません。例として、次のような句を万葉集から見つけることが出来ます。専門家といても、その説くところを、小学生の質問のように「どういして」、「どうして」と言い出すといけないのです。偉い人の「こうなっているの」を受け入れないといけないのです。
劔太刀 身尓取副常 つるぎたち みにとりそふと
剱刀 身尓佩副流 つるぎたち みにはきそふる
釼刀 諸刃利 つるぎたち もろはのときに
釼刀 名惜 つるぎたち なのおしけくも
釼 従鞘納野迩 つるぎたち さやゆいりのに
万葉集で使われる言葉「あしひき」を調べますと、その原文の漢字表記が歌の内容に応じてのバリエーションがあり、また、他に漢字表記した「ぬばたま」などの例からすると、万葉集の歌には新古今和歌集以降の和歌修辞技法の内の枕詞技法を一律に適用するには無理があります。鎌倉時代から昭和中期まで、万葉集を「訓読み万葉集」の形で享受していて、歌学者や研究者が原文から万葉集を研究することは邪道扱いでした。それで、次のような万葉集での表記の違いを知りませんでした。あくまで「訓読み万葉集」により「あしひき」と理解していました。
あしひきの表記例
足引乃 許乃間立八十一 あしひきの このまたちくく
足引之 八峯之雉 あしひきし やつをしきぎし
足曳之 玉蘰之兒 あしひきし たまかづらしこ
足疾乃 山乎隔而 あしひきの やまをへだてて
足病之 山海石榴開 あしひきし やまつばきさく
足檜之 山橘乎 あしひきし やまたちばなを
足桧乃 下風吹夜者 あしひきの あらしふくよは
足桧木乃 山左倍光 あしひきの やまさへてれる
足比奇乃 山櫻花 あしひきの やまさくらはな
足比木乃 山二文野二文 あしひきの やまにものにも
足日木之 山鳥尾乃 あしひきし やまとりのをの
足日木能 石根許其思美 あしひきの いはねこごしき
足氷木乃 清山邊 あしひきの きよきやまへを
悪氷木之 山下動 あしひきし やましたとよみ
蘆桧木乃 山道者将行 あしひきの やまぢをいけど
その「訓読み万葉集」から「あしひき」と理解していた人たちが、一字一音の借字での真仮名表記法ではない、山口女王が詠う集歌616の歌の「劔大刀」を、単純に枕詞として処理していいのかどうかを確認する必要があります。それに、一番の問題は、この歌を詠ったのは女性である山口女王であって、男性では無いことです。そうした時、女性が自分の名の形容に殿上人たる大夫を示唆する「劔大刀」の言葉を使うか、どうかです。まず、そのような歌の意味合いからも「劔大刀」の言葉を枕詞とするには無理があるのではないでしょうか。
ここで、山口女王が詠う集歌616の歌が「本歌取」の技法の歌と考えたら、どうでしょうか。この視線で万葉集を見てみますと、本歌と推定される歌が万葉集の人麻呂歌集の中に収められています。それが次に示す歌です。
集歌2499
原文 我妹 戀度 釼刀 名惜 念不得
訓読 我妹子し恋ひしわたれば剣太刀(つるぎたち)名し惜しけくも思ひかねつも
原文の漢字表記では「釼刀 名惜」と「劔大刀 名惜雲」との違いはありますが、訓読みでは共に「剣太刀名し惜しけくも」と読むことが出来ます。集歌616の歌が「本歌取」の技法の歌ですと、集歌2499の歌がその本歌と推定されます。なお、集歌2499の歌は集歌2498の歌との二首相聞歌として解釈するのが良いと考えます。従いまして、「本歌取」の技法での「本歌を背景として用いることで奥行きを与える」と云う狙いがあるのなら、本歌取での本歌の世界は集歌2498と集歌2499との歌、二首相聞歌として鑑賞・理解する必要があると思います。
集歌2498
原文 釼刀 諸刃利 足踏 死ゞ 公依
訓読 剣太刀(つるぎたち)諸刃(もろは)し利(と)きに足踏みて死なば死なむよ君し依(よ)りては
私訳 貴方が常に身に帯びる剣や太刀の諸刃の鋭い刃に足が触れる、そのように貴方の“もの”でこの身が貫かれ、恋の営みに死ぬのなら死にましょう。貴方のお側に寄り添ったためなら。
集歌2499
原文 我妹 戀度 釼刀 名惜 念不得
訓読 我妹子し恋ひしわたれば剣太刀(つるぎたち)名し惜しけくも思ひかねつも
私訳 剣を鞘に収めるように私の愛しい貴女を押し伏せて抱いていると、剣や太刀を身に付けている大夫たる男の名を惜しむことも忘れてしまいます。
当然、山口女王が詠う集歌616の歌が本歌取の技法の歌とする時、大きな問題が生じます。本歌取の技法の歌が成立するには、先行する古歌(本歌)が和歌を詠う人々に認識されている必要があります。つまり、古歌(本歌)が収容される人麻呂歌集が写本などのような形で流布している必要があります。
ではその可能性はあるでしょうか。そうした時、本歌取の技法に適う歌を万葉集に探してみると、次のような歌を見つけることが出来ます。
笠女郎の大伴宿祢家持に贈れる謌廿四首より抜粋
抜粋1;
集歌593
原文 君尓戀 痛毛為便無見 楢山之 小松之下尓 立嘆鴨
訓読 君に恋ひ甚(いた)も便(すべ)なみ平山(ならやま)し小松し下(した)に立ち嘆くかも
私訳 貴方に恋い慕ってもどうしようもありません。奈良山に生える小松の下で立ち嘆くでしょう。
本歌
集歌2487
原文 平山 子松末 有廉叙波 我思妹 不相止看
訓読 平山(ならやま)し小松し末(うれ)しうれむそは我が思(も)ふ妹し逢はず看(み)む止(や)む
私訳 奈良山の小松の末(うれ=若芽)、その言葉のひびきではないが、うれむそは(どうしてまあ)、成長した貴女、そのような私が恋い慕う貴女に逢えないし、姿をながめることも出来なくなってしまった。
抜粋2;
集歌603
原文 念西 死為物尓 有麻世波 千遍曽吾者 死變益
訓読 念(おも)ふにし死するものにあらませば千遍(ちたび)ぞ吾は死に返(かへ)らまし
私訳 閨で貴方に抱かれて死ぬような思いをすることがあるのならば、千遍でも私は死んで生き返りましょう。
本歌
集歌2390
原文 戀為 死為物 有 我身千遍 死反
訓読 恋するに死するものしあらませば我が身千遍(ちたび)し死にかへらまし
私訳 貴方に抱かれる恋の行いをして、そのために死ぬのでしたら、私の体は千遍も死んで生き還りましょう。
山口女王が詠う集歌616の歌、笠女郎が詠う集歌593と集歌603の歌が、人麻呂歌集の歌の句と偶然の一致でないのなら、これらの歌は人麻呂歌集の歌を本歌とした本歌取技法の歌となります。逆に、この技法が成立することから推測すると、奈良時代中期の歌人たちは人麻呂歌集の歌を知ることが必然の教養となっていたと考えられます。
当然、専門家はこのような歌句の類似は良く知っています。しかしながら、この「歌句の類似」は万葉集の研究では「類型歌」として扱われ、「本歌取の技法を使った歌」としては扱いません。専門家は「本歌取の技法を使った歌」は古今和歌集の紀貫之以降と云う約束があるようです。しかし、「剣太刀、名し惜しけくも」と云うフレーズが共通表現の頻度の高いものかと云うそうではありません。枕詞の検証例で示しましたが、非常に特殊な表現です。ですから、一般的な歌枕を持つ類型歌とするには無理があると考えます。
ここで、万葉集の歌もまた本歌取の技法で詠われた歌が成立すると云う立場で、再度、山口女王が詠う集歌616の歌を見てみたいと思います。この時、本歌は集歌2499の歌となります。集歌2499の歌の「剣太刀」の言葉は「殿上人たる大夫の身分を持つ男」を意味します。集歌2498と集歌2499との歌が二首相聞歌の関係としますと、女から見て「剣太刀」たる男は「女に死ぬほどの思いでの性愛の喜びを夜通し与える男」です。これが、山口女王が詠う「剣太刀」の情景です。
従いまして、集歌616の歌の初句「剣太刀」は「大夫たる男」=「大伴家持」を意味し、さらに、以前に「山口女王に死ぬほどの思いでの性愛の喜びを夜通し与えた男」をも示唆することになります。
山口女王賜大伴宿祢家持謌五首より一首を選抜したもの
集歌616
原文 劔大刀 名惜雲 吾者無 君尓不相而 年之經去礼者
訓読 剣太刀(つるぎたち)名(な)し惜しけくも吾はなし君に逢はずて年し経ぬれば
私訳 柿本人麻呂たちが歌に詠う、その「剣太刀」のような貴方。私にはもう淑女でなければならないと云う女の評判を惜しむと云う気持ちは、もう、ありません。貴方に逢えないままに年月が過ぎて往きましたから。
標準的な現代語訳 「万葉集 伊藤博 集英社文庫」より
意訳 浮名が立つのを惜しがる気持ちは、もう私にはありません。あなたに逢わずにこんなに年月が経ったものですもの。
本歌取の技法が成り立つとすると、この歌は、世のしがらみや相性などの理由で一人の男を奪い合う女同士の戦いに負けた女が、愛されなくても良いから、せめてもう一度、一夜の愛欲に溺れさせて欲しいと願う歌となるのではないでしょうか。
本来、集歌616の歌は五首一組の歌です。五首連続で鑑賞すると、男に性愛の喜びを教えられ、そして、身も心も満ち足りた時、その男は他の女へと去って行った、その若い女の悲鳴が聞こえて来るのではないでしょうか。大伴家持は、この山口女王との罪作りな恋愛に前後して、笠女郎にもまた女に捨てられた悲鳴のような歌を作らせています。大伴家持は、この頃に、山口女王や笠女郎から大伴坂上大嬢へと愛情を移しています。
山口女王の大伴宿祢家持に贈れる謌五首
集歌613
原文 物念跡 人尓不見常 奈麻強 常念弊利 在曽金津流
訓読 もの念(おも)ふと人に見えじとなまじひし常し念(おも)へりありぞかねつる
私訳 物思いをしていると人からは見えないようにと生半可に我慢して、貴方を常に慕っています。生きているのが辛くてたまりません。
集歌614
原文 不相念 人乎也本名 白細之 袖漬左右二 哭耳四泣裳
訓読 相念(おも)はぬ人をやもとな白栲し袖漬(ひづ)つさへに哭(ね)のみし泣くも
私訳 私を慕ってもくれない人をいたずらに恋い慕い、夜着の白い栲の袖を濡れそぼるほどに忍び泣きします。
集歌615
原文 吾背子者 不相念跡裳 敷細乃 君之枕者 夢尓見乞
訓読 吾が背子は相念(おも)はずとも敷栲の君し枕は夢(いめ)に見えこそ
私訳 私の愛しい貴方は私のことを愛してくれなくとも、床に敷く栲の上で共寝するでしょう貴方の、その枕姿だけでも、私の夢の中に見えて欲しい。
集歌616
原文 劔大刀 名惜雲 吾者無 君尓不相而 年之經去礼者
訓読 剣太刀(つるぎたち)名(な)し惜しけくも吾はなし君に逢はずて年し経ぬれば
私訳 柿本人麻呂たちが歌に詠う、その「剣太刀」のような貴方。私にはもう淑女でなければならないと云う女の評判を惜しむと云う気持ちは、もう、ありません。貴方に逢えないままに年月が過ぎて往きましたから。
集歌617
原文 従蘆邊 満来塩乃 弥益荷 念歟君之 忘金鶴
訓読 葦辺(あしへ)より満ち来る潮のいや増しに念(おも)へか君し忘れかねつる
私訳 葦の生える岸辺に満ち来る潮のように、ひたひたと満ち来る貴方への慕情でしょうか。私は貴方が忘れられません。
おまけの一首
標題 山口女王賜大伴宿祢家持謌一首
標訓 山口(やまくちの)女王(おほきみ)の大伴宿祢家持に賜(たまは)れし謌一首
集歌1617
原文 秋芽子尓 置有露乃 風吹而 落涙者 留不勝都毛
訓読 秋萩に置きたる露の風吹きて落つる涙は留(とど)めかねつも
私訳 名残の秋萩に置いている露が、風が吹いてこぼれ落ちるように、貴方に逢えない寂しさに私の瞳からこぼれ落ちる涙は留めることができません。
さて、歌の鑑賞は、鑑賞者の心です。剣太刀の言葉を枕詞とするか、本歌取の一部とするかは、皆さんの鑑賞に委ねます。
参考として、山口女王や笠女郎は、ほぼ同じ時期(天平十年前後?)に、人麻呂歌集の集歌2498と集歌2499との二首相聞歌を題材に歌物語のような歌群を大伴家持に対して詠っています。偶然の一致としては出来すぎでしょうか。穿って考えると、元正太上天皇のサロンで歌会のような宴があり、そこで山口女王や笠女郎たちが歌会の相手となる男達に対して歌物語を競ったのかもしれません。その歌の記録者は内舎人の家持でしょうか。なぜか、このような可能性を空想してしまいます。山口女王の歌五首や笠女郎の歌廿四首は、歌物語として鑑賞すると非常に楽しい歌群で、これに地文を付けると、ある種、長編小説のように鑑賞することが出来ると思います。歌物語かも知れないと云う色眼鏡で、鑑賞をしてみてください。
次に、万葉集の時代に本歌取技法で作歌することが、一つの標準的な技法だったかと仮定して、もう少し、与太話を展開します。その仮定を下に、最初に紹介する歌は万葉集ファンと新古今和歌集以降の歌論ファンとの間で、その解釈が大きく分かれる歌です。教科書的には新古今和歌集の歌を鑑賞するような立場で紹介する歌を鑑賞しますから、初夏の香具山の風情を見ます。一方、近年の万葉集ファンは歌に新春の宴での打ち解けた諧謔の風流を見ます。
天皇御製謌
標訓 天皇の御(かた)りて製(つく)らせしし謌
集歌28
原文 春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山
訓読 春過ぎて夏来(き)るらし白栲の衣(ころも)乾(ほ)したり天の香来山(かくやま)
万葉集ファンの立場でこの有名な持統天皇の詠う集歌28の歌を鑑賞するとき、この歌を踏まえて詠われた東歌があることを思い浮かべます。それが次の集歌3351の歌です。
集歌3351
原文 筑波祢尓 由伎可母布良留 伊奈乎可母 加奈思吉兒呂我 尓努保佐流可母
訓読 筑波嶺(つくばね)に雪かも降らる否(いな)をかも愛(かな)しき児ろが布(にの)乾(ほ)さるかも
私訳 筑波の嶺に雪が降ったのでしょうか。違うのでしょうか。愛しい貴女が布を乾かしているのでしょうか。
この集歌3351の常陸国の東歌は、万葉集の専門家の中では集歌28の御製歌を踏まえると共に、催馬楽(さいば)や風俗歌の感があるとして有名です。例えば、新日本古典文学大系では『「雪景色を歌ったものではなく、筑波山麓の聚落の生業として、白布を雪とまがふまで干し並べる、殷賑のさまを歌ったものであることは、言ふまでもない」(「私注」)。「甲斐が嶺に、白きは雪かや、いなをさの、甲斐の褻(け)衣や、晒す手作りや、晒す手作り」(風俗歌「甲斐が嶺」)』と解説されています。また、万葉集全訳注では『「筑波山の白さに興じた民衆歌で、やがて官人にもてはやされた、「催馬楽」(さいばら)のごとき歌。巻頭五首中これだけに訛りがある。「甲斐が嶺に、白きは雪かや、いなをさの、甲斐の褻(け)衣や、晒す手作りや、晒す手作り」(風俗歌)』と解説されています。つまり、集歌3351の歌は、山麓に干す日曝しの布をあたかも雪のように見立てた歌として解釈することになっています。奈良時代初期の段階で「歌を詠う時に、見立ての技法が東国にもあった」と、歌の専門家は認めています。
ここで、万葉集全訳注の指摘に従い巻十四の巻頭五首を見てみます。
東歌
集歌3348
原文 奈都素妣久 宇奈加美我多能 於伎都渚尓 布袮波等抒米牟 佐欲布氣尓家里
訓読 夏麻(なつそ)引く海上潟(うなかみかた)の沖つ渚(す)に船は留めむさ夜更けにけり
私訳 夏の麻を引き抜き績(う)む、その海上潟の沖の洲に船は留めよう。もう夜も更けました。
集歌3349
原文 可豆思加乃 麻萬能宇良末乎 許具布祢能 布奈妣等佐和久 奈美多都良思母
訓読 葛飾(かづしか)の真間(まま)の浦廻(うらま)を漕ぐ船の船人(ふなひと)騒(さわ)く波立つらしも
私訳 葛飾の真間の入り江を操り行く船の船人が騒いでいる。浪が立って来たらしい。
集歌3350
原文 筑波祢乃 尓比具波麻欲能 伎奴波安礼杼 伎美我美家思志 安夜尓伎保思母
訓読 筑波嶺(つくばね)の新(にひ)桑繭(くはまよ)の衣(きぬ)はあれど君が御衣(みけし)あやに着(き)欲(ほ)しも
私訳 筑波山の新しい桑の葉で飼った繭で作った絹の衣はありますが、愛しい人と夜床で交換する、その貴方の御衣を無性にこの身に着けたいと願います。
集歌3351
原文 筑波祢尓 由伎可母布良留 伊奈乎可母 加奈思吉兒呂我 尓努保佐流可母
訓読 筑波嶺(つくばね)に雪かも降らるいなをかも愛(かな)しき子ろが布(にの)乾(ほ)さるかも
私訳 筑波の嶺に雪が降ったのでしょうか。違うのでしょうか。愛しい貴女が布を乾かしているのでしょうか。
集歌3352
原文 信濃奈流 須我能安良能尓 保登等藝須 奈久許恵伎氣波 登伎須疑尓家里
訓読 信濃(しなの)なる須我(すが)の荒野(あらの)に霍公鳥(ほととぎす)鳴く声聞けは時過ぎにけり
私訳 信濃の国にある須賀の荒野で過去を乞うホトトギスの鳴く声を聞くと、天武天皇が王都の地を求めたと云う過去の栄華は過ぎてしまったことです。
ここで、万葉集全訳注の指摘を尊重して集歌3351の歌を除く集歌3348の歌から集歌3352の歌までの四首で、万葉集を遊んでみます。その遊びの様子を次に紹介します。
遊びの鑑賞 その一
集歌3348の歌は、東国を旅する官人が経験した情景を詠ったものと思いますが、その歌は集歌1176の歌と集歌1229の歌を重ね合わせて作った、記憶力の歌の感があります。この作歌は、後年に本歌取りなどと紹介される技巧ですが、歌自身は歌人でない秀才の歌です。
集歌1176
原文 夏麻引 海上滷乃 奥津洲尓 鳥簀竹跡 君者音文不為
訓読 夏(なつ)麻(そ)引く海上(うなかみ)潟(かた)の沖つ洲(す)に鳥はすだけど君は音(おと)もせず
私訳 夏の麻を引き抜き績(う)む、その海上潟の沖の洲に鳥は集まり騒ぐけども、貴方は音沙汰もない。
集歌1229
原文 吾舟者 明且石之潮尓 榜泊牟 奥方莫放 狭夜深去来
訓読 吾が舟は明且石(あかし)の潮(しほ)に榜(こ)ぎ泊(は)てむ沖へな放(さか)りさ夜(よ)深(ふ)けにけり
私訳 私が乗る舟は、明石の急な潮流に舟を操り行き泊まろう。沖へは出ていくな。夜は更けている。
集歌3348
原文 奈都素妣久 宇奈加美我多能 於伎都渚尓 布袮波等抒米牟 佐欲布氣尓家里
訓読 夏麻(なつそ)引く海上潟(うなかみかた)の沖つ渚(す)に船は留めむさ夜更けにけり
私訳 夏の麻を引き抜き績(う)む、その海上潟の沖の洲に船は留めよう。もう夜も更けました。
遊びの鑑賞 その二
集歌3349の歌は、ちょうど、集歌1228の歌が示す地名を集歌433の歌で示す地名に入れ替えただけのような歌です。そこには、歌の感情や技巧よりも、歌い手がどれほどよく古い歌を知っているかを自慢するような感がありますし、聴き手もまた、その知識を要求されるような歌です。
集歌433
原文 勝壮鹿乃 真々乃入江尓 打靡 玉藻苅兼 手兒名志所念
訓読 勝雄鹿(かつしか)の真間(まま)の入江にうち靡く玉藻刈りけむ手児名(てこな)し念(おも)ほゆ
私訳 勝鹿の真間の入り江で波になびいている美しい藻を刈っただろう、その手兒名のことが偲ばれます。
集歌1228
原文 風早之 三穂乃浦廻乎 榜舟之 船人動 浪立良下
訓読 風早(かざはや)の三穂(みほ)の浦廻(うらみ)を榜(こ)ぐ舟の船人(ふなひと)騒(さわ)く浪立つらしも
私訳 風が速い三穂の入り江を操り行く舟の船人が騒いでいる。波が立って来るようだ。
集歌3349
原文 可豆思加乃 麻萬能宇良末乎 許具布祢能 布奈妣等佐和久 奈美多都良思母
訓読 葛飾(かづしか)の真間(まま)の浦廻(うらま)を漕ぐ船の船人(ふなひと)騒(さわ)く波立つらしも
私訳 葛飾の真間の入り江を操り行く船の船人が騒いでいる。浪が立って来たらしい。
遊びの鑑賞 その三
集歌1260の歌は、古歌集に載る歌ですし、集歌1314の歌は藤原京時代の古い歌と思われます。これらは、詠み人知れずですが巻七に載る歌ですので、万葉時代には多くの人に知られた歌だったようです。
こうした時、集歌3350の歌は集歌1260の歌や集歌1314の歌を踏まえた上で、東国を旅した官人が、筑波の地名と名物を織り込んだように感じてしまいます。
集歌1260
原文 不時 斑衣 服欲香 衣服針原 時二不有鞆
訓読 時ならぬ斑(まだら)の服(ころも)着(き)欲(ほ)しきか衣(きぬ)の榛原(はりはら)時にあらねども
私訳 その季節ではないが神を祝う斑に摺り染めた衣を着たいものです。榛の葉で縫った衣を摺り染める、その榛原は神を祝う時ではありませんが。
集歌1314
原文 橡 解濯衣之 恠 殊欲服 此暮可聞
訓読 橡(つるばみ)の解(と)き濯(あら)ひ衣(きぬ)のあやしくも殊(こと)に着(き)欲(ほ)しきこの暮(ゆふへ)かも
私訳 橡染めの服を解いて洗って、そして縫った貴方の衣が、不思議なことに無性にこの身に着てみたいと思う、この夕暮れです。
集歌3350
原文 筑波祢乃 尓比具波麻欲能 伎奴波安礼杼 伎美我美家思志 安夜尓伎保思母
訓読 筑波嶺(つくばね)の新(にひ)桑繭(くはまよ)の衣(きぬ)はあれど君が御衣(みけし)あやに着(き)欲(ほ)しも
私訳 筑波山の新しい桑の葉で飼った繭で作った絹の衣はありますが、愛しい人と夜床で交換する、その貴方の御衣を無性にこの身に着けたいと願います。
遊びの鑑賞 その四
集歌3352の歌は、ちょうど、集歌227の人麻呂歌集の歌と集歌1475の大伴坂上郎女の詠う歌を重ね合わせたような歌です。天平年間に集歌3352の歌が、東国に旅した官僚により詠われたのですと、時代での和歌のテキストを忠実になぞったような感がします。
集歌227
原文 天離 夷之荒野尓 君乎置而 念乍有者 生刀毛無
訓読 天離る夷の荒野に君を置きて思ひつつあれば生けりともなし
私訳 大和から遠く離れた荒びた田舎に貴方が行ってしまっていると思うと、私は恋しくて、そして、貴方の身が心配で生きている気持ちがしません。
集歌1475
原文 何奇毛 幾許戀流 霍公鳥 鳴音聞者 戀許曽益礼
訓読 何(なに)奇(く)しもここだく恋ふる霍公鳥鳴く声聞けば恋こそまされ
私訳 どのような理由でこのようにひたすら恋慕うのでしょう。「カタコヒ」と鳴くホトトギスの啼く声を聞けば、慕う思いがさらに募ってくる。
集歌3352
原文 信濃奈流 須我能安良能尓 保登等藝須 奈久許恵伎氣波 登伎須疑尓家里訓読 信濃(しなの)なる須我(すが)の荒野(あらの)に霍公鳥(ほととぎす)鳴く声聞けは時過ぎにけり
私訳 信濃の国にある須賀の荒野で過去を乞うホトトギスの鳴く声を聞くと、天武天皇が王都の地を求めたと云う過去の栄華は過ぎてしまったことです。
このように万葉集で巻十四において東歌と分類される巻頭五首に対して、集歌3351の歌を除いて集歌3348の歌から集歌3352の歌までの四首で遊んでみますと、集歌3351の歌と集歌28の御製との関連を認めない専門家の鑑賞や解説に逆らって、巻十四の巻頭歌の比較と編纂から集歌3351の歌もまた、同じではないかと邪推してしまいます。この邪推を下に集歌3351の歌の鑑賞から集歌28の御製を訓み返してみますと、つぎのような鑑賞になります。こうした時、従来の鑑賞のように神聖で立ち入りが制限される天の香具山で、下女が洗濯物を干さなくても良いことになります。
集歌28
原文 春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山
訓読 春過ぎて夏来(き)るらし白栲の衣(ころも)乾(ほ)したり天の香来山(かくやま)
私訳 まるで寒さ厳しい初春が終わって夏がやってきたようです。白栲の衣を干しているような白一面の天の香具山よ。
素人の酔論におつきあい頂き有難うございます。いかにももっともらしく見せていますが、内容は素人の素人たる由縁のお粗末です。
参照事項ですが、補訂版万葉集本文編(塙書房)では「目録は、奈良時代末期を下らる頃に成ったと考えられるが、諸本によって出入り甚しい箇所があり、これに校合を加えて本書に収めても、そのままではほとんど利用価値がない」とされているように、万葉集においては歌を載せる歌巻本とその巻本の目録とは、その成立年代が違うために示す内容が一致しません。歌巻本と目録との関係を研究するのも、一つの有名な万葉学の分野です。
普段の解説では巻十四は東歌の巻として有名ですが、その歌巻本で東歌とされるのは中央官僚が東国を旅して詠ったと思われる巻頭五首のみです。巻十四に載るそれ以外の歌は、国別の相聞、譬喩歌、雑歌と国未詳の相聞、防人歌、譬喩歌、挽歌の区分になっています。つまりに万葉集における東歌とは、中央の人が東国をテーマに歌を詠ったとの意味合いで、東国の人が鄙言葉で詠った歌の意味合いではありません。従いまして「東歌」の本来の意味合いにおいて、奈良の京の大宮人にとっては、集歌28の歌も集歌3351の歌も知るべき歌となります。
また、和歌での本歌取りの技法は新古今和歌集時代に盛んに行われた技法とされますが、実際は平城京時代中期には既に一般的な技法であったことは、ここで示した通りです。この本歌取りの技法を葛井連広成たちは「古曲(ふるきおもしろみ)」と称したと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
