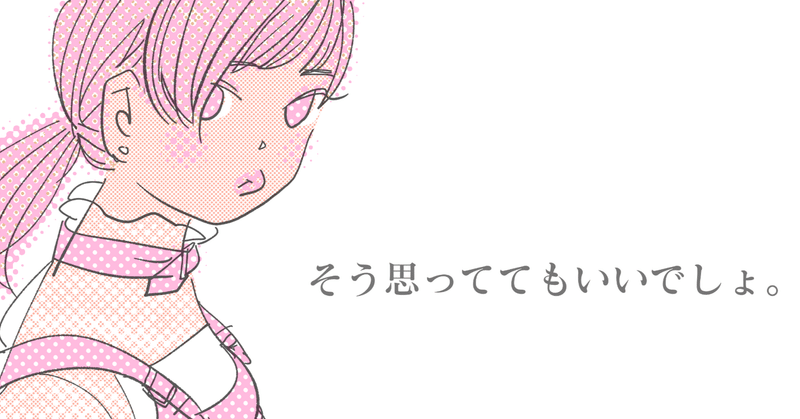
税金は誰のものか、墨者と儒者の論争
中国古典の眺め方で、税の徴収とその使い道から中国古典思想を眺めるという見方はまずしないと思います。特に儒学を税の徴収とその使い道から分析しますと、儒学は生まれながらの特権階級側の論理ですから市井の民にとってこれほど悪逆非道な思想提案は無いと思います。
以下は全くの与太話です。発端は万葉集時代の、そもそも論からの疑問への与太話です。さて、古代にあって当時の為政者が税金は誰のものかと思っていたかです。公地公民理論での契約による耕作する土地の使用料なのか。他方、土地は国の公地だから、そもそも、耕作する土地の利用の許可は領主からの善意の恩恵であって、収穫物は領主の物であり、その一部の収穫物を慈悲と言う徳目で農民たちに再配分するのかです。古代中国の思想では明確で、墨学では税金収入は民衆の公利のためのものですが、儒学では税金収入は国君のもので、それをどのように使うかは国君の徳によるとします。
この観点から万葉時代を眺めてみますと、天武天皇以降の皇親政治の時代、非常に特異的に朝廷は国内総生産を主に民衆のために使用しています。建前として公地公民制度を取り、税率と税の徴収方法は全国に公表されており、それも住民税と国税の二本立てです。確かに賦役や兵役は有りますが、その分、当該者に対して日当支給や納税免除などの損失補填制度があり、非常に公平に徴税体系は実施されています。
その住民税はある種、目的税で、地方自治運営費と地域の公共事業を主体として税は使われ、一部ですが救荒備蓄や独居老人や孤児救済などにも使われます。地方公務員の給与は公表され、地域の識字階級では徴税された住民税の使い方が監視できる体制でした。昭和時代には、地方行政職の郡司階級は世襲制だったとの考えがありましたが、現在に伝わる資料を下にすると、律令制度が適切に行われた時代、藤原氏が台頭する以前となる、天平21年の郡司候補の絞り込みに関する詔が出る以前では、地域で有力者となる数家の中から、識字能力や経理能力を基準に国司が複数名を選抜し、中央政府により能力確認と最終選抜が行われていましたし、定期的に考課も実施されていました。この時代、調税や庸税の納付の関係や中央で開催される祈年祭参集の関係から、地域の人々は上京の道中で他の地域の実情を毎年、見聞きすることになり、地域間競争は活発でした。調・庸制度の派生問題で、生産物の技術差が明確に現れ、それが物品価格に顕れます。中央での調庸税の納税が品目ごとの数量ベースの為、納税以前に市場で買場を行うことにより、実質の納付量に影響が出ます。記録では、天平時代中期、絹布では地域間の技術格差により実質納付量で15~20%程(但馬産680文、安芸産600文)の格差が生まれています。当然、地域の納税者となる農民たちは地域指導者の技量の差による納税格差を知っています。また、会計監査から公金流用があれば、郡司などの地方行政官は処罰され交代させられています。つまり、中央政府と国司による地方自治と住民税への監視とコントロールが効いていました。
また、国税の用途も皇室維持費用は公務員給与に準じて官位と職務に応じた俸給制度です。確かに民衆の生活水準に対して非常に高額ではありますが、規則を定めた俸給制度ですから、その認識では公地公民での国内総生産物は民衆の物との意識です。収穫物総取り後の天皇家の残余を分配すると云う考え方ではありません。民衆は全員奴隷であって、翌年の生産を保証する程度に最低限の食料と衣料を支給すれば良いとするのではありません。公務員給与等以外では、役所設備建設、国防、全国幹線道の整備、大規模河川の改修、大規模灌漑設備の整備、稲の品種改良、鉄製農機具の配布などに国税が使われ、それが、藤原氏が台頭するにつれて仏教など生産に関わらない方面にも使われるようになります。それでも、神亀年間以前の皇親政治の時代では、まだまだ、国税の非生産部門への使用では節度があり、特別徴収などは実施していませんでした。これは万葉集の歌の勃興期から最盛期に相当する期間です。民衆も請願を出し、街道整備、水路と公営の船便整備、治山治水などの事業の実現を図っていますし、朝廷も調税や庸税の納付の便利を担保する目的が根拠だからでしょうが、それに応えています。実際、調税や庸税の納付シーズンは9月から11月程度の話で、それ以外の期間では街道や水運は地元民政の便益です。
こうして万葉時代を税金の使い方から眺めてみますと、古代の専制君主時代に、国内総生産は民衆の物と言う思想で国家が運営されていたとは、不思議に思いませんか。支配する領地からの収入はすべて領主の物で、再生産に必要な最低限の食料を農民に再分配する、ある種、農奴的な扱いも出来たはずです。ところが日本の律令皇親政治時代は、そのような思想での統治はしていなかったと思われるのです。公地公民の思想による律令制度は大陸の隋唐から輸入した制度ですから、日本の古くからの自然発生的なものではなりません。あくまで、律令皇親時代の人工の制度です。この人工の制度が飛鳥藤原京時代から後期平城京時代頃までは、日本全国で、きちんと運用されていたのです。実に不思議です。
ただ、参考に天平15年に聖武天皇が東大寺の大仏建立の時、詔として「夫有天下之富者朕也。有天下之勢者朕也。」と発言していますが、詔勅のような行政命令ですと漢文で記述する規定から、漢文で天皇の立場と国家の財物との関係を示すなら、このようになるのでしょう。天下の富と権勢はすべて天皇の許に集約される、これが儒学的な四書五経を下とした漢学の世界です。儒学的な漢学の世界では、「夫有天下之富者朕也。有天下之勢者朕也。」が、統治では本来のあるべき姿で、その集めた天下の富を慈悲と言う仁の心で下々に公平に分配することが、君王に課せられた徳です。なお、宋時代に産まれた朱子学以降、民の教養レベルの向上に沿うように儒学は大きく変質していますから、隋唐時代までの徳とは、韓非子が示す「慶賞之謂德(慶賞、これを徳と謂う)」の定義の方です。つまり、「徳」は「上からの褒賞」であり、「公平な分配」のような意味をもつ言葉です。朱子学以降の再定義された教養レベルが上がった庶民をも対象とする「徳」(人間の道徳的卓越性)のようなものではありません。隋唐時代までは仁と徳は上から下へと行われるものです。
その時代、税収を民衆の公利のために使う思想があったかと言うと、唯一、墨学だけです。一般に、儒学者を中心とする研究者は、墨学は前漢時代中期以前に消えた学問で、清朝時代の乾隆四十八年(1783)の『経訓堂本墨子 畢沅註』により、学問的に再発見されたと評論します。一方、唐時代中期に韓愈が孟子を再評価すると同時にその比較根拠として『読墨子』を記したように、当時の知識階級では知るべき知識であったことも事実です。この唐時代中期にあっても中国の知識人では墨子を知ることは教養だったとの確認から、当時の日本国内の状況を見ると、日本書紀に次のような墨子に由来するような言葉が見つかります。
日本書紀: 於是、二神誅諸不順鬼神等(神代下 第九段本文)
墨子: 以祠說于上帝鬼神(兼愛下)
日本書紀: 然天命忽至、隙駟難停。(景行天皇四〇年)
墨子: 人之生乎地上之無幾何也、譬之猶駟馳而過隙也。(兼愛下)
日本書紀: 聖徳太子憲法十七条(推古天皇十二年)、八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡監、終日難盡。是以、遲朝不逮于急、早退必事不盡。
墨子: 今唯母在乎王公大人説楽而聴之、則必不能蚤早朝晏退聴獄治政。(非楽上編)
つまり、少なくとも唐時代中期までは、大陸側でも日本側でも墨学は知識人階級には知るべき教養だったことになります。また、それを受けて日本書紀などに墨学の影響が見られるのでしょう。
すると、墨学の理念を用いて天武天皇以降の皇親政治の時代は運用されていた可能性が推定可能となりますが、なぜ、大和朝廷は、本来なら為政者に都合のいい、標準的な漢学の世界の「夫有天下之富者朕也。有天下之勢者朕也。」では無かったのかです。唯一の可能性として、天武天皇が壬申の乱以降もその時の戦時体制を解かずに軍制で統治を行っていたからでしょうか。
つまみ食いで研究するような墨子研究者では誤解が非常に多いのですが、墨学の理念の根底には、戦乱を生き抜く方法論として防衛戦争では男女を問わない国家総動員令を用いる思想があります。ここが儒学には見られない特徴です。墨学では、城下住民、男女や老少を問わずに全員に、己の自身の命を賭ける攻城戦に対して等しく動員令を掛け、軍令に従い参戦することを強制します。一方、己の自身の命を賭けた攻城戦への参加に対し、男女や老少を問わずに軍功と参戦回数とを勘案した褒賞制度を設けています。
墨学城攻篇で示す、この戦時には男女や老少を問わずに動員令を掛け、軍功と参戦回数とを勘案した褒賞制度を運用するために、同輩の部隊員たちは互いの立場を尊重し助け合い、指揮命令には抗命することなく上官に従うことが重要で、また、戦闘を指揮する上官は有能じゃなければいけません。軍のトップは世襲の住民周知の人物が好ましいが、実戦部隊の司令官には実力主義で信賞必罰の運用が求められます。これを短く言えば兼愛、尚同、尚賢の思想です。ちなみに、墨学城攻篇では、城に地下にトンネル掘って攻め込む戦法に対抗するトンネル戦では、男女同数でそれぞれにトンネル戦の部隊を結成し、そのトンネルを掘り、攻防を戦う時の褒賞規定では、戦勝時の報酬は男女のそれぞれの小隊長に錢千が与えられます。また、城壁の上で戦う、武器を持っての戦闘部隊の褒賞規定では、女子の武器規定が矛だけなのを背景に、戦勝の報酬は男子よりも低く、女子部隊長には錢五千です。しかしながら、男女を問わず、公平な成功報酬の規定を設けています。
日本の状況を見てみると、天武天皇も天武二年に「夫、初出身者、先令仕大舎人、然後選簡其才能、以死当職。又婦女者、無問有夫無夫及長幼。欲進仕者聴矣。其考選准官人之例。」と男女出身を問わない登用規定を示します。その官人として登用された女性は、天武天皇十三年の「凡政要者軍事也。是以文武官諸人、務習用兵、及乗馬。」と、「男女、並衣服者、有襴無襴、及結紐、長紐、任意服之。其会集之日、著襴衣而著長紐。唯男子者有圭冠。冠、而著括緒褌。女年三十以上、髪之結不結、及乗馬縦横、並任意也。」を併せて解釈すると、女官でも折々の軍事パレードに騎馬及び武装姿で参加する必要があったと考えられます。つまり、墨学思想の援用に近いものがあります。これなら、万葉集で高貴な但馬皇女が「いまだ渡らぬ 朝川渡る」と、早朝に馬で飛鳥川を渡る風景を詠っても違和感は無いことになります。
加えて、古代日本は大陸や朝鮮半島とは違い、神武天皇即位前紀に「又、於女坂置女軍、男坂置男軍。」の記述や、舒明天皇九年の上毛野君形名の妻の行動、「而親佩夫之剣、張十弓、令女人数十俾鳴弦。」の記事が示すように、女性が女部隊を組織し女軍と称する戦闘行動をする国です。記録に残る上毛野君形名の妻を護衛する別式女たちは自身で弓に弦を張り、その弓を引ける力自慢の女武芸者で、それを奈良時代の人たちは違和感を持たないのです。このように、古代日本には、墨学が示す、戦時には男女や老少を問わずに動員令を掛けることへの国民的な素地はあるのです。
命を賭けての戦争参加の義務と、その裏返しである民衆の社会的地位及び権利意識が、天武天皇以降の皇親政治の時代の人々にあったのでしょうし、それを為政者が当然のこととして認めたのでしょう。裏返せば、平和が続き命を賭けての戦争参加の義務がうやむやになれば、民衆の社会的地位及び各種の権利を為政者が認める必要は無くなります。それが対熊襲・対蝦夷・対新羅・対大唐との紛争や戦争が無くなったとの認識が生まれた奈良時代後期から平安時代以降の日本なのでしょう。
また、近現代では畢沅が校訂を為して『経訓堂本墨子』を刊行して、墨子は読めるような本になったと評論しますが、他方、日本では、それ以前の享保16年(1731年)に『正統道蔵』に載る墨子が到来し、それが宝永7年(1757年)に版木本として刊行されています。
現代、中国と台湾で電子データ化されている墨子は、こちらの『正統道蔵』に載る墨子が、ほぼ、そのままです。逆に、儒学者の立場で清朝時代に校訂されたもの、『経訓堂本墨子』や孫詒譲の『墨子閒詁』などは、儒学者として都合が悪い箇所を、適宜、改文・改字していますから、逆に難解として読めない方向に導いています。
さて、歴史に墨子が現れたのが周代戦国時代前期です。この時代、中国大陸では群雄割拠の戦乱の時代、ど真ん中です。社会としては、日本の郡規模の地域で血縁関係を中心に農耕を中心とした社会活動を行い、そろそろ、地域特産物を交換する交易が盛んになって来た時代です。この穀物生産などに対する地力の差や特産物生産力の差により、地域力の優劣が生まれた時代です。地域力の優劣が生まれましたから、それぞれの地域の支配者に勢力拡大の欲望も生まれますし、人としての支配欲、名誉欲、性欲などを原動力に吸収合併運動へと突き進みます。周代春秋時代の二百以上の諸国が戦国七雄に集約され、最終的には秦帝国に吸収され、最初の統一王朝が生まれました。
この諸国諸侯の勝ち抜き戦では、正しく自分の領地の人口と土地を把握・管理し、適切に税を徴収することが国家運営の基本中の基本です。従来、日本の郡規模の地域で血縁関係を中心に農耕を中心とした社会活動から、一歩進んだ、統治技術が要求されるようになっています。この一歩進んだ統治技術には、文字の読み書きと計算が出来る人材が必要です。そうした時、最初に組織的な教育機関を作り上げたのが孔子で、その次が墨子です。
ただし、孔子は読み書き計算以外に儀式運営技術を教え、墨子は読み書き計算以外に建築土木技術を教えると云う、別々な専門分野を持っていました。孔子の儀式運営技術から儒学へと発展していき、墨子の建築土木技術は、途中、防衛陣地技術を生み、別には建築工学として中国の巨大建築や大規模土木の技術力と発展していきます。ただ、同じ時代に読み書き計算の技能を持つ人材を教育し、全国の諸侯に人材を紹介する機関同士ですから、当然、顧客である諸侯の取り合いや優秀な人材の取り合いとなります。その時、それぞれの教育機関の教育理念に対し、互いに誹謗中傷し、攻撃するのは必然です。
ここで、孔子の教育機関と墨子の教育機関での教育理念での大きな相違は、国家税収は、一体、誰の物かへの態度です。孔子は天から天下を渡された天子=国王のもの、私有財産だと考えました。国と云う土地の支配者は国王だから、その土地からの収入は所有者の物=国王の物と云う、非常に判り易い論理です。一方、墨子は、天子は天から天下の安寧な統治を行うことを委託されただけで、安寧な統治の享受者は民衆である。つまり、国家税収は民衆の安寧を保証する為に使われるべきものと考えです。
儒者は、国家税収は国王の私有財産と考えますから、私有財産を下の者へ分配する理屈を考案しました。それが徳の思想であり、慈悲の思想です。「徳」と云う漢字本来の意味合いは、韓非子が規定する「慶賞之謂德(慶賞、これを徳と謂う)」で、「徳」は「上からの褒賞」であり、「公平な分配」のような意味をもつ言葉です。国家財政を国王独りで抱え込まないで公平に分配が出来る人を有徳者と呼びます。徳は職務や功績に対する公平な分配です。職務や功績が無い人には、上から下への慈しみである慈悲と云う論理での分配を考案します。節度を持った慈悲の分配を孟子は仁を考えたようです。ただし、孟子は制度を設け自動的に困窮者への救済策を行うこと=墨者の云う公利の実施は否定しています。
墨者は、国家税収は民衆の安寧を保証する為の物との考えですので、用途を主に国家防衛、治安対策、食料備蓄などの飢饉対策、交通網整備、治水対策、独居老人・孤児対策などに使えと主張します。
この国家税収への考え方の差から、音楽・娯楽や葬儀でも態度が違います。儒者は国王やお客が楽しめるように女楽を入れた性を伴う演奏宴会が好ましく、葬儀は出来る限りの出費で葬儀を行うことが孝行とします。墨者は、音楽は全員参加型の村祭りのようなものを推薦し、それは人々の交流の場のようなものとしろとし、亡くなった人への哀悼は心で行い、形式としての葬儀自体は必要最小限で十分とします。
ここで、江戸時代のこの種の理解として、延宝七年刊行された大坂の地誌の『難波雀跡追』の序文は次のように語ります。
往還の旅客の知へとて、先人已に難波雀に岐路を囀らしめ、世にたすけとす。然ども、未美をつくさざるものあれバ、予糸染の嘆もだしがたくて、今又上高家諸士より下百工商賈及所士遊芸のもろ人まで、悉尋求て梓にちりばめ世に伝ふるものなりし。于時延宝七歴五月/難波隠士書之((延宝7年=1679年)
ここでこの解説として、
「糸染の嘆」は、墨子の故事にもとづく表現である。白い糸が黄にも黒にも、つまりどんな色にでも染まるように、人の心が環境や習慣などの影響で善くもなり悪くもなることを墨子が嘆いた、という。道に迷わないように雀が大坂の道案内をしても、“ 美をつくしていない ” のだから、墨子のようにどちらへも行けると泣くこともできない、というようなことだろうが、ややわかりづらく、唐突にも思える。だが、故事をもう一つふまえれば、『難波雀』と『難波雀後追』の序文はつながるのである。
楊子見逵路而哭之、為其可以南、可以北。墨子見練絲而泣之、為其可以黄、可以黒 。(淮南子)
前半の、四方八方に通ずる道の、北にも南にも、つまりどちらへも行くことができるように、人が善くなることも、悪くなることもできると楊子が泣いた、という故事が、後半の墨子の故事と対で語られている。『難波雀』は、道に迷わないように大坂を案内する、としていたが、『難波雀跡追』は、道に迷う、ということからわかれみちを連想することによって、楊子、さらには墨子の故事へとつなげているのだ。この墨子の故事への連想の飛躍が、「鶴」へと着地する次の連想をひきだし、『難波鶴』となるのである。
これが江戸時代の墨子などの立ち位置を示すものです。江戸時代に儒学が盛んになったと上辺では指摘しますが、実態は公民の立場から知識者の中では墨子の思想が必須だったのです。ここに江戸時代でも公は民百姓のために政を行うと言う、東アジアでは非常に特異な日本政治の背景があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
