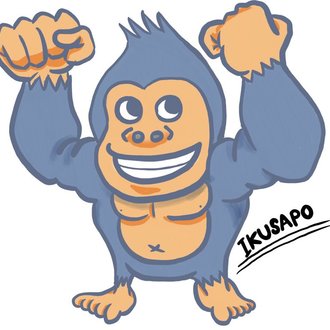肩こりはトレーニングで治す!上位交差性症候群に対する実践アプローチ
こんにちは!!
イクサポです!!
今回は、上位交差性症候群についてまとめていきます。
皆さんは肩こりや首の痛みに悩まされたことないでしょうか?
肩こりや首の痛みに付随して多くなる訴えで”肩甲骨の内側の痛み”があるのではないでしょうか?
肩こりや首の痛みを訴える方の多くは、肩甲骨の内側を押すと”そこが悪いポイント”であることが多いです。
また、最近では子供でも肩こりを訴える子が増えてきました。
そこで、今回はその肩甲骨の内側の痛みや肩こりの原因となる姿勢について、上位交差性症候群というパターンに落とし込んでどう対処していけばいいのかをまとめていきたいと思います。
それではいきましょう!
痛みが出るポイント
肩甲骨の内側の痛む場所で最も訴えの多い場所は、肩甲骨の内側の半分から上部になります。
ここが凝り固まってしまっている人は非常に多いです。

・僧帽筋
・菱形筋
・肩甲挙筋
・斜角筋
などがあり、肩甲骨の内側の痛みの大半は背部の筋が問題であることがわかります。
痛みのメカニズム
肩甲骨の内側の痛みのメカニズムですが、
「筋肉が引き伸ばされて弱化している」
ということが大きな原因として1つ挙げられます。
後ほど説明しますが、これは上位交差性症候群のパターンが当てはまります。
「背中(肩甲骨周り)の筋の弱化」と「頸部前面の筋の弱化」
「体幹前面の筋(胸筋群)の短縮」と「頸部後面の筋の短縮」
このような関係性があります。

こんな感じの姿勢でデスクワークをしていると、このような筋の弱化や短縮を呈します。
それでは上述した上位交差性症候群とは何なのでしょうか??
詳しくみていきましょう!!
上位交差性症候群とは?

エビデンスに基づく疾患別クリニカルマッサージ ー評価と治療より引用
上位交差性症候群は、上記の写真のようなパターンをとります。
簡単にいうと、
短縮する筋と弱化する筋が規則性(交差する)に生じる
ということです。
この上位交差性症候群になるとアライメントとしては、
・胸椎後弯による頭部前方偏移
・胸椎後弯による頚椎伸展
・胸椎後弯による肩甲骨外転
となり、一般的に言われる猫背の姿勢になります。
猫背になると日常から肩こりが酷かったり、腰痛に悩まされていたりしますが、それはこの上位交差性症候群になってしまっているため、身体の各部位に不具合が出てきているのです。
この上位交差性症候群を治療するポイントとして挙げられるのが、
ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥