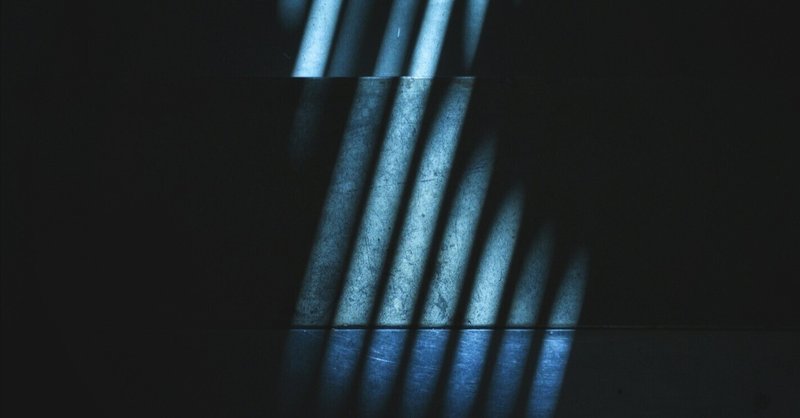
ないなら、つくることで生き延びる
世界に道具にされてしまう、という強い言葉が頭のなかに反芻している。
労働の歯車と化すこと、働けないものは道具として役に立たないと、勝手にどこか思ってまってはいないか。子どもを産めないのであれば、生殖器として機能しない、といったような政治家の発言。
仕事を辞めて2年間、留学していた間は、とにかく不安でしかたなかった。自分が働いてないから、社会に価値を生み出せていないのではないかと思った。その不安は、道具としての価値を帯びない自分はいてもいいのだろうか、という不安でもあった。と、そのとき思った。自分は、なんかいろんな物事から逃げたかったので、留学を逃避の言い訳にしていた。けれども、どこまで行っても逃げきれないのか、とその時思った。
昨日、尊敬する小説家・村田沙耶香さんの『地球星人』という原作を舞台演劇にした公演があった。ちょうど、出張と友人の結婚式があって、東京に行かないといけなかったので、いいタイミングだった。うずめ劇場、という劇団による公演だ。旧東ドイツ出身の演出家ペーター・ゲスナーが北九州にて設立したらしい。そのとき、その土地に自分が楽しめるような劇団がなかったからつくったんだ、と公演前にペーターさんは挨拶とともに話した。
「ないなら、つくればいい」ってなんてシンプルなんだろうか。多分みんな、本当に自分がしっくりくるものに囲まれて、つきあって、生きてるわけじゃあない。なんだか枕が少し高いなあと思って3年経ったり、チェーンの喫茶店で出る水にはなんでかいつも氷が入っていたり、そんなことばかりだと思う。でも、とんでもない適応能力と学習能力で、すぐそんな状況も苦しくなくなるように、身体と心を外側のフレームに合わせられる。
そして、なんかしっくりこなかったことなんて、いつの間にか忘れてしまうのだ。そうやって日々になんとなく満足していってしまう。ただ、100%の適応はできないと思う。意識では周波数あってんじゃんと思っても、どっかでずれているときに、その雑音はじんわりと気づかないくらいの毒になってるかもしれない。全員、そういうところはあると思う。全てにおいて全てが自分にぴったりフィットしているなんてあり得ないけど、受け入れて生きていると思う。
ただ、その中でも、どうにも我慢できないときもある。そして、そのしっくりくるものが、今ある選択肢の中から見つからないときに、もうつくるしかない。
・・・
『地球星人』の公演は圧巻だった。元々小説を読んでいたので、内容はわかっているが、小説の狂気が、かくも生々しく目の前にいる人たちの振る舞いから発せられると、怖くなった。
自らを魔法少女だと思っている主人公・奈月とポハピピンポボピア星からきた宇宙人である幼馴染は、一年のうちにお盆しか会えない。奈月は姉や親からもグズだと罵られ、塾講師から性被害に会い、逃げ場がない。自身を魔法少女だと思い込み、魔法をかけて外側の異常な世界や他者からの侵食を何も感じないようにする。なんとか身を保とうとする。
最終的には、ポハピピンポボピア星人となって、およそ人間とは思えない生活を送るようになる。それは、外側の世界=人々を道具化しようとする工場から逃れたいからこそ、異なる世界をつくるしかなかった。「なにがあっても、生き延びる」ための最終的な到達地点が、「ないなら、つくればいい」であると感じた。物語の内容を語るわけにはいかないが、人間からポハピピンポボピア星人に変容していく様子に宿る演者さんのふるまいは、本当におそろしかった。
ただ、そのおそろしさは工場的な日常世界を一層浮き彫りにしてしまう。最終的な結末はもはや倫理も何もない。人を殺してもなんとも思わないように、まさしく異人化していく。しかし、それを恐ろしいと思ってしまうのは、多かれ少なかれ自分も工場化されているからなじゃあないの?という問いを突きつけてくるちからがあった。本当にそんな公演だった。すごかった。
Twitter:より断片的に思索をお届けしています。 👉https://twitter.com/Mrt0522 デザイン関連の執筆・仕事依頼があれば上記より承ります。
