
話し手の責任を放棄しない〈88/1000〉
【ラジオ体操393日目】
『ニコチンレス生活114日目』
こんにちは。
学生を対象にして講義を実施すると、つまらない時にはつまらないことを態度でハッキリ示してくれるので、こちらが勉強になると感じるコマリストです。
○○君は黙って話を聞くことが出来ないからダメだ!
人が話している時は、相手の目を見て聞きなさい!
こんなことを言われたり、言ったりしたことはないでしょうか?
これって、本当でしょうか?
聞き手側からして全く興味を持てない内容にも、『聞く姿勢』を示し続けるというのはかなりの苦痛を伴います。
大人になった今でも、経済の話だったり、政治の話だったりが苦手な人は多いし、宇宙とか物理の話をされてもわからないから興味を持てないという人も多いはず。
興味を持てないこれらの話を30分も1時間も相手の目を見ながら、欠伸をすることなく真剣に聞き続けるのってしんどくないですか?
今日は、話を集中して聞かない子供を責める前に、話し手としての責任を果たせているのかを考えないとただの拷問になるというお話です。
わりと偏った考え方だと思うので、賛否両論ある内容です。あくまでコマリストの私見であり、自戒の念を込めた内容だということをご承知おき下さい。
校長先生のありがたいお話
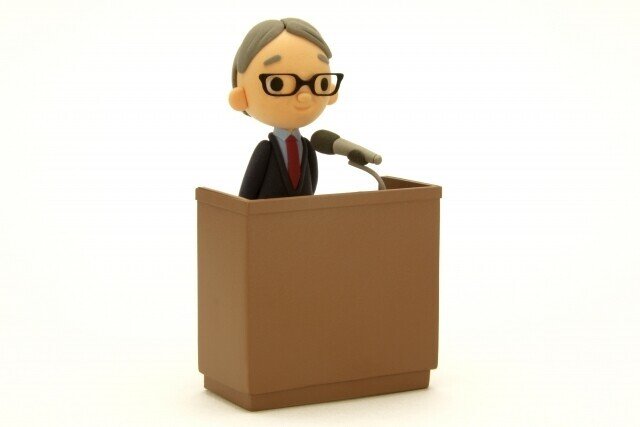
さて、いきなり少し棘のある内容に触れていこうと思います。
皆さんは小学校・中学校・高校時代の集会で校長先生が話をされるのを聞いた記憶があるでしょうか?
恐らく多くの学校で、何かしらの集会や運動会等の行事が行われる度に、冒頭もしくは最後の締めのあたりで校長先生が話をする時間が用意されていたと思います。
となると、小学校であれば最低でも年間10回以上を6年間。中学校・高校でも最低5回以上を計6年間。合計すると約100回の『校長先生のお話』を聞いてきたことになります。
もちろん、途中で先生が変わることもあるし、進学すれば毎回別の校長先生に代わります。
ということで、同じ人ではないけれど、校長先生という肩書を持つ人の話を100回近く聞いていることになります。
さて、ここで2つの質問をします。
❶100回の校長先生の話の中で、印象に残っている話は何ですか?
❷校長先生の話が楽しみで仕方がなかったという人はいますか?
もちろんこの答えには、個人差があると思います。ということで、私自身がどうかということだけ晒します。
①について、たった1つの話すら覚えていません。
②について、楽しみだと思ったことは1度としてありません。
私の性格が悪いことは認めていますが、同じ答えだという人、結構いるんじゃないでしょうか・・。
自分たちが苦痛だとすら思っていた校長先生のありがたいお話。
静かに聞きなさい!目を見て聞きなさい!
これをするのが正しい教育なんでしょうか、、
提供する側が責任を果たしていないように感じるのは私だけでしょうか。。
教育とは

では、校長先生の話など聞かなくていいから、さっさと集会から退出するのが正しい行動か?
もちろん、この行動が100%正しいと言うつもりはありません。
現代教育において、集会で校長先生の話を聞かずに退出しようものなら、その生徒は”問題児”と揶揄され、学生としての評価を下げられることになります。
なので、これらをリスクだとして避けたいという気持ちが学生本人にあるのであれば、「我慢して聞く」という選択肢も正解になることがあると思います。
個人的には、「評価が下がる」「問題児扱いされる」というのは、大人側が作った拘束具みたいなもので、従うことを強要されている状態なので健全ではないと考えています。
教育とは、大人たちが武器を片手にルールを強要するものではない。子供たちが自ら考え、選択することを支援するものであってほしい。
ということで、○○するのが正しいからそうしなさい!と強要するのではなく、どうして○○するのが良いと思うかを自分で考えさせてほしい。
いくら公式を教え込んだところで数学力は向上しないんです。どうしてこの公式が生まれたのかという考え方を教え、自ら公式を生み出せるようになってこそ数学力が高まったと言える。
少なくとも私は、自分が正しいと信じるものを強要するのではなく、子供たちが導き出した答えを正解だと言ってあげることが出来る大人でありたい。
そして、そのための支援であれば惜しみなく提供したいと思う。
話し手としての責任

さて、実はここからが本題です。
話を黙って聞かない生徒や、集中して聞けない生徒を悪い生徒だと注意する姿はよく目にする光景です。
ここで、考えてほしいのは”この生徒たちが何故、集中して聞けないのか”ということ。
少なくとも日本では、どの時代の子どもたちも、自分の好きなことや好きなものに夢中になる時間を過ごしていることが多いです。
もちろんみんな同じものに熱狂しているわけではなく、ゲームだったりスポーツだったり、読書だったり、ピアノ等の習いごとだったりと子供によって異なります。
さて、この「好きなものに集中している子供たち」は、集中して取り組むことを強要されたでしょうか?
そんなことはないはずです。
自ら率先して時間を忘れて集中しているので、親としては時間を決めて他のこともやる時間を作るように声をかけるほどのはず。
これはつまり、子どもたちに集中力がないわけではないということ。
ハッキリ言います。
話し手である校長先生や学校側に”も”問題がある。
子どもたちにメッセージを届けたいのであれば、子供たちが興味を持つ言葉を使い、たとえ話を使い、自ら聞きたいと思える空間を作るのが提供者としての責任です。
その努力をせずして、話を聞かない子供たちは集中力がない!と決めつけるのは、責任放棄も甚だしい。
民間であれば、自社が扱っている商品を買わない消費者に対して、こんな良い物を買わないなんて常識外れだ!と怒っているようなもの。
#それで売れるならいくらでも怒る
これがいかにおかしいことであるかなんて、普通に考えれば分かると思います。
なのに教育現場では、その努力をしないままに、校長先生の話は黙って聞くのが正しい。そうしなければ評価が下がる。と子供たちは強要される。
そりゃ、聞く気もなくなります。
#すべての学校ではないです
#生徒が目を輝かせて聞いている学校もある
もちろん、校長先生は噺家ではないし、話をするプロではありません。
なので、毎回めっちゃめちゃウケる話をしなければいけないということはないです。
#たまにはウケてね
ただ、生徒が理解できる言葉を選ぶ必要はあるし、生徒が見ている世界から分かりやすい説明をする必要はあると思います。
そして、聞き手は”どんな内容なのか”だけではなく、”誰が話しているのか”ということも興味の基準として持っているはずです。
そういった意味で、日頃から生徒たちとどんな接し方をするのか、生徒たちからどんな校長先生だというイメージを持たれているかということも、話を聞いてくれるかの重要な要素です。
ちなみに、今回は、学校における話し手と聞き手を例にあげて説明しましたが、これは学校に限った話ではありません。
社会人として、誰かに話をする時も、誰かの話を聞く時も、関わってくる重要な考え方だと思っています。
私たちは”言葉”でコミュニケーションをとる唯一の生き物です。
これを極めることが人生に於いてどれだけ重要なことであるかは言うまでもありません。
自分が聞き手になった時、相手の話の内容を責めるのではなく聞き手としての在り方を問いかける。
自分が話し手になった時、相手の聞き方を責めるのではなく、話し手としての在り方を問いかける。
重要なのは「自分自身がどう在るか」ですよね。
じゃ、またね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
