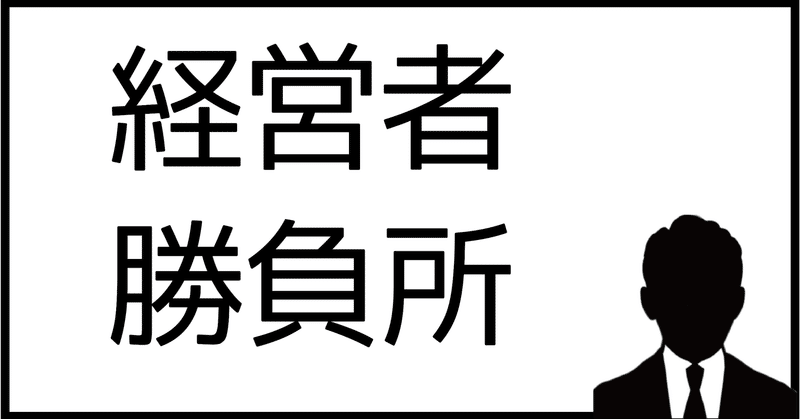
経営者の勝負所
ここ5年程、私は経営者として「ぬるま湯」につかっていた。
しかし、この度、少し無理をして「熱い湯」へ入ってみようと考えた。
今回は、この辺りのことについて書き綴っていく。
なぜ「ぬるま湯」につかるのか?
私の言う「ぬるま湯」とは、最近よく聞く言葉で「コンフォートゾーン」というものに似ている。
ここで言う「ぬるま湯」とは、経営者として、会社の業績や心理的な負担のバランスがとれた状態のことだと思って欲しい。
個人差はあるが、経営者は経営が長くなると、自然と「ぬるま湯」につかるようになる人が多い。
好んで「ぬるま湯」を探すと言うより、いつの間にか水温が下がっているというイメージだ。
私の経験上、早い人は経営10年程で「ゆるま湯」へ入る。
そして、20年もすれば「ゆるま湯勢」は、かなり増えている。
年齢的なことも関係していると思う。
「50歳を超えると終わりが見えて来る」という経営者は多いが、まさに私も最近その気持ちが少しだけ分かるようになった。
ちなみに、私が20代の頃は、そんな言葉を発する人の気持ちが全く想像できなかった。
「ぬるま湯」に入るまでの経緯は、以下のようなパターンが多い。
1.満足に生活できる収入が得られるようになった
2.リタイアする年齢に近づいた
3.自分の力量や器を理解し、その限界まで達した
4.会社を前進させるアイデアが尽きた
5.少なくともリタイアするまでは、会社が安泰だと確信した
6.既にリタイアできる資産を築いた
「ぬるま湯」につかっている経営者は、淡々と日々の業務をこなす。
殆どやることがない人も多い。
「ぬるま湯」が続いた結果、「このままでいけない」と、会社の経営を他人へ譲ったり、会社や事業を売却(M&A)する人もいる。
たしかに、これができれば、新しい経営者によって、再び水温を上げてもらえるかもしれない。
ただ、この選択は後継者(後継社)あってのものだ。
いつでも会社を廃業して、清算できる準備が整っているという人は、残念ながら殆どいない。
特に、会社に関わるスタッフ、外注先、取引先のことを考えると、なかなか純粋な廃業は難しい。
多くの良心的な経営者は、意図的かつ計画的に実行しなければいけない。
――― 様々な事情で「ぬるま湯」は続いてしまう。
「ダラダラと経営を続けている人」が多いと思われているのは、この辺りが原因なのではないかと思っている。
なぜ「ぬるま湯」から上がるのか?
私の経験上、「ぬるま湯」から上がる人は、以下のパターンが多い。
1.そもそも会社の業績が悪くなり、尻に火がつく
2.後継者が見つかり、最後の大仕事(事業承継)を得る
3.会社の売却に目途がつき、高く売るために業績を上げる
当然、1のケースが圧倒的に多い。
これは想像に容易いと思う。
しかし、上記以外だと「何かしら心境の変化」があり、再び温度を上げるということになる。
私の場合
ここからは、私の例を具体的に書き綴っていく。
くだらない話なので、鍵をつける。
その「ダサくて、くだらない、個人的な話」に興味がある人だけ読んで欲しい。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
