
弱者逆転の法則 勝てる土俵では勝負する!
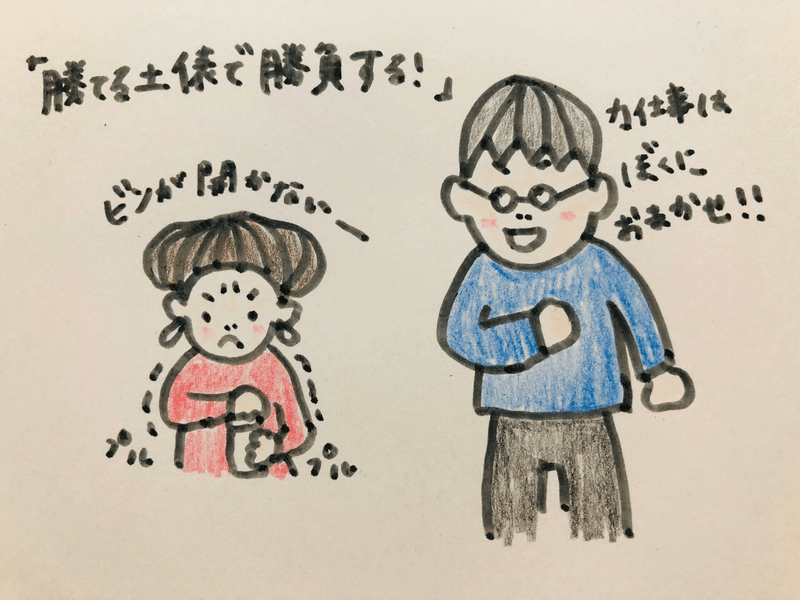
最近マーケティング理論とかを調べたりするけど、かなりの確立で近いことが孫氏の兵法に書いてあるのを発見して少しだけ嬉しくなった【まるメガネ】です。
恐ろしや!孫氏の兵法!!!
今日もマーケティングの基本知識を復習
勝てる土俵で勝負するランチェスター戦略について。
弱者逆転の法則とも言われるけど有名な戦略だね。
マーケティングって実は戦争での戦い方をベースに現代に当て込んでいるだけって知ると、今まで歴史に興味がなかったけど、昔の戦いがどんな戦略だったか?なぜ勝てたのか?逆になぜ負けたのか?分析するのも面白い。
ランチェスター戦略も第一次世界大戦で生まれた戦略を少しづつ時代に合わせて変化させただけ。
元々の理論は
「戦闘力=兵力の質✕量」という法則、戦いにおいて「戦闘力」はとても重要。
「戦闘力」を数学的に、定量的にアプローチすることをはじめて論じたのがランチェスターってこと。
簡単には、まずは数値で表現することで強者か?弱者か?を知ること。
わかりやすい基準は、戦闘力→資本力。
これが1番わかりやすい指標。
ただ、資本力だけが高いことがそのまま戦闘力が高いか?といえばそうではない。
重要なのは自分の戦闘力を知り、周りの戦闘力を数字で理解することは重要。
企業での数値はシャア率、売上額、
YouTuberであれば登録者数。
目安となる数値を持っているのとないのとでは戦略が大きく変わるけど、結構ここを知らずに戦うと成果が上がらない。
ビジネスにおいての基本戦略は大手と中小企業では全く違う戦略をとらなければいけない。

ランチェスター戦略では
強者→市場シェア26.1%以上の1位のみ
弱者→そうではない全プレイヤー
この戦略の大前提はほとんどの人が弱者という設定。
その前提で、
自分より強いライバルに勝つための方法の基本戦略は、強者と差別化を行い局地戦で戦うことで、差別化戦略すること。

逆に強者のポジションになったら、弱者と同じフィールドで戦うことになるから弱者から
ミート戦略(マネをする)が大切!
このランチェスター戦略を上手く使いこなしたのが松下幸之助。
創業当初は徹底的に差別化戦略で販売網を急速に広げるることで販売シェアを取った。
販売シェアをとったら、次に他社の作った製品を真似して類似の製品を作り、それを圧倒的な販売網の差を生かして売ることで、開発元メーカーのお株を奪った。
せっかく研究開発を重ねてオリジナルの製品を作っても、最大手である松下にすぐに真似されては、差別化できない。
強者になったら差別化を無効果させることでボジションを盤石にした。
その戦略は松下幸之助を皮肉を込めて
マネシタ電器と呼ばれる位有名だね。
市場ボジションによって戦略は使い分けていくというのが重要。
最近ではサムスンがまさにランチェスター戦略を実践した企業。
最初は技術力がないから、とにかく優秀な人材を高額報酬で引き抜き技術力を上げつつ、コストを大幅にさげ、さらにデザインを追加した。
技術+低価格+デザイン性で差別化を図りながら市場規模を拡大させ、今では日本の電器メーカーとは大きな差が出てしまった。
シェアをとってしまったら、後は守ることに専念する為に他社の技術をマネし、低価格でデザイン性を付け加えて販売することで、競合をなぎ倒していくと思う。
逆に失敗したケースは洋服の青山だね。
言わずと知れた、スーツ専門店で国内シェアNO.1企業。
ただ、スーツ市場全体が衰退していく中で焦って差別化戦略を打ち出したのが大きく業績を落とした。
去年の消費税増税後10月にこれまでの販売手法だった、『何点買ったら〇〇OFF』という自ら作ったロードサイドスーツ店の常識を壊した。
これまではOFFを前提に製品の価格を高く設定していたことをやめて、OFFしなくてもいいような値段に全品下げた。
これまで、OFFでお客さんを集客していた手法を捨てて、百貨店やファッションビルのようなOFFをしないで販売する方法を選んだ。
結果、大きく売上を落とす結果となった。
面白いのが競合他社の結果。
業界1位の洋服の青山が一律製品を安くしたことで、業界2 AOKIも同じように安くした。
業界3位のはるやまは何も変えなかった。
業界2位のAOKIも洋服の青山と同じく、一時70%台のの売上を落とす結果となった。
逆に何もしなかったはるやまは、洋服の青山、AOKIからお客さんが流れて100%以上の売上を出した。
現在はAOKIは元の販売手法でもあるOFF戦略に戻したことで70%台だった前年比は毎月上がり2月で109%となったが、この結果こそがランチェスター戦略の悪いパターンの象徴。


※青山商事 実績
新たな販売手法を導入してから回復傾向はない。

※はるやま商事実績
確実に業界1.2位からのお客さんがきて売上維持
何を見誤ったのか???
①スーツ業界がスーツ需要落ち込みで衰退産業となり、毎年度市場規模が縮小し焦った
②業界1位企業なのに差別化戦略を導入した
勿論差別化戦略は大切だけど、前提条件は市場規模で、衰退産業なのに大きな差別化戦略はそもそも不必要だったということ。
今、青山商事がやるべきことは単純に競合は資金力がなく弱ってくるから強者のメリットを活かして、他社からシェアを奪うことで耐えること。
その中で、市場規模に合わせて効率化を図ることで最低限の利益を確保することが優先だったのが完全に見誤った結果となった。
この例を見ると、強者は強者の戦略をし弱者は弱者の戦略が必要ってことが凄く理解できた。
市場規模が大きくなる産業であれば、市場規模にあわせ強者のマネをするようなこれまでのAOKIの戦略は通用したけど、市場規模が小さくなっている中で強者のマネは無駄でしかない。
ランチェスター戦略は、市場の規模成長度も考えて動かないといけないなぁと思った。
そう考えると、成長市場とは何か??
今の日本に成長市場はあるのか?
、、、ほぼないよね。
だったら今できることは、何かのマネをしてシェアをとりにいく戦略は弱者である中小企業はしてはいけない気がする。
何事にでもそうだけど、先発企業は利益が高く、後発企業になればなるほど利益は薄くなる。
今、大切なのはどんなに小さくても自分の得意とする分野で、さらに大手ができないこと、マネされないことで市場を作った方が安定すると思う。
それをする為には、勝てると思える土俵を作ること!!!から始まる。
勝てると思える土俵が見つからない場合は、遅かれ早かれ間違いなく潰れる。
小さいなら、小回りと柔軟性を持った勝てる土俵をまずは磨き、ニッチ産業でシェアを確保する方が今は正攻法かも知れないって凄く感じる。
大手のマネをして儲かる時代は終わった。
それが理解できないと、いつまで経ってもジリ貧だろうね。
一応、差別化戦略の5つの戦法
①局地戦 →領域と数を絞り込む
②一騎討ち →オンリー顧客を狙う
③接近戦 →直接販売で戦う
④一点突破 →勝てる土俵を貫く
⑤奇襲攻撃 →周りが予想できない方法
最低限、これだけわかっていたら戦える。
頑張ろう!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
