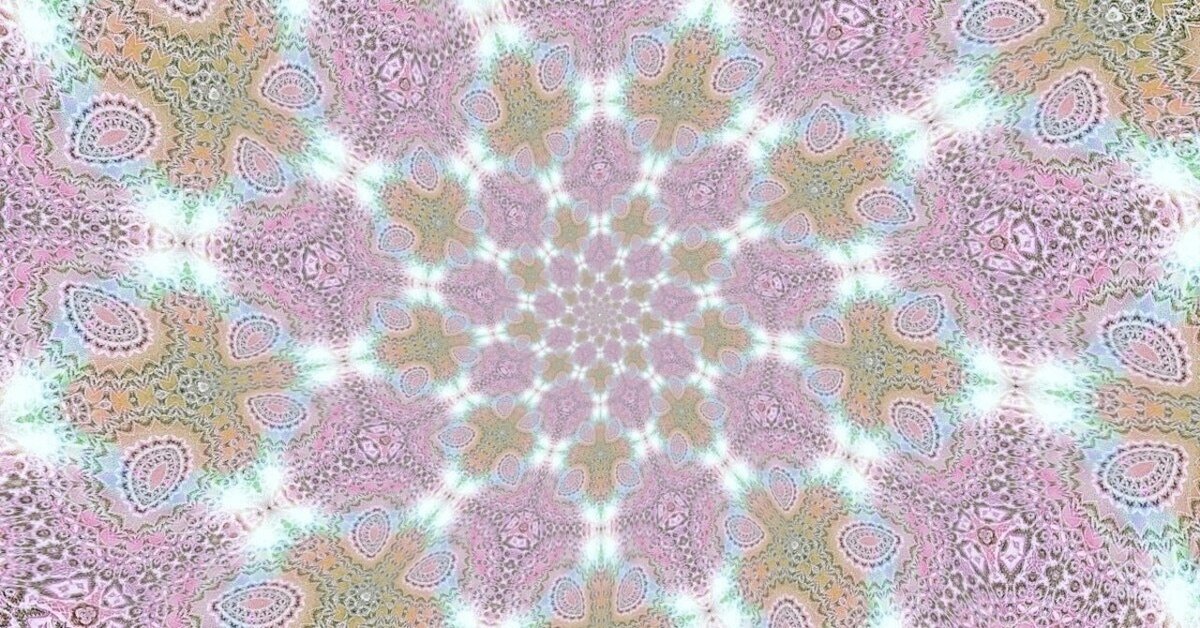
記憶の底に隠れていた愛に半世紀ぶりに出会った話
きちんとしたプロフィールを書くために、幼少期からの出来事をつらつら書き出していた。
3人姉妹の真ん中として生まれる。
おそらく随分とゴンベ(やんちゃ、わがまま)だったのだろう、3つ年上の姉にも結構イジメられた記憶がある。
このころの鮮明な記憶は、一枚の写真。
50年前なので当然白黒、
2、3歳ごろの私が、指しゃぶりをしながら下を向いて、カメラの方に向かってくるところの写真。その背景には、姉とその友人が険しい顔をして仁王立ちをしているところが写っている。
おそらく遊びの仲間に入れてもらえなくて、泣きながら家に帰る場面だったのだろう。
自分の幼少期はこのような寂しいイメージで固定されている。
3歳下の妹が生まれた後は、赤ちゃん返りをした私がそれまでに輪をかけて、手のかかる状態になり、その上生まれたばかりの妹にちょっかいを出す、ということを繰り返していたのだろう。(そこんとこ全く記憶にはございませんが)
正義感の強い姉にボコボコにいじめられ、「〇〇なんかいなかったらいいのに!」などと普通に罵られていた(これは覚えている)。
当時の親世代といえば、我が子に平気で「お前はうちの子やない、橋の下から拾ってきたんや」と言い放っていた。それが子供心に傷をつける、ということも知らなかったんだろうなあ。
私はずうっと親から「厄介者」扱いを受けていて、愛情をかけられた覚えもなく物心ついてから抱きしめられた記憶もない。
同居していた祖母と母の折り合いが悪かったので、家の雰囲気はいつもギスギスしていて家が心休まるあったかい場所だと思ったことはなかった。
こんなふうに書き出している時、ふと思い出したことがあった。
とても衝撃的で、悲劇的で、鮮明に覚えている出来事。
なんで忘れてたんだろう?
妹がまだ1歳の時。私はその時4歳。
私が誤ってやかんの熱湯を妹の上にぶちまける、という事故が起きた。
その時の様子はこうだ。
ちゃぶ台の対角に妹が寝かされていた。食事時だ。料理が机いっぱいに並んでいるので、私が自分のスペースを広げようと目の前のお盆を少しどかしたら、お盆に連なるお皿が次々と押されて、机の反対の端、つまり妹側の端に置かれていたやかんが押し出されてしまった。
やかんには熱湯が入っていた。
その熱湯を、妹はかぶった。
火がついたように泣き出す妹。
半狂乱になる母。
固まって動けない私。
その時は、何がどうなったのかわかっていなかったが、自分のやったことで妹が熱湯をかぶったことはわかった。
事の重大さに、どうしたらいいのかわからなくて、ただただ「ごめん、ごめん」と連呼しながら泣いていた気がする。
妹は、左腕全体にひどい火傷を負った。
入院し、太ももから皮膚をとって、左腕に移植する手術をした。
命に別状はなかったが、妹は「ケロイド体質」という事で、火傷のあとは溶けてただれた状態のまま残り、移植用の皮膚をとった太ももも盛り上がりただれた傷痕になって残った。
何度かの移植や形成手術の後、ケロイド状の火傷のあとは、ようやく一本の縫い跡を残して消えた。
妹はもう高校生になっていた。
妹の痛々しい火傷のあとと何年にもわたる治療は、私にずっとその時の様子を思い出させたけど
事故の後、私は誰にも責められなかった。
母は、事故の時半狂乱になりながらも、「ごめん、ごめん」と繰り返す私に向かって「あんたのせいやない、あんたのせいやないで!」と言い続けていた。
母は母で、なぜやかんをあんなところに置いたのかと、とことん自分を責めていたから、その責めの一端でも子どもに負わすことはできなかったと思うけど
そのおかげで、その事故が私の大きな心の傷にならずにすんだのだと、書きながら気づいた。
私を罪の意識から守ってくれたんだな、と思う。
素直に気持ちを表現したり人を褒めたり認めたりするのが苦手で、いつも嫌味なことばっかり言う人だったから、
今まで母から「愛されている」と言う実感は全然なかったけど
この時は、確かに守られていた。
守られていなかったら今頃どうなっていたかと思うと、ゾッとする。
おそらく妹の火傷の痕を見るたび、罪悪感にさいなまれて、心に深い傷を負ったまま大人になっていたことだろう。
そうはならなかった。(少なくともこの件に関しては)
愛されていたんだね、私。
その愛情のおかげで、私はその事故の記憶を、脳の底の方へ自然に沈めていくことができた。他のなんでもない記憶と同じように。
守られていた、愛されていた、と言う実感も記憶とともに沈んでいったと言うわけだ。愛されていた故に。
プロフィールを書き始めるまで、すっかり忘れていた出来事だった。
思い出せてよかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
