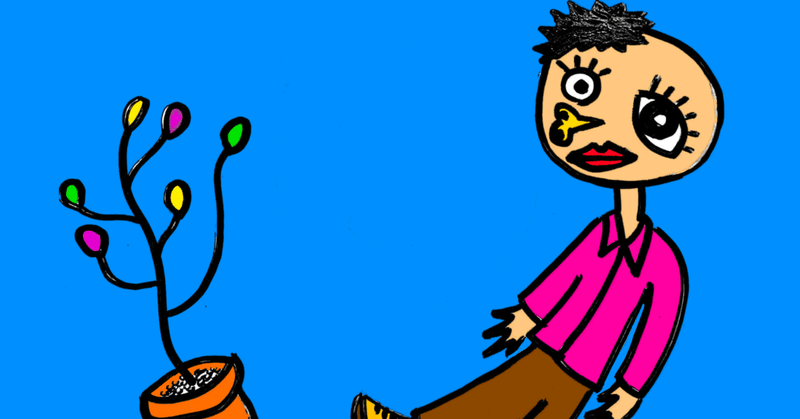
臨床心理士による放課後等デイサービスへのコンサルテーション6
事例
【対象児】
小学校2年生の男児。
ASDとADHDの診断あり。
コンサータ服用中。
【事業所が困っている対象児の行動】
①奇声をあげたり、大声を出す
②失敗すると落ち込んでしまい、一旦落ち込んでしまうと気持ちの切り替えが難しい
【上記の行動に対するスタッフの対応】
①声のものさし(声の大きさを視覚的に示したもの)を使い、今の本人の声の大きさと、適切な声の大きさを伝えている。
②一人にする時間を与え、クールダウンの時間を作っている。タイミングを見て職員が声をかけ、話を聞くようにしている。
#1~#2「枠組みの共有」
コンサルタントとして事業所に入ると、「私たちが抱える問題に対する答えを教えてください」というスタンスで待ち受けられることが多い。
過去にはコンサルティの求めに素直に応じ、筆者が問題を見立て、問題の答え(支援方法)を考え、スタッフに答えを伝えるという手法をとることもあった。
ただ、前回書いたように、それでは専門家への依存とスタッフの自信の低下を引き起こしてしまう。
そこで、コンサルテーションに入る前に、「問題の答え」を教えるというスタンスではなく、「問題解決のための話し合いの方法」を教えるというスタンスで関わりたいということを事前に説明した。
それでも最初はイメージが湧きづらいためか、「答えを教えてください」というスタンスはなかなか崩れない。
筆者としても、答えを教える方が手っ取り早いため「教えたい」という欲が湧いてくるのを感じていた。
その欲に負けずに、「教えてください」と「教えたい」の間にただ存在するということを意識していた。
次回に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
