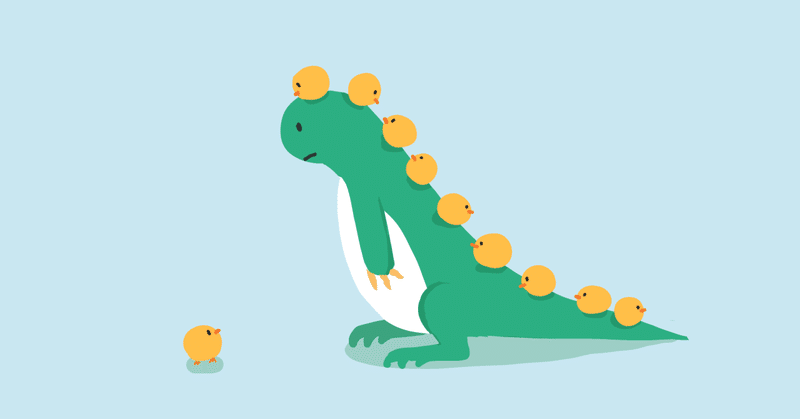
作家、朝井リョウ氏のことばから
本日は、平成生まれの気鋭の小説家、朝井リョウ(1989/5/31-)氏のインタビュー記事(NHK「素晴らしき“多様性”時代の影にある地獄」2019)の内容を読んで思ったことを記録に残します。
平成生まれの小説家の旗手
朝井リョウ氏は、2009年早稲田大学在学中に『桐島、部活やめるってよ』で華々しくデビューを飾りました。2013年には映画化もされた『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、2021年には『正欲』で柴田錬三郎賞、と数々の賞を受賞している売れっ子作家です。私は、小説としては『何者』しか読んでいませんが、次々と話題作を発表しており、注目している作家の一人です。
インタビューの中で、その時代の空気を象徴する時代の文献的に作品が読まれる小説家がおり、かつての田中康夫氏や綿矢りさ氏のように、自分もその席に座った一人なのだという認識をしています。鋭い自己分析だと思います。
内側から腐っていく痛み
記事の内容にはどれも共感する部分が多かったのですが、
● 他者や社会から評価されて烙印を押される辛さ=外から火傷を負わされるような痛み
● 多様性礼賛の世界の中に異ながら自分を誰かと勝手に比べて、自分で自分の意義や価値をジャッジし続ける辛さ=内側から腐っていく痛み
という捉え方は、見事だなと感じました。
世界から順位をつけられる苦しみを手放す代わりに、自分で自分を見つけられない終わりのない旅の始まり
という似た表現もしています。自問自答し続けて行き詰った先には、精神的自滅、更には社会や他者への攻撃となって暴発する危うさが潜んでいるという分析には共感します。
多様性ということばは、時代のキーワードとして好意的に多用されてきましたが、最近になってその負の側面を指摘する論考もチラホラ見るようになってきました。多様性を推し進めることによって副次的に現れてくる生き辛さも覚悟しながら、生きていかねばなりません。
言葉にできないものを自覚する
更に朝井氏のことばの中で共感したのは、言葉の限界を語る部分です。事象や感情に、特定の言葉を当てはめることで、確実に芳醇なエッセンスの幾つかを削り落とし、別物へと変質させている訳です。どうしても伝えきれない部分が残り、逆に誤解を生むことも少なくありません。
ことばを紡ぐ一流の小説家でも、正確に伝えきれないもどかしさに苦悶するのかと思いきや、「言葉に収めきれないとわかってからは、逆に気楽になった」というのが面白い感覚だと思いました。精一杯考え抜いたことばを置ければ、その努力は伝わる、という考えに変化してきたというくだりは興味深かったです。
サポートして頂けると大変励みになります。自分の綴る文章が少しでも読んでいただける方の日々の潤いになれば嬉しいです。
