
道具と装置(人間について)[CCBT meetup #2]
藤幡正樹先生がCCBTで行う連続meetup #2(2024年6月16日)にオブザーバーとして参加させていただいた。連続meetupには受講生のみが受講できるのであるが、なんと200名の応募があったそうだ。80年代からメディアアーティストとして活動し、最近では香港での展示やUCLAの州立招聘教授を務めるなど"世界"のアートやテクノロジーを中心とした文化形成の中心にいる先生から学べると言うことで先鋭50名ほどが選抜され2024年度末まで授業を受けるという。
私はオブザーバーとして参加している人間として、記録できる範囲記録していこうと思う。そして、この note が藤幡正樹先生の授業の内容を知りたい一般の方々はもちろん授業を受けている方々にも今後の振り返りの参考になればと考えている。
<藤幡正樹CCBT meet up項目>
・第1回:アートとテクノロジー
・第2回:道具と装置(人間について)
・第3回:猛烈最短美術史(絵画史)
・第4回:鑑賞と関与(見ること)
・第5回:コンセプションとメディウム(孕むこと)
・第6回:生命と機械(知ること)
・第7回:作品と表現(価値について)さて、本日お届けするのは、第2回目は「道具と装置(人間について)」である。
早速授業の冒頭で「道具とは?」と問いかける藤幡正樹先生に
数名が挙手しながら道具とは?への考えを述べる。「身体の代わりになるもの」「作る←使うもの」「身体の記憶とか記録を外部化する」「人間の手でやりづらい作業を補うもの」・・・いくつか出てきた上で、今度はみんなにmiroに書き出してもらう。
総勢100名ほどが道具と考えるものを一気に書き出していく。全部で500
ほどあげられただろうか?
膨大な量の「道具」が書き出されていく。なぜこれを書き出しているのだろうか?それは「カテゴライズ」する訓練のための題材であると言うのだ。次回の講義では「カテゴライズ」したものを発表するのだ。
ギリシアの哲学の時代から身の回りの道具をどのようにカテゴライズするか?というのを人間は永遠と続けてきている、その哲学的でもあり、人々と議論をするためのフレーミングの材料をみんなでまずは集めていくのだ、とmiroにみんなが書き出しているものを見ながら藤幡正樹先生は語る。
道具とは?
さて、ある程度miroの作業が落ち着いたところでスライドに移る。
「道具とは(1)」 何か?

私が興味深く聞いていたのは、「人間というのは道具と共に生まれてきたものだ」というアンドレ・ルロワ=グーランの説である。
おや?これは私が小学校の教科書で並んだ「人間(もしくは我々の祖先の猿)が道具を作った」という説と違う。We, 私たち、人間が道具を作り文明を作ってきたと思っていたのだが、アンドレ・ルロワ=グーランの説をみると私たちの文化は道具と共に生まれてきていそうである。
つまり上記の「道具とは(1)」はあまりにも人間中心的な考え方なのである。
藤幡正樹先生は、私たちが今まで学んできた考え(既成概念)のままでいくと、先ほどmiroで書き出した道具のカテゴライズをする時にも人間中心になってしまう危険性を示す。
また、気にすべきことはアンドレ・ルロワ=グーランのカテゴリーや、藤幡正樹先生のカテゴリーだけが唯一ではないことも疑っていくべきものである。まだ発見されてない道具のカテゴライズがあるのかもしれない。そのような取りこぼしている埋もれてきるカテゴライズ(世の中のフレーミング)を探していくのもこのCCBTの授業の方針である。これは「道具」だけではなく、自分の感情や、身の回りの関係性なども見直してみると新たなカテゴライズができてきそうな新たなリフレーミングの視点である。

言葉の違い、恣意的な違い
「石竹色(せきちくいろ)」という色がある。石竹の花の淡い少し青みも感じる色を指すのだが英語名では「Pink」となってしまう。この複雑な色味も言語が変わると「Pink」と単純化されてしまう。ある文化圏が持つ概念は他言語に翻訳されるときに単純化されてしまう危険性がある。このような単純化は、言語の翻訳はもちろん、カテゴライズを行う際にも発生すると藤幡正樹先生は続ける。

確かにそうだ。ちょうどお昼にフランス人と会話している時に、私が無意識に「部屋」と言っているものに対してもフランス語ではChambre(シャンブル=ベッドルーム)というか Salle (サル=部屋)、Salon(サロン=リビングルーム)という違いがあることを学んだ。もちろん私たちにも居間や寝室など言い方あるが私のざっくりいう「部屋」に対してフランスの友人は明確な差別を示してくれる。
さて、私の個人的な感想をぼんやりと思い起こしている中で、新たな"道具"が紹介される。
村本剛毅氏が手掛けるMedia of Langue だ。これは検索キーワードに入れる言葉を軸に関連する言葉をビジュアルで関連性を示してくれるものだ。今日のテーマである「道具」については以下のような感じでてくる。

さて、藤幡正樹氏はなぜこのMedia of Langueを持ち出したのだろう。それは、語義の広がりを理解する(感じる)ための道具として有効だからだ。
(外来語が日本語に翻訳された時に、偏った翻訳がなされてそのままになっている危険性を探るためのものとしても有効そうである)

Media of Langueを開発した村本剛毅氏は翻訳という行為が「連想ゲーム」ではなく「伝言ゲーム」である危険性も伝える。"間違った"翻訳のあり方に危険性に感じつつも曖昧なままで有耶無耶になってしまうものも、このMedia of Langueを使うと言葉の関連性、そしてそのラベルのされ方で違和感を感じるものを気づくためにも大事なツールであることが見えてくる。
ここで藤幡正樹氏が受講生に「せめて英語、できれば中国語も学んでほしい」と伝える。外国語を学ぶことにより間違った翻訳に気づくことができるというのだ。言葉をあるがままに受け止めるのではなく、疑い、アップデートしていく意識を芽生えさせる必要があるというのだ。
※このMedia of Langueのアップデートにもコラボレーターとして参加することも「今ある言葉に違和感を感じる」ためにも大事だろう。
※このMedia of Langueプロジェクトには欧州やアジアの方が多く協力していてるが日本人の参加者が少ないという。日本人は与えられた言葉に甘んじすぎているかもしれないことをこの場でも気付かされる。
「道具」を掘り下げる:InstrumentとEquipmentの違い
Instrument と Equipment をGoogle翻訳で翻訳してみよう。計器と機器。だ。なんとなく同じようなものに受け取れる。

ただ、Media of Langueで見てみるとInstrument と Equipmentは距離があることがわかる。

Instrument : music instrument 楽器。音を出しながら身体で感じる。
Equipment : 人間が存在しなくても機能を果たす。
藤幡正樹先生としてはアート作品を作る上ではEquipmentを作るのではなく、Instrumentを作ることが身体との関わりを感じるものとして目指したいものであるというのだ。私たちは安直に「道具」「装置」「デバイス」と何かしらの道具や装置を指してしまうのだが、実はその「言葉の選択」を丁寧に考えるだけでも作品として伝えられるものが変わるのだ。

さて、スライドを使っての説明が続く。聞きなれない言葉としては Apparatus (アパラタス)も、ある。ApparatusでGoogle検索すると以下のようなイメージ検索に出会えた。「特定の目的のための複雑な器具や機構」がApparatusアパラタス、だ。
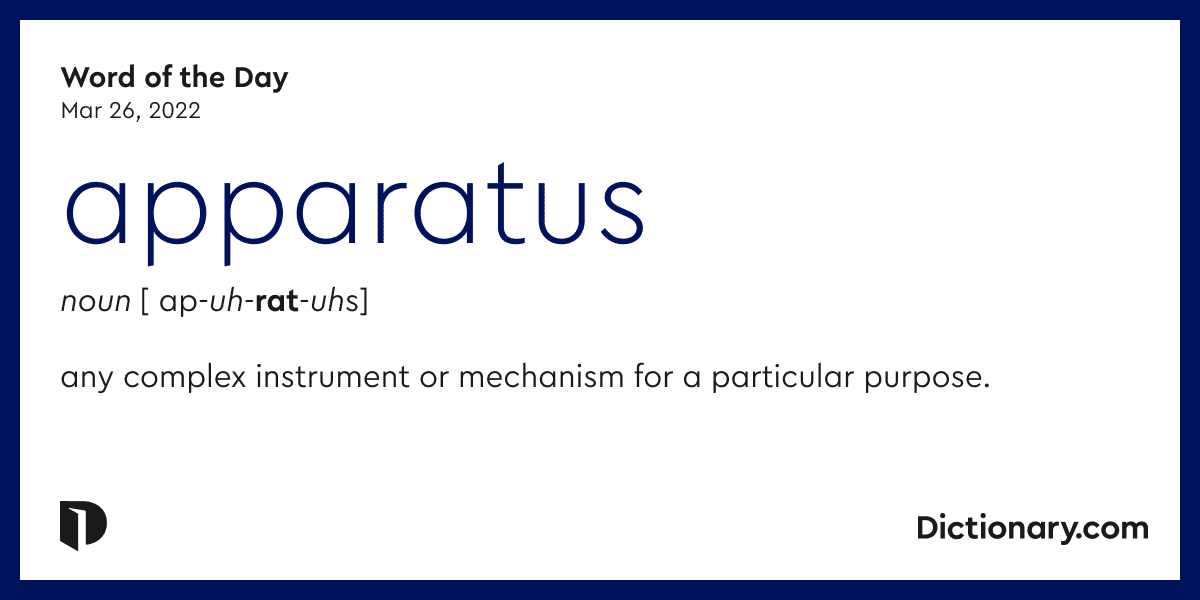
藤幡正樹先生はこのApparatusを紹介する際に、フランス語のAppareil(アパレイユ)についても言及する。フランス語カメラではappareil de photoアパレイユ・ドゥ・フォトという、写真の器具、だ。明確に器具であることを表している。
ちなみにフランス料理でケーキの生地(固まる前の流動的なもの)もアパレイユ(appareil )という。「写真の生地」としてのカメラというニュアンスもあるのだろうか?かつて写真を現像する際には液体(酢酸など)につけて現像したことを思い出すと、なかなかフランス語のカメラを指すappareil de photoアパレイユ・ドゥ・フォトは奥深いものがある。
ハイデガー「芸術作品の根源」
余談ではあるが藤幡先生と話をする際に、よくハイデガーが引用される。藤幡先生が問題視する「アートの文脈では西洋第一主義となっている」、その西洋アートの土台を担うのが哲学であり、その哲学者の一人がハイデガーであるというのだ。
ちなみに私は最近サザビーズのアートヒストリーを学んだのだが、そこではフーコーやニーチェが出てくる。哲学はアートを学ぶ上では切り離せないことを改めて認識する。
さて、藤幡先生のハイデガーの引用は以下のスライドから始まる。


さて、今日の講義は「道具」を中心に進めているが、ハイデガーによると
道具は透明で見えない、という。どういうことか?
藤幡正樹先生はここでハイデガーの「芸術作品の根源」で使われてい
るゴッホの「農夫の靴」をサンプルに持ってくる。
ハイデガーは道具をメインに描いた絵として、ゴッホの「農夫の靴」を扱う。農夫の人についてこの靴は見えない道具であるというのだ。確かに、農夫にとっては日々使う道具である靴をいちいち意識をしていない、当たり前のもの、透明な存在になる、ということが道具だというのだ。

さて、鑑賞者である私たちはこの「農夫の靴」を見た時に意味を探してしまう。その意味性よりも、藤幡先生はこの絵が描かれた背景を想像するのも大事であると語る。
ゴッホは誰からこの靴を借りたのか?
この靴の持ち主に対してどのような説得をしたのか?
この靴の持ち主は、ゴッホが絵を描いている間に農作業を休んでいたのか?どうなのか?
考えてほしい。農夫にとって大切な道具である靴を借りてくるにはなかなかの説得が必要になるだろう。そのことを想像するのも面白し、そのような背景を考えることも意味があるというのだ。
ハイデガーによる「世界」

ハイデガーについての七沢智樹さんの文章の中で「世界」というキーワードがボールドとして強調されている。藤幡先生曰く、ハイデガーの中では「世界」と「大地」が大切なキーワードであるというのだ。
「大地」とは無自覚な存在であるのに対して、
自覚するものが「世界」というのだ。
自覚があって「世界」が立ち上がってくる。
この「世界」の立ち上がりには、ヨーゼフ・ボイスの例も挙げられる。蜜蝋をギャラリーに持ち込んだことによって初めて「蜜蝋」が意味を持つ。蜜蝋がアートの世界に存在することを指し示したのがヨーゼフ・ボイスであり、指し示すためにはギャラリーの存在もとても大事である(ギャラリーに蜜蝋を持ち込むことにより、「蜜蝋」が作品として意味を持つようになる)。
さて、このギャラリーという作品が安心して存在を明かす場所の中でも壁の存在を認識することも、アートの世界の土台となっている西洋アートの文脈を理解するためには大事である。「壁の存在、その不動な対象があって、初めて、ヨーゼフ・ボイスの蜜蝋にも意味が出てくる。蜜蝋が畳におかれていても、やはり意味不明になるだろう」と藤幡正樹先生は語る。
これまた私が最近学んでいるアートヒストリーからの視点であるが、西洋アートのギャラリーの前身には「Cabinets of Curiosity」というのもある。自分たちが初めて目にした生物や絵画を一様に集めている博物館の原型のようなものである。その頃から西洋では部屋を区切ってそこに展示をするという流れがある。私たちの障子や御簾などの風通しの良い文化と「壁に飾る」「壁に区切って飾る」という文化の差異があることを意識して、この「風通しの良い空間での作品を愛でる価値」を世界に伝えていくことも大事ではないか、と考える。
ポエムについて
言葉についての本来の意味を知る上では、藤幡正樹先生が「ポエム」をピックアップしたのもとても面白い。ポエムの語源は「ポエーシス」、隠れている何かを発芽させるもの、というのだ。つまり、詩人はゼロイチの創造者ではない。隠れている何かを見つけて発芽させるものだ。農業の原点はポエーシスである。詩人は自分の中にあり気が付かなかったものに気づき、水をやり、芽を出させるものだ。
さて、ここまでが前半戦だ。藤幡正樹先生がハイデガーを今回ピックアップしたのは、ヨーロッパ文化が構造化されていることを理解してもらいたいからだ、という。私たちが「適当に」言葉を選び、使っていることに対して疑いを持ち、厳密な意味を考えていくべきなのだ。また、私たちの「通じるだろう」という甘い考えで臨むと「伝わるだろう」という甘い考えで作品を作り展示してしまうと、構造化された、哲学を基礎に、長年のアートヒストリーを踏まえた西洋アートの前では、日本のアートは立ち行かないというのだ。
言葉を多言語を学んだ上で比較し、
選んだ言葉が歴史や哲学的にどのように使われているのか?
意識して作品を、日本を伝えていくべきというのだ。
さて、ここで今日の私の時間はtime up! してしまうので、また別途誰かが作るアーカイブにマージしながらここから生まれるであろう「ポエーシス」の芽を育てていきたいと考える。非常に乱雑ではあるが、先生の授業のエッセンスが少しでも伝われば幸いであり、誰かの note とのマージも今後起きてくるかもしれない。このアーカイブの行く末も楽しみである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
