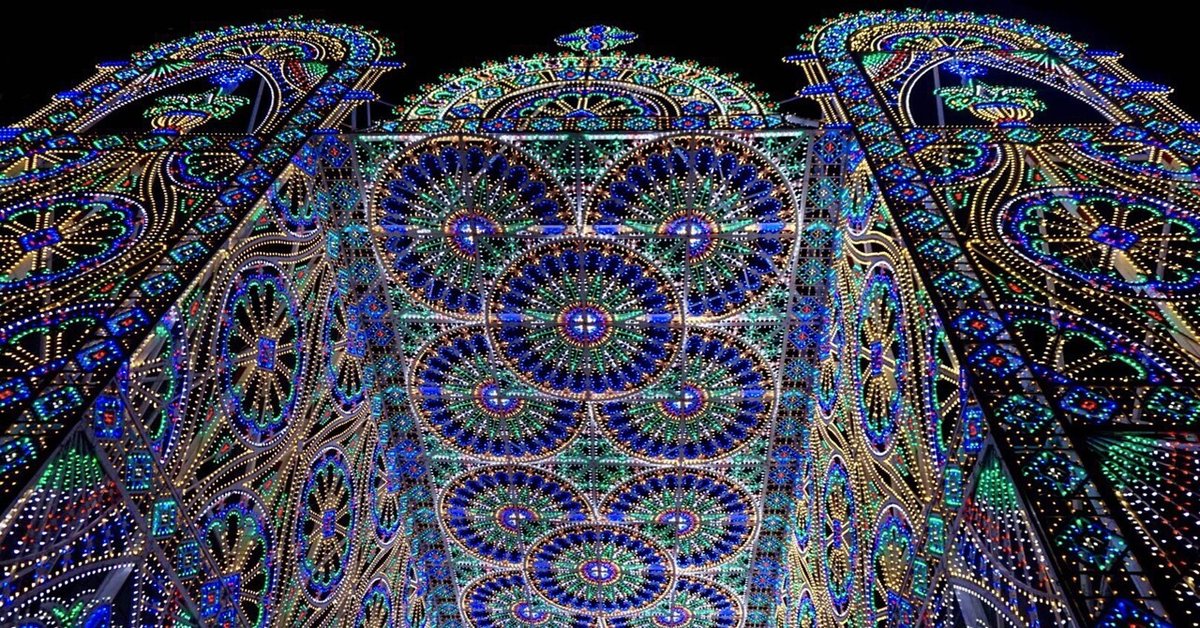
1.17
夜中にそぼ降った小雨が風に倒れた看板の上で氷結している。
山から降りてくる身を切るような風。
どんな暖冬でも、なぜかこの日だけは必ずといっていいほど特別に寒い。
山手から街に降りる真冬の坂道、ひったくりも眠りについているようなこの時間帯には新聞配達のバイクのほか、自分以外の人影はまったく見あたらなかったが、次の交差点で2人増え、次の大きな道で5人増え、まるで細胞に行き渡った赤血球が心臓に戻っていくように無言で早足の人の数は増え、市役所前でそれは大静脈となる。
記憶は風化しているというが、なぜか毎年のように雨後のぬかるみにようになる足元の悪い公園では、集まる人の数が減っているような感じはしない。
近しい知人や家族には犠牲者は出なかったが、この街に生まれ育って住んでいる者として1月17日は時を経てもやはりきわめて特別な日である。
それは名前も顔を知らない 6500 人の犠牲者に対する哀悼の気持ちばかりではなく、あのときの「偉大なる市民」であった神戸の人々を忘れずにいたいという思いがあるからだと思う。
たいして顔も知らなかった近所の人たちが一丸となって倒壊した家の瓦礫をかきわけ下敷きになっている人を助け出し、通りがかりの車がその人たちを病院に運んだ。
1キロほど歩いてやっと開いているコンビニがあった。停電のためレジは使えず、店員は電卓で計算している。その前には整然と並んだ市民の姿があった。暴動や火事場泥棒どころか、誰ひとりとして文句を言う者もなく、ただ黙して並び、水を2本手にした人は、からっぽになった商品棚の前でため息をつく別の客に1本を渡した。(あのような未曾有の大災害であったにもかかわらず暴動のひとつも起こらなかった民度の高さを、海外のメディアが高く評価していたという。)
空には無数のヘリコプターが飛び交っているが、救援物資を運ぶものではなくすべてが野次馬メディアだった。次の日かろうじて停電を免れた場所で見たテレビでは、生田新道に立った地元のレポーターが涙声でレポートをしていた。東京のキーステーションでは、アンカーのアナウンサーが「この地震が東京で起きなくてよかった」と言っていた。
その頃、米第7艦隊が紀伊半島沖を航行中で、日本政府に空からの救援を含めた米軍による救護を打診していた。またスイス、ドイツ、スカンジナビア諸国や、アジア諸国をはじめとした世界各国が災害救助犬を伴った救助隊の派遣準備を進めていた。
昼近くにもなってやっとのことで県知事が自衛隊の出動を要請。日が暮れ、風が強くなり火災がどんどんと広がっていく中、政府は情報不足、受け入れ態勢不備という理由にもならない理由を重ねて、海外からのすべての救助オファーを断り続けた。(後にそのときを振り返った当時の村山富市首相は「なにしろ初めての経験だったもので」・・・・)
災害発生当日せめて二日目までに海外を含めた専門のレスキュー隊が投入されていたら救われた命は10や20の単位ではなかったと思うととても悔しい。
18年を経ても、そして20年、50年経っても、生き残った神戸の人々は大きな悲しみを心のどこかに宿して生きていくだろうが、また同時に、あのときに化けの顔を剥いだ東京政府に対する恨みも決して忘れることはないだろう。
今日はどこにチャンネルを合わせてもニュースは1.17のことばかりで、何度も何度も何度も目頭を熱くしてしまう。
震災に関する気持ちの整理はまだついていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
