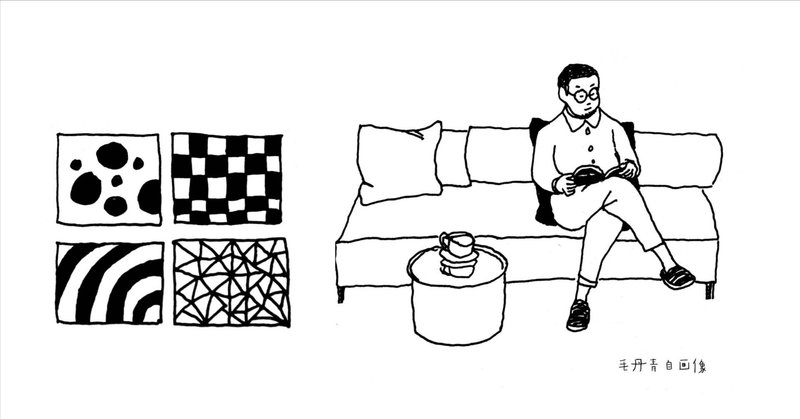
亡き母に捧げる
四年ぶりに北京に戻ると、心にはたくさんの思いをめぐらせていた。街の変化は大きかったが、個々の記憶は時折、世間の激変を凌駕しながらも、小さな永遠となる。母はパンデミック初期の頃、北京市内で亡くなった。国際線運航便が一時運休していたため、最期のお別れをすることもできなかった。ぼくにとって、心を切り裂くような一生の痛みになった。
母は歴史学者で、明の歴史や社会文化史を専攻し、幅広い読書と多くの蔵書を持っていた。ぼくが子供のころ歴史の物語をよく語ってくれた。ただ、自分は学者二世というか、感情的にしばしば、逆のものになり、まるで「他力本願のことを知らない」といったような感じだった。
日本に移住して約40年になる。最初は留学のためだった。母はぼくを強く支持し、手紙もよく送ってくれた。後に、生計を立てるために大学から中退し、大学院進学への計画を断念し、魚屋で働きはじめた。これで母と激しい口論になった。若者が学問をするのであれば、根気よく努力し、左右に揺れてはいけないと考えていた母、ぼくとは意見が全くあわなかった。人は一生懸命であれば、何をしても価値があるというものだから、ぼくにとって、魚を売る喜びと本を書く喜びは同じで、両者はなんら違いもない。母はぼくのことを「いい学者二世ではないね」と評した。
魚の商売は急成長し、遠洋漁業の貿易にまで発展した。ニュージーランド駐在の時代に、漁港の近くに小さな哲学専門書店を見つけた。毎日、船凍魚の入荷や検品などを終えてから、いつもその店でくつろぎの時間を過ごし、コーヒーを飲みながら好きな哲学書を熱心に読み込んでいた。母に手紙を書いて国際郵便で送ったところ、その返信で「いいかどうかは別にして、学者二世だね」と書いてくれた。実際のところ、この言葉は常にぼくを励ましてくれている。
その後、自分の経験を日本語で書くことを決意し、非母国語である日本語で挑戦した。しかし奇妙なことに、はじめての著書には魚の取引の場面はいっさいなく、その代わりに1年間にわたる日本各地への取材の記録だけをまとめて綴っていた。これを知ると母はぼくのことを「やっぱり学者二世だね」と手紙で書いた。同じ頃、ぼくは神戸で文学賞を受賞した。「日本語のことは、もう君に任せるから」と言い放った母はとても可愛かった。

日本語作家としてデビューした後、母とは、文章を書くための使用言語が異なっているため、文体や表現についての交流が次第になくなった。それでもぼくは母が新聞や雑誌に寄稿した文章をよく読んでいた。その筆致の力強さには透明感ですら感じたこともある。その後、ぼくは日本の大学で教鞭をとるようになり、「日本文化論」を日本人学生に教えはじめた。これでやっと学界に戻ることができたから、若い頃の努力が報われたと感じた。
今回北京に滞在する際、学者の仲間たちや友人、そして学生諸君からの助けもあって、母の蔵書をすべて太原師範学院に寄付した。また、母の遺品を整理していると、多くの手紙を発見した。母とぼくの手紙だけでなく、著名な学者との通信もあった。たとえば、胡縄(元中国社会科学院院長)氏との通信もそうだった。最初は、母が受け取った手紙ばかりなのかと思ったが、驚いたことに母が自分で書いた手紙を複写用紙に残した。以前から何度も聞いてきた母の言葉を思い出す。「歴史は記録だ。記録以外にも記録だ。ほかに何もないね」
手紙のやり取りには複数の著名な学者とのものが含まれているから、今になって活字化した化石のようにたいへん貴重だ。このほかにも母の遺品から、ぼくの知らなかった過去がたくさん見つかった。古い手紙から祖父母や大家族の姿が時折浮かび上がり、夢にまで現れたこともある。
時間が重い鎖をひきずるようにして通過している。父と母、そしてぼくの最愛のいとこも今、北京西山のふもとで眠っている。ぼくにとって、北京はみんなとのつながりを持つ永遠の地だ。母は、大家族の頼れる大黒柱だった。
春休み終了、大学も始まった。日本に戻る飛行機の窓から白い雲を眺めながら、歳月の流れを感じた。そして母はいつもぼくのそばにいるような気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
