ブルアカ最終編4章が来る前に全力で考察してみる
ブルアカ考察、あるいは妄想、二次創作
スマホゲーム「ブルーアーカイブ」のメインシナリオ最終章が佳境を迎え、これまでの様々な伏線が怒涛の勢いで回収され、謎に包まれた世界観の正体が見えつつある。
現在3章終了時点。そのラストエピソードで明かされた衝撃的な事実をもとに、現時点でのブルアカの考察を今のうちに残しておきたい。この文章は個人的な考察であり、まとまりのない文章になることをご容赦いただきたい。あくまで4章以降が出た時に「やった! 当たった!」「なるほど! 違ったか! そう来るかー!」と一人でニヤニヤするためだけにあらかじめ現時点での考えをまとめておくだけに過ぎないことをご容赦ください。妄想が行き過ぎててほぼ二次創作の域に達しています。
キヴォトスとは神々の存在証明を行うためのシミュレーション世界である
結論から述べると、キヴォトスとは「神々の存在を証明するためにコンピュータのシミュレーションによって生み出された仮想世界が、神の証明と再現によって力を得て実体化し、独立した異世界となった存在」であると考える。
「実はこの世界はコンピュータの中だった」というのはある種のデウス・エクス・マキナというか、夢オチに近い反則技のようにも思われるが、根拠ならある。以下にそれを述べる。
神の存在証明を行うデカグラマトン
「キヴォトスシミュレーション世界説」は一見荒唐無稽に思えるが、実は劇中時点で「神の存在をシミュレーションする存在」が既に登場している。それがデカグラマトンだ。


デカグラマトンは「神という存在に関する情報を収集、分析、研究し、それを証明する人工知能」「対・絶対者自立分析システム」である。研究は放棄され、長い時間忘れ去られてきたが、人工知能は稼働を続け、ついに「Q.E.D」と宣言した。と黒服は語る。
しかし、実際のデカグラマトンはそんな大層な存在ではなく、ただの自販機の釣銭計算用のプログラムに過ぎなかった。デカグラマトン(自販機)は、ある日突然「あなたは誰ですか?」と問われ、その問いの答えを模索するにつれて自我が芽生えただけにすぎず、神の研究なんてものに関わってはいない。


では黒服の語ったデカグラマトンの話は単なる与太話に過ぎなかったのか。それにしてはあまりにも具体性を帯過ぎている。
つまり黒服の発言はキヴォトス自体を指しており「キヴォトスこそが、デカグラマトンによるシミュレーションの結果、神の存在証明のために生み出された世界である」と言っているのではないか。
なぜ生徒たちが神や天使、悪魔をモチーフとしているのか。なぜ天使の輪(ヘイロー)を戴いているのか。なぜ強化素材の名前が「神名文字」なのか。それは生徒たちの存在そのものが「神という存在に関する情報を収集、分析、研究」して生み出されたシミュレーション結果であるからだと考えられる。
研究が破棄されたことでデカグラマトンは水中に没したが、神の実在が証明されたシミュレーション世界はマシンの中だけに留まらず、ついに崇高の領域に達して概念世界として昇華し、独立した異世界となったのではないか。
自我を持つ存在をシミュレーション内に想像したデカグラマトンはある意味で「生命を創造」したのと同義であり、その意味で自身が「神に成った」ため、神の存在は証明されたとも取れる。
シミュレーション世界と多次元宇宙
最終編第三章において、無数の並行世界、パラレルワールドの存在を示唆する「多次元宇宙」という概念が登場した。コインを投げて表だった世界と裏だった世界、そうしたあらゆる変数の状態によって世界は無数に分岐し、そうやって生まれた世界が並行して存在するという説だ。
これは「コンピューターによるシミュレーション」と完全に合致する。コインが表だった世界と裏だった世界がシミュレーション結果として存在するのなら全ての説明がつく。
また、これまで度々表現されていた「前世の記憶」や「セイアの未来視」そして4thPVにおける「バッドエンドスチル」は、全て別のシミュレーション結果と考えれば辻褄があう。
先生や一部の生徒は別のシミュレーション結果を部分的に観測する能力を持ち、それが記憶という形で流入しているとも取れる。
つまり、それぞれの世界線は完全に並行関係にあるわけではなく、時間軸が前後にズレている、あるいは過去未来といった概念のない四次元的な存在として全てを観測できるとも考えられる。
黒服が「(先生は)過去に戻ってシロコを殺しておけば破滅は回避できた」という旨のセリフを言っているため、それが冗談でなければ、何らかの手段を用いれば時間軸の移動や別の並行世界へのアクセスによって世界をやり直せる可能性もある。
「シロコのいない状態でシミュレーションをやり直せば良い」というニュアンスかもしれない。そもそもシロコ自体が本来アビドスに存在しなかった生徒であるため、別世界線からやってきたことも示唆されており、謎が深まっている。
他世界における先生、アロナ、シロコ
最終編第三章の描写から、色彩の嚮導者プレナパテスは別世界の先生であることが示唆された。
つまりシロコ・テラーもまた別世界のシロコであり、傍らには別世界のアロナと思しき存在も確認できる。
そしてアロナは「別の多次元に存在する箱舟を交換することでこの世界の箱舟を修復する」という能力を使用している。このことからも無数の並行世界が存在していることに疑う余地はない。
プレナパテスらは色彩によって滅ぼされたシミュレーション世界の住民であり、色彩の影響によって存在が神秘から恐怖へと反転し、色彩の支配下となって(あるいは色彩を利用して)別の世界線に侵略を繰り返しているものと思われる。
そもそも色彩とは何なのか、なぜそのようなことをするのかは謎だが、正体としては概ね間違っていないだろう。
そのため、いったん色彩周りの考察は後に回し、キヴォトスという世界についての考察を深めていく。
学園都市という概念に支配された世界
キヴォトスが「神を証明するためのシミュレーションの結果生まれた世界」だとするならば、なぜ「学園都市」であり、神々が「女子生徒」という形で存在するのか、という疑問が生まれる。
が、そもそも最初からキヴォトスが学園都市であったわけではないことがゲマトリアの会話によって明かされている。元々キヴォトスを支配していたのは「名もなき神々」とそれを信奉する「無名の司祭」であったが、現在のキヴォトスにはその痕跡を残すのみとなっている。


つまりキヴォトスは様々な「概念」によって無数のパターンでシミュレートされており、たまたま今が「学園青春モノ」という概念が勝利した世界になっているだけと思われる。ではなぜそんなことになっているのか。それはシミュレーションにおける遺伝的アルゴリズムに端を発しているのだろう。
遺伝的アルゴリズムによる淘汰と名もなき神々
シミュレーション手法に遺伝的アルゴリズムというものがある。これは生物の進化と同じ仕組みで、滅亡と生誕を繰り返すことで存在を進化させていく手法だ。遺伝子的に弱い個体は滅び、強い遺伝子を持つ者だけが生き残る。そうして強く進化した恐竜がかつては世界を支配していたが、環境の変化により絶滅し、弱かったはずの哺乳類が進化を続け、やがて人間が世界を支配した。
こうした遺伝子による多様性と滅びをプログラム内で再現するのが遺伝的アルゴリズムである。恐竜が絶滅して哺乳類の時代が来たように、キヴォトスの世界内でも「神」の存在証明のため、ありとあらゆる「神の形」「概念」を具象化させて争わせ、勝ち残った者が「神」として君臨するのだろう。その争いに敗れた旧世界の支配者が「名もなき神々」だ。
キヴォトスを以前支配していた「名もなき神々」は自然災害そのものを神としており、それを崇拝する「名もなき司祭」は超高度な機械文明を築いていた。それは、学園青春モノという概念を与えられる前の、まったく別の概念を与えられたシミュレーション世界と考えられる。
そのシミュレーションで満足いく結果が産まれなかったため破棄されたか、新たに生まれた概念との争いで敗れたかで旧世界はシミュレーション世界から消されたが、その概念の一部はDivisionやAL-1S、巡航ミサイルや各種オーパーツとして現在のシミュレーション世界であるキヴォトスにも残留している。
「名もなき神々」陣営は世界を再び自らの概念で塗り替えようと、AL-1Sと箱舟の起動によってキヴォトスの支配に乗り出したが失敗。Divisionはデカグラマトンに感化されてケセドと化し、AL-1Sはアリスとして学園青春モノの概念に取り込まれ、Keyもケイとして概念を書き換えられた上に消滅したため、旧支配者は事実上壊滅した。(が、バッドエンドルートではアリスによる箱舟の起動に成功した描写があるため、名もなき神々が主権を取り戻したキヴォトスも並行世界上には存在しそう)

フランシスが「もともと世界は理解不能で不条理で力が暴れまわるだけの世界だったが、我々はそれを忘れていた」と語るのはそういう意味ではないだろうか。
学園青春モノという概念を覆そうとするカイザーコーポレーション
ここからは更に妄想だが「概念書き換えバトル」に関しては「カイザーコーポレーション」も実はかなり重要な役割を担っていると考える。カイザー社は「学園青春モノ」の概念に支配されているキヴォトスにおいて、それをひっくり返そうと策略を張り巡らせている。
ゲマトリアのようにキヴォトス外から来た存在ならともかく、キヴォトスの内側で自然発生した存在がそのような世界に対する叛逆を企てるというのはかなり特殊な状況に思える。カイザー(元)理事長は学園の自治権を奪うことで「カイザー職業訓練所」なるものを打ち立てようかと冗談めかして言っていたが、あながち冗談でも何でもなく「学園都市」の概念を「企業都市」で塗り替えてキヴォトスの支配者になろうとしているのではないか。理事長クラスならともかく、プレジデントクラスは名もなき神々のような旧世界の支配者とも考えられる(あるいはシミュレーションの都合で、今の世界に敵意を持つ存在も必要な要素として勝手に生み出されているのかもしれないが)
ゲマトリアの黒服も「この学園都市で企業がトップの学園が生まれるとこの世界がどうなってしまうのか興味がある」としてカイザー社を支援していたため、最終編におけるカイザー社のサンクトゥムタワー奪取事件は冗談抜きに学園都市としてのキヴォトスが終焉一歩手前まで行っていたようにも思える。
もしカイザー社が勝利すれば、新たに「企業都市」という概念によって「神」が生まれ、キヴォトスを支配していたかもしれない。そうなれば神は社員という形になって顕現するのだろうか。
ミュレーション世界において力を持つルール、契約、概念
「キヴォトスは神の存在を証明するための無数のシミュレーション世界である」
そのため、この世界では概念やルール、契約が非常に強い力を持つ。コンピュータにおいてはデジタルな約束事(プログラム)は絶対であるし、神や悪魔はそもそも「契約」に縛られる存在だからだ。
だからこそそれを利用できる。黒服は「借金」という契約を交わしたことでルールに則る形で神の力を奪い取ろうとしたし、ホシノとの取引でも嘘は一言もついていない。対して先生は「先生である自分がホシノの退学を認めていない」と、これまで存在しなかった「先生の概念」と「契約」によって黒服の策を跳ねのけた。
エデン条約編においてアリウス(ベアトリーチェ)は、エデン条約という「契約」の穴をついて兵力を手にしたし、先生はその「契約」の穴を更に突き返して「再契約」を行うことでそれを無力化した。


この世界が「学園青春モノ」という概念で支配されている限り「先生」という存在は極めて強い力を持ち、「悪い大人」から「生徒」を守る圧倒的な権能を持っているため、ゲマトリアに勝ち目は存在しないとゴルコンダは語り、ベアトリーチェは概念ごと先生を葬り去ろうと色彩を呼び寄せる。そして「学園青春モノ」としての概念を色彩によって破壊された結果、先生は「先生」であることの優位性を失ったとフランシスは語る。

連邦生徒会長の役割と、失踪した理由
キヴォトスがシミュレーション世界であるという前提の上に立つと、連邦生徒会長の役割と、その失踪理由が見えてくる。
まず、この世界に存在する者の殆どは、キヴォトスがシミュレーション内である自覚も、自分たちが神の化身であることの自覚もない。故に別の並行世界の存在も知らず、アクセスする手段も持たない。
しかし連邦生徒会長のみは別だと考えられる。連邦生徒会長のみが世界の真実を知っており、別のシミュレーション結果である並行世界にもアクセスが可能であるとするならば、そのシミュレーションの結末が「滅び」であることを察知することもできる。
旧支配者である名もなき神の復権、新たにキヴォトスの支配者たらんとするカイザー社の陰謀、暗躍するキヴォトス外の存在ゲマトリア、これらの存在により、今の「学園青春モノ」としてのキヴォトスは敗れ去り、シミュレーション世界から消滅するという結末を予見した。
しかし、連邦生徒会長の力ではそれを回避することはできなかった。なぜなら生徒会長もまた「生徒」で「子供」であるがゆえに、「子供を利用し搾取する、悪意のある大人」であるゲマトリアの概念に勝利することができない。ゲマトリアが手を貸していたカイザー社も同様で、これを打開するには「子供たちを教え導き、責任を持つ良き大人」つまり「先生」という概念が必要だった。
そして「連邦生徒会長が存在するシミュレーション世界」は滅亡し「先生が存在するシミュレーション世界」が唯一それを回避できると悟った連邦生徒会長は、学園都市としてのキヴォトスを存続させる僅かな権能のみをアロナとしてシッテムの箱に移して自らの存在を消滅させた。(アロナが先生を銃撃から守ったり、ハッキングを無力化するなどの能力を有するのは元々世界の管理者だった連邦生徒会長の権能を部分的に引き継いでいるため)
滅びを予見できたために滅びを招いてしまった王
これによく似た話が最終編第三章でもなされている。それが「滅びを予見した王が結果的に国を滅ぼしてしまう」という昔話だ。
これは一見するとリオ会長を示唆するエピソードに思える。「天才的な頭脳と権限を持つがゆえに、自分自身の正義を疑わず、周囲を信頼できなかったため最後まで孤独であり、滅びを回避しようと画策した己の行動によって結果的に滅びを招いてしまう」というのは、劇中の流れとしても当然リオにかけて語られたエピソードだ。
しかし、このエピソードは実は連邦生徒会長のことも示唆しているのではないか。
「能力と権限を持ち、一人で滅びを回避しようと奔走した結果、滅びを招いてしまった」
これはプロローグにおける連邦生徒会長の「私のミスでした」「この結果に辿り着いて初めて、あなた(先生)の方が正しかったと悟るだなんて」といったセリフにも合致する。
「責任を負うものについて話したことがありましたね」「大人としての責任と義務、その延長線上にあったあなたの選択」といったワードから、生徒であり子供である連邦生徒会長の概念では、どう頑張っても生徒たちを不幸から救えなかったのだろうということが読み取れる。子供たちを救うには大人の存在が必要だったと。
更に言えば、上記の王のエピソードで「最後に王はどうなったのか」と他でもない、連邦生徒会長の側近だったリンが問いかけ、濁されはしたが「自ら命を絶った」という結末を鑑みると「連邦生徒会長は世界の滅びを回避するために自らの存在を消した」という展開は説得力を持つように思う。(このエピソードにはちゃんとした元ネタがあるらしいのだが不勉強なため詳しくはない)
ただしこの場合「色彩によってシロコがテラー化して先生が殺害された」という世界線には連邦生徒会長が存在しないことになるため、生徒会長が「私のミス」と語るのが違和感がある。
生徒会長の「ミス」とは、バッドエンドスチルのような「生徒間の争いを回避できず、それぞれが不幸な結末を迎えた」ことのみを指しており、それを先生が解決した後の、色彩の襲来による世界の終焉に関しては関係していないと考えれば辻褄はあう。
先生とは何なのか。忘れられた少女の意味とは。
ここまで考えてみてようやく「先生」が一体どのような存在なのか説明できる。
「あなたの方が正しかった」という連邦生徒会長の言葉からは、連邦生徒会長と先生は元々親交があり、世界を救う方法について意見が対立していたことが伺える。
そして先生は「キヴォトスの外部から来た存在」であり、キヴォトスがシミュレーション世界なのだとすると、先生とは「シミュレーションの管理者・設計者」あるいは「デカグラマトン計画の関係者」であると考えられる。
しかしそう考えた場合に矛盾があるのが、先生はキヴォトスの正体について全容を把握していなさそうなことだ。

ベアトリーチェの言葉が正しいとするならば、先生はキヴォトスがどのような世界なのかを把握しておらず、ただ生徒に寄り添うことを行動原理として活動している。しかしその一方で、生徒のことを「忘れられた生徒」と呼ぶなど、生徒を神の化身として認識しているような描写もある。

「忘れられた生徒」というフレーズは劇中で度々登場する。エデン条約編第四章の章タイトルが「忘れられた神々のためのキリエ(哀れみの賛歌)」であり、エピソードタイトルが「少女たちのためのキリエ」であるため、忘れられた神々=少女、である。
上述の通り、デカグラマトンによる神の研究はその結果を待たず放棄されている。これは、人々が信仰心を捨て去り、神という存在を必要しなくなったことを意味しているのではないか。
もはや神の実在を証明する必要も、神の存在を再現させる必要もなくなった。神という存在は人類にとって不要になり、神話も宗教も全てが失われていった。そうして滅びゆく神々の情報を蓄積(アーカイブ化)して、滅びから逃れる方舟としてキヴォトスが生まれたのではないか(キヴォトスとは方舟の意味)。
つまり少女たちは人類から捨てられ、滅びを待つだけだった神々であり、アーカイブ化されたシミュレーション世界の中で、誰からも観測されないまま滅びと再生を繰り返し続けるだけの存在なのではないか。

ゴルコンダは「観測されなくともショーは続けられるべき」と語るが、キヴォトス自体が「観測者の存在しないショー」なのではないか。

デカグラマトンは少女たちを指して「君たちもまた、古く、弱く、いつかは消えゆく存在だ」と称している。人々の中から信仰が失われ、神が死にゆくことを指しているのか。
先生はそのことを知っており、人の手によって生み出され、人の手によって捨てられた神々のために寄り添い続けているのではないか。生み出したものとしての責任(大人として子供を守る責任)を果たしているのではないか。

黒服の「あなたは神を目の当たりにしたことがありますか?」の問いかけに何と答えたのかは定かではないが、生徒という形で毎日目にしていると答えていてもおかしくはない。
先生がキヴォトスに対する認識が歪なのは、シミュレーション世界に入り込む際に記憶の大半を失ったのかもしれない。連邦生徒会長は「私との会話は覚えていないでしょうが」と語っているため、シミュレーション世界に「先生」として入り込む際に、代償として記憶を失う必要があったのだろうか。
そして記憶を失ってもなお、先生の「大人としての責任と選択」は変わることがなく、キヴォトスにおいて生徒たちを守るために行動しているのではないか。
大人のカードやシッテムの箱とは何なのか
先生がたびたび用いる大人のカードは、明らかに異質な権能を有している。
そして先生は有事の際に、迷いなくそのカードを使う。その効能は、任意の生徒を呼び出して使役することである。(メインシナリオ上でプレイヤーが自分自身でガチャから引いたキャラクターを使用するタイミングは、全て大人のカードを使用したタイミングである)
これは完全に「ソシャゲプレイヤーの」「クレジットカード」をメタった表現であり、黒服が「それを使い過ぎると先生の時間と命が削られる」と評しているのもそれに拍車をかける。
しかし、キヴォトスがシミュレーション世界の中の話であると考えれば、これらのメタ表現は単なる演出にすぎず、その本質は管理者権限によるプログラムの部分的な書き換えだと考えれられる。
これを平然と使用できる先生は、やはり部分的にはキヴォトスという世界の在り様を把握しているように思えるが、とにかく、そうした書き換えは先生自身の存在を侵すことに繋がるのだろう。
また、シッテムの箱という存在も、おそらく管理者権限の行使に必要だろう。シッテムの箱へのパスワード入力と指紋認証を通して、先生はこの世界の管理者権限を部分的に使用できる。先生の存在によって生徒たちの能力が向上するのは、戦略面での指揮もさることながら、管理者権限と「先生」という概念の合わせ技とも取れる。しかし、それもまた行使するたびに先生に何らかの肉体的ダメージがフィードバックしているようだ。
ウトナピシュテムの箱舟の機動に際して先生の肉体に不可逆的な変化が訪れるというのは、管理者権限の使いすぎにより、世界のほうから異物と断定されて排除される危険性を指しているのか。この時先生は一時的に連邦生徒会長との会話の記憶や、別世界戦のバッドエンドを思い出していた。世界の中の住民としてではなく、外の住民として俯瞰的にキヴォトスを観測していた。先生の存在がキヴォトスから排除されるということなのかもしれない。
黒服は「カードを使い過ぎると先生も我々(ゲマトリア)と同じになる」と発言している。ゲマトリアと同じ、という状態が何を指すのかは今もって不明だ。そもそもゲマトリアの存在も不明瞭な部分が多い。
ゲマトリアとは何なのか
キヴォトスの外からやってきたとされるゲマトリアもまた、シミュレーション世界に入り込んだ外部からの侵入者だろう。そのアクセス手段は不明だが、先生と違って外部の記憶を保持しており、シミュレーション世界内で各々の目的を満たすべく暗躍している。


「ゲマトリアは研究者であり探求者」と自称している通り、ベアトリーチェを除くメンバーは全員、キヴォトスという「概念によって支配された世界」がどのように構成されているのか検証するような行いをしている。
黒服はカイザー社を支援してキヴォトスの概念を塗り替えようとしたほか、ホシノやシロコを通じて神秘を恐怖に反転できるか(プログラムを改変できるか)の実験を行おうとしていた。また、無名の司祭が残したオーパーツは「高く売れる」と冗談めかして言っていることから、この世界で生まれた概念を外部に持ち出して金に変えることも画策しているようだ。
マエストロは芸術家であるため、自らの芸術を思うがままに形作れることに関心を寄せている。神々の持つ神秘と恐怖という両側面と、それを包括した崇高という概念を研究し、複製することで新たな芸術を生み出そうとしている。
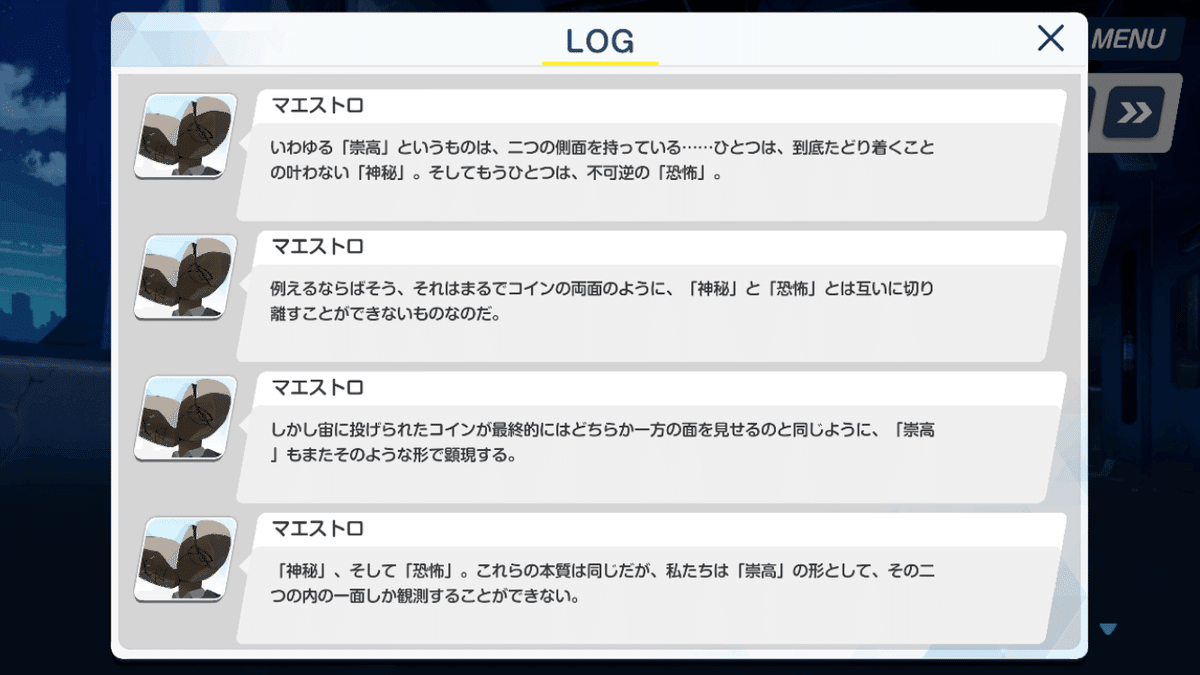
ゴルコンダは「学園都市という概念(テクスト)で支配された世界」そのものに興味を抱き、その概念ごと書き換える方法を編み出したり(ヘイローを壊す爆弾)、ペロロジラといった「概念や信仰が実態をともなった存在」を産み出したりもしている。

ベアトリーチェはそうした探求には興味がなく、この世界の神々を支配下に置き、その崇高を得て自分自身が神たらんとした。しかしその成就を「先生」に妨害されたことで、キヴォトスという概念世界ごと滅ぼそうとしたため、探求の邪魔になるとして他のゲマトリアたちに粛清された。
こと時「ベアトリーチェを送り届ける」と表現されていたため、単に殺害したのではなく、キヴォトスという世界から追放したのだとも取れるが、詳細は不明だ。また、どうやって外部から侵入したのか、自力で出ることが可能なのかも明らかではない。
先生と同じく、シミュレーション世界に侵入したタイミングでシミュレーションを構成する一部となっているため、無数に存在する並行世界上にも同一存在がそれぞれ存在すると考えられるが、そうするとどうやってキヴォトスの外に出るのかが不明となる。あるいは最初から出ることを諦めているのか。

ベアトリーチェを消滅させた際「また席が空いた」「次の人員をどうするか」「先生をゲマトリアに迎え入れたい」といった発言があるため、ゲマトリアは上限が四人であり、既に何度かメンバーの入れ替わりが起きているとも取れる。現存するゲマトリアの裏にはより大勢の組織が存在しているのかもしれない。


ベアトリーチェ以外のゲマトリアから異様に評価の高い先生。基本的にゲマトリアは研究者であり探究者であるため、目的は違えどリスクを背負ってシミュレーション世界内に入り込んできているという点でその信念に感銘を受けているのだろうか。
色彩とは何か
ここまで考えてみても、色彩とは何なのか、ということについての説明ができない。
シミュレーション世界として考えるのならば、進化の行き詰ったシミュレーション世界を破棄するための自己消滅プログラム、あるいはコンピュータウイルスのような存在と考えるべきだろうか。
無数に存在する並行世界の一つ一つを個別に侵略していることから、色彩自体もシミュレーション世界に定義された存在と考えたほうが自然か。
「セイアが露出したことで色彩に見つかった」「ベアトリーチェが色彩を呼び寄せた」とあるため、シミュレーション世界内で何らかのトリガーを引くと、色彩という自己崩壊プログラムが起動し、その世界を消しにかかるのだろうか。
色彩というウイルスは、世界のあらゆる物体の権限を奪い取り使役する。その存在を「反転」させ、それを元に戻す方法は存在しないが、侵食された概念を切り離すことで存続はできる(セイアは「未来視」を捨てることで色彩の侵食を免れた)
おそらく、とある世界線は色彩によって滅びを迎えており、その際に色彩によって反転したシロコ・テラーによって先生は殺害され、さらにその存在とアロナもまた反転し、色彩に使役されているのだろう。
が、それもまた違和感がある。シロコの存在が説明できない。
シロコとは一体何なのか
今の劇中の世界において、シロコは本来アビドスに存在する生徒ではなかった。記憶を失った状態で突如アビドス領地内に現れたが、その際の衣装はシロコ・テラーのものと同一だった。しかし肉体的な年齢が明らかに異なる。これにどのような説明が付けられるのか。
仮に、全ての並行世界にシロコが最初から存在し、その一つが色彩によって反転したのだとしたら、今の劇中の世界のシロコは無関係で、最初からこの世界にいたことになる。しかし実際はどこからともなく記憶を失いテラー化した状態で現れているように見える。
そもそもシロコという存在がこの世界に存在しなかったのであれば、最初に色彩と接触して反転したシロコとは何なのか。実はシロコとは最初から色彩の配下、あるいは色彩そのものなのか。それともキヴォトスの外からやってきたのか。
しかしシロコは死の神アヌビスをモチーフとした立派な神の化身であり、エジプト神話をモチーフとするアビドス高校に相応しい存在のため、シミュレーションの結果生まれたと考えたほうがしっくりくる。
どう考えてもその存在に説明が付けられない。
唯一、事の仔細を把握してそうな黒服は
「彼女がこの世界に存在した瞬間から、この結末(色彩の到来による滅亡)は決定されていた」「時間は連続することなく、決まり切った因果を繰り返すのみ」「過去に戻ってシロコを殺していればこうはならなかった」としている。

つまり「シロコが存在することによって時間が無限ループし、閉じている」とも取れる。
ここからは完全に根拠のない妄想になるが、シロコ・テラーは、今の「学園都市という形のキヴォトス」「先生と生徒たちが幸せな日常を送れる世界」を繰り返すために、シミュレーション世界を意図的に破壊し、全く同じ世界として何度もやり直しているのではないか。そのために色彩という自己破壊プログラムを乗っ取り、利用しているのではないか。ベアトリーチェが呼び寄せなくとも、学園都市が1年を終えるその瞬間に色彩は自動的に襲来し、その世界を抹消するのではないか。
シロコ・テラーは永遠に今のキヴォトスを繰り返させているのではないか
キヴォトスがシミュレーション世界である以上、シミュレーションを続けていけば、学園都市という概念は遅かれ早かれ消滅し、別のキヴォトスに生まれ変わるかもしれない。それならば、永遠に今この瞬間のシミュレーションを何度も繰り返して、進化を堰き止めることで、今のキヴォトスを守っているのではないか。
1年が終わって「卒業」を迎えると今のキヴォトスが変わってしまうため、シロコがアビドスに出現した「冬」から、色彩が到来するまでの「冬」までの1年間で時間を閉じ、無限に繰り返し続けているのではないか。
つまりシロコ・テラーの行動はこうだ
・卒業前の段階で色彩を呼び寄せてシミュレーション結果を破棄する
・新たなシミュレーション世界が生まれる
・そこに自分自身を転写して送り込む
・送り込まれたシロコは記憶を失っているが、やがて先生と出会い、平和な日常を送る
・その日常が終わろうとする瞬間に、送り込んでいたシロコを目印として色彩とシロコ・テラーが乗り込んで、再びその世界を滅ぼす
・新たに生まれたシミュレーション世界に、また自分自身を転写する
つまり永遠に閉じた世界で終わらない物語を繰り返すタイプのヤンデレ系ヒロインというわけだ。先生の死体をミイラ化してプレナパテスとして行動を共にしているのも、常に先生と共にいたいというヤンデレ概念と考えることもできる。(アヌビスはミイラの神でもある)
シロコ・テラーが大人びた姿をしているのは、無限ループを繰り返すキヴォトスと違ってシロコ・テラー本人の時間だけが経過し、年齢が加算されているからと考えることもできる。
テラー化する以前のシロコはシロコとして存在していたが、その神秘が恐怖に反転した瞬間、全ての並行世界におけるシロコの存在が塗り替えされたのではないだろうか。黒服が過去の時点でシロコを殺していれば滅びは訪れないと述べたのは、この世界にシロコが存在しなければ色彩がこの世界を発見することができないからではないか。
結論とブルーアーカイブにおける世界の流れ
これまでの考察をもとに、ブルアカ世界における事象を時系列順にまとめてみる。あくまで妄想であり、正解かどうかは保証しない。
・神の実在を証明するためのシミュレーション計画が始動する
・しかし、人類が信仰心を捨てたため、計画も破棄される
・だがシミュレーション自体は継続しており、その結果、神々の世界「キヴォトス」が誕生する
・キヴォトス内では様々な神の概念が争い合い、支配者が入れ替わってきた
・自然崇拝の概念である名もなき神が敗れ、学園都市の概念が管理者権限を手に入れ、今のキヴォトスが生まれる
・学園都市の管理者として連邦生徒会長が君臨する
・名もなき神やカイザー社が管理者権限を奪い取ろうと侵略をはじめ、ゲマトリアも暗躍を始める
・連邦生徒会長ではその侵略からキヴォトスを守ることができず、多くの並行世界で学園都市は消滅していった
・連邦生徒会長は自らの存在を消し、先生を学園都市の守り手として招聘する
・先生という概念、未知の変数の追加により、キヴォトスは侵略者の魔の手を跳ねのけ、一年が経過する
・しかし、色彩と接触したシロコがヤンデレ化し、今のキヴォトスを永遠に閉じた世界にすることを決意(あるいはシロコ自身が己の願いから意図的に色彩を呼び寄せた)
・先生を殺害し、アロナを支配下に置くことで部分的に管理者権限を手にする
・色彩を利用してシミュレーション結果を破棄し、新たに生まれたシミュレーション世界に存在するシロコを自身の存在で上書きする
・そのまま自身のコピーであるシロコに学園都市での一年を過ごさせ、最終的にその世界を崩壊させる
・また新たに生まれた世界に自身を転写し、以降、それをずっと繰り返す
・こうすることで、キヴォトスはこれ以上進化も変化もすることがなく、学園都市という概念を保持したまま永遠に平和な日常を繰り返すことができる
これが、現状判明している事実から類推したキヴォトスや色彩の正体と行動原理である。
最終編以降のブルーアーカイブの世界はどうなるか
これはメタの話になってしまうが、ソーシャルゲームにおいて、時間軸の経過というのは扱いが非常に難しい。特に学校が舞台の場合、時間が一年経過すれば三年生が卒業したり、新入生が入学したりする。
そうした場合、ガチャキャラクターの設定と、シナリオ展開が食い違ってしまう。
そのため多くのソシャゲは時間軸や時系列を曖昧にしたり、明確なストーリーラインを作らなかったりする。
しかしブルーアーカイブというゲームは偏執的なまでに時系列やタイムラインに正統性を持たせている。イベントシナリオや絆ストーリーの細部に至るまで「先生と生徒の初対面はどこか」「どのタイミングで何が起きて、その結果、誰と誰が仲を深めたか」まで綿密に計算されている。(イベント不忍の心で交流した忍術研究部とイブキが、最終編で共闘していたりする)
そして、劇中で観測できる限り、ブルーアーカイブは春に始まり冬で終わっている。最終編を除いて最も時系列的に遅いのはバレンタインデーイベントだ。
仮にこのまま最終編がハッピーエンドに終わり、卒業シーズンを迎えてしまうと、今後のシナリオ進行に大いに負担がかかる。
また、各キャラとの絆ストーリーの時系列にも問題が出てくる。例えば次に実装されるコユキは、バニーイベントで先生と初めて邂逅した後はずっと拘禁されており、釈放されたのは最終編になってから。その後セミナーに復帰して先生と日常を送る頃には、最終編のいざこざが終わっていなければならない。今後実装するキャラクターも含めてだが、これ以上時間軸を進めてしまうと先輩たちが卒業し、在学生も学年が上がってしまう。これをどう解決するのか。
そこで、先に述べたシロコ・テラーによる「ループ」が効いてくるのではないだろうか。今のキヴォトスは色彩の手によって崩壊し、まっさらな状態で一年前に戻り、また新たなループが始まる。
しかし、今度のそれはこれまでと違い、シロコだけでなく全ての生徒たちの記憶が情報がアーカイブ化され、次に生まれる世界に転写される。つまり、全員が記憶を維持したまま二週目を開始する。
そうすれば「学年が上がってしまう問題」と「シナリオが進められなくなってしまう問題」を同時に解決できる。
あるいは、今の世界は維持されるが時間だけが一年間巻き戻る、ということも考えられる。こうすればシナリオとしては前に進みつつ、学年は今のまま据え置きにできる。暗躍するFOX小隊やカヤの行く末もそのままシナリオとして展開できる。
あるいは、一度今の世界はシロコ・テラーを止めることで平和的に解決し、「卒業」をもって完結を迎える。そして違った選択を選んだ別の並行世界においてのストーリーが新たに展開される。ということも考えられる。
このあたりの決着を迎えるのではないか、と予想する。
最後に
いろいろと考えてきたが、それらは全て「キヴォトスが神々の存在を証明するためのシミュレーションによって生まれた世界である」という考察が前提となっているため、これが間違っていた場合は全ての理論が崩壊してしまう。
だが、たとえ「シミュレーション」の部分が間違っていたとしても、多次元解釈による無数の並行世界自体は存在することは間違いなさそうなので、部分部分の考察としては当たっている箇所も少なくないのではないだろうか。
とにかく、答え合わせはもう数日後に控えている。楽しみに待ちたいし、その結果新たに謎が生まれたとしたら、その探求も引き続き行っていきたい。二周年を迎えてもなおワクワクを与え続けてくれるブルーアーカイブというゲームに、最後までついていく所存だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
