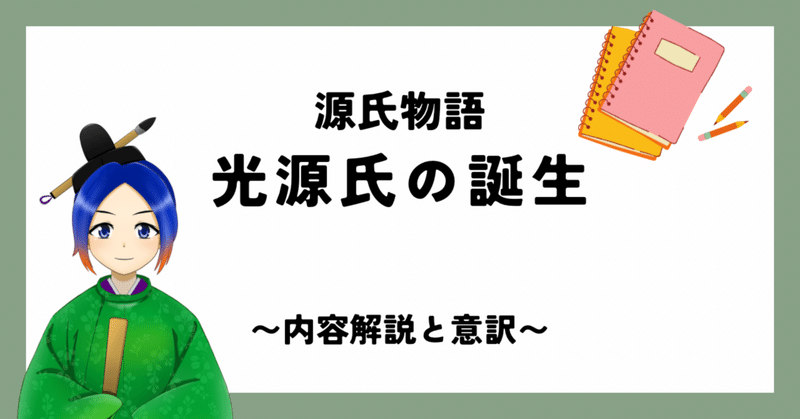
【古文解説】桐壺・光源氏の誕生〈源氏物語〉内容解説|万葉授業
こんにちは、よろづ萩葉です。
YouTubeにて古典の解説をする万葉ちゃんねるを運営している、古典オタクVTuberです。
ここでは、源氏物語の一節『光る君誕生』の内容解説を記していきます。
源氏物語とは
紫式部によって書かれた長編小説。
非常に長い物語で70年近い時間が描かれており、登場人物は430人を超えると言われる。
物語なのでキャラクターも全て架空の人物だが、この時代の政治や生活について知ることができる。
源氏物語は全部で54巻まであり、それぞれに名前がつけられている。

橋姫(はしひめ)から夢浮橋(ゆめのうきはし)までを宇治十帖という。
桐壺では、光源氏の誕生から12歳までが描かれている。
今回は桐壺更衣が光源氏を産んで周りから迫害を受けるまでの話である。
原文
いづれの御時にか、女御・更衣あまた候ひ給ひける中に、いとやむごとなききはにはあらぬが、すぐれて時めき給ふありけり。初めより我はと思ひあがり給へる御方々、めざましきものに、おとしめ、そねみ給ふ。同じほど、それより下﨟の更衣たちは、ましてやすからず。朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふ積もりにやありけむ、いとあつしくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよ飽かずあはれなるものに思ほして、人のそしりをもえはばからせ給はず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり。上達部・上人なども、あいなく目をそばめつつ、いとまばゆき人の御おぼえなり。唐土にも、かかることの起こりにこそ、世も乱れあしかりけれと、やうやう天の下にも、あぢきなう、人のもて悩みぐさになりて、楊貴妃のためしも引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにて、まじらひ給ふ。
父の大納言は亡くなりて、母北の方なむ、いにしえの人の、よしあるにて、親うち具し、さしあたりて世のおぼえはなやかなる御方々にもいたう劣らず、何事の儀式をももてなし給ひけれど、とりたててはかばかしき後見しなければ、ことあるときは、なほよりどころなく、心細げなり。
前の世にも、御契りや深かりけむ、世になく清らなる玉の男皇子さへ生まれ給ひぬ。いつしかと心もとながらせ給ひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなるちごの御かたちなり。一の皇子は、右大臣の女御の御腹にて、よせ重く、疑ひなきまうけの君と、世にもてかしづき聞ゆれど、この御にほひには並び給ふべくもあらざりければ、おほかたのやむごとなき御思ひにて、この君をば、私物に思ほしかしづき給ふこと限りなし。
初めよりおしなべての上官仕へし給ふべききはにはあらざりき。おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせ給ふあまりに、さるべき御遊びの折々、何事にもゆゑあることのふしぶしには、まづまう上らせ給ふ、あるときには大殿籠り過ぐして、やがて候はせ給ひなど、あながちに御前去らずもてなさせ給ひしほどに、おのづから軽き方にも見えしを、この皇子生まれ給ひてのちは、いと心ことに思ほしおきてたれば、坊にも、ようせずは、この皇子のゐ給ふべきなめりと、一の皇子の女御はおぼし疑えり。人より先に参り給ひて、やむごとなき御思ひなべてならず、皇女たちなどもおはしませば、この御方の御いさめをのみぞ、なほわづらはしう、心苦しう思ひ聞こえさせ給ひける。
かしこき御かげをば頼み聞こえながら、おとしめ、疵を求め給ふ人は多く、わが身はか弱くものはかなきありさまにて、なかなかなるもの思ひをぞし給ふ。御局は桐壺なり。
人物

桐壺帝
この時代の天皇。
一の皇子
第一皇子。のちの朱雀帝。
右大臣の女御
弘徽殿の女御。右大臣の娘。

内裏
皇居のこと。
天皇が生活をするのは「清涼殿」。
「紫宸殿」は、天皇元服やその他さまざまな儀式を行う、内裏の正殿。
今回出てくるのは「弘徽殿」と「淑景舎(しげいしゃ)」。
「淑景舎」は庭に桐を植えてあったことから、桐壺とも呼ばれる。
女御・更衣
天皇の妻。
他にも「皇后」「中宮」という言葉もあり、
皇后は正妻、中宮・女御・更衣は側室。
側室の中でもランクがあり、
更衣は女御より地位が低い。
文法
助詞「が」
いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めき給ふありけり。
この「が」は逆接を表わす「接続助詞」ではなく、「同格を表す格助詞」。
現代語訳を考えてみる。
それほど高貴な身分ではない方( )、非常に帝からのご寵愛を受けていらっしゃる方があった
()の部分に、「が」の現代語訳が入る。
それほど高貴な身分ではない方(であって)、非常に帝からのご寵愛を受けていらっしゃる方があった
同格の格助詞は、このように訳す。
「それほど高貴な身分ではなくて、非常に帝からのご寵愛を受けている」人がいた、という意味である。
現代の感覚だと、「が」は逆接、
それほど高貴な身分ではない方だけれど、と訳したくなるが、
「が」がこの様な意味を持つようになったのは、もう少しあとの時代とされている。
最高敬語
この話には「せ給ふ」や「させ給ふ」がいくつか出てくる。
これは最高敬語と言われ、ここでは天皇である桐壺帝に対する敬意を表している。
敬語について詳しくはこちらの動画をご覧ください。
語句

意訳
どの帝の時代であったか、女御や更衣が大勢いた中に、あまり高貴な家柄ではない方で、
帝から特別好かれている「桐壺更衣」という方がいた。
そのため、「自分こそは帝に好かれるはず」と思っていた他の女性たちは、
桐壺更衣を妬んでいた。
彼女と同じ身分か、それより下の身分の更衣たちはなおさら穏やかではなかった。
周りから妬まれ続けたため、桐壺更衣は身体を壊してしまい、療養のため実家に帰りがちになってしまった。
そんな彼女を、帝はますます可愛らしいといって溺愛する。
上達部や殿上人などは「困ったことだ、中国でもこうしたことが原因で世が乱れたんだ」と嘆いていた。
世間からも非難されるようになり、桐壺更衣はさらに体調を崩していくが、
帝からのこの上ない愛情だけを頼みになんとか宮仕えを続けている。
彼女の父は亡くなっていた。
母は由緒ある方で両親も揃っているので、
他の女御・更衣にも劣らないようどんな儀式に対しても母親が取り計らっていたが、
桐壺更衣には後見人がいないのでやはり大事な時には心細そうである。
帝と桐壺更衣は前世でも縁が深かったのか、見たこともないほどの大変美しい男の子が生まれた。
第一皇子は右大臣の娘である女御の子どもで、後見人の勢いも強く
「将来必ず皇太子になる」と世間から思われていたが、
桐壺更衣の子どもの美しさには及ばない。
帝は桐壺更衣の子どもをとても大事にしていた。
本来であれば桐壺更衣は普通の上官仕えをするような軽い身分ではないが、
帝が彼女を常にお側においているので、周りからは桐壺更衣がまるで軽い身分かのように見えていた。
だが男の子が生まれてからは、桐壺更衣を特別に扱うので、
第一皇子の母である右大臣の女御は「桐壺更衣の子どもを皇太子にするのかもしれない」と疑っている。
この女御は誰よりも先に入内して、子どももたくさんいたので、帝はこの女御の苦情だけは「気の毒だ」と思っていた。
桐壺更衣は帝の庇護を頼みにしながらも、彼女の悪口を言う女御・更衣が多いので病弱になってしまい、かえって悩みが増えていってしまう。
解説
帝の桐壺更衣への愛情が強すぎたので、更衣は虐められ病気がちになってしまった。というお話でした。
ここで生まれた美しい男の子が、光源氏。
源氏物語の主人公です。
やがて桐壺更衣は亡くなってしまい、光源氏の物語が始まります。
このあと光源氏はどのような人生を歩んでいくのでしょうか。
動画
ご覧いただきありがとうございました🖌️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
