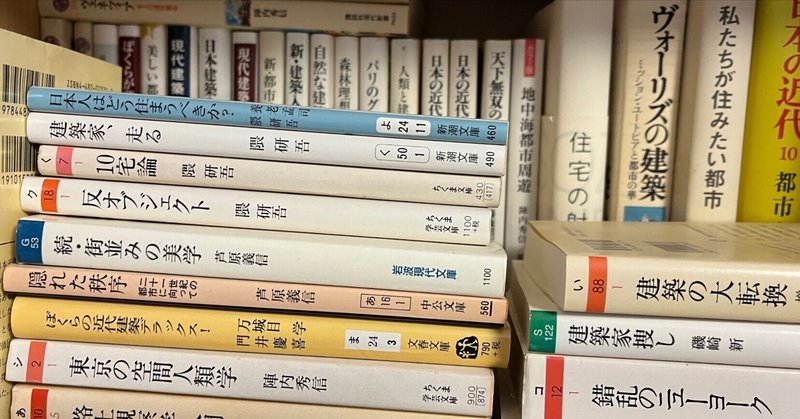
今月読んだ本 (9)
2023年12月
今年最後になる今月もkindleでの読書の話から始めます。今月読んだのは、KARIN SMIRNOFF というスウェーデン作家の"THE GIRL IN THE EAGLE'S TALONS"でした。日本ではまだ無名の女性作家によるアクション・エンタテインメント作品ですが、どうして私がこの本を選んだかというと、これが「ミレニアム」シリーズの最新作だったからなんですね。「ドラゴン・タトゥーの女」「火と戯れる女」「眠れる女と狂卓の騎士」からなる「ミレニアム」三部作が日本で出版されたのは、もう15年ほど前のことですが、全世界で1000万部も売れたというだけに、日本でもベストセラーになりました。本国やハリウッドで映画化もされました。当然、私も読んで大興奮しました。でも、その時には著者のスティーグ・ラーソンは既に故人になっていたんですね。
でも彼が生み出した主人公たち、特に「ドラゴン・タトゥーの女」であるリスベット・サランデル(私はずっと英訳で読んでいたので、サランダーと呼んでしまいます。昔テニスの選手でエドバーグという人がいましたが、本国での発音であるエドベリと呼ばれるようになった時の違和感を思い出します。)の魅力はあまりにも大きくて、たった三作で終わらせるのは惜しいと関係者の全てが思ったのでしょう。ラーソンの死後に作者を変えて、彼女らを主人公にした「ミレニアム」シリーズの続三部作が書かれました。作者はダヴィッド・ラーゲルクランツ。スウェーデンのジャーナリスト兼作家でした。彼は「蜘蛛の巣を払う女」「復讐の炎を吐く女」「死すべき女」の三部作を残しました。なかなか評判が良くて、最初の一作はハリウッドで映画化もされました。私もずっと楽しんで読んでいましたが、さすがに最後の三作目になると、もう「ミレニアム」シリーズはこれで最後にした方がいいんじゃないかと思いました。なんだか、ストーリーに必然性がなく、無理矢理話をつくっているような気がしたからです。
というわけで、もう終わったものと思っていた「ミレニアム」シリーズが、突然、ゾンビのごとく復活したのが今回紹介する作品です。内心もういいやと思いながらも、本国や英語圏ではすでにベストセラーになっているそうだし、ひょっとすると掘り出し物かもしれないと、読んでみることにしました。結論を書きます。残念ながら、この女性作家は「ミレニアム」の水準に達していないように思いました。特に、悪役にまったく魅力がないのです。最初の三部作では、まさに怪物としか言えない、サランデルの父親が敵役でしたし、続編の三部作では、サランデルの双子の姉が敵役として登場しました。二人とも敵役としての魅力がありましたし、血を分けた者同士が殺し合う宿命のドラマとしての哀しみもありました。それらに較べると今作での敵役はあまりに魅力に欠けます。サリドマイドで両脚がなくて車椅子に乗っている。あまり頭が良くなさそうだし、しかも巨根で女好きなどという、いかにも倫理的にもどうかと思う、とってつけたような設定ではね。
しかも、この作品では雑誌「ミレニアム」は紙媒体としては廃刊となり、もう一人の主役であるブルムクヴィストは誘拐された孫を救おうとする老人となり、サランデルは昔の自分自身を思い出させる孤独な姪の面倒を見ることになります。もう彼らの時代ではないんですね。まるで、満男くんが主役になった後の寅さん映画のような気がしました。著者と出版社の契約がどうなっているのか知りませんが、こんな気が抜けた状態で、あと二作も続けるつもりなんでしょうかね。たぶん、私はもう読まない。

次に読んだのは、小説デビュー作が権威ある読売文学賞を授賞したことでも話題になった、川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」でした。前から読みたかった作品ですが、文庫になったのを機会に読んでみました。予想通りというか予想を超えるというか、まことに驚異的な小説でした。なんと評していいのかわかりません。ただただ感嘆した、面白かったというしかありません。年をとると視力も体力も落ちるし、長い小説を読むのは辛くなってくるんですが、最後まで集中して読み切ることができました。「真実の生涯」といいながら大嘘ばかりのストーリーももちろん面白かったんですが、とにかく情報量の凄さに圧倒されました。川本さんは、もともと英米文学を研究する評論家だったそうですが、ノーマン・メイラーやトルーマン・カポーティなど、私も若い頃に親しんだ懐かしい作家たちが登場して、アメリカ現代文学史の裏面をたどり直す楽しさもありました。また、小説内小説として、アレクサンダー大王の物語が登場した時には、先日読んだ、塩野七生さんの記述を思い出しながら読めたのも、この小説の面白さを倍加させてくれました。先ほどとは逆の事を書くようですが、かなり分厚い小説で読むのがしんどく、結局、読了するのに一週間もかかってしまいました。でもそれは、とても楽しい一週間でした。
なお、この小説の構造は、アメリカの作家が残した「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」という回想録を川本さんが訳したという体裁をとっています。構成としては、川本さんによる「日本語版序文」、アンソニー・アンダーソンという作家が書いた「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」の本文、そして、訳者あとがきに代えて収録したという、川本さんによる、この本の日本語版出版に至る経緯を書いた「ジュリアン・バトラーを求めて」が続きます。問題はその後です。詳細な、数十ページにわたる「主要参考文献」が紹介された後、白紙のページをはさんで最後に、「この小説はフィクションです。」という一行が現れました。これを見た私は、かつて著名なSF作家、スタニスワフ・レムが「完全な真空」という、架空の書籍の書評集を出したことがあった事を思い浮かべて、この「主要参考文献」自体もフィクションなのではないかと、じっくり眺めたんですが、どうやらこれらは本物だったようです。そこはちょっと残念でした。もちろん、読者には、最後の一行をもフィクションとして読む権利がある。つまり、これは全て真実の物語であると。参考文献も含めてね。まるで、クレタ人は全て嘘つきであるとクレタ人が言ったというような話ですが。

次に読んだのは、古川薫「失楽園の武者 小説・大内義隆」でした。先月、たまたま山口市へ旅行で行くことがあって、山口を「西の京」にした大内氏に興味を持ちました。その旅行のことは、「山口線の旅」としてnoteに投稿してありますが、この小説はその時に参考書として読んだものです。古い小説なので本屋では買えませんが、amazonのkindle本で手に入れることができました。大内義隆は、その伝承によると百済王家の系譜を引き継ぐ古い家柄の、最後の頭首となった人物で、中国から北九州までの数カ国の覇者であり、また、フランシスコ・ザビエルに山口での布教を許したことでも記憶されていますが、あまりに公家化してしまったために武士としての活力を失い、支流の家老によって滅ぼされてしまいました。この小説は、そんな大内義隆時代の山口の光景が目に浮かぶように描かれていて、それはそれで楽しかったのですが、主人公がそんな滅び行く人物だったせいか、歴史小説としてはやや生彩に欠けるものでした。

その後、今月は新書本を三冊読みました。まず最初は、倉本一宏「紫式部と藤原道長」。来年の大河ドラマ「光る君へ」の予習として、関連本が書店に溢れる中、馴染みのある倉本さんの本を選びました。倉本さんは平安時代が大河の舞台に選ばれたことを喜びつつも、紫式部や道長がドラマに描かれたような人物であったと一般に思われては困ると、この本では、一次史料のみを用いて、今のところは確実に分かっている二人の人物像を描くことに努めたそうです。
この本で知った史実のいくつかを紹介する前に、大河ドラマの話を。私は、「花の生涯」以来、大河ドラマを数十年間も見続けているファンですが、前回の「鎌倉殿の13人」は出色の面白さでした。その後が、大阪人である私がどうしても好きになれない家康が主人公。しかも演じるのは(問題が起きる前でしたが、)ジャニーズのタレント松本潤とあって、まったく何の期待もなく、ただ習慣で見始めたんですが、終わってみると、なかなかどうして、素晴らしいドラマでした。さすがNHK大河。やはり脚本家の力は大きい。考えてみると、この物語は「鎌倉殿の13人」とまったく同じ構造だったんですね。多感な優しい若者が周囲の荒波にもまれて、冷酷な策謀家に変貌していく物語。最初から脚本の古沢さんが目指していたのはこれだった。最終回に小栗旬を天海役で登場させたのはやり過ぎだと思います。あまりに意図がわかりやすすぎる。もっともこのキャスティングは古沢さんの指示ではなかったようですが。
「紫式部と藤原道長」に戻ります。「源氏物語」の誕生に、藤原道長が密接に関係していたことは既に知っていました。高価な紙の話もどこかで読んだことがあります。一条天皇を娘の彰子のいる後宮に足繁く通わせるため、そして彰子に天皇の子を懐妊させるために紫式部の「源氏物語」を利用したという話も聞いたことがある。でも、この本で、清少納言のいた定子のサロンと紫式部のいた彰子のサロンがライバル関係にあったというのは俗説だと知りました。二つのサロンは同時代的に存在していたわけではなかったんですね。紫式部が彰子のサロンに入った時には、すでに定子は亡くなっていた。したがって定子のサロンはもう存在していなかった。また、「源氏物語」は同時代からすでに有名で、天皇以下おおくの貴族や女房連中が競って写本をつくって読んだそうですが、もはや過去の人になりつつあった清少納言の「枕草子」が宮中で広まったのは、彰子の産んだ子、つまり道長の孫が次期天皇位を継ぐことが確実視される中で、(道長にとっては姪にあたる)定子の忘れ形見であった皇子の存在を忘れさせないようにするためだという話にはなるほどと思いました。「枕草子」は華やかだった定子サロンの光景を回想した文章だったから。
また、この本では、今までは名前しか知らなかった、紫式部の夫だった藤原宣孝のことをある程度知ることができたのが収穫でした。紫式部は、結婚適齢期だった頃に学者でもあった父親が無役だったために、まあ、行き遅れた。父親がようやく県知事のような役職につけたので、二十代の後半を過ぎて、やっと結婚することができたわけですが、正妻ではなかった。しかも相手の宣孝は、紫式部よりも二十歳くらい年長で、紫式部よりも年上の息子もいた。当時の貴族の習慣で、正妻以外に何人も訪ねていく妻がいた。紫式部はそれらの妻の一人として迎えられたことになります。紫式部はそんな宣孝との間に一女をもうけますが、わずか二年ほどの後に宣孝に先立たれました。紫式部が文才を買われて彰子のサロンに出仕したのは、その後のことだったようです。さて、このような史実をテレビドラマはどう膨らませて見せてくれるのでしょうか。今から楽しみです。
なお、「源氏物語」に関して書いておくと、私が尊敬する中村真一郎さんはプルーストと比較して読み、丸谷才一さんは、せめて「若菜」だけでも原文で読むことをすすめておられましたが、私が実際に読んだのは与謝野晶子による現代語訳だけでした。この機会に、来年はもう一度「源氏物語」を読もうか。誰の訳がいいかな、それとも原文で?

二冊目の新書本は、隈研吾「日本の建築」でした。8年をかけて書いたという、隈さんの決意と創見に満ちたこの日本建築論は、従来の私の隈研吾イメージを覆す硬派の書でもありました。一般向けに書かれた小さな新書本の体裁ですが、その中身は同業の建築家や建築評論家たちに向けた決意表明の書とも言えるものでした。いや、次世代の建築家たちに向けた「日本建築宣言」かな。
隈研吾さんは、いつ建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を受賞してもおかしくない、世界的な建築家ですが、そのいかにもクマさん的な大柄で丸顔の風貌やその太い声でのゆったりした語り口や、「負ける建築」という従来の主張から、おっとりした大人の風格の持ち主だというイメージがあり、軽妙なエッセーの書き手でもあるという印象でしたが、この本は、それらのイメージを払拭するほどのインパクトを持っていました。この本には、はっとするような言葉と熱気があふれていました。
隈さんが書いているのは、私なりにまとめると、こういうことです。かつて日本の浮世絵がフランスの印象派絵画を生み、日本料理がフランスのヌーベル・キュイジーヌを生んだように、コルビュジエやミースの現代建築を生みだした淵源は日本建築だった。それは、日本建築の影響を深く受けていた(そして、その事実を隠していた)ライトの影響を受けて、コルビュジエもミースも仕事を始めたからである。しかし、その事実を知らなかった日本の建築家たちは、コンクリートと鉄とガラスの、コルビュジエやミースの建築を革命として受け止め、彼らを神格化していった。私たちは、環境保護思想が主流となり、反建築さえ叫ばれている今こそ、真の日本建築を再発見すべきである。日本の近現代には、西洋の影響を受けながらも日本建築の良き伝統を生かした、素晴らしい建築家たちが存在した。彼らは折衷的建築家とバカにされたが、折衷こそ、東と西をつなぐ架け橋だったのである。この本で、隈さんが大きな愛情とともに描いた折衷建築家は、藤井厚二、堀口捨己、吉田五十八、村野藤吾、アントニン・レーモンド、シャルロット・ペリアンの六人でした。
以下に、特に印象深かった、隈さんの言葉をいくつか引用させていただきます。
民藝と考現学が関東大震災直後に活動を開始したことは、注目に値する。(略)災害による建築不信とモノへの傾斜が、日本という災害多発国の文化を動かしてきたと僕は考える。
建築を新しく手に入れることが可能になった人々は「小さな建築」を作り始める。その「小さな建築」にふさわしいデザインとしてモダニズムは生まれ、急激にパワーアップしていった。その意味で様式建築からモダニズムへという転換は書院造りから数寄屋建築へという転換によく似ている。モダニズムとは西欧における数寄屋建築だったのである。
(格差が拡大する一方の)昭和から平成へという時代の大きな流れに対して最も批判的な目をもっていたのは、残念ながら建築家ではなかった。建築家は、磯崎や黒川のようにコンクリートによる「縄文化」を先導し、縄文が飽きられると、それをアートというキャッチフレーズに置き換えることで、より大きな建築、よりアーティステックな都市を作ることに加担し続けた。その流れに違和感を持つ建築家たちは「和風」という領域に閉じこもって、日本の伝統建築という豊かな資産を、趣味的で商業的な世界に閉じ込めて衰弱させ死体化させた。
ここで「縄文化」というのは、岡本太郎がその美を発見した「縄文」を安易に現代と直接的に結びつけることで、弥生以降の長く豊かで多彩な日本の伝統文化の数々を捨ててしまったことを指します。隈さんは丹下健三のことは高く評価していますが、その弟子だった磯崎新、黒川紀章の両人については、日本の建築を間違った方向に導いた建築家だと、否定的に見ていたんですね。現代の日本の建築家はほとんど磯崎さんの影響下にあるわけだから、大胆な発言です。私が尊敬する安藤忠雄さんの名前はあがっていませんでしたが、たぶん、否定的なんでしょうね。

今月読んだ三冊目の新書本は、臼杵陽「世界史の中のパレスチナ問題」でした。昨年のロシアによるウクライナ侵攻から始まった戦いが今も終わらずに泥沼化する中で、イスラエルによるガザ侵攻まで始まってしまった。すでにガザ住民の死者は、女性や子供を含めて、2万人を越えています。それなのに、いつ停戦できるかわからない。もう70歳を越えてしまった私が生まれる前からイスラエルとパレスチナの間の紛争は続いているわけですが、これだけの死者が出たのは初めてだと言われます。どうしてこんな事になったのか。イスラエルとアメリカを除く世界中が一刻も早い停戦を望んでいるわけですが、イスラエルはテロリストであるハマスを殲滅するまでは戦いを止めないという。遠い日本にいて、無力感と絶望感にかられるばかりですが、そこまでイスラエルが頑なになる理由はなんだろうと、この10年前に出版された本を手に取りました。この問題の歴史的背景がよくわかりましたが、それだけにこの問題の根深さもよくわかりました。
10年前から著者の臼杵さんは絶望感を抱いていたようです。以下は、この本を読んだ私の感想で、臼杵さんが書いていることではありませんが、歴史をひもとけば紐解くほど、歴史の糸が余りにもこんぐらかっている事がわかります。その解決のためには、それこそアレクサンダー大王の剣が必要になるでしょう。パレスチナ問題とは、もともとは帝国主義国家だった当時のイギリスが造り出した問題ですが、今では誰も解けない問題になってしまいました。普通に考えれば、イスラエルとパレスチナ2国家併存を決めたオスロ合意の時点に戻るしかないわけですが、当事者のイスラエルが拒否している限り、それは不可能です。しかも、オスロ合意を認めないネタニヤフ政権になって以来、数十年にわたって、イスラエルはヨルダン川西岸のパレスチナの領域に入植をすすめ、今では、パレスチナ国家を独立させるといっても肝心の国土がほとんどないのです。現状は、イスラエルという単独の国家の中に、その最大のものとしてのガザを含む、パレスチナ人の居留地があるという、かつての南アのようなアパルトヘイト国家になっていると見た方がよいようです。
イスラエルは、ユダヤ教徒の中でも特に狂信的なシオニストが中心になって建国した国です。イスラエルの存在を認めないハマスと共存することは絶対に不可能です。では、アラブ諸国から嫌われながら、アメリカはどうしてイスラエル支持をやめないんでしょう。臼杵さんは、強力なイスラエル・ロビーの他に、アメリカにおけるキリスト教の宗教右派の存在の重要性を指摘します。キリストの再臨を信じる彼らにとって、ユダヤ民族がイスラエルの地に戻ることが絶対に必要なのです。実は、日本の無教会派のクリスチャンにも、同じ考えを持つ人たちがいるといいます。ため息が出ますね。パレスチナ問題は政治問題であるとともに宗教の問題なのです。これでは解決の方法がない。でも、諦めてはいけない。毎日のようにガザの子供たちが死んでいるのだから。でも、私たちに何ができるんでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
