
今月読んだ本 (7)
2023年10月
今月もkindleで読んだ英語の本の話から始めます。今月は、WALTER ISAACSONの"ELON MUSK"を読みました。何カ国語に訳されたのか知りませんが、世界同時発売されたこの本の日本語版は上下二巻。kindleだと厚みがないので長さがよくわからないのですが、読んでも読んでもなかなか終わらない長い本でした。でも、日本でもかなり売れたようですね。なにしろ、現代の世界で最も興味深い人物の一人であり、間違いなく歴史に残る事業家イーロン・マスクの伝記ですから。しかも著者が、スティーブ・ジョブスやレオナルド・ダヴィンチの伝記を書いたアイザックソン。これは期待しない方が無理です。期待通り、とても面白く読みました。アイザックソンは2年間もマスクに密着して取材し、マスクの紹介で、マスクの家族や友人、元の部下などとも膨大な取材を重ねたそうです。マスクは今回の本の内容については一切口出ししなかったとか。たぶん、著者がマスクが尊敬するジョブスの伝記を書いたアイザックソンだからだったのでしょう。
アイザックソンの2年間の密着のおかげで、現在進行中の巨大なドラマ、マスクによる旧Twitter(現X)の買収についての生々しい内幕を知ることができましたし、現在大きな話題を呼んでいる生成AIに、マスクは早くから関心を持ち、ChatGPTで有名なOpenAIの共同創業者だったということを知ったのも、この本を読んだ収穫です(マスクは、生成AIの危険性を早くから指摘していた)が、私としては、先々月に読んだ「創始者たち」で知ったPayPal時代のマスクの前と後を知って、彼の人生が繋がったことの喜びの方が大きかった。(マスクはまだ若いので半生に過ぎませんが。)この本ではまず、南アフリカで生まれ育ったマスクの少年時代が語られます。アイザックソンが強調するのは、父親の性格と行動の異常さです。父親本人にも取材しているのにここまで書くかと思えるほどですが、このエンジニアだった父親の起伏の激しい性格が後のマスクの人格形成に大きな影響を与えたというのが、アイザックソンの考えのようです。マスクは自らをアスペルガー症候群だと言っていますが、さすがにそれは父親からの遺伝ではないでしょう。いずれにしても、この伝記は、今後、起業家をめざす人たちだけではなく、精神科医らにとっても興味深いものになっているのではないでしょうか。
事実、この父親から離れるために、少年のマスクはカナダの親戚を頼って、一人で南アフリカを離れました。(後に母親と弟らも合流しました。)後にアメリカの大学で学び、アメリカ人女性と結婚することでアメリカ国籍を取得することになります。時代と環境がマスクの味方をしました。父親に似て理数系に優れていたマスクは、学生時代に自らプログラムを書いて起業して成功し、その株を売却することで大金持ちになります。その後に起業したのがX.comで、後にPayPalと合流することになります。このあたりの時代のことは既に「創始者たち」で読みました。その後の事です。PayPalを「追放」されたマスクは、SF少年だった頃からの夢である宇宙に目を向けます。まず、火星に人類を送るためにSpaceXを起業しますが、ふとした偶然から電気自動車のベンチャー起業Teslaの出資者となり、ついには自分の会社にしてしまいます。この時点ではまだ海のものとも山のものとも分からなかった二つの革新的な新興企業を二つも同時に経営することになったマスクは、当然ながら、苦境に陥ります。倒産するかもしれないと覚悟したマスクに救いの手を差しのばしたのが、かつてPayPalを追い出した、ピーター・ティールら、かつてのPayPalマフィアだったという部分には思わずほろりとしました。
現在、世界一の金持ちであり、現今のTwitter(X)をめぐる一連の騒動を除いて、順風満帆のように見えるマスクですが、ここまで来るには、当然ながら、いくつもの凄まじい試練があったのです。それらを乗り切ってきたのは、なによりもリスクを愛する、マスクならではの闘争的な性格があったからなのでしょう。とても私のような常人には無理なことです。たぶん、現代の日本が経済的に凋落しているのは、日本にはマスクのような起業家がいないからなのでしょう。この他、この本には、マスクが地球上の人口減少を憂い、自ら、試験管ベビーの形で何人もの女性たちとの間に子供を持っていることなど、プライバシーに関することも驚くほぼ率直に書かれていました。またマスクは、スティーブ・ジョブスと同じく、尊敬すべき企業人である反面、従業員にとっては悪魔のような経営者であり、彼らにとても無理だと思える課題を次々に与えては、それが達成できないとなるとすぐにクビにするというような、日本の企業ではとても出来ないことをする人物であることも正直に書かれていました。マスクはSF少年がそのまま大きくなったような夢想家であり、織田信長やカエサルと同じような現場の人でもあります。社長室でいばりちらすタイプでは全くない。だからこそ、そんな暴君にも付いていく親衛隊員のような社員も多くいたのです。マスクがTwitterの社員の多くを解雇した時、そんな親衛隊員がSpaceXやTeslaから駆けつけて、Twitter(X)をなんとか機能させ続けたというわけです。いずれにしても、とても面白い本でした。それにしても、ジョブスと違って、マスクはまだまだ若くて元気です。アイザックソンは、もう一冊、これと同じくらい長い、マスクの後半生の伝記を書くことになるんでしょうか。

次に読んだのは新書の鼎談本、養老孟司+茂木健一郎+東浩紀「日本の歪み」です。養老先生と茂木さんの親しい関係は以前から知っていましたが、ここに東浩紀さんが加わることはちょっとした驚きできた。若い頃の東さんなら考えられなかった組み合わせです。でも、この三人の発言は食い違うどころか、なにやら和気藹々としたものでした。若い二人が養老先生に話しを合わせているというわけではなく、本当に共感している感じなのです。この本のまえがきで養老先生はこう書いています。「人文科学系の人が私は苦手だったが、東さんは良い意味での常識家で、安心してお話ができたと思う。」話題は多岐にわたります。先の戦争の話。戦争の死者と宗教の話。憲法の話。天皇の話。現在と未来の戦争の話、等々。ですからこの本の内容を要約するのは無理だし、意味もありません。ただ私は、この「三賢人」の清談をそうだそうだと静かに聴くだけでした。養老先生以外は年下なのに。つまり、ほとんどの発言に異論がありませんでした。ここでは、この本で記憶に残った発言をいくつか書き抜いておきます。
茂木:この日本の歪んだ暗闇に光を照らすのは、右とか左とかそういうイデオロギーではなく、インテリジェンスだと信じている。
東:でも日本は、1945年にそれまでの日本を否定してしまった。(略)日本は「日本のものはだめなのだ」というシンプルな歴史観を作ってしまった。そこに戻れないので、なかなか出口がない。
養老:まさにそれが「日本の歪み」の本質です。
養老:身の丈に合っていないんですよ。「経済大国」とか、経済なんて変なモノサシで見るから錯覚が起こっているだけで。
東:日本は大国に向いていない。やはり、十九世紀に清帝国が崩壊したのが大きかったのでしょうね。本当なら「清vs.ヨーロッパ」になっていたはずですから。
養老:その通りですね。
東:あのとき清がグズグズになってしまったので、辺境の国・日本も頑張らざるをえなくなってしまって、明治維新が起きた。そして中国まで手に入れようとしたわけが、どうもおかしい。(略)
東:この国には、本当の意味で「公」のことをやろうとしたら「私」でやらねばならないというねじれがある。これは非情に不幸なことだと思います。
茂木:それはある。そして同意だけを求めていくと、どんどんつまらなくなる。尖ったものが、あとから文化的に広がって、追認され、スタンダードになっていくという文化のメタボリズムが欠けてしまう。
東:公共的であることと、全員が同意することはイコールではありません。日本の未来のために問題提起したり、未来を見据えたりすることは、必ずしもその時代に全員が同意することではないはずです。でも、日本でそれをやろうとすると、私費を投じて世論から身を引き離さないといけない。
東:知というのは後から来るものです。哲学や社会学はあくまでも「後付けの分析」として使うべきであって、未来を作るために哲学や社会学を振りかざすのは危険であるというのが、二十世紀の共産主義の失敗が残した最大の教訓なんじゃないでしょうか。にもかかわらず、二十一世紀に入って、エリートが知識によって社会を導くというタイプの思想が戻ってきつつあることは憂慮しています。シンギュラリティとかAIとかの話がそれです。ただ、そこで使われる知識は社会学的・哲学的なものではなく、理学的・工学的なものに替わっています。

次に読んだのも新書本。佐藤信編「古代史講義」【海外交流篇】。古代史の本を読むのも私の楽しみのひとつで、最近では、関祐二さんの本などを愛読しています。関さんは大学に籍を置く学者ではないので、いつも大胆な仮説を展開するところが面白い。まあ、半分娯楽として読んでいるわけですが、関さんの本は決してトンデモ本ではなく、ちゃんと史料はおさえている。つまり、虚実のあわいにある魅力があります。今回読んだ本は、ちくま新書の歴史講義シリーズの一冊。古代史講義としてもこれが5冊目の出版になるので、いかに古代史が読者に人気があるかわかりますね。邪馬台国の話も面白いが、私が興味を持っているのは特に国際関係ですから、この本はぴったりでした。
日本古代史は東アジア国際関係史でもあります。最近ではイタリアを加えて6カ国になったようですが、ラグビーでかつて5カ国対抗というものがありました。イングランド、スコットランド、ウエールズ、アイルランドとフランスの5カ国(ラグビーやサッカーでは、イングランドとスコットランド等は別の国の扱いなんですね。)による対抗戦です。東アジアの古代史においては、中国は別格ですが、高句麗、新羅、百済と日本(当時は倭国)が互いに闘ったり同盟を結んだり、さまざまな交流をしていた。そこが面白い。でも、この本の執筆陣は真面目な学者ばかりなので、原則として、ちゃんと史料にあることしか書かない。読者サービスの大胆な仮説は封印。そこがちょっと歯がゆいところでした。それでも、いろいろ勉強になりました。
特に、新羅の話。「日本書紀」を書いたのは百済からの渡来人だし、仏教も百済から来た。少なくとも文化的には日本人はほとんどが百済人の子孫である。今でも一部の日本人が韓国・朝鮮人に反感を持つのは、新羅によって朝鮮半島から追われた百済人としての恨みを深層に抱えているからだという説があって、私はほとんど賛成しているんですが、この本の第7講にちょっと面白い記述がありました。柿沼亮介さんの「新羅と倭・日本」という章です。朝鮮半島を統一した新羅と日本との外交関係は8世紀になって悪化します。日本は新羅からの使節を何度も追い返すし、遣唐使の航路も、かつては朝鮮半島の沿岸を航行していたのに、東シナ海を横切る危険な航路に切り替えざるをえなくなります。でも、民間の商業活動や文化活動においては両国の関係はかえって強まっていた。円仁の「入唐求法巡礼行記」には、唐に在留する新羅商人のおかげでさまざまな活動が出来たと書かれているといいます。当時の新羅商人は日本を含む東アジア一帯にネットワークを築いていたんですね。ただ、9世紀に入って新羅の国内が混乱します。賊徒化した新羅人が、日本の島嶼部などを襲うようになりました。現在の日本人の朝鮮半島の人々への嫌悪感と排外意識の淵源がこのあたりにあるのかもしれないというわけです。これは新しい視点でした。
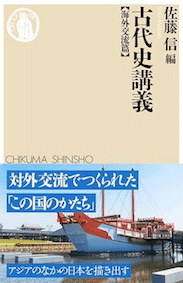
次に読んだのは、岡田暁生+片山杜秀「ごまかさないクラシック音楽」でした。私の世代は後にビートルズ世代などと呼ばれたりもしますが、大正教養主義の影響を受け継いだ最後の世代でもあって、若い頃は、クラシック音楽の知識を持つことが一人前の大人への道だと思っていました。お金がなかったのでコンサートにはほとんど行けなかったし、LPレコードもわずかしか買えなかったけれど、サラリーマンになってからは、給料が出ると安いCDを見つけて、バッハ、ベートーヴェン、モーツアルトなどを中心に、かなりの数を集めました。「指輪」などのワーグナーの楽劇やオペラも、DVDでかなり揃えていました。丸谷才一さんの影響もあって、音楽評論家の吉田秀和さんを神様のように尊敬していて、その全集も全巻ではありませんが持っていました。それなのに、自分ではピアノも弾けず、楽譜も満足に読めない。まあ、実践のともなわない、半可通のクラシック音楽ファンだったわけですね。
岡田さんと片山さんは私よりも10歳ほど年下ですが、現代最高の音楽批評家です。片山さんなどは、音楽批評家は肩書きの一つでしかない、本職は思想史研究家の化け物のような万能学者ですし、岡田さんも名文家として知られる音楽学者です。二人とも驚嘆すべき博覧強記。だから、この対談も単なるクラシック音楽談義ではなく、人物論であり歴史談義であり文明論でもあり、しかも楽しいエピソード満載。実に興味深いものでした。書名の「ごまかさない」というのは、専門家というのは知識があればあるほど物事を断定できなくなるものだけれど、ここは読者のために思い切って明確に言おうという意味のようです。だから、この対談では、自身の音楽の嗜好についてもはっきりと述べられていて、今まで聞いたことがないような斬新な創見に満ちていました。目からウロコが何枚も落ちました。クラシック音楽の世界は実に奥深い。
この本の帯には、「最強の入門書!」とありますが、対談だから決して難解ではないけれど、入門書としてはあまりに高度な内容で、むしろ、私のように、いっぱしのクラシック音楽通だと自認しているような素人にとっての「再入門書」というのが相応しいと思います。私はもう年ですから、余生はバッハさえあれば、後のクラシック音楽はもう必要ないと思っていましたが、この本を読んで、もう一度、さまざまなクラシック音楽を聴いてみようと思いました。ご両人も言うように、クラシック音楽はジャンルとしてはもうとっくに終わっています。だからこそ今は、かつての教養主義から自由になって、自分の好みの音楽を見つけるチャンスなのです。広大なクラシック音楽の世界はまさに宝島なのですから。とりあえず、この対談でも言及されている、あの懐かしい大阪万博の時代に戻って、シュトックハウゼンなどを聴いてみようかな。岡田さんはコロナ禍の最中、かつて苦手だったワグナーをYouTubeで見続けたそうです。そういう気軽な方法もあるんだと知って、ちょっと心が軽くなりました。昔はクラシック音楽と付き合うとなると、ちょっと身構えて肩に力が入っていましたから。きっと日本人の西洋コンプレックスの象徴だったんでしょうね。

次に読んだのは、國分功一郎「スピノザ」でした。私はアインシュタインも愛読したというスピノザに昔から関心があって、若かった時に「エチカ」を読もうとしたことがあります。その時、いわゆる幾何学的様式で書かれた文章はとても格好良いと思ったんですが、内容の理解に関しては、まったくとりつく島もないという感じでしたね。何が書いてあるのかまったくわからない。自分には哲学の素質がないと痛感しました。そんな私にとって、数年前に読んだ、國分さんの「はじめてのスピノザ」は画期的な本でした。もともとNHKの「100分de名著」が元になっていることもあって、こんなにスピノザが解リ易くってもいいのかと思ったほどでした。今回の「スピノザ」は初心者向けから中級者向けになったということなのでしょうか。スピノザの全体像と思想がより明確になりましたが、歯ごたえが増した感じでもありました。ある意味で、かえってスピノザの思想が解りにくくなったようにさえ感じました。それでいいのだと思います。学者の仕事は、他の学者たちの研究成果を適当に案配して、そこに自分の思いつきをちょっと足してでっち上げるというような安易なものではなく、厳密緻密に原典を読みこむことで、新しい鉱脈を発見し、大量の岩石の中から一塊の金を精錬するような、粗雑な頭脳と移り気な気質を持つ自分のような人間にはとても出来そうもないプロの仕事なのだなと、改めて実感させてくれる読書でしたから。要するに、ちょっとしんどい読書でした。それだけに、スピノザが同時代人であるフェルメールの絵のモデルになったかも知れないというような、ちょっとしたエピソードが書かれているとほっとしました。ここで、本書から少し引用させていただきます。
自由は至福と同様、言葉で説明されるのではなくて、経験されるものである。(略)意識は我々の行為の決定に関わっている。意識は何をなしうるか。意識は自由をもたらしうる。だとすれば、我々が本当に『エチカ』を理解したと言えるのは、我々自身が『エチカ』の言う意味で能動的に生きて、ある時にふと、「これがスピノザの言っていた自由だ」と感じた時であろう。倫理学という実践的なタイトルを与えられたこの書は本当に実践的な書である。スピノザは言葉を用いて、言葉が到達しうる限界にまで、我々を連れてきてくれたのである。
國分功一郎さんは、東浩紀さんよりも年少の哲学者としては、現在、千葉雅也さんと並んで最も読まれている学者の一人です。私も「暇と退屈の倫理学」にはずいぶんと感心しました。かつては西田幾多郎や三木清のような哲学者が大きな影響力を持った時代が日本にもあったようですが、いつの間にか、その役割は、小林秀雄以来、文芸批評家のものになり、さらに最近では社会学者のものになっています。再び哲学者の時代がやって来るのでしょうか。この「スピノザ」には、「読む人の肖像」という副題がついています。そして、この本の最後にはこんな文章がありました。近代哲学の祖であるデカルトを読むことから出発して全く異なる哲学の可能性を示したスピノザについて書きながら、これは実は國分さんの自画像であり自戒の文章でもあることは言うまでもありません。
読む人とは、自分たちに託されたものを確かに受け継ぎつつも、その批判的検討を怠らない者のことである。読む人としての哲学者スピノザに倣いつつ、今度は、我々自身が、スピノザが遺した本を読む人となって、新しい哲学を作っていかなければならない。

最後は、東浩紀「訂正する力」。東さんは二ヶ月で三度目の登場ですね。この新書本は、先月紹介した「訂正可能性の哲学」の入門編あるいは実践編の位置づけだと思いますが、この本単独で読んでも面白くて有益な本だと思いました。実際、かなり売れ行きもいいようでご同慶の至りです。広く読まれるべき本だと思います。この本の内容については、東浩紀さん自身が「おわりに」で書いている以下につきると思います。
本書は語り下ろしです。聞き手と構成は、近現代史研究家として活躍中の辻田真佐憲さんにお願いしました。(略)結果は期待以上でした。辻田さんが引き出さなければ、ぼくが平田篤胤や司馬遼太郎について語る機会はなかったでしょう。本書は、ぼくのいままでのどの本ともまったく異なった、新しい東浩紀の本になっているのではないかと思います。ぼく自身が、この本によってまた新たに「訂正」されてしまったと感じます。
私もまったく同感です。この本がこんなに読みやすく説得力もあったのは、辻田真佐憲さんの力が大きかったと思います。それと、これは決して批判ではありませんが、この本では「訂正」という言葉や概念が、あらゆる問題の処方箋として使える万能薬であるかのように描かれています。これはなにやら松岡正剛さんが「編集」という言葉を使う時に似ているなと思いながら読みました。念のために書いておくと、松岡正剛さんは東浩紀さんの仕事を高く評価しています。余談でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
