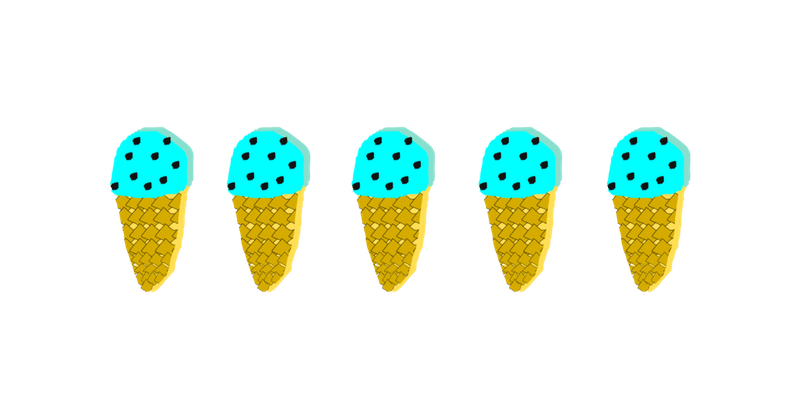
このアイス、好きなんだよね。
娘の習いごとに付き添ったときのできごと。
「春の短期集中レッスン」として、娘は体操教室に3日間参加した。跳び箱や逆上がり、側転など、今はまだうまくできない技ができるようになりたいようで、彼女は熱心に取り組んでいる様子だった。
3日目の教室が終わったあと、がんばったから、と自動販売機でアイスを買うことに。彼女は少し迷ったあと、カラフルなチョコチップが散りばめられた水色のアイスを買った。
「このアイス、好きなんだよね。ここで最初に食べたアイスだし」
車内でアイスを舐めながら娘がつぶやいた一言に、ぼくは少しおどろいてしまった。
「ここで最初に食べたアイス」って、いったい何才の記憶だ?
娘は今8才。
この施設にはプールもあり、水泳を習いに3年前くらいから時々訪れている。
そんな幼いころに食べたアイスのことを覚えているなんて。
37年以上生きたぼくにとっての5才の記憶と、娘にとっての5才の記憶の鮮明さを比べるのはハンデが大きすぎるとはいえ、当時の記憶なんてもはやほとんど思い出すことはできない。
それでもかろうじて思い出せるのは、保育園で友だちといっしょに固い泥だんごをつくっていたとか、さわると葉っぱが閉じる不思議な植物が園庭のはしっこで育ててあったとか、そんなささいな記憶だ。
もはや思い出すことのできない膨大な時間のなかで、わずかでも残っている記憶は、どういうわけか自分にとっては大切なもののようにも感じる。思い出せない記憶が多すぎるからだろうか。
泥だんごきれいにつくれたなぁとか、この葉っぱなんでうごくんやろ?というわずかに揺れた感情がどこかに引っかかり、自分にとっては捨てるに捨てられないものとして残っているのかもしれない。
当時の友だちの顔。
先生の名前。
母がつくったいつかの晩ごはん。
思い出せないことばかりなのに残っているささいな記憶が、たしかにある。記憶とは不思議なものだ。
彼女はふとしたタイミングで、またこのアイスを思い出すんだろうか。
これはあそこで初めて食べたアイス。好きなんだよね。
そんな、どうしようもなく些細なできごとだけど、なんだか大切なワンシーンに立ち会えたようで、ぼくは少しだけうれしくなった。
この記憶はいつまで残っているのだろう。それも楽しみである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
