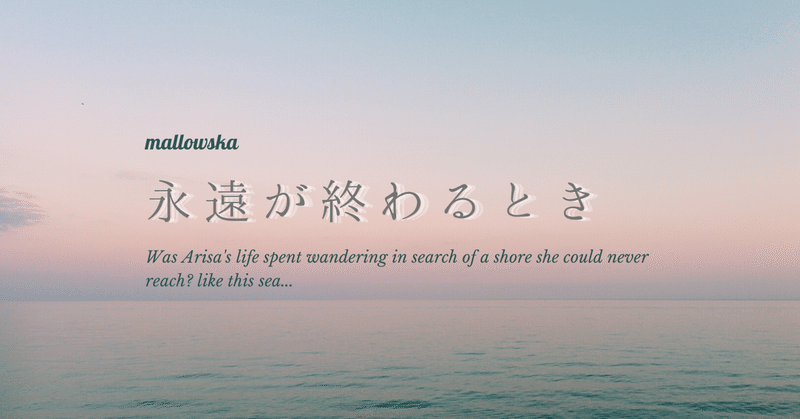
【連載小説】永遠が終わるとき 第三章 #1
3月にあった大きな組織変更から3ヶ月、6月のある日のことだった。
その日はイノベーション発掘のための異業種交流会に、斎藤室長の代理として参加していた。
協賛に大企業が名を連ね、参加企業はベンチャーも含め80社近かった。
当社も決して大企業というわけではない分、イノベーションには早くから着目し、重い腰になりがちな大企業と張り合うために、ベンチャーと手を組んでかなり柔軟に挑戦をしてきたと思う。
今まではこういったイベントは常に野島部長…当時は次長だったが…と共に参加していた。
彼の鋭い洞察力、それに反する直感力の絶妙なバランスで、次々と若い企業と協働プロジェクトを立ち上げ、大手企業のバックアップを取り付けたりしていた。
当社の手を離れて成長していくプロダクトもあれば、プロトタイプで終わったものも当然あるけれど、企業や優秀なリーダーとのパイプはそこで多く生まれ、会社としてもどんどん成長していくのを感じていた。
そういった特定の顧客以外の外部との関わりを持つのが企画営業部であり、そこに配属されたことは私の転職の大義を全うするものであり、そこのリーダーに野島部長がいたことは本当に大きかった。
彼のスマートな仕事っぷりは本当に流石だった。いつまで経っても私は隣で舌を巻くばかりだった。
けれどもう隣に野島部長はいない。彼は欧州で、今までそうしてきたように会社を更に大きくしていくことだろう。
私は組織変更後の挨拶も兼ねて、多くの企業に名刺を配った。
そこでも会社の代表として来ているのが私であることに、野島はどうした、という多くの声が挙がった。
あの頃野島部長の隣にいたのが私だということも憶えている人がいて、君も出世したんだなぁ、という人もいた。
そんな中、普段は接点がなかなか持てないような大企業の関係者と名刺交換をすることもできた。
そのうちの一人が、一代で巨大経営組織を築いた深山ホールディングスの会長の息子、深山仁だった。
渡された名刺の肩書はホールディングス本体の『COO』となっている。
「COOと言っても、まだまだ修行中の身でありますが」
そう言って少しはにかんだように笑う。ふわりとした髪、優しい顔立ちでスラリと背も高く、その第一印象だけでもタレント性のある人だと思った。
当社の事はある程度知っていて、野島部長の名前にも記憶があるという。
「僕は直接面識を持っておりませんが、弊社のグループ会社が参画したプロジェクトの陣頭を取られていた方だと伺っており、お会いしたいと思っていました。そうでしたか、今はベルリンにおられるんですね」
「申し訳ありません。私もまだまだ役不足で、野島の足元にも及ばず…」
いえいえ、と深山さんは両手を大きく振った。
「僕こそこんな肩書担っていますけど、本当にまだ現場から上がったばかりで、役不足も甚だしいです」
「そんなこと…」
いくつか研究課題となっている案件での協働プロジェクトが出来ないか、今回も実際に検討に入ってくれることになった。
斎藤室長は私に権限を一切譲渡してくれているため、野島部長に倣いたい気持ちもあって、推進を即決した。
仮の商談が成立し、ほっと一息つくと会はお楽しみの懇親会へと流れていく。
その立食パーティでも、深山仁は気さくに話し掛けてきた。
彼は私より4つ歳下の31歳で、日本の大学でMBAを取得をした後、イギリスに渡りオックスフォード大学院に進学している。
しかも日本では野島部長と同じ大学の出身だった。
「そうだったんですか、野島さんは先輩なんですね。ますますお会いしたかったな」
「お伝えしておきます。私も学生時代にイギリスに留学したことがあるんです」
「そうでしたか! 奇遇ですね! どちらで何を勉強されていたんですか?」
「エディンバラ大学で心理学や言語科学を学びました」
「エディンバラですか? スコットランドか。羨ましいですね。僕はオックスフォードで…何も面白みがないです」
「そんなことありませんよ」
御曹司のわりにはお金持ち特有のちょっとした仕草や言葉尻に嫌味を感じるようなことが全くない人だった。
女性も羨むような形の良いふっくらとした唇をしていて、瞳は大きくてはっきりしている。
可愛らしい人…御曹司で地位もあるし、さぞかし女性に人気があるのだろう。
プロジェクトが始まれば、現場の人とのやりとりになるだろうから、会う機会もそうないだろうと思っていた。
私の中に何かが残るようなことはないと。
* * *
そうしてプロジェクト発足の件を社に持ち帰る。
「今回も深山グループとタッグを組むことが出来ましたか。さすが野島さんの申し子だけありますね」
斎藤室長はそんな言い方をした。彼なりに精一杯褒めているのだとは思うが、いつも野島部長の名前を引き合いに出すことが私への当てつけに感じてならない。
「はい…、深山会長の息子さんが野島部長のことを少しご存知だったようで、話が早かったです」
「まぁでも今回は野島さんのお陰ではなく、前田さんの功績ですよ」
「ありがとうございます…」
「どうですか前田さん。今回の件、PM(プロジェクト・マネージャー)をやってみませんか?」
「えっ…私がですか!?」
「もちろん先方のメンバーと相談になるかとは思いますが、ぜひ立候補してきてくださいよ。僕の権限は全て前田さんに委任します。もちろん相談は受けます」
室長補佐とは役職ランク的にはそれほど高い位置にいるわけではない。いくら小規模なプロジェクトとはいえ、そんな立ち位置の私がPMなどとは…。
「前田さんは元々PMOの経験も持っているじゃないですか。野島さんでもあなたにやらせたと思いますよ。あの人は可能性のある人にはどんどん責任のあるポジションを与えてきたでしょう。飯嶌優吾が配属初っ端からリーダーに任命されたように」
「えぇ、まぁ…」
彼は彼で野島部長のことを非常に尊敬して慕い、部長もまた彼のことを優秀な人物だと認めていた。
「やってみてくれますか、前田室長補佐」
私は「はい」と頷くほかなかった。
* * *
後日、プロジェクトの詳細を詰めるために来社したメンバーに、まさか深山仁が自ら訪れるとは思わなかった。受付に現れた来客3名のうちの1人が彼だった。
「前田さん、先日はありがとうございました!」
「深山さん…まさか自らお越しいただくなんて…」
「初めはきちんとご挨拶も兼ねてお伺いしなくては、と思っていましたので」
相変わらず爽やかな笑顔を満面に浮かべてそんな挨拶をした。
深山さんは自らがCEOを務めるクリエイターグループ『JIN CHAOTIC Design』のディレクターとデザイナーを引き連れて来ていた。それぞれ名刺交換する。
今回のプロジェクトはビッグデータを用いた街づくりの一環として、プロトタイプのアプリを開発するというもの。
期間は4ヶ月で納期は11月末を予定する。それほど規模の大きなプロジェクトではない。
実施内容、体制、スケジュールについて大まかに話し合った後、
「今回のプロジェクト、よろしければ私にPMを務めさせていただければと思うのですが、いかがでしょうか?」
そのように申し出ると異論はないとのことだった。特に深山さんは拍手を交えて賛同してくれた。
「いいですね。前田さんのような聡明な方が牽引してくださるなら安心です」
「全く、役不足だと思いますが」
「そんなことはありませんよ」
こうして深山グループの御曹司、深山仁と "ビジネスの" 付き合いが始まった。
第三章#2へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
