
音楽家 佐久間順平と会った_3
ゆっくり話を聞きたいと思っていた人がいた。さりげない振る舞いや、ふと発する言葉に惹かれた。自分の場所で生きているように見えた。どんな来し方をしてきたのだろう。覗きたくなった。そんな人たちの探訪記「あの人を訪ねる」。
第四回には、佐久間順平クンに登場していただきました。
佐久間クンとボクとは、高校で同級生でした。高校時代に二人が組んだデュオ「林亭」の活動は、休止期間を挟みつつ今も続いており、以来50年余の永き時を重ねました。
そしてお互いの年齢は、70歳の古希になりました。この人生の節目のタイミングに、佐久間クンからじっくり話を聞いてみようとの思いから、このロング・インタビューがスタートしました。
3回目の今回は、長年にわたってサポートを続けた高田渡さんから与えられた影響について、そして高校時代からの友人であり、映画監督として世界的な名声を得た小林政広クンの映画作品において、音楽監督として仕事をした経験を語ってもらいました。
前編の
「音楽家 佐久間順平と会った_1」はこちらから、
「音楽家 佐久間順平と会った_2」はこちらからご一読ください。
詩と詩人を愛した高田渡。
大江田: お葬式のあと、奥さんの友恵さんがご馳走してくれたじゃない。
佐久間:いせやの2階で?
大江田: うん。葬儀委員長の筑紫哲也さんも来たりして大宴会だった。「あの時の飲み代を、オレ払います」と言って、家に行ったのね。友恵さんが「お茶でも入れますから」といって台所に行くじゃない。その間にね、棚に並んでいる渡さんの蔵書とレコードの背表紙をざっと見て、ああ、そうなんだなってすごく腑に落ちたんだ(笑)。
佐久間:ああ。
大江田: 左翼系詩人の詩集が並んでいてね。渡さんの魂の在処ってここなんだなということを、全身で受け止められる気持ちになったんだよ。こういう本を素朴に愛していたんだなって、思った。
佐久間:うん、うん。長兄の高田驍(たけし)さんが、自治労の委員長やってたでしょ。何万人のトップだよ。その影響もあって、やっぱり若い頃に共産党に近い考え方を持つんだよ。
大江田: へえ、お兄さんの影響があったんだ。最初に就いた仕事は、赤旗を刷っている印刷会社の文選工だったものね。
佐久間:そういう影響があって労働運動から労働歌、そしてアメリカの公民権運動で歌われたフォークソングに近づいたんだよね。
渡さんが、日本人の詩人の詩に曲をつけて、大事に歌うようになるじゃない。渡さんが歌った「ブラザー軒」の詩を書いた詩人の菅原克己さんにも、似たところがある。あの人も共産党の機関紙のガリ版刷りやってた。でもさ、ある時に共産党から除名されて、詩の運動の方に入ってくる。ああ、渡さんと似てるなと思ってね。
大江田: 音楽評論家の三橋一夫さんの場合も、似ているかもしれない。劇団プークに所属してスタッフの一人として脚本を書いたり、資料を揃えたりしていた。三橋さんの初期の著作の「フォーク・ソング アメリカの抵抗の歌の歴史」は、共産党系の出版社から刊行されている。三橋さんは、ピート・シーガーと知り合って交流していた。渡さんは17歳の時に、三橋さんの家を訪ねているよね。
三橋さんの本を読むとわかるんだけど、ある時に共産党に幻滅するっていうかな、なにか違うんじゃないかという思いを抱いて、ものすごく悩んで苦しんだ末に、共産党と袂を分かつんだよ。
佐久間:オレが勘違いしてたのがさ、「風」の歌詞は共産党系の詩人の書いた詩だなと思っていたのに、全然違ったことにびっくりしてさ。これは詩人でコピーライターの朝倉勇さんが、金子光晴さんのポスターに寄せた詩だったんだよね。
佐久間:金子さんは、人間の駄目さ加減を、ものすごく事細かに見てた人だよね。もちろん戦前の軍部も駄目だし、政治も駄目だし、官僚も駄目。寄ってたかって日本がぐちゃぐちゃになっていく様子をずっと見ながら、ろくでもないなって思いながら詩を書いてたよね。なぜ人間ってこうなんだろうってね。
大江田: そういう金子さんと比べると、渡さんの方がロマンチックというか、人間に夢を見てるというか、ささやかなところに喜びを見いだしているというかな、そんな感じがするけど。
佐久間:金子さんの詩をつらつら読んでいると、どこにも救いもないし、未来もないなっていう感じで書いている。絶望的なんだよ。でも、そこに何かしらの人間愛が感じられる。だからびっくりしちゃう。東南アジアの売春宿のね、女の哀しみを書いた詩にしても、そこに愛のある目線が感じられるんだな。
高田渡から与えられた影響。
大江田: 渡さんが見つけてくる日本の詩人に目を見開かされて、こんな人がいたんだって僕らが知らされたことは、いっぱいあったよね。
佐久間:ああ、いっぱいあった。だって、日本の詩人の詩に着目する人なんて、あまりいないんだよ。あのさ、韓国では詩がすごい流行ってて、みんなが詩が好きで詩集が売れるんだよ。ロマンチストだよね。そこら辺のことをもっとちゃんと知りたいと思ったのが茨木のり子さんで、韓国語の勉強を始めて、韓国の詩人の詩を日本語に訳した。
大江田: 茨木さんは、金子さんのことが大好きだものね。茨木さんや谷川俊太郎さんたち櫂の同人の詩人たちは、詩は人々の生活のためにあるべきだ、人々が生きていく時の力となる言葉として、日常的に目の前にあるべきだ、それが詩なんだって考える人たちだ。
佐久間:そういう考えって、歌と似てるんだよね。歌って、そういうものなんじゃないかな。ちょっとでもさ、人に夢と希望と勇気と生きる力が伝われば、いいわけじゃん。それ以上のことはあんまりないんだよ。
大江田: たまに佐久間が「所詮さ、歌なんだからさ」という表現を使うことがあってね、どういう思いでこの言葉を使っているのか、昔からずっと気になってた。「所詮さ、歌なんだからさ、いいんだよ」なんて粗末にしてるかのように言いながら、実はとても大事にしてるんだよ。
佐久間:人間の作るものってさ、ある種は「所詮」なんだと思うんだよね。残るものは、何一つないと思う。でも、もしも少しだけでも残るものがあるとしたら、それはそれで良かったってことじゃないかって、オレは思っててさ。例えばキリストの教え、ブッダの教え。教えとして数千年残っているかもしれないけど、あと千年たったら消えるかもしれないんだよ。でもその間にさ、何か少しでも人を助けたりできるんだったら、それはそれでいいことかなと思うんだよね。
大江田: 佐久間順平として高田渡から与えられた影響を感じますか?
佐久間:そりゃ、常に思ってるよ。つまり歌を届けること。その届ける時の方法だよね。相手に向かって、ぶつけるっていう感じだな。何かを演じたり、口先で歌うんじゃなくて、ぶつけるっていう感じ。それが大事なんじゃないかなあと思う。歌だけじゃなくて、演奏もそうだね。相手に届けるっていう気持ちがないとさ、届かないんじゃないかな。渡さんは、届ける気満々だったような気がしてさ。
あの人さ、寂しがり屋じゃない。だから人が好きなんだよね。「あんたのことが好き」っていうのが表に出ちゃうからさ(笑)。聞いてる皆んなも、好きになっちゃうんだよ。


小林政広の映画作品で音楽を担当した。
大江田:ところでここで小林政広との話をまとめて、聞いておきたいんだけど。小林とは学生時代に合宿したり、バンドやったりという付き合いがあった。小林は高校卒業後に大学に進学しないで、渡さんとライブハウスを廻って歌ったりしていた。20歳くらいで、そろそろ歌には見切りをつけようかということになったって、自伝に書いている。
佐久間とはだいぶブランクがあってのち、小林が撮ることになった映画の音楽制作をしてくれって頼まれたんだよね。
佐久間:うん。小林はあの頃は東京の杉並に住んでいて、ちょっと打ち合わせに来てくれって連絡があった。鍋をやりながら、「こういうのを撮るんだけどさ」なんて、言うんだ。後に出来上がった映像を見たら、なんだよ、このマンションで撮ったんじゃないか、自宅が撮影場所かよって、笑っちゃったよ(笑)。
彼の初期作の「CLOSING TIME」(1997)だね。オレが44歳の時だったんだな。自主制作の映画でね、主役が深水三章さん、マスター役に中原丈雄さん。ほかに夏木マリさん、北村一騎さんなどが出演していた。
大江田:小林が映画を撮るとなると、名のある役者さんたちが来てくれてるって、いいよね。
佐久間:うん。自主制作の秘密っていうのかな、役者さんが何らか興味を持ってくれて、ほとんどギャランティもないような映画に出てくれる。深水三章さんは、知名度があったけど、北村一騎さんはまだ無名だったかな。夏木さんは、大ヒットした歌手だったしね。面白いよね。
大江田:テレビドラマのシナリオライターをしていた10年間で貯めたお金を、すべて吐き出したらしいね。音楽予算はないけど、やってくれみたいな依頼だったの?
佐久間:そうそう。どういうものが欲しいのかって聞いたらね、あいつが出してきたのがさ、ヨーロッパ映画のクラシカルな弦楽アンサンブルのサウンドだったのね。そうか、似てればいいんだなと思って(笑)、家で宅録した。その頃はまだデジタル機器はなくて、アナログの4チャンネルのカセット・レコーダーを駆使して作ったのね。
小林が映像を撮るときにはね、これを撮ろうというテーマが決まっていて、そのテーマに合う音楽を、ずっと聞きながら撮影する。もしくは頭の中に巡らして、撮ってるらしいんだな。サン=サーンスの「動物の謝肉祭」の「水族館」を使いたいとか、言うんだよ(笑)。あいつは言うだけだからさ(笑)。しょうがないからスコアを買ってきて、譜面を見ながら音楽を聴く。するとね、これはギターでいけそうだなと思った。それでファースト・ラインとセカンド・ラインをガット・ギターだけで録音した「水族館」を渡した。そしたらさ、あるときアイツが登壇する映画祭のコンペティション会場のBGMに、オレが作ったその音源を使ってるんだよ(笑)。まったくさ(笑)。
大江田: 「愛の予感」(2007)の時には、ラッシュを見た佐久間が、「これには音楽入れなくていいよ」って言ったんだよね。
佐久間:あまりにも、ストイックな映画だからね。音楽で色つけちゃうんじゃなくて、もうモノクロームのこの感じでいいんじゃないのって、言った。映像作品で何を人々に伝えたいのか、どのように伝えたいのかっていうことが、まず前提としてあるよね。音楽なんて補助だからさ。何をどう伝えたいのか、よく見えてこないときに、どのように補助していいかわかんないから、「音楽が無い方がいいよ」とか言っちゃったんだけどさ(笑)。そしたら、小林は「あ、そーか」みたいな反応だったな。
大江田:映画音楽家として佐久間を起用しているだけじゃなくて、音楽が必要かどうかも含めて、佐久間が相談相手だったのかな。
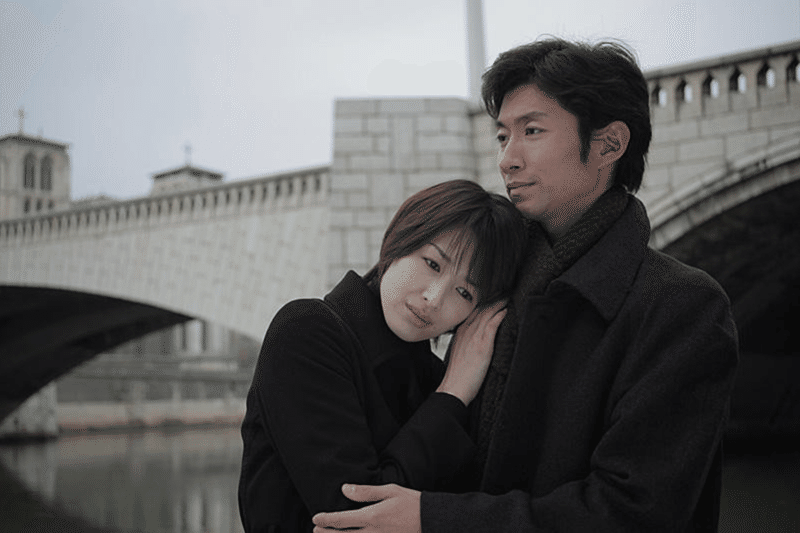
佐久間:「白夜」(2009)の時にも、クラシックを欲しがるんだ。今度はサン=サーンスの「白鳥」を、「あれなんだ」って言うんだよ(笑)。しょうがないから、またスコア買ってきて、なるほどこうなっているのかって思いながら譜面書いて、弦楽三重奏でやったかな。
大江田: 原曲のままのカタチでやったの?
佐久間:そうだよ。ほぼサン=サーンスの「白鳥」のままだよ。
そのほかオーダーされた音楽のすべてを、7、8時間かけて録った。「じゃあ、これでいいね」って帰ろうとしたら、「ここにさ、もうちょっと何か欲しいんだよ」って言い出したんだ。夜の喫茶店に入ってきた男女2人が、温まるシーン。スタジオの予定時間はもう過ぎているんだけど、しょうがないからさ、車に楽器を取りに戻って、自作のボサノヴァの曲をソロで弾いた。「これは?」って聞いたら、「ああ、これでいい」って(笑)。
映画「春との旅」での音楽作り。
大江田: 「春との旅」(2010)の音楽制作のとき、林亭の練習が終わって帰り際に、「明日から3週間、他の仕事を全部断って小林の映画に没頭するんだ」ってキミが言ったことがあったんだよ。他のことを一切自分の体から抜いて、小林の映画のことだけを考える時間を作る。そこまで小林との一体感を持って映画の音楽を作る、さらには音楽を考える試練を自分に与える。佐久間の言葉からそう感じて、オレはすごく感心したんだ。
佐久間:「春との旅」ではスポンサーが付いて、ギャランティも確保できたんだ。役者さんのギャランティも、それなりだったみたい。でもこっちの音楽予算はさ、今回はこれこれでって言って、それで全部まかなえって言うわけ。あいつはもう、どんぶり勘定だからさ。
大江田: スタジオ代もミュージシャンへの支払いも、エンジニア代も佐久間のギャラも、なにもかも全部?
佐久間:そうだよ。映画音楽の制作ってさ、音楽監督がいて、作曲家がいて、ミュージシャンを手配するスタッフがいて、写譜屋さんがいて、スタジオを押さえるスタッフがいる。本来はさ、そういう風に仕事が流れていくでしょ。それをさ、全部、オレがやらなきゃならないわけ。
しょうがないからさ、予算組みから始まるわけよ。これだけは大編成で録りたいから、第一バイオリン6人、第二バイオリン4人、ビオラ2人、チェロ2人のストリングス奏者を頼もう。ピアニストは江草啓太さんに、スキャットは李政美さんに頼む。残りはなるべく自分で録音する。そうしようって決めたんだ。一口坂スタジオの方に、大きめのスタジオの使用時間とスタジオ代の相談をしたら了解してくれたので、スキャットとピアノとストリングスを、"せいのドン"で録音したんだよ。別々に分けて録音する方法は取らなかった。
中島啓江さんの仕事の時に知り合いになったマネージメントの方のストリングスに、お願いした。「こういうもので、実はこれだけの予算なんですけど、やってやっていただけますか」って聞いたら、「あ、大丈夫ですよ」って言ってくれたので、ストリングスのアンサンブルの設定ができた。助かったよ。
それでね、大編成の曲から順番に何曲か録って、終わった人には順番に帰ってもらって、少しずつ小さな編成になる。最後はチェロと自分のギターだけを録音した。そういう風に段取って、数時間で終えたんだよね。
通常のレコーディングだったらさ、オレが書いたスコアを写譜屋さんがパートごとに書き起こしてくれるでしょ。でもさ、予算の限度があるから、自分でパート譜を書いた(笑)。譜面にミスがあると恥ずかしいから何回も読み直して、それぞれの弦楽器のパートを一回、自分で弾いてみたんだ(笑)。
大江田: いろいろと大変だねえ。
佐久間:なかなかねえ(笑)。
大江田: でも、小林とやる映画音楽の仕事は面白かったんでしょ。
佐久間:初めての体験だしね。なかなか、いいよね。
大江田: 小林と仕事をする以前に、TBSラジオでラジオドラマの音楽の仕事をしてるよね。「アドルフに告ぐ」(1993)、「明日の風」(1994)、「遥かなるズリ山」(1995)と、3年連続で芸術選奨の作品賞を受賞した作品で、それぞれ音楽担当だった。映画とラジオドラマの音楽制作は違うものですか。
佐久間:ちょっと映像とは違うんだよ。そういえば、渡辺謙さんが出演したラジオドラマ「北方謙三 三国志」(1999)の音楽もやったなあ。後にこうせつさんのコンサートに渡辺さんがみえて、その時にご挨拶したっけな。
映画音楽作家としての佐久間順平。
大江田:小林と一緒に映画音楽の仕事をして得たものは何だろう?
佐久間:映画というものがさ、自分にとってすごい遠いものだった。オレは観る側だったから。
作る側に回ってみるとね、いろいろと見方が変わったな。過去に自分が観た映画を思い返して、あの人々はどういう思いで作ってたんだろうなんて思っちゃってさ。
映画から超有名になった楽曲ってのが、昔はたくさんあったじゃない。映画音楽のヒットね。その最後が「ニュー・シネマ・パラダイス」(1988)なのかな。あの映画には、ものすごく感心したんだよ。イタリアのシチリア島の映画館のお話なんだけど、エンニオ・モリコーネの音楽がなんとも素晴らしくてさ。あれを最後に、映画音楽で印象に残ったものがない。その前の50年代、60年代、70年代の映画音楽っていうと、すごくいいよね。
大江田:インストルメンタル音楽作家の佐久間順平に、オレは昔からずっと興味がある。楽器を使って音楽を表現する人、佐久間順平にね。かつてキミが自分の映画音楽だけを収録して作ったCDRを、オレにくれたんだよ。それが、ほんとに良くてさ。多分そのCDRには、複数の映画に書いた曲が入ってるんだろうね。それを佐久間順平の音楽として、オレは聴く。このメロディーは暖かい眼差しを感じるなとか、また別の曲ではこういう悲しみってあるなあとか、そんな感想を持ちながら受け取る。キミの音楽は静かだからね。ずっと遠くの静かなものに向かって進んでいく音楽だから、そこがオレは好きなんだろうな。
佐久間:自主制作から始めた小林が、映画界のいろんな重鎮たちと知り合いになって、いつしかコンペティションに出したいっていう夢を持つ。いろんな人脈をたどって、コンペティションに出すための内容がどうあるべきかというノウハウを、少しずつ勉強した。何かの真似では駄目で、日本人としてのアイデンティティがないと成り立たない独自性ということを、彼はすごく考えたんだと思う。それで大衆受けはしないような、コンペ向きの映画というかさ(笑)、そういうものを作り始めたなって感じがしたよ。
大江田: 小林とはそういう話をしたの?
佐久間:してないよ(笑)。小林とは、たまに用事もなく会うこともあった。そういう時はさ、蕎麦屋なんだよ。飲みながら、ああでもない、こうでもないって、ただ世間話をするんだけどさ(笑)。じゃあ、もう一軒行くかなんて言って、何軒か行ったり(笑)。小林が、大阪に住んでたことがあったよね。たまには大阪で会うかってことになって、オレの仕事の翌日の昼に会う。昼間だけど、飲み屋を探した(笑)。それが昼からやってる老舗の飲み屋で、いい感じなんだよ(笑)。ひと段落して、ちょっと珈琲でも飲むかって心斎橋で美味い珈琲飲んで、じゃあもう一軒行くかなんてまた飲み屋に行くうちに、暗くなってきてさ(笑)、もうそろそろ帰るかみたいな感じで、オレは東京に帰るわけ(笑)。
大江田:二人でいったい何を喋ってんだよ(笑)。
佐久間:こんなことがあった、あんなことがあったって、映画をつくる上での細かいことが、小林の口からとめどなく出て来るんだ。「あの役者は実はこうこうで、ろくでもなかった」とか、「仲代達矢さんは30秒のシーンに3分もかけたんだぜ。どこで切れって言うんだよ」とか、そういう役者と監督の丁々発止の戦いの話も出てくる(笑)。役者はこう膨らました方がいいんじゃないかって思うけど、そんな長さはとれないって監督は思うとかさ、すごい面白い話なんだよ(笑)。
大江田: いやあ、いい話をいっぱいしたんだねえ。
TBSテレビで深夜に放送されていたR30っていう番組に小林が出演したことがあって。
佐久間:ああ、国分太一くんが司会をするインタビュー番組でしょ?
大江田: うん。「自主映画も撮ってらっしゃった小林さんです」って紹介されると、「自主映画なんかじゃない。自費映画だ」って小林が言うんだよ(笑)。
佐久間:(笑)
大江田: 「もう1回やり直しさせてください」って言う役者がいるけど、「お前にやらせるか馬鹿野郎。フィルム代がいくらかかってると思っているんだ」って内心でつぶやくという話もしてた(笑)。あの頃は、まだフィルムを現像する時代だから、経費がかかっていたんだろうね。小林があれこれ悪口を言いながら映画作りの話を喋ってるのが、おかしくてしょうがなかったよ(笑)。
佐久間:10年前からオレは自分でCD作るようになって、出来ると小林には送ってたんだ。そしたらどのアルバムの時だったかな「やっと佐久間の歌が、聞こえるようになってきました」って感想をよこしたんだ(笑)。
大江田: 音楽を必要とする映画を撮り始めて以降は、2006年の「幸福」を除いて、小林は佐久間以外の音楽家とは、組んでないんじゃないの?
佐久間:そうなのかな。
2003年ごろに、小林は糖尿病になった。糖尿病の薬ってさ、症状を抑えることはできるけど、病気そのものはなかなか改善しないらしいんだ。基本は食事療法、運動療法だから。途中からもう薬をやめてさ、食事制限して、そしてとにかく歩くという療養をずっと長く続けていたんだけど、そうこうしてるうちに大腸ガンになった。手術をしたという連絡があって、お茶の水の病院に入っている時に、見舞いに行ったんだ。
その2日前に、オレは熊本でのこうせつさんの野外のコンサート「南こうせつコンサート in 産山村」の日に、ちょっとした段差につまずいて、足首を骨折した。骨折直後は、ちょっと痛いなみたいな感じしかなくて、すぐにはわからない。リハーサルを終えて、昼ぐらいから本番。間奏のときにオレはステージの前方に出てって、演奏するのね。2曲ぐらいは前に出られたんだけど、3曲目ぐらいからもうひどい痛みで出られなくなっちゃった。スタッフに椅子を頼んで、その後は最後まで座って演奏した。終演後も、楽屋まで歩いていけないほど痛い。楽屋でも痛みで真っ青になった。その夜に別府の病院に行ったら、「立派な骨折です」って言われて(笑)、その場でギプスをつけてもらった。それからしばらくは、松葉杖生活だよ。みんなは打ち上げに行っちゃったんだけど、オレはうどん一杯を食べて(笑)、ホテルの部屋で寝たんだ(笑)。
次の日に東京に帰ってきた。その翌日は監督の代島治彦さんが高田渡さんのライブを撮影した映画「まるでいつもの夜みたいに」(2017)の上映後トークショーに、出演する約束をしていた。自分で車を運転して、松葉杖ついて劇場に行くわけ(笑)。代島監督の娘さんがインタビューする、ほんの5分か10分のトークだった。それでその足で、小林のところに行ったんだ。
佐久間:松葉杖ついて見舞いに行ってるっていうのが、なんだかおかしくてね(笑)。小林は喜んでたけど、手術の後だったし、やっぱりちょっとつらい状態だったな。糖尿病を併発してるからさ、どうしても気分がすぐれないし、元気がない感じでもあった。少し喋って、また来るねって帰ったんだ。
大江田:2017年の5月のことかな。それが最後なの?
佐久間:そうだなあ、最後かもしれないな。
小林政広は、やりたいことをやった。
大江田: 2022年の夏に亡くなってしばらくして、佐久間が小林の歌を特集するライブを組んだよね。その時のMCで、彼は自分が撮りたい映画は全部撮ったんじゃないかみたいなことを、ポロッと言ったことがあるでしょう。
佐久間:うん。
大江田: やるべき仕事を果たした人だって。
佐久間:やりたいことの全てじゃないよ。でも、やりたいことをやったとは、言えると思う。出来るところまでやったんじゃないかって、そんな感じはするな。
あのテンションの凄さをどう説明すればいいんだろうな。映画の現場に入る時には、まず台本からシーン組みをするじゃん。撮影場所と撮影する時間を決める。もちろん予算もあるから、無尽蔵に出来るわけじゃない。撮影場所と必要なスタッフと日数、それから移動の車と宿泊の宿を手配する。そして費用の計算をする。天候の具合もあるし、いろんなことがあって、予定したスケジュール通りにはいかないんだけど、それをもう何とかやりくりして予定した日数で撮り終える。その時のテンションがさ、もうすごいよね。予算組みとスケジューリングといろんなことで、小林の頭が爆発しそうなんだよ(笑)。おいそれと声なんてかけられないぐらいのテンションでさ。食うものは卵かけご飯、そしてタバコと焼酎。あとは珈琲(笑)。もう体にとって、ろくでもないよね、どう考えても。映画監督なるものが、みんな不健康に見えるんだけどさ、しょうがないと思うんだよ、オレは(笑)。もういつまでもずっと考えて考えて、鬱屈して鬱屈して、発散する場所がないよね(笑)。
ところがさ、ミュージシャンってさ、発散するじゃない(笑)。健康的なのよ。
だからさ、小林は大変な仕事を選んだな、偉いなあって思うわけ。
彼は、最初に映画監督のトリュフォーに憧れた。トリュフォーの映画を見てさ、人に楽しませる、人を惹きつける、そういうものが作れたらなって思ったんだろうな。オレはやりたいってね。
そういえば一回だけだけどな、すごくぶつかったことがあるんだ。あまりにも訳のわかんないことを小林が言う。オレは音楽制作のヒントが欲しいから聞くんだけどさ。しまいにはアイツがプッツンと来てさ、「台本に全部書いてある」って言い出すんで、「いや、これ読んでもわからんよ」って、こっちも突っぱねた。だんだんと険悪になって、「もういい」ってなったんだ。「もう二度と話さない、お前とは」(笑)。お互いに、啖呵切って終わり(笑)。
大江田:でも仲直りしたんでしょ?
佐久間:まあねぇ。時間が経ってからねぇ。
大江田:なるほどね。
もう30年近く前のことだけど、吉祥寺でライブをする小林に呼ばれて、オレが歌いに行ったことがあった。「神田橋」だったかな、何曲かを小林と二人で歌った。小林が気を遣って打ち上げと称して珈琲を飲みに喫茶店に移動するんだけど、映画制作の若手が一人と、小林がピンク映画を撮ってた時に仕事してた女優の葉月螢さんが一緒だった。そのころレコード会社に勤めて宣伝の仕事をしていて、オレにそういう体質が染みつていたからだろうな、制作の彼がスタッフを扱うようにオレに対して振る舞ったら、その瞬間に小林がものすごく怒ったんだ。「バカ、お前。この人はゲストで歌ってくれた人だぞ」って怒鳴る小林の態度を、へぇすげえなと思ったんだよ(笑)。小林は怒ると、そもそもの江戸っ子の地が出て、急に口が悪くなる。監督の前でとるべき態度をわかってないと、スタッフは、こりゃ現場にいられないんだろうなって思った(笑)。映画の現場って、そういうものなんだろうなって、すごく印象に残ってるんだ。
佐久間:監督はさ、ある種、独裁者のような感じでいないと駄目なんだよ。
大江田:現場が廻んないんだろうね。
佐久間:うん。スタッフは全面的に監督の言うことを聞くという状態じゃないと、うまく行かないんだよね。
大江田: 小林が作った「最終列車」を、佐久間はよく歌うじゃない? 林ヒロシ名義で発表したアルバム「とりわけ10月の風が」(1975)に収録の曲だね。あれはすごく小林らしい歌だよね。
佐久間:うん、ずうっと未来を見通して歌ってる感じがするじゃない。彼はもう亡くなったけど、さて、小林くんは天国に行けたのでしょうか?って思うじゃない(笑)。
大江田: 行けたよね、あんだけ自分の映画を撮ったんだから。
佐久間:行けたんじゃない。
大江田: 凄いなと思う。映画って、監督1人だけじゃ作れないからね。
佐久間:うん。
大江田: 監督を信頼してお金を集めてくれる人がいないと、作れないからね。学生時代の彼を思い出すとちょっと不思議な気もするけれど、信頼されてたから映画を作れたんだものね。
佐久間:映画制作において一番重要なのはさ、どうも金集めらしいんだよ(笑)。そこがうまく行かなかったら、出来ようがないんだよね。何かの拍子にスタックしちゃう映画が、たまにあるじゃない。社会問題が起きて、これ以上は撮れないとかさ。そうなると、プロデューサーは金が全部すっからかんになるんだよ(笑)。
大江田:(笑)では、小林くんの話はこの辺にしましょう。


音楽家 佐久間順平に会った_4 に続く
佐久間順平オフィシャルサイトはこちら。
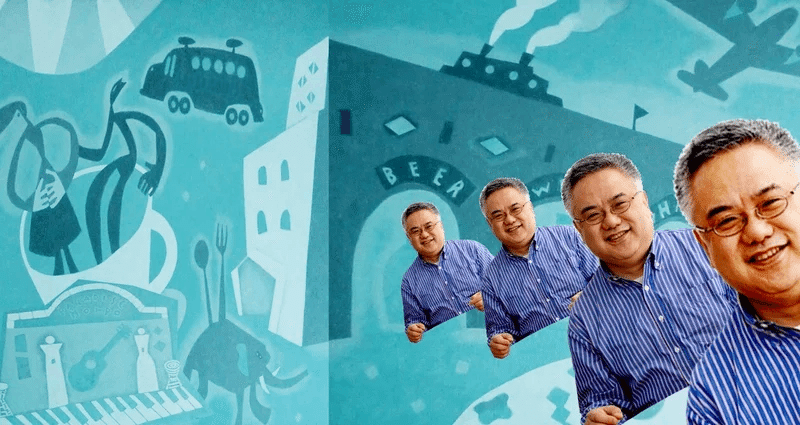
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
