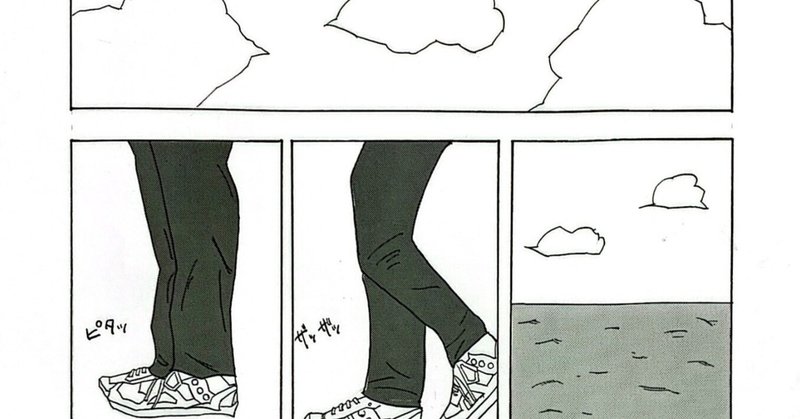
小説:怒りを食う
青い空白い雲どこまでも広がる広い海。
いや、白い雲はないか。
穏やかな情景と見せかけて人のほとんどいないこの場所には切り立った崖に激しくぶつかる波の音がしきりにうなっている音しか響いていない。空気は良い。
「良いことなんて何もなかったなぁ。」
生きていたら何かいいことはあるはずだとか言うやつがいるけれどそれはそいつらの主観の中だけでの物語であって俺とは何の関係もない。
他人が話す言葉を言葉通りに理解することはできるが、全然違う環境の中で育ち全然違う脳みそを持っている他人が発する言葉は結局全然違う生き物から発せられているものにすぎない。
犬が吠えているようなものだ。
基本的に人間は自分の人生を歩んでいく為の重要な決断をする際の相談相手に犬は選ばない。
他人に相談してそれを聞き入れるということは犬に相談を持ち掛けることと同じようなものだ。
崖の上に靴をそろえる。
飛び降りる前のこの行動は一体誰が考えたんだろう。
ミステリードラマが発端か何かなのか。
ここから飛び降りたことを示す証が靴なのだろう。
海外での自殺者もこのように靴をそろえて旅立つのだろうか。
ここに証のようなものを残すことに疑問を感じ靴を崖下へと蹴り落した。
遺書も残さない。
書き残して自分の思いを伝えたい相手なんか1人もいないからだ。
この世には。もちろんあるとすればあの世にも。
ありがとうを残しておく感謝の言葉も出てこない。
そんな感情があるのなら今ここに立っていることはないだろう。
「いい天気だね。」
いつの間にか近くに人が立っていた。
その男はぼさぼさの天然パーマで無精髭を生やしていた。
「カモメになりてぇよな。」
全く共感ができなかった。
男はクタクタになっているアロハシャツの胸ポケットからソフトのラッキーストライクを取り出し1本口に咥えマッチで火を点けた。
タバコに火を点け終わって役目を終了したマッチ棒は軽く2、3度振られてそのまま崖下の海へと放り込まれた。
「ん、タバコ駄目だったか?」
ずっと見つめている俺の視線に気が付いて男が言った。
「いや、特に気にならないよ。」
「それならいいか。最近どこもかしこも禁煙だもんな。」
結構前から嫌煙のブームだったとは思うのだが。
あまり世間と関わりを持つタイプには見えないのでそういうことに疎いのかもしれない。
「こんなところで何してんだよ。って裸足で人気のない崖上に立ってちゃあ大方の想像はつくけどな。」
目線を自分の足へと向ける。
「足、痛いだろ。靴履けよ。」
顎を上げてタバコを空に向かって吐き出す。
「もうないよ。」
「はぁ?もうないってなんだよ。じゃあここまで裸足で来たのか?周りから変人みたいな目で見られたろ。」
「そうじゃな…」
「あ!まさか崖下に落としたとか?それじゃあ遺書と靴の定番のセットは置かずに逝くつもりだったのかよ!寂しいやつだぜ全くよ!」
初対面なのによくしゃべる人だな。
「いや、寂しいって言えばブーメランになっちまうか!中年男がこんな平日の真昼間に1人でこんなとこに居るんだから。」
うるさいなぁ。1人でよくしゃべるタイプの人間のようだ。
「まぁ立ち話もなんだしこっちこいや。」
「ちょっと忙しいんであっち行ってもらえませんか。」
「冷たいこと言うなよ。ここで会ったのも何かの縁だろ。年上の頼みは聞いておくもんだぜ。」
「そんな考え古いですよ。それより知らない人に付いていくなって小さい時に習いませんでしたか?」
「他人に優しくするっつーことに古いも新しいもあるもんか!無学な家庭で育ったからそんなこと習ってもねーよ。」
男はそう言いながらロープの内側に、って言っても俺から見ての内側だから崖側、つまりロープの外側に足を踏み入れていた。
「危ないですよ。」
「誰が言うとんねん。」
「なんで関西弁。」
「どっかから血ぃ引いとんねやろな。」
ポンと左肩に右手を触れてきた。
すると左肩の後方へ男が肩を叩いたのとは逆の方向へと空気の塊のようなモノがぷくぅっと膨らんでいった。
大体バレーボールくらいの大きさになったそれは空中をぷかぷか浮かんでいた。
それを男は両手で受け止めた。
「おっとっと。やっぱずいぶん大っきいのが取れたな。そりゃ平日の昼間に死にそうな顔で崖の上なんかに立ちたくなるわ。」
そういうとそのボールみたいなものをどんどん食べだした。
もちゃもちゃもちゃ。
まるで餅のように食べている。
「何ですかそれ。」
もちゃもちゃもちゃ
「答えてくださいよ!」
「お、元気になってきたな。その意気やでもちゃもちゃ。」
「う、うまいんですか?」
「んーほとんど無味やな。ほんま醤油つけずに餅食うてるようなもんやわ。」
「へー。お腹いっぱいになりそうでいいですね。」
「なるかいな!人の感情食うて!」
俺たちは観光客が多くいる方の崖へと向かいベンチに座った。
心なしか男が肩からでてきた餅を食ったあとから気持ちが楽になった。
「さっき人の感情を食べるみたいなことを言ってましたけど、もしかして感情そのものを食べるみたいなことができるんですか?」
「半分おうてるってとこやな。」
男は何本目かのタバコを吸っている。
カシャッ
缶ビールを開けてぐびぐび飲みだした。
どこから持ってきていたのか。
そんな男の足元は便所サンダルだ。
「怒りをくうねん。」
「怒り…ですか?」
「そうや怒りや。」
うまそうにビールをぐいぐい飲んでいく。
「お前もそやったけど人は心のどこかではみんな怒ってんねや。通勤電車とか会社での異様なピリピリ感とか経験したことないか?なんか空気が固いっちゅーか。あれも周囲の大勢の人間が怒ってるからあんな空気ができあがんねん。そんな場所にずっとおったら普通の人間はなかなか耐えられへんわな。今や平和な世界に暮らしてるのにまるで毎日戦争に向かいよるような顔してるやついっぱいおるやろ?目合っただけでいちゃもんつけてきたり、ほんまええ迷惑やでな。そんな状況で怒りをちょっと食うたるとなちょっとはその空気が軽なるねん。ほんまやで。今度見せたるわ。そんな人が抱えてる自分でも気づきにくい怒りという感情をさっきみたいに具現化さして食うことができんねや。」
自分が過去に体験した記憶を思い出す。
通勤中に少し躓いただけで舌打ちをされたり、会社では明らかに無理と分かる仕事を押し付けられたうえで失敗したら前責任を擦りつけられ無視されたり、歩行中スレスレのところを車が急なアクセルを踏み通過していったり。
それらのことも人に溜まっている怒りに起因するのだろうか。
「いつからできるようになったんですか?」
「最近できるようになってもうた。」
「漫画みたいですね。」
「漫画みたいやろ。」
カシャッ2本目のビールを開けた。
「怒りが溜まりに溜まってあかん行動に移すまでになってもうたやつの怒りを食うてあげてんねや。」
「それは仕事ですか?」
「半分そうで半分違う。」
缶ビールを飲む。
「お前にしたみたいに思いつきでさっとやったりもするな。」
「なるほど。でも怒りを食べることで自殺って止めれるもんなんですか。」
「そうやな。自殺しよう思ってるやつらは少なからず自分に怒ってるってとこもあるんやろな。あとは世の中の流れ自体に。それはどうしようもないもんやからな。今の自分の目の前のことを片づけていくことしかできひんのやから。」
「それはそうですね。」
「すぐ反省してしまうようなやつなんかは特に自分や世間っていうどうしようもないもんに怒ってしまうんやろ。なんでこんな目にあうねんとか。なんでこんなこともできひんねやとか。プロ野球選手でも野球をやっていける環境、やりたいと思えるかどうか、人より練習して体の動きをしっかり把握して結果を出せるか、それを若いうちから全部そろえたうえでスカウトに拾ってもらわなあかんし、プロ入っても結果を出し続けな一気に失業してまう。ここまでの巡りあわせに出くわしたうえで結果を出し続けてさらにスター選手になろうなんかほんま運としか言いようがないわ。」
「そうですかね。」
「そうや。たとえプロ野球選手になれたとしてもなれんかった世界線で経験できる可能性はなくすことにもなる。悔しさとか挫折とかそこからどう立ち直ってどういう方向に自分を持っていくのかとかを考える機会はなくしてその分会えたはずの人に会えんかったりもする。プロ野球選手にはなったことないからわからへんけどどっちが幸せな道かっていうのはそもそも比べること自体が間違っている。どちら側にしか自分の身は置けへんのやから。ほんまどう転ぶかわからんような世の流れとか自分の能力にいちいち反応して怒っててもキリがないわ。」
「そうかもしれませんね。」
「お前は仕事何してんねん。」
「銀行の仕事をしていました。」
「また大変そうな仕事やな。」
「ええ、まぁ。」
男は缶を振って2本目のビールが空になったことを確認した。
3本目はもう無いようだった。
俺は本当にポンコツな人間だった。
それでもなんとかここまで生きてこれたのが奇跡のようだと思う。
なぜそんなに出来損ないの人間だと自覚してしまうのか。
今まで身を置いてきた環境での自分の立ち位置がそれを思わせる。
それじゃあその環境が悪いのでは?
それに気づかせてくれる人との出会いがなかった。
それも毎回どんな環境でも同じような形でうまくいかない自分がそこに立ち尽くしていた。
幼少期から親によくボコボコに殴られ泣きながら生きてきた。
「金食い虫」と言われることもあった。
通勤電車の中でも息が詰まる車内から目を逸らす為に外の景色を眺めていると向かいのサラリーマンと目が合ってにらまれたり改札口で数秒もたついただけで舌打ちされ「早くいけよ。」と捨て台詞を吐かれたりしたこともあった。
職場でもそうだった。
「おはようございます。」
「昨日あんだけ怒られといて何普通の顔して出勤してきてるんだよこいつ。」
「どんな神経しているんだよな。」
「…。」
「こいつ発達障害なんじゃないの?」
「もう死ねよ。」
こういうことを平気で言うやつが上役としてそこに座っているような会社にいることそんな会社があることに絶望もした。
雑居ビルの1室。
俺と男はそこに居た。
崖の上で出会ってから一緒に仕事を手伝うことになった。
「お前もう仕事辞めて暇やろ?」
「まぁそうですね。」
「これからどうすんねや。」
「特には決めていないです。てか死のうとしてましたし。」
「ならうちで仕事手伝わんか?」
「いいんですか?」
「よくないなら誘わんけどな。」
というような流れだ。
「おはようございます。」
「うぃーす。」
「ちょっと事務所汚すぎません?こんなんじゃ依頼人が来てもビビって帰ってしまいますよ。」
「そこそこ汚いほうが良いねん。やってる感あるし。」
「何をですか!てかあなた自身もちゃんと清潔にした方がいいですよ。」
灰皿には吸い殻がたっぷり、床には空き缶が転がっている。
空き缶だけでなくチリ紙やお菓子の袋、コンビニの袋など多種多様だ。
「いきなりおかんみたいなこと言いやがって。」
仕方なさそうにシャワーを浴びにいった。
シャンプーをしてトリートメントをする。
天然パーマの長い髪が顔を覆っていく。
シャワーを終えて髭を剃る。
「これでいいかよ。」
バスタオルで髪をわしゃわしゃやりながら話しかけてくる。
「上出来です。」
「何だよ雇用主に向かって生意気に。」
「身だしなみのことは関係ないですよ仕事とは。で、俺は何をやればいいんです?」
「そうやなぁ。まずは事務所の掃除からやな。」
「ちゃんとした依頼人からの仕事はくるんですか?」
「…。」
「アルバイト始めないと。」
「まぁ依頼が無いっちゅーことは平和でいいってことやんか。掃除終わったら街のパトロールでも行こか。」
「俺らの方が職質されますよ。」
男がパソコンでカタカタと文字を書く仕事をしている間に俺は事務所の掃除をした。
どうやら怒りを食う仕事だけでは全然ご飯が食べれないことがわかった。
失業保険の給付期間を終えたらアルバイトをしよう。
まずは机の上にまではみ出している灰皿を処理した。
次に床に転がっているコーラやビールの缶、瓶類を地域のゴミ出しのルールに則って分別した。一通り水でさっとゆすいで乾かす時間はないので水を切って袋に投げ込んでいった。
掃除機はなかったので埃のかぶった箒とちりとりで床の掃除をし、同時に窓を開けて換気と太陽光の取り込みを行った。換気扇もフル稼働している。これで幾分かは空気が清潔になっただろう。
箒で掃いただけではまだまだ埃っぽかったので床は雑巾で水拭きをした。
よくわからない書類は逐一男に要不要を確認し不要なものは紐で縛った。
ほとんどが不要な書類だった。
「終わったか?」
何本目かのタバコを吸いながら必要な書類に分類された山の影からこちらの様子を遠巻きにうかがっていた。
無視した。
床に散乱していたゴミや書類などを捨てたり棚に整理したりしたことでこの事務所の本来の広さがなんとなくわかってきた。そこそこ広い。
「こんなもんかな。」
「終わったの?」
無視した。
事務所の掃除を大方終えて男に清潔な格好をさせると俺たちは街に散歩に出かけた。
といってもまともに着れるものはアロハシャツしか持っていなかったのだが。
「大体どれくらいの頻度で依頼が来るんですか?」
「企業秘密だなそれは。」
「来たことないんじゃないですか?胡散臭いし。」
「さすが俺の見込んだ男だ。いきなり核心をついてくる。」
「はぁ。本当に他のアルバイトを探さなきゃ食っていけないや。」
「いいか物事の本質はお金を稼ぐことじゃない。人に喜んでもらうことにあるんだ。」
「そんな大層なこと言ってただ営業努力を怠っているだけでしょう。」
男は鼻の横を掻いて聞いていないふりをした。
俺たちの過ごしている街は多くの人でにぎわっている。
その分犯罪や犯罪に近いことも人の少ない田舎よりかは多く起きる。
完全な犯罪であれば警察は動くが限界はある。
そこで働く警察官ひとりひとりの主義主張もあるし仕事としての働きなので犯罪一歩手前の事件のようなものは見過ごされることが多い。
人手が必要になるし何分面倒だからだ。
「おい。どこに目をつけて歩いてやがんだよ。」
道路上でいかにもって感じの男が怒鳴っている。
「よし、ちょうどいいのがいるな。」
そう言うと男は怒鳴っている男にわざと肩をぶつけにいった。
ぶつかった時にその男の左肩からまたあの餅が膨らんで出てきた。
それをすれ違いざまにさっと受け取りそのまま食べ始めた。
「てめぇ。なにぶつかってき挨拶もなく去ろうとしてんだよ。こっちこいよ。」
もちゃもちゃと。
本当にただの餅みたいだがあんな男から出た成分を食べるのは気が引ける。
よくやってるなと思う。
「あれ。何しようとしてたんだっけな。」
その餅が食べ始められるとさっきまで怒鳴っていた男は憑き物が落ちたようにさっぱりとした顔をして何が起きていたのかを全く覚えていなかったように前を向いて歩きだした。
その時、何かボタンのようなモノがポケットから落ちていった。
「これは。」
とつぶやいて男はそれを自分のポケットにしまい込み散歩を終えて事務所へと引き返した。
「あいつもストレスが溜まってたんやろうな。すっきりしたような顔してったで。このボタンなんか貴重なものやったんたやろか。」
「いいでしょうそんなボタンの1つくらい。他人にむやみに突っかかってくる罰ですよ。ああいう人の怒りを食べても変な味はしないんですか?」
「人を見かけで判断するな!あいつのもなんも味はせんな。基本みんなそうや。」
自分が同じ能力を持っていたらああいう人のは食べたくないなと思った。
そんなこんなで日々を過ごしているが一向に依頼人が事務所にやってくることはない。
俺たちは2人で昼間から街に出てビラ配りをしたり事務所の前に立てかける看板をつくったり散歩をして怒りを貯めこんでいるやつが居たら食ったりして過ごしていた。
「ほぼほぼ事務所専属の専業主婦みたいなことしかしてませんよ。」
「焦るなよ。いいことないぞ焦っても。」
ガチャり。
普段ここにいる男2人しか開けることのない玄関のドアが開いた。
「すいませーん。なんか探偵みたいなことをしているとこってここであってますか?」
「ようこそいらっしゃいました。ここであっていますよ。」
かなり無理をして作った笑顔で男が対応する。
その間に俺はすかさずコーヒーの準備をしにキッチンへと向かった。
「どうぞおかけください。なにかお困りごとでもありましたか?」
淹れたコーヒーを彼女の前に差し出す。
「ありがとうございます。」砂糖もミルクも入れずに飲む。
「実はご相談したいことがありまして。」
「大丈夫ですよゆっくりで。」
そう言ったものの男の顔には嬉しいといった表情が隠せずもろに出ている。
辛い話だったら知らないぞと思った。
「彼氏が急に出ていったまま帰ってこないんです。」
「それはお気の毒に。他の女のところですか?」
「おい!少しはオブラートに包め!」
遂ため口で突っ込んでしまった。
この男には出会ってからそういうところが多々ある。
怒りを食うくせに人の気持ちを慮れないところが。
「んーでもそれはどうしてなんでしょうね。」
「彼は商売をしていましてそれ関連かとは思うのですが。ある日自宅のポストにこのボタンが放り込まれていまして。」
そのボタンは先日道端で荒れていた男が落としていったものと似ていた。
同じマークが施されていた。
「どうやらそれはこの街のギャングのものですね。同じものを僕たちもこの前偶然街で拾いました。街ではそこそこ有名なようです。」
「ええそのようですね。それで相談を。」
俺はこの街に来てまだ間もないのでそういう状況はあまり把握できていなかった。
ギャングが現存し知れ渡っているという状況を。
「ある程度事情を把握しておきながらなぜ警察ではなく僕らに相談を?」
おれはわざわざ仕事が来たのにそれをよそに持って行かせようとするような発言をした男を睨む。
「警察がギャングに対して何も干渉できないっていうのはご存じでしょう?今すぐに彼を助けて欲しい。そう思ったらあなた方民間の方が行動は早いと思ったのです。」
なるほど。
「わかりました。しっかりお話をして対策を練っていきましょう。相手はギャングです。慎重にいかないと命の危険もある。」
そうして俺たち3人は何度か話し合いを通して相手について、また、こちらに何ができるかについてを可能な限り徹底的に洗い出した。
そもそもこの男はそんなに喧嘩が強いのか?
大した武器も持っていないように見えるが。
能力としても相手に触れて、その上出たものを自分で掴んで咀嚼しないと効果がはっきりと出ないものなのに。
出たとしても相手の怒りの感情を食うだけだぞ。
この前はたまたまうまくいっただけでギャングも悪いことをすることで飯を食っているプロの集団だ。
怒りという感情とは別に行動している者も多いだろう。
それはつまりうまく相手の怒りを食うことができても相手の凶暴性や行動力を抑止することはできないのではないかという不安だ。
「勝算はあるんですか?」
「なきゃあ受けないよ。」
「意外とまともな考えをしていて安心しましたよ。」
「俺を誰だと思ってんねん。経営者やぞ。そのくらいは考えるわ。」
「失礼しました。」
依頼者の彼氏奪還作戦は着々と進んでいった。
一方、捕らわれている彼氏は殺風景な事務所のようなところにいた。
「僕を捕まえていてもあなたたちの利益になることはなにもありませんよ。何度も申し上げていますが。」
相手が警察官だったのならそれはまるで取り締まりを受けているような風景だった。
「お前はまだ状況がうまく把握できていないな。」
彼の前に向かい合っているのは街で絡んできた太った男だった。
灰皿にタバコを押し付けている。
「お前を捕えているというこの状況は捕えていないことに比べればいくつも利益がある。」
「簡潔に言ってくれよ。僕はあまり頭がよくないんだ。」
バンッと大きな手のひらで机を叩いた。
机はグレーの事務机だった。いかにもお金がかかっていなさそうだった。
「調子に乗るなよ。乗っていいのは我々の方だけだ。お前じゃない。」
何本目かのタバコを胸ポケットから取り出して深呼吸をするように思い切り吸い込んだ。
それでもむせないのがすごいところだ。指はごわごわで唇は汚い。
「お前を捕えている理由は2つある。この2つは今お前に話しておけるという点で2つということだがもちろんそれ以上にもいくつもメリットは存在する。まず一つはお前の連れだ。お前の連れの親は大橋ビル産業株式会社の会長をしている。そこを抑えることができれば我々の活動がしやすくなるという利点がある。縄張りを増やせるということだ。もう一つにお前がやっている産業で得た利益のことがある。お前は確か果物屋をやっていたな?そこそこ稼いでいるそうじゃないか。お前の解放と引き換えにこの2つを手に入れる。お前の店の利益を元手に連れが持っている土地のエリアで儲けようって話だ。」
「なるほどな。金ね。必要だよな金は。」
「そうだな。ほとんどなんでも手に入れることができるからな。この資本主義社会では。それをどうやって手にするかなんてことに美学は用いない。ただ持っていればいいんだよ持っていれば。」
「まぁいずれにせよ。僕をこんな所へ縛りつけているだけじゃ君たちの期待するような額を手に入れることはないだろうよ。」
「この減らず口めが。おい、あれをやれ。」
「うす。」
部屋の隅に座って書記のようなことをしていた小柄な男が立ち上がった。
何をはじめる気だ。
ぎぎぎぎぎぎぎ。
机の引き出しからミニサイズの黒板のようなものを出し爪でひっかいて音をだしはじめた。
ぎぎぎぎぎぎぎ。
幸いこの手の音は僕の苦手分野ではなかった。
太った男の顔の方が歪む。
「おい。もういい次だ。」
「うす。」
僕は椅子の後ろに手を回され手錠をかけられている。
足は前に位置しているがこちらも縄でギチギチに縛られている。
身動きが自由に取れない状況だ。
指示された男はまたもや机の引き出しに当たるところから何か棒状のようなものを出した。
棒の先には何かがついていた。
男は即座に僕の前に立ちわきの下にその棒をくぐらせてくすぐりはじめた。
脇の下に棒を配置されただけでくすぐったかったのがくすぐりという行為をはじめてなおさら刺激が強くなり我慢ができずに声を出してしまう。
「ぎゃははははははははやめてくれははははは」
くすぐりには僕は弱いのだ。
「辞めて欲しければお前のパートナーか親に連絡して財産贈与の話をきっちりしろ。」
「そんなの今すぐに無理だはははははははは。」
ピンポーン。事務所のインターホンを誰かが押した。
「ここがどんな場所かわかっていないやつがいるのか。おいお前は構わず続けろ。」
「うす。」
モニターを覗くとピザの配達員だった。
本当にこんな作戦でうまく彼を奪還できるのか。
そう思ったのは依頼人だけではない。俺もだ。
だが、もう相手の本拠地まできてインターホンを押してしまっている。
もっと序盤に止めておくべきだったのかもしれない。
しばらくして玄関先には中年の女性が出てきた。
「はい。」
俺たちは一瞬呆気にとられた。
「ピザのお届けです。」
「あれピザなんか頼んだかしら。」
エプロンをつけた明らかに主婦である女性は困惑していたが急に思いついたような表情になった。
「ちょっと待ってね。まさしー!!あんた頼んだんじゃないの!!」
奥の部屋に向かって大声で呼びかける。
扉が開ける音とこちらに向かってくる足音が聞こえた。
「頼んでないよ。なんだよてめーら。あっ。」
その男は前に街で会った男だった。
すかさず右手で彼に触れ怒りを取り出した。
それを素早くつかみ食べると同時に横にいた女性に鋭い手刀を食らわし気を失わせた。
すごい手際だ。
その道のプロか何かか?
「なにかやってたんですか?」
気を失い崩れ落ちかけた女性を支えながら聞く。
「いや咄嗟に手が出ただけだけどね~ひゅひゅ~」
めちゃくちゃ動揺していた。彼の過去には触れない方がいいようだ。
一方怒りを食われた男は意識はあるものの放心状態で玄関先の廊下でへたりこんでいた。
「怒りを抜かれただけでこんなことになるなんてこいつの感情のほとんどは怒りかよ。」
彼を後に残して前に進み始めた。
女性はそっと床に寝かせて防犯上の理由で玄関の鍵を閉めた。
この場合侵入しているのは俺たちなのだが。
「あいつはあのまま放っといてもいいんでしょうか?まだ意識はあるみたいですが。」
「問題ない。しばらく我を忘れてるやろ。」
俺たちは家の奥。男が出てきたところへと向かっていった。
本当にこんなところに依頼者の彼氏が居るのだろうか。
ピザ屋の衣装は既に意味をなさないので着崩していた。
奥にあった扉に手をかけた。
部屋の中は殺風景で2人の男が居た。
おそらく椅子に縛られているのが依頼者の彼氏だろう。
2人は向かい合って座っている形でそこにいた。
扉から入ると依頼者の彼氏と目が合う配置だ。
「連れ戻しにきましたよ。さあ帰りましょう。」
俺がそう声をかけると手前に座っていた小柄な男がこちらを振り返った。
その表情は驚きと疑念と怒りが混じったようなものだった。
怒りが少しでも感情に含まれていればこっちのものだ。
「兄貴はどうした?」
「あのデカブツか?一撃でのしたよ。雑魚だったんでな。」
最期の一言が決定的となり小柄な男の表情に怒りの割合が増えていったのがわかった。
「ふざけやがって!!」
椅子をはじき飛ばしなぜか俺に向かって殴ろうとしてきた。
「兄貴がお前らなんかにやられるはずg…」
すかさず横から右こぶしが視界に入ってきてそれはそのまま小柄な男の鳩尾に入った。
背中から例のごとくぷくーッと怒りが出てきて。それを俺が捕まえてパスする。
さながら息の合った二遊間コンビのように。
小柄な男は床に倒れ伏し悶絶していたが男が怒りを食べ終わると次第に柔和な表情になっていった。
後日わかったことだがギャングだと思われていた彼らはただの家族に過ぎなかった。
玄関に出てきたのは彼らの母親で男たちは実の兄弟だった。
母親は彼らの企みを何も知らなかった。
母子家庭で貧しい思いをしていたのでなんとかお金を手に入れて母親に楽をさせてかったらしい。
そういうものは時間をかけてしっかりと考えて行うものだとおれは思う。
ただただ目の前に大金が積まれていても使い方を間違えれば幸福になれないようにお金の手に入れ方も納得のいくようなものでなければ幸福にはなれないと思う。
「ほんとうにありがとうございました。これからは私たち一緒に暮らそうと思うんです。今度はこんなことが起きないようになるべく近くで行動しようって。」
「そうなんですね。それはよかったです。」
銀行員の時には決して出ることのなかった満面の笑みで答える。
男は仕事を終えて安心したのか元依頼人を前にしても気にせずふてぶてしくタバコをふかしていた。
「これは今回の謝礼です。依頼料とはまた別なんですが身体を張って助けていただいたので。」
「そんなそこまでは…。」
後ろから手が伸びてきて封を奪い去っていった。
男はタバコを加えながら中身の勘定をはじめた。
「さすがにそれは失礼でしょうが!」
「依頼は解決したからええやん。」
「そういう人間としてダメなところがあるからいつまで経っても仕事が増えないんですよ!」
「おいおい怒りすぎやって。食うたろか?」
「いい加減にしろ!!!」
元依頼者は笑いながら俺たちのその光景をみていた。
本当にこの先こんな男について行っても大丈夫なのだろうか。
1人雑居ビルの屋上に出て考える。
空にはあの男と出会った時のような青空が広がっているがあの時とは気分が180度違う。
男を真似てタバコを吸ってみたがケホケホと煙たすぎてむせた。
どこに向かっているのかは自分でもわからないが。確実に前には進んでいる。
そんな気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
