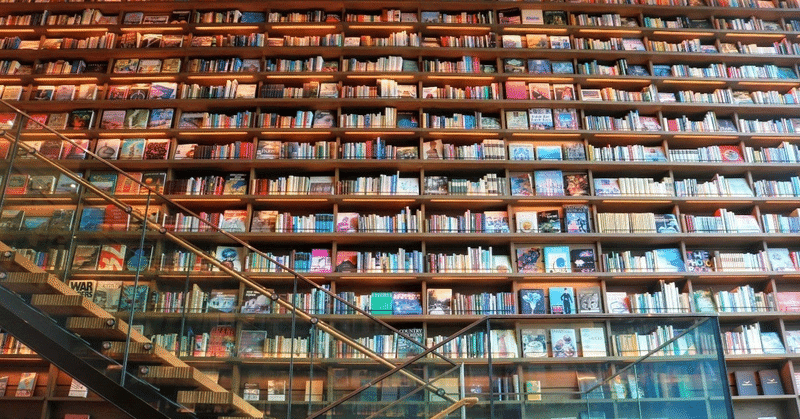
塾・予備校無しで阪大文系(外語)に現役合格した経緯(5年前)
こんにちは。大学を卒業して最近ふとこれまでの人生や学生生活を振り返る時間がありました。そういえば高校一年の終わりまで大学受験のことなんかなんも考えてなかったなとか、色々と背伸びして大学入ってよかったとか、大阪での学生生活楽しかったなとか、色々思い出したのですが、大学受験の時色々勉強方法を試行錯誤していた時期を思い出し、自分の経験をnoteでシェアしようと思いました。自分のような境遇の人に少しでも力になれたらと思います。自分がやった参考書や問題集などは参考にならないかもしれないですが、基本的な受験に対する意識や勉強法はもしかしたら参考になるかもしれません。もう5年も前の話でセンター試験という単語も死語になりつつあり?(昔の人が言う「共通一次」的な)、情報が古いかもしれませんがご了承ください。
前提として、国立文系志望、共通テストレベル以上を対策してくれるカリキュラムの高校に通っている人(偏差値60くらい以上?)で、得意教科(進研模試偏差値70~)の科目が英国数の内1教科以上既にある人だと再現性が高いかなと思います。
合格のために私がとった方法 TL;DR
まずはセンター試験、赤本を見て、自分の学力と志望校のレベルの差、出題傾向、配点などを把握して、とにかく効率を意識した勉強の計画を細かく立てる
家で自習できない性格の人や部活で忙しい人は、通学時間、始業前、休み時間、放課後を最大限活用+授業は全集中して身につける意識で取り組む
闇雲に参考書などに手を出さず、教科書、授業中にとったノート、宿題などで出た問題集(数学であれば4STEPなど)をやり込む
YouTubeやWebサイトをフル活用する(英語リスニング、数学問題解説、など)
学校の先生、設備もフル活用する(質問しまくる、朝早く来て放課後も最後まで粘る)
解けなかった問題や忘れた単語に目印をつけていき、その問題を解けるようになるまで復習する
解けるようになっても応用問題などを復習して基礎が定着しているか定期的に確認する
嫌いな教科も興味を持とうと意識する(「好きこそものの上手なれ」)、自分が既に知っている知識を繋いでいく意識を持つ → よりよい記憶の定着につながります。
適度な息抜きも忘れずに(50分に一回10分休憩)
受験勉強前
私は8年前(もうそんなに経ったのか!)田舎の中学校から地方都市の偏差値60くらいの高校に入学しました。洋楽とギターが大好きだった私の志望動機はその高校に海外ホームステイプログラムがあったからでした。高校卒業後は何も考えていませんでした。高校一年まではギター、バイト、グラセフ(オンラインガチ勢でした)とローテーションを回す感じで過ごしていました。
イギリスのバンドや海外のYouTuberが好きだった私は英語が得意で、(よく受験界隈でディスられる)進研模試で偏差値70~80くらいでしたが、それ以外はからっきしでした。高校1年の終わりに受けたセンター試験の模試の数学で、IAが30点とかだったのを覚えています。
高校1年の終わりは今思えば転機で、それまで高校でバンドをしようとしていたのがメンバーが集まらず頓挫し、鬱屈していたところ、同じクラスの友達に誘われ陸上部の長距離走を始めました。その顧問の先生にある日、「お前の英語の成績だけ見たら東大目指せるぞ」と言われて、「俺東大いけるって言われた」と勝手に勘違いしたのがきっかけで、大学受験を意識し始めました。
受験勉強開始
とは言え、母子家庭であまり親に負担をかけたくないと思った私は塾や予備校に通わずに勉強することにしました。かといって家では勉強できない性格だったので、効率のいい勉強をしないとやばい、と勉強法、受験科目、試験の内容など色々と調べました。調べるとどうやら東大は社会科目が3科目(世界史B/日本史B/地理Bの内2つと倫理政経)必要で、そもそも高校のカリキュラムが対応してなかったので諦めて、2科目でOKだった阪大文系に絞りました。
模試の結果を見て、一番対策しなければならなかったのはどう見ても数学と国語でした。あとは得意であったとは言え、成績を維持するために英語の勉強もまあまあ必要でした。最初は法学部の国際公共政策学科を目指していましたが、数学と国語の成績が心もとなかったので、最終的に二次の英語の配点が他の教科の3倍のウェイトを持つ外国語学部に絞りました。
また、受験生で結構悩むのは部活と受験勉強の両立だと思います。僕も悩みましたが、今後の人生的にも部活の時間はかけがえのないものだと判断して、3年6月の高校総体まで部活をやりきりました。結果的にもそれで逆にメリハリと受験勉強に対する体力がついてよかったかなと思いました。あまりに忙しい部活(週6+放課後7〜9時まで居残り+朝練7時からなど)は避けた方がいいかもしれませんが、そうでなければ続けた方がいいかなと思います。
各教科の勉強法
数学
私は数多の文系生の例に漏れず、数学が大の苦手で嫌いでした。しかし阪大文系となると二次試験に数学が必要なので、避けては通れませんでした。阪大文系だと、英語、国語がそこそこ取れる人ならば、数学は大体二次試験で5割前後取れれば合格だったと思います(忘れたので各自で確認してください)。数学二次試験大問3問のうち、理系共通問題を捨てて2問を最後まで解にたどり着ける感じで4〜5割前後を目指せるので、そのレベルまで頑張りましょう。
となると、私の高校のカリキュラムでは教科書、問題集をやり込み、基礎を固めることで達成できました。
青チャートもやっていたのですが、最終的に宿題などで出されていた問題集4STEPをやり込むことが一番効率的であると思い、4STEPの問題全問を解けるようにしました。宿題の取り組み方が適当だったにしろ、やはり見覚えがある問題を解いて解法を身につける方が、初見の問題集や参考書を闇雲に解いていくより効率が良かったです。もちろん、一部の人々から酷評されている通り4STEPの解答集は貧弱ですが、先生に質問するなり、スマホで問題を検索するなりすれば、理屈は理解できると思います。逆に先生に質問することで記憶がより定着するかもしれません。
4STEPは大体11月までに対策完了するイメージで、そこから共通テスト対策1ヶ月、共通テスト後から赤本解くイメージで進めました。阪大文系数学20ヵ年とか解いてた記憶があります。
本番での結果はセンターIA、IBで7割、2次試験で4割でした。(外語でなかったら落ちとるやつ〜)あれだけ大嫌いだった数学はやっているうちにセンター試験数ヶ月前から好きになって、(特に関数でピカチュウとかなんでも表せれるとかに気づいて数学すげえって感動、数学が美しいって言う人のことを理解できるようになった)もっと勉強したいなと思いながら受験勉強が終わりました。その数年後、コンピューターサイエンスを勉強するために高校数学の復習と離散数学の勉強を始めるとは思ってもいなかったです。人生何があるかわかりません。
英語
英語はもともと得意で勉強もあまり苦でなかったとはいえ、英語は文法、単語、長文読解、リスニング、英訳、和訳と大きく分けて5つの能力を伸ばす必要があったので、結構骨が折れる作業でした。特に外国語学部の英語は他学部とは異なるレベルの問題が出るので、英語得意な人でも苦戦すると思います。しかしながら、結局は9教科なり全体で合格点を取ればいいので、ここでもまずは受験勉強の戦略を先生に相談して、何割目標で行くかを決めましょう。外語は英語の配点が他教科の3倍なので、ここはガッポリ稼ぐほうが他が楽になります。
でその阪大英語の(僕なりの)攻略ですが、英語はやはり文法、単語を固めないとあとの3つが攻略できません。
文法は通常の教科書に加え、NextStage、名前を忘れた問題集2つ(まあまあ難しかった)くらいをやった記憶があります。構文集では英語の構文150も良書だと思います。文法も同じように、覚えるまで繰り返し復習することが重要です。頭の中で覚えた文法を使ってみたり、応用したりすることが大事です。
単語はひたすらターゲット1900を電車の中で毎朝毎晩復習していました。通学中1日で20単語ずつくらいを目標に、忘却曲線を意識して(実際の効果は知りませんが…)印をつけながら完全に覚え切りました。単語帳の隅の方に載っている同義語やイディオムも全て覚えました。それ以降は難しい問題を解いている時やBBCの記事を読んでいる時に遭遇した単語を単語帳に追加して覚えていきました。(東大生のインタビュー動画でも同じように遭遇した単語をノートにメモして覚えてた人がいたので、結構効果あり?) 単語もアウトプットが重要で、その単語を使って英作文をしたり、風呂で一人二役で英会話したりして覚えていきました。
これらと並行しながら、BBCの記事を通学時に読んだり、好きなバンドのインタビュー記事を読んだりして、長文読解の練習をしていました。長文はニュース+興味があるものを読むことがおすすめです。ニュース記事を読むことで結構時事問題に対応できるようになる気がします。その中で特にBBCはかなりおすすめで、The GuardianやIndependent紙と比べて平易な単語が多く、難関大学受験レベルに結構適していると思います。センター1ヶ月前までに標準問題精講も終わらせ、センター試験後は阪大20ヵ年と京大理系の英語とかを解いていきました。
また、長文読解で特に評論文の場合、アカデミック英語の読み方も知っておくといいと思います。基本的に段落の最初の文でその段落が要約されているので、それらを最初に読み長文の大意を掴みましょう。すると問題の解答が書かれている文の大体の位置がわかり、読解のスピードが上がります。
リスニングについては、普段から好きな海外のYouTubeを見まくりましょう。ゲーム実況でも、ドキュメンタリーでも、PewDiePieでも、なんでもいいです。まずは英語字幕あり+0.5倍速とかから始め、最終的に字幕なし+等倍速くらいで聞けるようになれば、基本的にどの大学でも無双できると思います。好きなことや興味があること、心理的にハードルが低い勉強法で勉強することが一番効率的です。共通テスト対策は直前に問題慣れする程度に過去問を解くくらいで十分でしょう。
英訳和訳については、逆に国語力が試される分野だと思います。英訳は、難解な日本語を英語に訳しやすい日本語にどう咀嚼するか、和訳は単語力(と単語の推測力)と日本語力が必要かなと思います。両方とも文や単語の意味が持つ情景を想像して小慣れた表現を見つけるといった作業に近いと思います。対策するには、英単語の持つニュアンスや包括的な意味合いも意識しながら英単語を覚えていくことが必要かなと思います。英訳和訳も練習あるのみで、特に英訳は先生に添削してもらいまくりましょう。
これらを全てやった後の本番では、センター試験筆記満点近く、リスニング8割、2次で6.5割という結果でした。多分もっと効率いい方法は色々ある気がしますが、英語が好きな私にとって一番苦痛が少なかったのが上記の勉強法でした。
国語
国語は正直何をやったのかはあまり覚えてないです。なのであんまり参考にならないと思うので他のサイトを見ることをおすすめします。それでも書くと、そもそも国語は特に現代文は対策がしづらいと思いますが、漢文/古文ヤマのヤマ、入試現代文へのサクセス基礎・発展・完成編あたりをやりました。特に現代文はやはり、授業中や勉強中になぜその答えになるのかという論理的な考え方、問題文の読み方を身につける意識が重要かなと思います。古文の単語は授業で配られた単語帳を英単語と同じ要領で覚えていきました。漢文の漢字も同じような感じで覚えていきました。国語はセンター試験3ヶ月前まで得点が安定しませんでしたが、7~8割で徐々に安定して行ったのを覚えています。二次試験対策はこれまた赤本を7年分かそこらを解いて行った覚えがあります。最終的にセンター試験では7.5割、2次では5割の得点でした。
その他センター科目:社会(地理・倫政)・理科基礎(生物・地学)
これらは僕は「俺の出す宿題授業をちゃんと聞いとけばセンター9割余裕」とかかましてた先生を信じて授業中に配られた教材と問題集をやっていきました。地理は昔から暇な時にGoogleMapや地図帳、参考書を眺めるくらい好きで得意だったので、授業中真面目に聞く以外あまり対策という対策はしてないです。理科基礎に関しては、それらプラスでセンター前1ヶ月くらいで過去問対策をして、生物基礎では満点を取りました。倫政のみに関しては、「入試で使う人は自分で勉強してね〜」っていう適当な感じだったので、あの黄色い「はじめからていねいに」を買って自分でやっていきました。倫政はセンター半年前から気が向いた時に対策していった記憶があります。
最終的に地理は9割強、倫政は8割、地学基礎8割、生物基礎満点という具合で、先生すげえってなりました。あと倫政コスパ良すぎ。(あんま参考にならなくてすみません)
まとめ
結構書いていて記憶が曖昧で雑なところもありあまり参考にならないかもしれませんが、一番伝えたいことは、いろいろ余裕がなくても、成績がまだまだ足りなくて悔しくて焦っていても、上記のことを意識してコツコツと努力することで大学受験は突破できるので、めげずに頑張ってください。乗り越えた先はすごい景色や体験、環境が待っていた(阪大の感想はまた今度書きます)ので、それを経験できるように頑張ってください。それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
