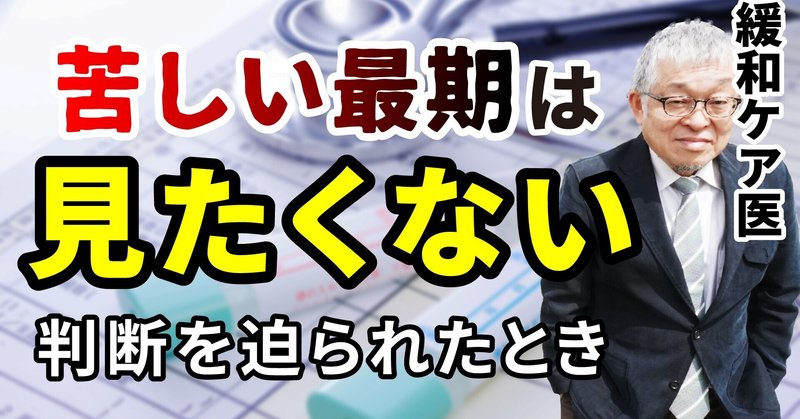
どんな「がん」でも最期に苦しませない方法があります(緩和ケア,鎮静,安楽死)【家】#169
こんにちは、心療内科医で緩和ケア医のDr. Toshです。緩和ケアの本流へようこそ。
緩和ケアは患者さん、ご家族のすべての身体とこころの苦しみを癒すことを使命にしています。
今日のテーマは「鎮静の誤解を解く」です。
動画はこちらになります。
あなたは鎮静を知っていますか?また、鎮静と聞いてどのようなイメージがありますか?
鎮静=安楽死だ。
鎮静をするときはモルヒネを使う。
鎮静をすると寿命が短くなる。
これらのことは本当に正しいのでしょうか。実はこれらはすべて間違いです。
今日は、緩和ケアにおいて誤解されやすい鎮静についてお話します。
鎮静はがんの終末期にはだれでも使う可能性がある症状緩和の方法ですので、全てのがん患者さんとそのご家族に知っておいて欲しいことです。その他にも、がんになるのが怖い人、がんで苦しみたくない人、鎮静について知りたい人にもこの記事はぜひ見ていただきたい内容です。
この記事の中で、医師から実際に「鎮静をします」と言われた時、どのように対応すればいいかについてもお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。
今日もよろしくお願いします。
緩和ケアにおける鎮静は症状緩和の方法の1つ
結論から申し上げます。
緩和ケアでいう鎮静は、症状緩和の方法の1つです。
終末期においては、がん患者さんには疼痛、呼吸困難、せん妄など様々な症状が生じるようになり、それにより患者さんは苦痛を訴えます。私たち緩和ケア医は、その症状をしっかり緩和することにより、苦痛をやわらげます。
しかし、症状緩和をしても、どうしても和らげることのできない苦痛が残ることがあります。そういう時に、鎮静薬という眠らせる薬を使って、患者さんの意識を低下させることで、苦痛を和らげる方法が鎮静なのです。
ところが、鎮静を多くの人は誤解しています。よく誤解されているのが冒頭でもお話した3つです。
①鎮静は安楽死と同じ
②鎮静にモルヒネを使う
③鎮静は寿命を短くする
この3つです。
①鎮静≠安楽死
鎮静を安楽死だと思っている人がいますが、鎮静と安楽死は全く違います。
安楽死とは、終末期に苦痛を訴える患者さんに、死に至る薬物を投与して死なせることです。安楽死を法律で認めている国もありますが、日本では法律で禁止されています。
一方、鎮静は患者さんの意識を低下させることで、苦痛を和らげる方法であり、もし、鎮静した後に亡くなっても、それは自然に亡くなったということで、死を早めたわけではありません。後でも説明いたしますが、これは本当によく誤解されることですので、しっかり理解していただきたいと思います。
②鎮静にモルヒネは使わない
鎮静をする時にモルヒネを使う、と思っている人は多いかもしれません。
ところがモルヒネは、疼痛や呼吸困難などの症状緩和のために使う薬剤です。鎮静にはドルミカム®やサイレース®などの鎮静薬を使います。
モルヒネは鎮静薬ではありません。そして、鎮静は終末期に行うものです。モルヒネは決して終末期だけに使う薬だというわけではなく、疼痛緩和が必要な時には早期からも使う薬です。このことを知っておいてください。
③鎮静は寿命を短くしない
鎮静すると、寿命が短くなると誤解している人もよくいます。しかし、鎮静をしても寿命が短くなることはありません。これは最近の研究でも証明されました。鎮静をしても寿命は短くなりませんので、安心してください。
また、医療の中で、「鎮静」という言葉は様々な意味で使います。
例えば手術の時、麻酔をかけて眠らせることも「鎮静」です。精神科で統合失調症などの患者さんが興奮している時、薬を使って落ち着かせることも「鎮静」です。
一方、緩和ケアにおける鎮静は、どうしても和らげることのできない苦痛を、鎮静薬を使って患者さんの意識を低下させることで、苦痛を和らげる方法です。その結果、患者さんは苦しまずに最期を迎えることができます。
鎮静を正しく知って、患者さんが終末期になった時に主治医から鎮静の話をされた時にも、慌てないでしっかり話を聞いてほしいと思います。
緩和ケアにおける鎮静を正しく知ろう
それでは緩和ケアにおける鎮静について、もう少し詳しくお話していきます。
1.どんな時に鎮静するのか
繰りかえしますが、鎮静はどのような症状緩和を行っても取り切れない苦痛を取る症状緩和の方法です。
こうした、どのような症状緩和を行っても取り切れない苦痛が出てくるのは、患者さんの残された命が、1~2週間から数日くらいになった時です。ですので、鎮静は患者さんが終末期を迎え、死が近くなった時に行うものであるということを知っておいてください。
2.鎮静の判断は誰がするのか
鎮静を行うと、患者さんは苦痛が和らぎますが、意識を下げることにもなりますので、会話が困難になる場合が多いです。最期までコミュニケーションが取れずに亡くなってしまうこともあります。
したがって、鎮静を行う判断をするのは、細心の注意が必要であると私たちは思っています。
では、鎮静を始める判断は主治医だけでするのでしょうか。
もちろん医学的な判断は医師が行いますので、主治医の判断は重要です。しかし、医師だけで鎮静を開始する判断をするわけではありません。
もちろん患者さんご本人の意思、さらにはご家族の意見も必要不可欠です。さらには医師以外でケアに関わっている、看護師などスタッフの意見も大事にします。つまり、関わっている全員の意見がそろって、はじめて鎮静開始となります。みんなで相談して決めることが大事であり、必要なのです。
ご家族であるあなたも、鎮静開始においては、意思決定の重要な一員であることを知り、十分話し合い、納得してから鎮静を行いましょう。
3.鎮静の具体的な方法
鎮静を行う際には、鎮静薬と言われる薬を使って、患者さんの意識を低下させます。しかし、いきなり患者さんの意識を昏睡状態にするわけではありません。
まずは「間欠的鎮静」といって、患者さんが苦痛を訴えた時に、鎮静薬の点滴で少しの間だけ眠るようにします。
「間欠的鎮静」では、薬が切れてくると目が覚めます。そしてまた患者さんが苦しくなると点滴をします。
最初はこれだけでも苦痛が取れることが多いので、まずはこの「間欠的鎮静」から開始します。これだと、薬を投与していない時には、患者さんの意識があるので、コミュニケーションをとることが可能です。
ところが患者さんが目を覚ましている間、常に苦痛を訴えるようになることがあります。その時は24時間鎮静薬を投与して、患者さんの意識を落とすことが必要になってきます。これを「持続的鎮静」といいます。
ただし、はじめは鎮静薬の量は少量から始めますので、周りのことがわかる程度の状態が多いです。そして徐々に量を増やして、完全な眠りの状態にしていきます。
鎮静を始めると患者さんとは全く話ができなくなると思っている人も多いかもしれませんが、このように段階を踏みながら鎮静をしていきますので、多くの場合、患者さんとはコミュニケーションは取れることが多いことも知っておいてください。
4.鎮静した患者さんの最期はどうなるか
こうして鎮静をした患者さんは、ほとんどの場合、苦痛を訴えることもなく穏やかに最期を迎えられます。そして最期まであなたが傍にいることがわかりますので、安心してください。
安楽死と鎮静と違い
ここでもう一度安楽死と鎮静の違いをお話します。
安楽死とは、終末期に苦痛を訴える患者さんに、死に至る薬物を投与して死なせることです。一方鎮静は、意識を低下させることはしますが、積極的に死なせることではありません。つまりその方の寿命まで、症状緩和をすることが鎮静であるといえます。
鎮静は安楽死ではありません。
安楽死は、今の日本での考え方では、殺人あるいは自殺という解釈になっています。
安楽死に関しては、様々な意見があるでしょう。法律で認められている国もあることは事実です。しかし、私たちがこの世に生まれてくるということは、命を天から頂いたということだと私は思うのです。
私は頂いた命を最後まで大切に使うことは、私たちの義務であると思います。最期まで自分の人生を生き抜くことこそが、私たちにとって大事なのではないでしょうか。
医師から鎮静の相談があった時
最後に、あなたの大切な家族が終末期になり、医師から「患者さんに鎮静が必要です」とあなたが言われた時に備えて、考えておかなければいけない大切なことをお話します。
1.ACPの中で鎮静のことを話し合うこと
患者さんが元気な時に、最期どのように過ごしたいかを話し合うことはとても大事なことです。
どこで誰と暮らしたいか、最期まで大事にしたいものは何か、残された家族に伝えたいものは何か、色々あるでしょう。私たちはこれらのことを、アドバンスケア・プラニング・ACPと呼んでいます。
こうした話し合いの時に、「鎮静」についての思いも患者さんから聞いておいてください。なぜなら、鎮静を選択しなければいけない状況の時には、患者さん本人の意思が聞けなくなっていることが多いからです。
まだ患者さんが元気なうちに「鎮静」に対する思いを患者さんから聞いておいて、医療者に伝えられるようにしておきましょう。
2.医師に聞けば良いこと
鎮静を医師から提案された時には、次のことを医師に聞いてください。
①なぜ鎮静が必要なのか。
②十分症状緩和はなされたのか。
③鎮静以外の苦痛の緩和の方法はないのか。
④持続的鎮静ではなく間欠的鎮静から開始できるのか。
この4つです。
特に4つ目の質問に関して、医師から持続的鎮静から開始すると言われたら、間欠的鎮静から始めてほしいと頼むことは可能です。これらを質問して、あなたが十分納得できた時、鎮静の承諾をしてください。
3.鎮静状態になった患者さんへの付き添い方
間欠的鎮静の段階では、ほぼコミュニケーションは取れますので、患者さんとしっかりお話をしてあげてください。
もし持続的鎮静になったとしても、最期まであなたの声は聞こえます。最期まで、あなたが傍にいることもわかっていますので、手を握って耳元で声をかけてあげてください。そうすることで、患者さんを一番安心させてあげられるのです
以上、鎮静について様々な視点でお話してまいりました。
この記事をご覧になって、緩和ケアにおける鎮静について正しく理解ができ、安心していただけたら幸いです。
あなたに伝えたいメッセージ
今日のあなたに伝えたいメッセージは
「鎮静は安楽死ではありません。鎮静とは、終末期の患者さんがどんな方法をとっても苦痛が取れない時、鎮静薬を使って、患者さんの意識を低下させることで苦痛を和らげる方法なのです。緩和ケアにおける症状緩和の方法の一つであることを知ってください。」
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私は、緩和ケアをすべての人に知って欲しいと思っています。
このnoteでは緩和ケアを皆様の身近なものにして、より良い人生を生きて欲しいと思い、患者さん・ご家族・医療者向けに発信をしています。
あなたのお役に立った、と思っていただけたたら、ぜひ記事にスキを押して、フォローしてくだされば嬉しいです。
また、noteの執筆と並行してYouTubeでも発信しております。
患者さん・ご家族向けチャンネルはこちら
医療者向けチャンネルはこちら
お時間がある方は動画もご覧いただき、お役に立てていただければ幸いです。
また次回お会いしましょう。
お大事に。
ここまでお読み頂きありがとうございます。あなたのサポートが私と私をサポートしてくれる方々の励みになります。 ぜひ、よろしくお願いいたします。
