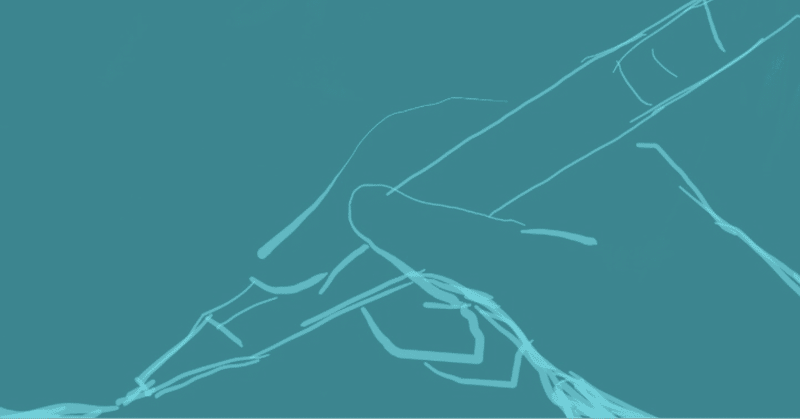
小説未満 新作小説創作途中中継だよ②
自分の読書習慣のきっかけって子どものときに読んだファンタジー小説だったよなーと。
小学生のときに「ハリーポッター」シリーズ読んで、これはめちゃくちゃ面白いって読んで、新作を待ち遠しく思っていた。最終巻が出たのが確か高校三年生のときで、受験勉強中の自習室で1日つぶして本読んじゃった思い出。
あと、中学受験したのだけど、受験勉強のときに問題文に使われていて、出典気になって読んだのが、ミヒャエル・エンデの「果てしない物語」。で、第一志望の中学に落ちて落ち込んでいたときに、親がなんでも買ってやるって言われて、買ってもらったのがそれだった。
中学生のときは、学校の図書館の人に、この本読んでみればとおすすめされたのがトールキンの「指輪物語」。当時、ロードオブザリングの映画も上映してて、それも楽しく観たなと。小説の中でも映画の中でも大好きで恋したのはアラゴルンでしたね。
ファンタジーの世界観が物語に没入する喜びを最初に教えてくれたかもしれない。中学生のころにはうすぼんやりと小説書いてみたいなと思い始めていて、いつかはファンタジー小説書きたいけど難しそうだなーなんて思っていた。実際に大人になってから小説を書くようになってからも、最初はファンタジー小説ではなく、恋愛物だったり群像劇だったりとか、ちょっぴり不思議な世界観が入った物語とかは書いていたけれど、がっつりファンタジーは書いたことがなかった。
今回初の試みで書いてみようとしている。
またまた、創作途中中継です。
はじめてファンタジー小説を書いてみるということで、思いついた物語のシーンを書きながら、同時に設定やキャラクターを考えている途中です。
今回は途中まで物語のシーンを書き進めて、あ、見えてきたかもっていう、世界観の設定や登場人物の関係性などをまとめているところで本日の創作は終了。
また創作進行がまとまったら創作中継としてまとめます~
ーーーーーー書きなぐり途中の物語のシーン(メモなので多分改稿すると思う)ーーーー
前回書いたのはここまで
給仕係が「パチェイ」という菓子を準備し、フィリッポは黄色いピソを持ってきた。
「そろったかな。ではともにエネルギーを補充しようぞ」
エラディンもグランディン王の前の席についた。
腹が減っていたので、黄色いピソを大口あけて食べる。口にいれた瞬間、ギムの香りが広がり、目をつぶれば、あの日見た懐かしいギム畑の光景が広がるようだ。ああ、うまい、ピソ職人の力量によってその美味しさは変わる。フィリッポのピソはこんなにうまいものなんだな。一口食べて咀嚼して飲み込んでからは、二口目、三口目とがっついて食べてしまう。
その様子を横でフィリッポが満足げに、そして誇らしげに見ていた。黄色いピソでこんなにもおいしいのだから、さも出来立ての金色ピソはいかほどおいしいか。
「よいかな、よいかな、フィリッポのピソはうまいだろう?」
グランディン王は少し前まで、ピソをたらふく食べ、それだけでなく、給仕係が用意した料理もきれいに平らげていたのにも関わらず、あらたに給仕係が用意した異国の菓子パチェイをもりもりと食べている。この男の食欲に限界値というものはないのであろうか。尽きることのない食欲は力を欲する権力者たるゆえん。ジャーニマー国という広大な領地を治める王の器の持ち主である
「このパチェイも美味であるな、ピソとはまた違う、エネルギーを感じる」
「そのパチェイは先日隣国の使いが持ってきたものですね」
フィリッポは、パチェイに強い興味を示していた。
パチェイとはジャーニマー国の隣国であるタランティー国の名物の菓子のことである。タランティー国にはダズル豆がよく取れ、ダズル豆から抽出された油をもとに砂糖と魔法族の秘伝の粉と一緒に固めたもので、食べるとある種の陶酔した気分になる菓子だ。パチェイを作れる職人も限られていて、ジャーニマー国のピソ職人のような認定制度があるわけではないが、特殊技能のある職人でないと作れない菓子であった。
フィリッポは職人としての好奇心があるのだろう、タランティー国の使いがグランディン王にパチェイを献上したときに、どのようにしてパチェイが作られるのかを使いの者に聞いていたらしい。
「タランティー国も旅しただろう?エラディン」
「はい、最初に旅した国であります」
「パチェイは食べたことがあるか?」
「はい、旅で出会ったパチェイ職人に少しもらったことがあります」
「フィリッポにその話をするがよいぞ、パチェイ職人に出会っているのであれば、特にな」
「そうですね、フィリッポにはまたのちほど」
グランディン王は二つ目のパチェイに手を伸ばし、うまいなぁと言いながら食べている。エラディンはグランディン王が本題を話すまで、黙々と目の前のピソを食べた。食べれば食べるほど、旅の疲れが癒えていくようであった。
グランディン王は、パチェイを食べ終え、給仕係に食後の茶をもってくるように言いつけたあと、口火を切った。
「ときに、わしがお主を呼び戻したのは、なぜだと思う?」
グランディン王がまっすぐにエラディンを見る。その視線はエラディンの心を見透かすかのような鋭さだった。うかつなことは言えない。
「それは…、情けないですが、私が期待に沿うような働きができていないからです」
「まあ、そのとおりだな」
「申し訳ございません」
「お主が旅した国々との関係性はいまだによくはなっていないからな。タランティー国のほかにはな」
「不甲斐ないばかりです」
「まあ、わしが期待をかけすぎた部分でもあるわな。ただでさえ、勇者の素質があるものは多くはないからな。治安維持のために各地に派遣している勇者が多く、他国へ派遣できる勇者の数も多くない」
ジャーニマー国は、もともと小さな国であった。グランディン王が君主になってから、大きく領土が広がった。筋骨隆々で力の王と呼ばれていたグランディン王が率いる軍は強力で勢いがすさまじかった。各国に侵攻しながら領土を得てどんどんと巨大な国になった。急激に巨大化した国はその後に内部統制していくのが大変であった。油断をすれば、反乱を起こし独立しようと試みる勢力が生まれてしまう。そこで、軍の勇者たちをそれぞれの地域の治安位置のために駐在させていた。また、急激に拡大したジャーニマー国は周辺諸国から警戒され、敵意を向けられることもあった。ジャーニマー国としてはこれ以上の領土拡大を望んでいるわけではなかったが、周辺諸国からはいつ、ジャーニマー国に戦争をしかけられ、侵略されるのではないかと恐れられていた。だからこそ、不要な争いが生まれないように、周辺諸国への和平交渉をせよと命じられていたのがエラディンであった。
ーーーーここまで書いたところで、頭の中で思いついて出てきた設定や登場人物をまとめようとして箇条書きでまとめることにーーーーーーーーーーー
・・・思いつき途中だからこれから整理しながら増えると思う。
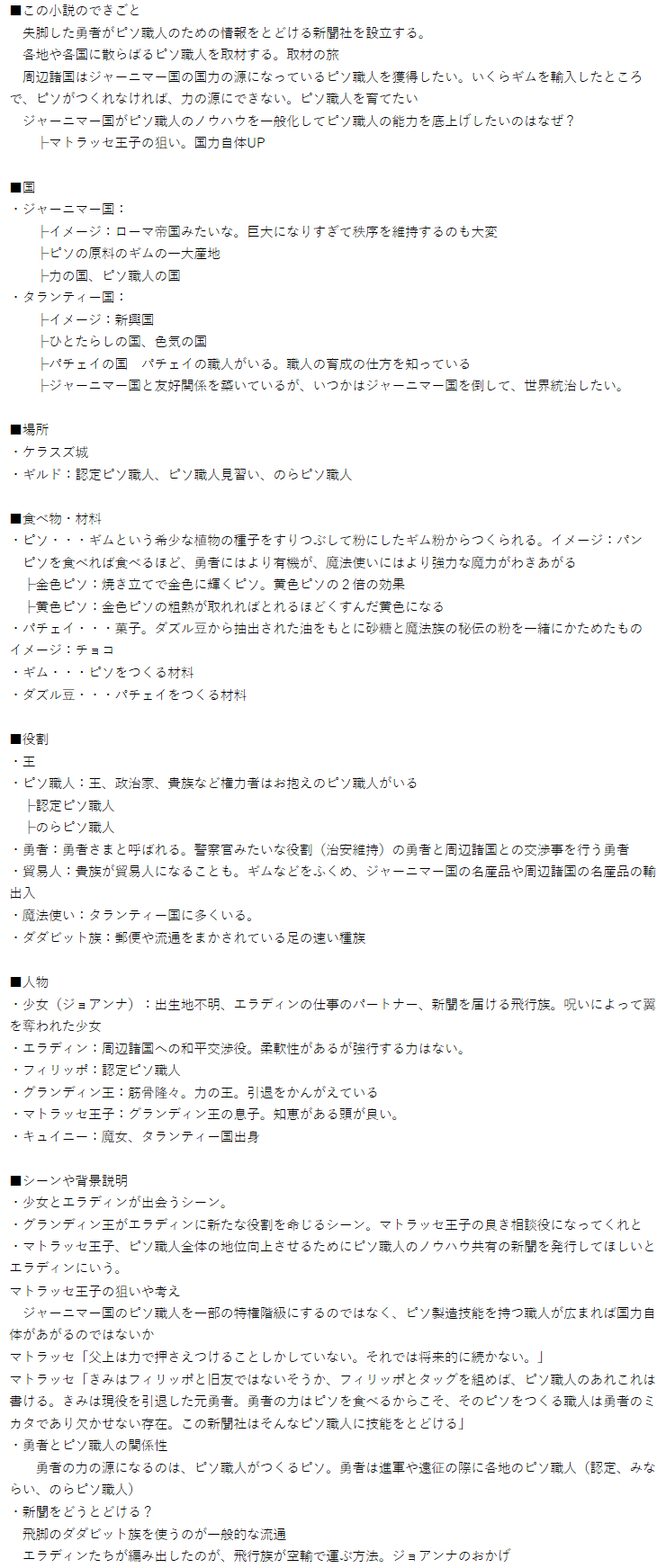
いいなあと思ったらぜひポチっとしていただけると喜びます。更新の励みになります。また今後も読んでいただけるとうれしいです。
