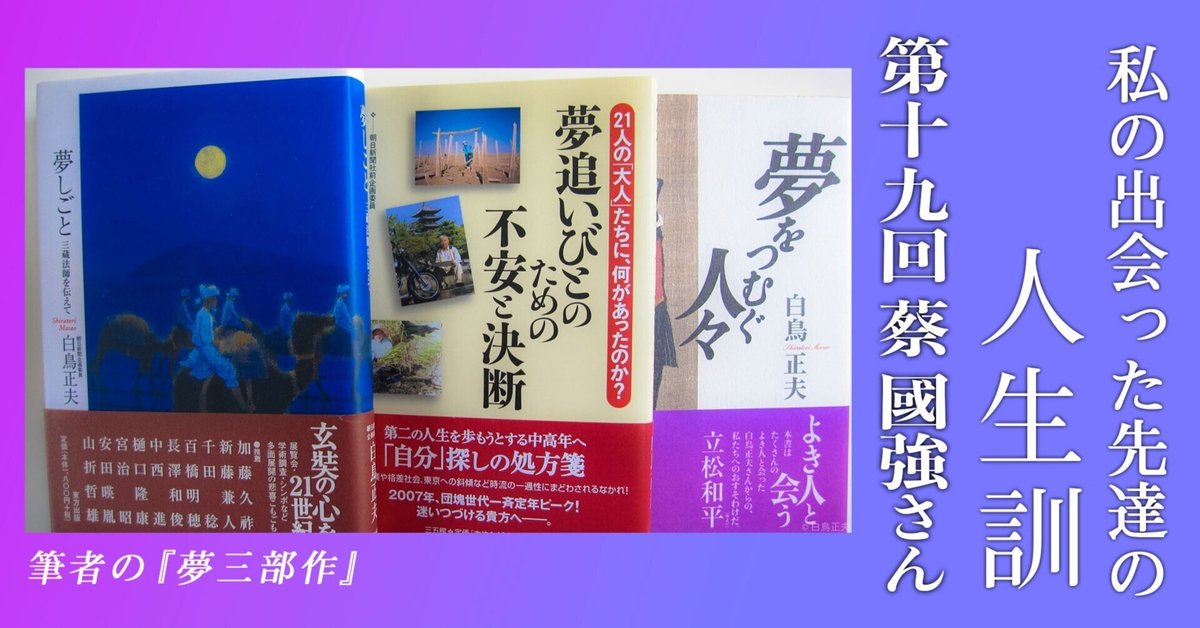
壮大な挑戦、進化し続ける美術家の蔡國強さん「戦争と破壊」や「平和と再生」などをテーマに芸術表現
私が4半世紀前に出会ったアーティストの一人、蔡國強(さい・こっきょう、ツァイ・グオチャン)さんは、今や現代アートの世界的なトップスター
になった。国立新美術館とサンローランは、6月29日から8月21日まで、「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」を開催。日本では8年ぶりの


大規模な個展だ。朝日新聞社時代、広島と神戸で実施された蔡プロジェクトに関わった私は、その後の海外展示を含め着目してきた。壮大な挑戦をし、進化し続ける蔡さんの芸術と人生についてリポートする。
火薬を爆発させる大規模なパフォーマンス
蔡さんは1957年、中国福建省泉州に生まれた。上海戯劇学院で舞台芸術を学んだ後、1986年から95年にかけて日本に滞在し、筑波大学の河口龍夫研究室に在籍する。80年代後半から、火薬を使用した作品の制作を始める。この間、福島県いわき市などに滞在し火薬を用いたドローイングや、野外で火薬を爆発させる大規模なパフォーマンスに取り組む。「戦争と破壊」や「平和と再生」などをテーマに先駆的な作品を発表し続け、とりわけ花火を使う美術家として名を馳せる。
現在はニューヨークを拠点に世界を駆けまわる。1999年の第48回ヴェネチア・ビエンナーレで「国際金獅子賞」を受賞し注目された。日本では、第7回「ヒロシマ賞」(2007年度)、第20回「福岡アジア文化賞受賞」(2009年)、第24回「高松宮殿下記念世界文化賞」(絵画部門)(2012年)を受賞している。
この間、2005年には、ヴェネチア・ビエンナーレ初の中国パヴィリオンのキュレーターを務めて展覧会企画にも才能を発揮した。2006年のメトロポリタン美術館や、2008年のグッゲンハイム美術館での回顧展などでも個展を開催し、国際的にもっとも影響力の大きい芸術家の一人として活躍中だ。
とりわけ、2001年に中国で開かれたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の記念イベントで大都市化の進む上海を舞台に、23の建物を仕掛け花火で結び、夜空に巨龍を描いた。2008年の北京オリンピックでは、華やかな開閉会式を演出した芸術監督を担当し、「巨人の足跡」を演出した。
今回の「蔡國強 宇宙遊」展では、宇宙と見えない世界との対話を主軸に、作家として歩み始めた中国時代、アーティストとしての重要な形成期である日本時代、そしてアメリカや世界を舞台に活躍する現在までの創作活動と思考を遡り、宇宙が膨張するかのように拡大してきた、これまでの活動を検証する。
国内の国公立美術館の所蔵作品と、日本初公開のガラスや鏡に焼き付けた新作を含む作家所有の約50件の作品が展示され、知られざる多数の貴重なアーカイブ資料や記録映像、そしてアーティスト自身による一人称の説明が掲示される。展示室全体がまるで一つのインスタレーションのような展示を通じて、蔡さんの深遠かつ軽やかな思考と実践の旅路をたどる。



展示の中心となるインスタレーョンでは、火薬で描いた7つの屏風ドローイングが爆発的に放射状に広がるように配置され、蔡さんが「外星人のため」と「人類のため」に実現しようとするプロジェクトを表現している。蔡さんは「〈原初火球〉—それは私の思想とビジョンに基づく出発であり、今日まで私に付き添ってきた」とのコメントを寄せている。
広島と神戸の企画展に関わり、京都で再会
私が蔡さんを知った広島でのプロジェクト《地球にもブラックホールがある》に触れておこう。広島市現代美術館と朝日新聞社では1994年に広島で開かれた第12回アジア競技大会の前日、広島市中央公園を会場に、ヘリウムガスで膨らませた風船に導火線をらせん状につるして点火した。ものすごい爆音と閃光と煙を発し、炎は瞬時に土中に吸い込まれていった。近代都市として再生したヒロシマへの祝賀と鎮魂を願った作家の意図は、見る者に衝撃的な印象を与えた。

(1994年、広島市中央公園)
当初はアジア競技大会開会式の聖火を、ヘリコプターから導火線を吊るし点火しようとの趣旨で、蔡さんは「原爆投下の同じ高さから、平和の灯を点したい」との発案だった。しかし安全性の問題以外に、被爆者団体から原爆投下の再現を連想してしまうと意見も。広島での鎮魂は空からよりも地中にあるとの言い分を汲み、最終的には導火線に点火し、地中に掘った穴の中へ消える芸術表現に変更したのだった。こうした経過を通じ、蔡さんの美術家としてのスケールの大きさに感嘆した。


その後2002年には、新装された兵庫県立美術館で開館記念展「美術の力 時代を拓く七作家」を朝日新聞社が共催することになり、私もスタッフの一人として、箱根の森美術館で開かれた展覧会で滞在中の蔡さんを訪ね打ち合


わせなど開催の2年半前から取り組んだ。蔡さんのプロジェクト《青い龍》は、震災で心に痛みを負った多くの人々に、美術の根源的な力に触れてもら


い文化復興をアピールするものだった。ここでは美術館に隣接する水面に99の舟を浮かべた。アルコールの青い炎は天空を清め、横たわる龍は天地を過去から未来へつなぐ意図を示していた。室内展示でも小さな黄金舟99隻を空中に吊るし、未来への船出を表現した。

2008年の「ヒロシマ賞」の受賞記念展にも駆け付けた。この時も二つの美術館外プロジェクトを実施していた。その一つが《無人の自然》と題した作品のための火薬ドローイングで、見事な山水図を描き出した。展覧会開幕直

前に広島市立大学の体育館で半日かけ制作。火薬で描いた絵画は、横幅45メートルもの作品で、大きな太陽や険しい山が半円状の壁面に描かれており、まるで水墨画を見るようだった。展覧会場には約60トンの水をたたえた巨大な水盤が作品の前面に設けられ、水面にも山水図が映りこむ幻想的な空間をかもした。「湖のほとり」を散策しているような気分を味わいながら鑑賞できた。

(「蔡國強展」図録より)
もう一つの《黒い花火》は開会日の午後1時から90秒間、太田川河川敷で黒色花火1200発を次々に打ち上げた。原爆ドーム後方上空に黒煙の固まりが上がり、原爆犠牲者への鎮魂と平和への願いを表現したのだった。
そして2015年、京都で開催された二つの展覧会に、蔡さんの作品が展示された。その一つが「京都現代芸術祭2015」(パラソフィア)だ。21の国・地域から45人の作家が出品したが、最重要作家が蔡さんだった。

京都市美術館1階の大展示室を専有して、中央に高さ15メートルの巨大な塔を建てた。青竹約300本をくみ上げた塔で、西安にある大雁塔を模している。周囲には、京都の子どもたちが不用品で組み立てた作品や各種ロボットが動き、《京都ダ・ヴィンチ》と称する世界を創出した。これからの美術は、過去の権威にとらわれず、作る側も見る側も、大衆社会の中で共生して以降との意図が読み取れた。
京都市美向かいの京都国立近代美術館で開催された「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展 ヤゲオ財団コレクションより」にも蔡さんの作品《葉公好龍》(2003年)と題された、火薬の爆発の痕跡が龍の姿に見える作品が出ていた。その京都で世界連邦運動協会京都支部が主催して蔡國強講演会「異文化に交わる世界の中から」があった。その機会に有志らによる懇親会がもたれ、参加した。



「ヒロシマ賞」の時以来、京都での再会となった蔡さんは、これまでのプロジェクトの動画をみせながら、文化論や芸術論を語った。そして懇親会場では、私に同行した仲間らとも気楽に懇談した。別れ際、「白鳥さんとはすぐに横浜でお会いしましょう」と、横浜美術館で開催の個展「帰去来」展に誘われたのだ。
20年を経て原点・日本での「帰去来」展
「蔡國強 帰去来」展が横浜美術館で2015年7月に催され、開会前日に訪れた。残念ながら、蔡さんは、親戚の方のご不幸があり、急遽、故郷の中国・泉州経由でニューヨークへ旅立っていて、会えなかった。京都でお聞きしていたが、まさに会心の展覧会に仕立てられていた。一段と進化した蔡芸術に感服した。
「帰去来」のタイトルは、中国の詩人、陶淵明の代表作「帰去来辞」から引用された。官職を辞して、故郷に帰る決意を表した詩だ。日本で東洋的な美学に触れ、アーティストとして、その後の発展につながった蔡さんが、日本を離れて約20年、もう一度、原点である日本に戻り、日本文化や人間の本質を見つめ直したいとの意図が込められていた。

会場に入ると、グランドギャラリーと称する広大な空間がある。その前面の壁いっぱいに描かれた最大級の火薬ドローイング《夜桜》が飛び込んできた。蔡さんのプロジェクトは事前に展覧会場となる土地の歴史や特性、テーマ性を探る。《夜桜》は日本美術院を創設した横浜が生んだ思想家である岡倉天心ゆかりの地を訪ね、天心門下の横山大観の《夜桜》などに着想を得たという。



「桜の花は儚く、薄くてつややかだ。この繊細な美を、激しい火薬で描けるだろうか。桜の花のいのちは短いからこそ尊い。火薬が爆発する一瞬と、永遠を追い求めること、これらはその運命において通じるものがないだろうか」と蔡さんは考えた。火薬で桜を描くという、とんでもない構想に挑戦したのだった。
グランドギャラリーでの火薬爆発は、消防などへの手続きを経て、難題を超えて制作にこぎつけた。蔡さんが型紙に下絵を描き、ボランティアがカットし、和紙やキャンバスなどの支持体の上にカットした型紙を乗せ、カットされた部分に火薬をまく。支持体のまわりに仕込んだ導火線に火を付けて爆破させ、火薬ドローイングの《夜桜》を完成させた。蔡さんには長年の経験からの完成図が予測されていたと思われるが、この壮大な作品を見上げていると、「アーティストというより魔術師の成せる技だ」との印象だった。

もう一つの火薬絵画作品《人生四季》にも驚いた。日本の春画をモチーフに女の一生が描かれていた。こちらは月岡雪鼎の作品《四季画巻》から着想を得ている。娘から成年へ、そして妊娠して年老いていく女性の姿と、自然の




中の四季を絡めての色彩豊かな作品だ。もちろん火薬を使っている。本人の弁によると「これまでの私は、火薬を使って絵を描くことから始め、屋外での爆発プロジェクトにまで発展させることが多かった。だが今回は、昼用花火の効果と材料を、平面上の絵画に凝縮させた」とのことだ。長年、蔡さんの作品を見てきたが、こんな新手に初めて接した。
大作2点のほか、表面に繊細なレリーフが施された磁器作品《春夏秋冬》もあった。故郷の中国・泉州にある窯の白磁で花鳥画を制作した。白磁の4枚のパネルに牡丹・蓮・菊・梅を中心とした四季の情景を造形した。焼成された白磁板に火薬を撒いて爆発させ、陰影を表現している。また横浜美術大学の学生との協働によってテラコッタによるインスタレーションの新作《朝顔》を制作、展示室に吊り下げられていた。

時代を問い、異文化を考え、「美」を追求
「帰去来」展で、圧倒された作品に99匹の狼が群れをなして疾走する《壁撞き》があった。2006年にベルリンで発表され、ニューヨークのグッゲンハイム美術館や上海当代芸術博物館などで話題になった作品だが、日本では初公開となった。狼たちはガラスの壁に当たって落下するものの、立ち上がり群れの後ろについて何度でも壁に向かって挑みかかる。ベルリンの壁を意識した作品で、本来のガラスの壁も同じ高さで作られている。ドイツ再統一の過程で東と西の見えない壁を、広く世界に存在する文化や思想などの目に見えない壁を暗示している。99は中国の道教において、永遠に循環することを象徴する数字で、蔡さんの作品のキーワードになっている。

Photo by KAMIYAMA Yosuke

この作品はポスターやチラシで見る限り絵画的であるが、展示空間にインスタレーションされた迫力満点の立体作品なのだ。発表時から話題になり、早く作品を見てみたいと切望していた。2008年に開催された年度イベントで、浅田彰・京都造形大大学院長との対談があり、《壁撞き》について言及していた。
蔡さんは「私が日本から一番影響を受けたのは、素材と形への徹底的なこだわりです。たとえば、オオカミが飛んできて、壁にぶつかって落ちてくる、というような作品を作る時、中国人アーティストはもっと血が出て、激しく恐ろしく表現するでしょうけれど、私はそのオオカミの美しさとかラインの詩的な感じとか、落ちたらまたそっと起きて、また飛んでいくという様子を作る。恐ろしさと美しさの臨界点をみせるのです。作品の裏にある美学なり哲学をもっとみせたい。美学的な距離が大切だという考えは、日本にきてから身につけました」と、自分の芸術の本質を語っていた。
99といえば、東日本大震災で被災したいわきに、子供たちへ美しい桜の里山を残そうと、蔡さんが提唱し、桜9万9000本の植樹を目指す「いわき万本桜プロジェクト」が進められている。蔡さんを育てたいわきへの回帰で、すでに「いわき回廊美術館」も開館し、蔡さんといわきの関わりを記録した写真や、地域の小学生たちが描いた桜の絵が常設展示されている。
この一大プロジェクトには、蔡さんと、いわき市民の長い絆で結ばれた物語があった。川内有緒さんが著した『空をゆく巨人』(2018燃、集英社)に、詳しく綴られている。その中で、蔡さんは「アートは自由でないといけない。“正しいこと”をやろうとしてはいけない。正しいことをやろうとすると、アートは死んでしまいます。ときにパワー、規制、権威、常識、そういったものから自由にならないといけません」と語っている。

現代美術は時代を鋭く捉え、潜在しているものを表現するため、前衛的であり、抽象表現を伴い難解な面がある。しかし蔡さんの芸術世界は具象的で、私たちの既成概念や思考方法を覆すものだ。私たちが日常生活の中で気づかない人間や時代について価値観を問い直し、掘り起こしてくれる。それが美術の持つ「力」と「美」であることを確認できた。
ニューヨークを拠点に世界を駆けまわる蔡さんから「また面白い事をやりましょう」との便りを戴いていたこともあった。進化し続ける蔡さんは、これからも、想像を超える面白い世界をみせてくれることだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
