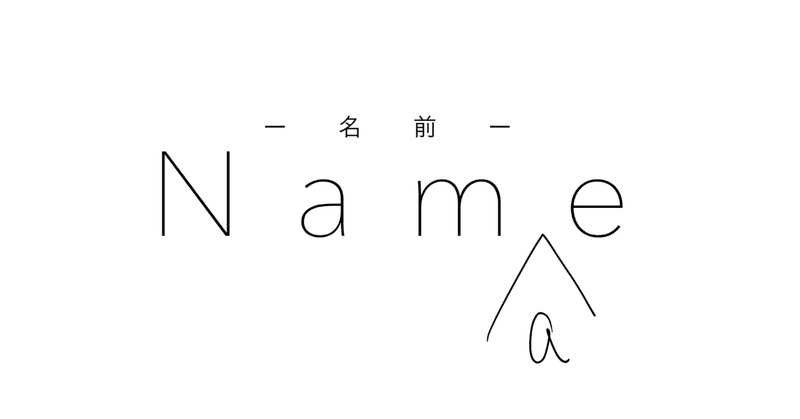
ビューティフルネーム 呼びかけないで名前を
喫茶店の店主であるnakazumiさんが、客からママと呼ばれたり、女将と呼ばれたりで複雑な思いをされていました。
そういう呼び方をするのはきまって年配男性であるとのことです。
なかなか興味深いです。
そう言えば、昔から日本をはじめ漢字文化圏では、人の名前を直接呼ぶことを避ける習慣があります。名前を呼ぶことが許されるのはその人の目上や親などに限られるのです。
なので下の者が上の人を呼ぶときには名前は言えず、役職名や、お父さん、お母さんなどの人代名詞が使われます。
逆に上から下を呼ぶときには名前が言えるので、その場合の人代名詞、娘とか弟とかを呼び方として使わないのです。
粗っぽく言うと、名前を呼ぶのは失礼と言えるのです。
なので時代劇で家来が上司である殿様の名前を言ってたら、おかしいのです。
また官職のある武将ならば、その上司であっても官職名で呼ぶのがたしなみとされています。
例えば本能寺の変のシーンが、
「おやかた様、敵襲です!」
「旗印はなんじゃ」
「桔梗です! 惟任様の軍勢かと」
「ぬ。日向か。是非にあらず」
であれば、おおー、わかってるー、とテンションが上がります。
明智光秀の官職名は惟任日向守ですから。
一方で、
「信長さまあ、明智勢に囲まれてますう!」
「なにい。おのれ光秀めえ」
となっていれば、格調は下がり観る気がなくなります。
さてボクがnoteで使っているハンドルネームは、高祖父の名前から取ってきたものですが、実は近所で屋号として使われていたものでもあります。
なので我が家は「孫兵衛さんち」で、ボクはその昔「孫兵衛さんちのお孫さん」「孫兵衛さんちのご長男」だったのです。
そして近所の古い家はそれぞれ屋号があり「ナントカのすけさん」とか「ナントカえもんさん」とかいろいろ呼び合っていました。屋号というより、農民だったので昔は名字がなかったからでしょう。
とにかく名前を忌避する代わりに便利な呼び方となっていた筈です。
しかし先日、とある寄り合い(地蔵講の集会)("集会"というよりも"寄り合い")(57のボクが最年少)("地蔵講"って、いかにもですが)(他に町会、農会、門徒会、氏子会など7種類くらいあってクラクラしますが)(ビジネス現場では考えられない議事進行でしたが)(注釈が多いな)に参加したところ、参加者の皆さんは、お互いをもう屋号では呼び合わなくなっていたことに気づきました。
昔は呼び合っていたのに。
もうこんな古いコミュニティの老人同士でも名前を忌避することはやらなくなったようです。
あだ名はやめよう運動も、目的は違えど名前を忌避しないベクトルでしょうね。
名前を呼ぶことを忌避する習慣のことを、実名敬避俗と呼ぶそうです。
実名を敬って避ける習慣、ですね。
名前は本人と霊的に結びついており、名前を口にするだけで人を支配できるという考えがあったとされています。
本当は名前を口にするのは失礼と言うより畏怖があるのです。
現代であってもその意識はかすかに残っていると思います。
親同士などでは、"誰々ママ"、"ナントカちゃんパパ"という呼び方のほうが名前を呼ぶより一般的な気がします。ボクにとっても呼び易い感触があります。
名前を呼ぼうとすると何かしら生々しさがあるような気がするのです。
この習慣は教えられたものではなく、何となく身に付いたものです。
しかも明確に自覚していません。言われてみれば、そう言えばそうかというものです。
無自覚で無意識のタブーですね。
しかしどうやら、その習慣も薄れつつあるようです。
喫茶店の女性店主をどう呼んでいいのかわからなくて、仕方なくスナックみたいに呼ぶ世代は絶えていくでしょう。
みんな実名で呼び合うようになるのです。
無意識のタブーがある状態、開いてはならない扉がある状態、聖域がある状態は何だかドキドキしていいのになー。
きっとそのほうが言葉に対して繊細になれる筈だ。
いや、スナック用語を持ち出す輩もいるからそうでもないか。
「やあ、ボクはロバート。コールミーボブ。ボブって呼んでよ」
なにがボブだ。どこがボブだ。
名前をおろそかに略して無邪気に呼ばせるような粗野なやつらと同じになっていくのだろうか。
まあ、アレはついにアレが出て久しぶりにアレしそうだからアレというアレはアレにアレしないほうがアレだよなあ。
ね。生々しい言葉は忌避されるのです。わかりにくいか。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
