
「ごんぎつね」ー何度も出会いたい、物語ー③
授業をすることそのものには、私は経験があった。
しかし、その全ても吹き飛んだかのような、
実習校での初回国語授業、「ごんぎつね」を終えた。
そんな私のもとに、担当クラスの子供が一人、近づいてきた。
「あんな、先生。授業ってさ、ちょっとお笑いに笑っちゃうような。
そんな楽しい、ユルい時も、あると嬉しいんですよね、おれ達。」
いつものおちゃらけた軽い風を装いながらも、
目は真剣であるその子供のことを、私は今でもよく覚えている。
私は、胸を突かれた。
彼は自分のクラスにいる「実習の先生」に気遣いながら、
明るい笑顔をもって、率直にコメントしてくれたのだ。
彼のやさしさと素直さに感謝すると共に、
その日は他クラスの授業参観にいても、
「ごんぎつね」の授業のことばかり考えてしまった。
放課後。
私の指導教員と担当学年の教員全員を前に、こう言った。
「先生方、既に用意していた「ごんぎつね」の指導案と計画、
全て見直したいと考えています。」
初回授業、私は指導案通りに進めることができた。
担当クラスの子供達は、皆集中を保ち、学習活動をしていた。
上手くいっているようだが、これは真逆だ。
私が一方的に与え込むことを、子供達は健気に受けてくれたに過ぎない。
子供達の姿を見ていなかった。
見ていたのは、授業をすすめようとする、自分の姿だけ。
学習単元からの子供達の思いや気づきを汲み取り、
柔軟に、かつ内容を深めながら授業展開したとは、到底言い難かった。
先生方に、授業後クラスの子供から言葉をもらったことも、共有した。
しばしの沈黙の後。先生の一人が、静かに口を開いた。
「hikari先生、私達が力になりますからね、大丈夫です。」
まずは、今一度、本文を読んでみませんか。そう提案された。

子供達にしてもらっているように、交替で音読をする。
本文を読んだ後、一人ずつ感想を述べる。
教員だから、大人数人。その間であるが、実に興味深い。
まず、一番インパクトがあった出来事の捉え方が、
それぞれに根拠がある上で、様々だ。
同じ場面からでも、違った視点からの感想が述べられることもある。
その感想を聞くと、自分の感想にさらに広がりが出る。
あらためて、気づいた。そうか、子供達もそうだった。
同じ物語も、読む子供の捉え方によって、感じ方も違う。
色々な子供達がいて、色々な読み取りや解釈があるからこそ、
集団学習は面白い。
その後さらに深く、先生方と本文を読み込む。
それまで何度も本文を読み、指導案を数授業日以上完成していたのに。
気づかなかった、物語の事実を知った。
まず、きつねの「ごん」の年齢である。
絵本の読者の子供が親しみを持ちやすいように、
「ごん」は子ぎつねの可愛らしい風貌で描かれていることが多い。
しかし、「ごん」は大人だ。
「小」ぎつねであって、「子」ぎつねではない。
その証拠に、独り暮らしをしている。一人称は、「わし」だ。
”子ぎつねだから、いたずらばかりしたんだ”という思い込みは正しくない。
そんな大人の「ごん」は、なぜいつも、いたずらばかりしていたのか。
①単に、そんな性分だった
②独り暮らしの寂しさを紛らわすため
③自分がすることが、いつも間が悪く、結果「いたずら」となっていた。
など、など。様々な理由が考えられる。
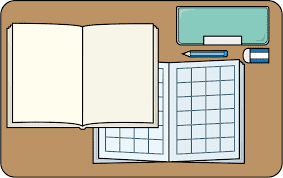
続いて、物語は「ごん」のほぼ完全な片思いで進行している事実。
その時まで、私は細かくその事実に気づいていなかったように思う。
ごんは、兵十に色々なことをしているのに、兵十はあまりにつれない。
おまけに最後は撃ってしまうなんて、ひどいもんだ。
と、このように思っていた。
この「ごん」の片思いっぷりの考察は、私の捉え方を大幅に広げてくれた。
以下、一部を紹介したい。
①「ごん」は、自分がいたずらをしたばかりに、瀕死の兵十の母親がウナギを食べる機会を逃し、そのまま亡くなってしまったと思い、悔やんだ。
→事実か不明。単に当時兵十は、川で漁をしていたに過ぎないかもしれない
②自分と兵十は、同じ独りぼっちだ。
→兵十も「ごん」に自分と同じ独りぼっちだ、と同士意識を抱いているわけではない
③「ごん」はウナギの償いのため、兵十宅にいわしを放り込む。
いいことしたと思いきや、その後兵十は、盗人の疑いをかけられ、
いわし屋に殴られる。「ごん」は、自分のせいで、兵十にかわいそうなことをしてしまったと、申し訳なく思う。
→「ごん」から償いが、兵十には本当に必要だつたのか?
そもそも、ウナギの件自体、「ごん」の通常のいたずらの一つに過ぎないとしか、認識していないのでは。偶然、第三者が同じタイミングで、兵十宅にいわしを放り込んだ可能性が100%無いわけではない。必ずしも「ごん」単独の仕業によるとは限らない。
④いわしの一件から、「ごん」は差しさわりがなさそうな、山の幸(くり・松茸)を拾ってもっていくようになる。
→兵十は、独り暮らし。毎日大量に配達される差し入れを消費しきれたのだろうか。好物でないなどの理由で、有難迷惑となっていた可能性も・・・。
その後の兵十と加助との間のやりとりから、差し入れには否定的でないことはうかがえるものの、心からの喜び、というトーンではないと感じる。
⑤ウナギの一件から、「ごん」はずっと、兵十に心を向けていた。差し入れをするのなどの行動もある。
→兵十にとって「ごん」との接点は、ウナギの一件から途絶えていた。
自宅周辺に出没する「ごん」は、前回同様、いたずらをする困った存在でしかない。
この記事は、企画「#教科書で出会った物語」に参加しています。
ありがとうございます! あなた様からのお気持ちに、とても嬉しいです。 いただきました厚意は、教育機関、医療機関、動物シェルターなどの 運営資金へ寄付することで、活かしたいと思います。
