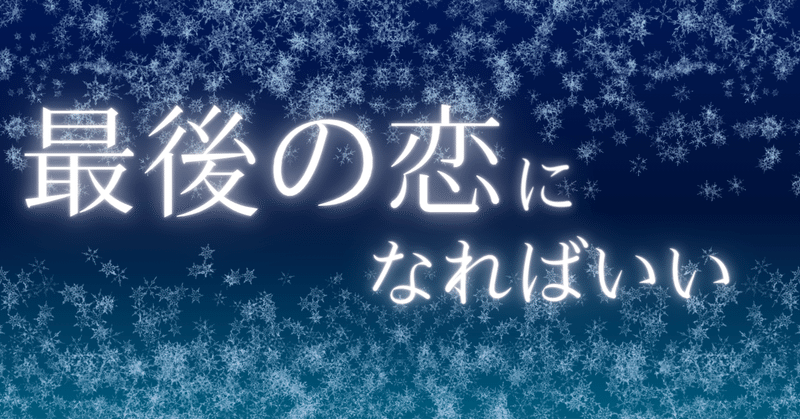
最後の恋になればいい 第13話
* * *
いつも『Bar OLIFANT』で見ている置物の何十倍も大きな実物の象が、目の前にいる。間抜けな着ぐるみ姿で象の展示を眺めると言うのもなんだかシュールだけれど、象がゆっくりと一歩ずつ歩くのと同じように、ここでは穏やかな時間が流れていて、こういうのもありかもしれないと思い直す。
「私動物園大好きなんですけど、ちょっとトラウマだったんです」
「ふーん。なんで」
二人とも象の方しか見ていないからなのか、まるでひとり言みたいにスルスルと言葉が出てくる。
「卓也と別れる前、動物園行こうって約束してたのに果たせないままだったから」
「……なるほどね」
「別れ話した後に、動物園、もう二人じゃ行けないねって言ったら、彼氏彼女としてじゃなくて友達としてでよかったら行こうよって言われて」
「は、マジか。ふざけてんな」
「ね。今思ったらなんだよそれ、ふざけんなってちゃんと思うんですけど、当時の私は馬鹿だったから友達って言う名前なら仲良くしてくれるんだって思ってちょっとの間頑張っちゃったんですよね、友達を……」
「……馬鹿だな」
その通り、馬鹿過ぎてぐうの音も出ない。だけどあの頃の私にとって、卓也は世界の全てだったから、その選択以外ないと思っていた。それがどれだけ自分を傷つける行為だったか、今ならちゃんとわかるのに。
「別れてるのに、二人で映画に行ったりドライブ言ったりしました。でももう友達だから、恋人の頃みたいに好きだよって言ってみたり、手を繋いだり、次はあそこに行きたいねとか、そういうのは、言えなかった。別れてからも色んな所に行ったけど、動物園だけはお互いなんとなく避けてました」
マスターの視線が、象から私へ移る。これでもう、ひとり言ではなくなってしまう。だけど私の口は止まらない。どうして、マスターの前では私はこんなにも剥きだしになってしまうんだろう。
「ある日卓也が改めて、動物園行こうよって言ってきたんです。もう暗黙の了解で行かないことになったんだなと思ってたから、本当にびっくりしました」
マスターはじっと、私の表情を伺うように黙って話を聞いている。実家の犬に何か弱音を打ち明ける時って、こんな感じだったかもしれない。
「私にとって動物園って、小さい頃から、彼氏が出来たらデートで行きたい憧れの場所だったんです。昔はほんと、毎週のように両親に連れて行ってもらってて……その時に見る、動物園デートしてるカップルが、なんかすごくキラキラして見えて」
今だってそう。通りすがるカップルも、夫婦も、私にとってはすごく輝いて見える。
「大好きな場所だから、いつか、大好きな人と私も歩いてみたかった。でも、卓也に改めて動物園に誘われた時、友達としてだったら行きたくないって思っちゃったんです。気づいちゃったんです、私。その時やっと。友達になんか戻りたくなかったんだって。ずっと無理してたんだって」
私にとっては心から特別で大好きな人でも、もう相手にとってはそうじゃない。私が夢見てた動物園デートとは、全然違う。
あの日、そのことに気付いてしまった時と同じように喉の奥がヒュッとなって、目頭が熱くなってくる。
「いいのかよ、そんな大事な場所俺と来て」
「……あれ、ほんとだ」
マスターに言われて、涙が引っ込む。
そう言えばそうだ。何も考えず動物園をリクエストしたけれど、こんなに涙が出そうになるほど動物園デートに思い入れがあると言うのに、どうしてサラッと、マスターとは実現させているんだろう。
「気づいてなかったのかよ」
「だって急に言われてもデートスポットとかわかんないですもん」
これは本当。そもそもデートの経験値が低いから自分の中で選択肢が少ない。
だけどそれでも、動物園はやっぱりとっておきのはずなのに、どうして私はマスターが相手だと、こんなにガードが緩くなるんだろう。
「ほんとに馬鹿だなお前」
「……はい」
否定できないし、認めるしかない。正真正銘、馬鹿とは私のことだ。
さっきまでの熱い動物園語りが急に嘘くさく、恥ずかしくなってくる。
「しょぼくれんなよ調子狂う……お」
マスターが何かを見つけて、腕時計を気にしている。「どうしたんですか」と聞く前に、マスターは私の手を引く。
「行くぞ。象のエサやり」
「えっ! そんなの出来るんですか!?」
「そこ。ハナコだって」
マスターが顎で指す先には確かに象のハナコのエサやり時間の案内がある。「なんだよ。やりたくねえのかよ」と言うマスターに、私は「やりたいに決まってます!」と、最初はマスターに引っ張られていたはずが、いつの間にか私がマスターの手を引いていた。
果物や野菜が入ったバケツを持って、飼育員さんの指示通り、象のハナコの前にマスターと二人で立つ。恐る恐るバナナをあげてみると、ハナコは器用に鼻を伸ばして、私の手からバナナを取って口に運んだ。
「すご……。私あんな看板あったの全然気付きませんでした。マスター、ありがとうございます」
「あんたは視野が狭いんだよ」
「……それ、友達にも言われたことあります」
「だろうな」
「ひど」
「真面目なんだよ、あんたは。浮気してどっか行った、俺の元カノとは大違い」
「えっ、そうなんですか!?」
突然のマスターの暴露に、エサやりどころじゃなくなった私のバケツから、マスターがキャベツを取って、ハナコに与える。
「おー」
なんでもないことのようにマスターは言うけれど、マスターみたいな人がわざわざ付き合うほどの相手だったのだから、そんな「おー」で済まされるような出来事じゃなかったんだろうと言うことはわかる。
「マスター、まだ好きだったんじゃないですか?」
「さあな」
笑っているけれど、それには自嘲も入っているような気がして胸が苦しい。『友達に戻りたい』というフラれ方でこんなに拗らせてしまった私が、もし浮気が原因でフラれていたらどんな拗らせ方をしていたのだろうと考えると、泣きそうになってくる。
「私だったら好きな人が自分を好きでいてくれるんだったらずっと好きでいられるのにな……」
なんとかマスターを元気づけたくて、こういう人間もいるよということを伝えたくて、思ったことを言う。
もうとっくにマスターは立ち直っているのかもしれないけれど、それでも。
「はは、お前が言うと説得力あるな」
「……それ、馬鹿にしてます?」
「ちげぇよ。信じられる、ってこと」
「え」
驚いてマスターを見ると、ちょうどマスターが投げたリンゴをハナコがキャッチしたところだった。
「お、やるじゃんハナコ」
マスターが嬉しそうに歯を見せて笑う。冬の乾燥した空気がそうさせたのかもしれないけれど、なんだか、キラキラと輝いて見えた。
「……マスター、残りも全部あげちゃっていいですよ」
「え、あんたは」
「だってマスターの好きな動物、象でしょ。お店にも置物あったし」
悪戯に成功した子供みたいにイヒヒと笑うと、マスターはバツが悪そうな顔で私からバケツを奪い取り、ハナコに残りのバナナやキャベツをあげ始める。マスターの表情はムスッとはしているけれど、どこか嬉しく感じているのが隠しきれていない。マスターと初対面の人にはわからないかもしれないけれど私にだけはわかって、なんだかそれが嬉しい。
「マスター。私、今日一緒に動物園来たの、マスターでよかったですよ」
「……そうかよ」
「はい」
いつだってマスターの前では本音ばかり零れてしまうけれど、これは今日一番の、心からの本音だ。今日があったから、また私は生まれ変われる気がする。
またマスターが投げたリンゴをハナコがナイスキャッチする。「今の見たか?」と私の方を振り向き、子供みたいな顔を一瞬見せたマスターに胸がギュッとなったのを、私は気づかないふりをした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

