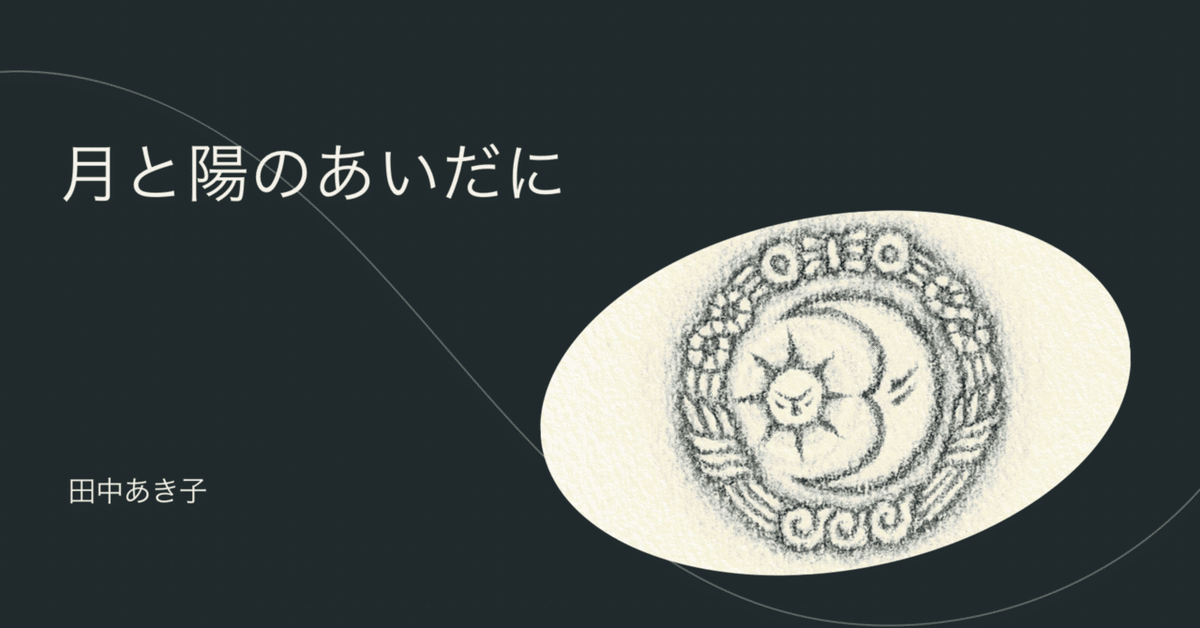
月と陽のあいだに 194
流転の章
華燭(2)
婚礼の準備のために訪れた白玲を、ネイサンは邸の奥の部屋へ連れていった。
重い扉を開けると微かに樟脳の匂いがして、部屋いっぱいに作り付けられた棚には、色とりどりの衣装が収められていた。迎えた女中頭が、うやうやしく頭を下げた。
「ここは亡き母の衣装部屋だ。ここにある衣装は、母が儀式の折に着たものだ。母は月族にしては小柄だったそうだから、そなたなら着られるかもしれない。お下がりが嫌でなければ受け取っておくれ」
言葉もなく部屋を見回していた白玲は、女中頭がいることも忘れてネイサンに抱きついた。
「本当にいただいていいの?」
もちろんだと、ネイサンは笑った。
「いつか私の妻に贈るために、代々の女中頭が手入れを続けてくれたから、どれもまだ十分着られるはずだ。きっとそなたの役に立つだろう」
月蛾国の貴族は、娘が生まれると衣装部屋を作り、その子が嫁ぐ日のために衣装を仕立て始める。また、祖母から母へ、その娘へと代々受け継がれる衣装もある。こうして十数年かけて整えられた衣装を持って嫁ぐことが、習慣になっていた。
だが、輝陽国から身一つでやってきた白玲には、衣装部屋はなかった。月蛾宮で暮らすようになって、必要な衣装はその度に整えてきたけれど、いかに皇家といえども、豪華な衣装を一度に用意することはできない。
「花嫁衣装は、内府でご用意いたしましょう。それ以外のお衣装は、婚礼の後で少しずつ整えていかれればよろしいかと存じます。ネイサン殿下は、姫様に良いようにお取り計らいくださるでしょう」
女官長はそう言ったが、白玲はそのことをネイサンに切り出せずにいた。
白玲は、結婚後の暮らしは二人で少しずつ整えていけばいいと思っていた。けれどもそれは庶民のあいだでのこと。貴族の慣習は、そんな気楽な思いを許してはくれない。ネイサンにかける負担を思うと、白玲は気が重かった。
そんな思いを知ってか知らずか、ネイサンは妃にふさわしい衣装を「母からの贈り物」として差し出してくれたのだ。
「ありがとうございます。もう、嬉しすぎてどうしていいかわからないわ。夢を見てるんじゃないかしら」
白玲は、今にも踊り出しそうにはしゃいでいる。ネイサンはその頬をキュッとつまんだ。頬を押さえて睨んだ白玲を、大きな鏡の前に導いた。
鏡の傍には、白金色に輝く衣装が整えられていた。宮廷で最も格式高い儀式のために着用するものだと、一目見てわかった。
「これは、母が亡き皇太子との婚礼の儀でまとった衣装だ。そなたが良ければ、私たちの婚礼でも、これを着てくれないか。母がそなたを守ってくれるように」
白玲は、婚礼衣装の豪華な刺繍にそっと触れた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
