
【運営メンバー紹介】田中健士郎 | 企業の垣根を超えて築く、新時代のファンベースコミュニティを実現したい
町プロタウン運営メンバー(クルーと呼びます)を紹介するシリーズ。第二弾は、おやっさんの妄想を町プロタウンというコミュニティに繋げた水先案内人、田中健士郎さんです。
新卒で製造業の海外営業担当になり、1年の半分を台湾やアメリカで暮らすというハードながらも楽しい生活を送りながら、未来の働き方へのワクワクに突き動かされてオンライン人材マッチングサービスを提供する株式会社クラウドワークスに転職。リアルとオンラインで人がつながり働くことで、新しい価値観が生まれ、世界がより良く変わっていくことを信じて活動しています。
「共創とイノベーションを創出し、社会に還元していきたい」というおやっさんと志をともにして、町プロタウンのコミュニティ運営に関わっている田中さんに、おやっさんとの出会いや、田中さんが考えるコミュニティについて、そして、町プロタウンが持つ可能性についてお話を聞きました。
プロフィール
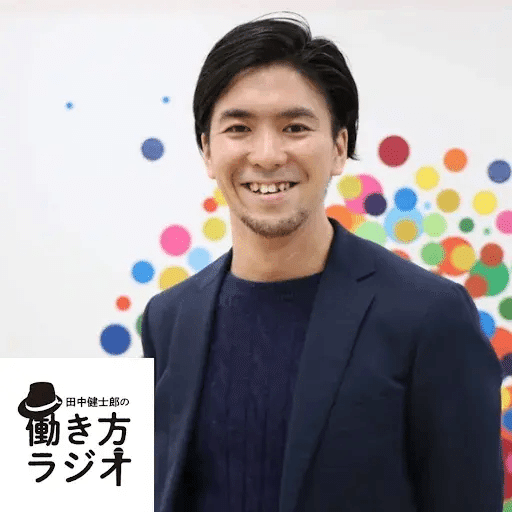
田中健士郎(株式会社SessionCrew 代表取締役・「田中健士郎の働き方ラジオ」パーソナリティ)
神奈川県逗子市在住。上智大学卒業後、大手製造業会社で電子部品の海外営業を担当。2015年株式会社クラウドワークスに参画し、30以上の自治体と連携した地方コミュニティ作りの他、オンラインスクール「みんなのカレッジ」・フリーランスライターのオンラインコミュニティ「ライターゼミ」を立ち上げ、コミュニティマネージャーを担当。5000人以上の副業・フリーランスに学びと仲間づくりの場を提供。2024年に株式会社SessionCrewを創業し、代表取締役に就任。法人・個人を対象としたコミュニティ作りと広報支援に従事。 https://twitter.com/tkenshiro
始まりはカラビナから
ー町プロタウン運営メンバーを紹介する第一弾で、おやっさんは「町プロタウンの構想は田中さんと話すことで湧いてきた」と語られていました。まずは田中さんとおやっさんの出会いについて教えていただけますか。
おやっさんと僕の縁を繋いだのは「栗原精機のカラビナ」です。
2023年4月に町工場プロダクツ(町プロ)のPOP UPを渋谷ロフトで開催中という情報をXでキャッチして、立ち寄ってみたんです。その展示を見て「町工場って下請けじゃないんだ!こんなに情熱を持って自社プロダクトを企画・製造して、販売までやっているんだ」と感銘を受けました。それで商品を応援したいなって、純粋な気持ちでXに投稿したら、おやっさんが喜んで反応をくれて。そこからDM(ダイレクトメール)での交流が始まりました。
お土産ゲットしましたー!
— 田中健士郎 | 働き方ラジオ | SessionCrew Inc.代表取締役 (@tkenshiro) April 28, 2023
カラビナ、キャンプで使おう😁#町工場プロダクツ #栗原精機 https://t.co/QECVbDWSI2 pic.twitter.com/jyFtlKtE8F
ー推し活をしたら、推している相手と繋がった、というわけですね。そこからどのような経緯で「町プロタウン」の運営に協力することになったのでしょうか。
僕がライフワークとして2020年7月から配信を続けているPodcast番組「働き方ラジオ」におやっさんにゲストとして来てもらったのがターニングポイントですね。
「誰もが自己表現をするように情熱を持って働く世界」を実現するための仲間づくりをしている番組なのですが、僕がおやっさんとDMで繋がったという話を番組の準レギュラーであるリサにしたら、おやっさんに個別にDMでゲスト出演を依頼してくれて。渋谷ロフトに行った2か月後にはおやっさんと番組で話をしていました。
「町工場プロダクツ」というコミュニティについての話も収録で聞いて「素晴らしい取り組みだな」と改めて思いました。そこから町工場プロダクツの中の人、デザイナーの眞鍋玲さんも加わって4人で定期的にコミュニケーションをとるようになったっていう感じです。
ーおやっさんは田中さんが主宰する「ライターゼミ」に影響を受けたと言っていますが。
僕が主宰している「まちをコンセプトにしたオンラインコミュニティ」ですね。Slackというチームコミュニケーションツールがメインの活動場所なのですが、そこではメンバー主体の提案から企画が次々と生まれています。
最初は各メンバーが毎月生まれた日に近況を報告する「月報」や、目標を宣言して報告しあう「目標達成の丘」、困ったときに相談できる「質問広場」など実務系のチャンネルが多かったのですが、その後少しずつ「あれもやりたい!」「こういうのがあったらいいんじゃないか?」とチャンネルが増えていって。スポーツについて語り合う「ライターゼミスタジアム」や、旅について発信しあう「ライゼミ空港」、とにかく思いついた企画を投入してメンバーでブラッシュアップする「アイデア出し公園」やサブカルチャーについての情報を交換し合う「サブカル通り」など、いまでは30以上のまちにちなんだネーミングのチャンネルが自然多発的に誕生しています。まさに活気溢れるまちとなっているんです。
このライターゼミのような活動を町プロと組み合わせたら、町工場もどんどん盛り上がっていくんじゃないか、という話をしたら、「まさにそれを今やりたいんだ!」とおやっさんの妄想が一気に溢れ出てきました。おやっさんの妄想を聞いて形にするお手伝いをしていたら、町プロタウンの構想がどんどん具体性を帯びていきましたね。
もともとは町工場のコミュニティをより広げるために、町工場同士のつながりを軸に異業種の方たちにも参加してもらえるといいなと考えていたようです。ところが僕と話したことで、ファンの存在にスポットが当たりました。町工場が生み出すプロダクトの個人のファンの方にも加わってもらい、一緒に作るコミュニティにしたほうが、熱量が高まり今までにない新しい取り組みも生まれるんじゃないか、ということに大きな可能性を感じてくれて、そこでおやっさんと意気投合しました。
毎日届く退会メッセージ!初めて作ったオンラインコミュニティが自走するまで
ー「ライターゼミ」についてもう少し詳しく伺えますか。どういった理由からオンラインコミュニティを作ろうと思われたのでしょうか。
クラウドワークスでは地方創生事業を担当して、広島県の福山市や宮城県の気仙沼市で地域コミュニティづくりの支援をしてきました。クラウドワークスには、自分らしい働き方の実現を支援するオンラインコミュニティ型の学びの場「クラウドカレッジ(現みんなのカレッジ)」があり、そのサービスも順調に成長していたので、次はオンラインでコミュニティを作ってみよう!とサブスク方式のオンラインサロンをスタートさせたんです......が.....これがなかなか難しかったんですよ。
教育サービスの延長線上にあるオンラインサロンなので、最初は「ユーザーにとってベネフィットのあるコミュニティにしよう!」と意気込んじゃって。とにかくみんなが価値があると思えるような有料級の講座をたくさん用意したり、自分でもセミナーを開催したり、みんなのキャリアを作るためにコーチング的なことをやったり。
「とにかくいいものを提供しなきゃ!」と思っていたのですが、最初はできても続かないんですよね。僕自身、コミュニティだけに時間を使えるわけじゃないし。それでどんどん疲弊して、コンテンツの提供頻度がだんだん下がっていったんです。するとみるみる参加者が減っていって。毎日のように「今日で退会します、お世話になりました。今後はXで交流させてください」というメッセージがSlackコミュニティで投稿されて、退会メッセージが一番多い時もあったくらいでした。けっこうショックだったし、めちゃくちゃ落ち込みました。
ーそれは辛いですね。そこからどのようにして、現在のような「共創分散型コミュニティ」に進化していったのでしょうか。
いろいろと悩みながら考えるうちに気づいたんです、「そもそも繋がれていなかったんじゃないか」と。いま思うと、僕が提供者として頑張って投稿するだけでは、メンバー同士の交流が生まれていなかったんです。「繋がっていたいという気持ちだけでサブスクのお金を払い続けるのは難しい」と思っていたところもありました。
残っているメンバーと意見交換をするなかで、どこかのすごい人を呼ぶんじゃなくて、実はこの中のメンバーにこそ面白い人がいっぱいいるんじゃないかということにも気がついて。そこからは、メンバーが主体となる活動へとシフトしていきました。ライティングで実績のあるメンバーがゼロからの実績づくりの体験を共有したり、人とコミュニケーションをとるのが得意なメンバーが入会したばかりのメンバーと1on1をしたり。
自分が主役になると、自分のことが話せますよね。自分を知ってくれる人が多いコミュニティには安心感が生まれるので、居やすくなる。メンバー主体の活動を続けることでより溶け込んでくれる人が増えてきて、退会者が減っていきました。
最初は僕が「これやってくれませんか?」って調整をしていたのですが、その後徐々に、メンバーの中で自主的に企画が生まれ、実現していって。仲間同士が共に創る企画が常に同時に複数あって、まさに共創分散型のコミュニティとして動いています。最近は僕はSlackもほぼ投稿はせずに、メンバーの動きを安心して眺めていることの方が多いです。
「ファンベース」で自社の価値や商品を広めていく
ー町工場プロダクツ(町プロ)と町プロタウンって、なにが違うのでしょうか。
町工場同士が協力をしながらギフトショーに出たり、POP UPに出店したり、新規事業を作るときの情報交換をしたりするという町プロは、すでにコミュニティとして価値があると思います。
ただ僕が渋谷ロフトに行って感じたのは「僕のようなファンは町プロのようなムーブメントにどう関われるんだろう」ということでした。僕がおやっさんのカラビナを買ってXに投稿したように、町プロって既にある程度ファンがいるんじゃないかと思います。ただそういうファンって、あまり可視化されていなかったり、一時的に興味を持ったのに離れてしまったりしているんじゃないでしょうか。そう考えたときに、ファンも気軽に集える場所があったらいいなと思いました。ファンと町工場が共創できる場があることで、僕のような町プロファンが、何か応援したい!何か関わりたい!と思って行動に移せる。するとみんなすごくハッピーになれるんじゃないかなって思ったんです。
ーファンと共創できるような場所......ですか。
「ファンベース」という、電通で活躍されていたプロの広告マン・佐藤尚之さん(さとなおさん)が提唱されている考え方をベースにしています。
集客や収益を生み出すために何をするべきかと考えたときに、大量に広告費を投下して多くの人に届けることで自社を知ってもらったり、CMを使ってブランディングをして一気に認知度を拡大したり、というのがいままでの広告スタイルでしたよね。ただ、これだけインターネット上の情報が多くなった時代に、企業がどれだけお金を払って情報を届けようと発信しても届かないし、SNSで発信しても全ての投稿が全ての人に届くわけじゃない。仮にバズって多くの人に届いたとしても、バズそのものが毎日何十何百件とあって埋もれてしまうじゃないですか。そこからその会社のことが気になって調べて購入するまでの道のりは、意外と遠いんです。
それなら、自社のことを本当に好きになってくれたり、自社の価値観や商品に共感してくれたりする人、つまり「ファン」をもっと大切にして、ファンと一緒になにかに取り組んだり、ファンを通して情報を広めていくという動きをした方が、最終的には多くの方に届いたり、本来届けるべき人に届くようになる、ということをさとなおさんはおっしゃっています。
クラウドワークスで「みんなのカレッジ」という教育事業を作った時に、ライターゼミのメンバーがみんなのカレッジのファンになってくれて、真っ先に講義を受けたり、一部のメンバーはスタッフとして講座を一緒に作り上げたり、講座の良さをさらに広めるために一生懸命SNSで発信してくれたんです。僕自身がそこでファンの熱量の高さを感じ、「ファンベース」の考え方が腑に落ちました。
この経験から、町工場がこれからやっていくべきなのは、自分たちのファンをしっかりと作っていくことと、身近なファン一人ひとりを大事にしていくことだと確信しています。ただ、そうはいっても町工場一つ一つが自社のファンコミュニティを作るっていうのは、すごく難しいし時間もかかる。僕はもともとコミュニティに興味があったので、ライターゼミというちょっと属人的なコミュニティを作って、それが結果的にみんなのカレッジという教育事業の成長にもつながりましたが、僕のような人がたまたまその会社にいることはそんなに多くないですよね(笑)。
メンバー同士が自発的に共創していける町に
ー自社だけではできないことをスクラムを組んでやる、ということですね。
そうです。一社だけで自社コミュニティを作るんじゃなくて、20社30社40社が一緒にファンコミュニティを作るんです。そうすれば、ファンコミュニティが運営しやすくなりますよね。
町工場と個人のファン、そして場合によっては、町工場と何か一緒に仕事をしたい企業さんも含めて一つのコミュニティを作り、どんどん共創や共感の輪を広めていく。町工場は自社のファンコミュニティを協力しながら作ることができるし、ファンの方にとっては、自分の好きな商品を作っている企業さんと一緒に時間を過ごしたり、そういうのが好きなメンバーと雑談をしたりして、コミュニティが自分の居場所になる。町工場以外の企業さんも、町工場さんとコラボすることで今までできなかった新しい取り組みができる可能性がある。みんながハッピーになれるような仕組みに、町プロを昇華できるんじゃないかと思って。
今までの町工場だけのつながりっていうところから、最終的にはファンや企業も巻き込んだ大きなうねりを作る。町プロタウンの未来にいまは純粋にワクワクしているし、僕のコミュニティ運営の経験や人と人とのつながりが、町プロタウンに役立てられればと思っています。
ー町プロタウンは2024年4月にスタートしたということですが、いまどんなフェーズですか。
2024年6月から、町づくり委員が始まりました。
町プロタウンは、ファンと町工場と企業さんが繋がることで共創や新たなイノベーションを生むというのがコンセプトにあるのですが、イノベーションを起こすためにはコミュニティとしての熱量や温度をある程度上げる必要があります。そこで重要になってくるのが、僕がライターゼミで体験してきたような、メンバーが主体となったコミュニティづくりです。町プロタウンというコミュニティをよりいい場所にしたいと思っている人、自分が当事者になって町を作っていくんだというやる気を持った人を一人でも増やしていくことが大切で、それが将来的に自走し続けるコミュニティの核になるのではないかと思います。まずは数人でもいいんです。
町プロタウンには、ギフトショーや催事に出展できるというサービスもありますし、もちろんそれは大きな価値ですが、これまでお伝えしてきたように、自社を応援してくれる人、応援だけじゃなくて一緒に盛り上げたり作り上げたりする仲間ができることがコミュニティの一番の価値だと僕は思っています。
ー田中さんが代表を務めるSession Crewは、コミュニティに投資する文化作りを推進されているとか。
そうですね。僕たちSessionCrewは、コミュニティ運営を軸にしたファン作り、集客支援、クラウドファンディング支援、PR支援を行っています。先ほど「ファンベース」の話をしましたが、企業がステークホルダーとの関係を築き、共存共栄を実現するためには、これからはコミュニティへの投資が欠かせないと思っています。
コミュニティが熟成するには時間がかかりますが、SessionCrewとしても僕やリサを中心に、ファンベースコミュニティ作りの経験を活かして町プロタウンの中をかき混ぜて発酵を促していきます。楽しんで過ごしていただくうちにいつのまにか自社のファンがどんどん増えている、そんな未来に期待して、ぜひ仲間になっていただければと思います。
編集:坂本リサ
取材・原稿:ロマーノ尚美
校正:森真弓
最後までお読みいただきありがとうございました!
2021年より活動を始めた「町工場プロダクツ」がさらに発展し、新しいオンラインコミュニティ「町プロタウン」が2024年4月にスタートしました。
町工場以外のどんな立場の方も関われるしくみができました。町工場のみならず、さまざまな業界、町工場が作るモノが好きで応援したいという個人ファンの方もご参加いただけます。
Biz.会員として、Fans会員として参加してみませんか?
申込みなど詳細は公式サイトをご覧ください!
コンタクトフォームもご用意しています。
質問・お問い合せもお気軽に。
